Interview #249 ダレル・シャインマン (Gearbox Records)
Darrel Sheinman (Gearbox Records)
photo above: Eisuke Sato
Interviewed by Eisuke Sato 佐藤英輔 May 24, 2022 @Connel Coffee, Tokyo
ギアボックス(Gearbox Records)という、ヴァイナルに力を入れるレコード会社がロンドンにある。2010年代半ばごろからリリース数を増やし、同社は2020年から日本にもオフィスを置くようになった。当初はタビー・ヘイズやロニー・スコットら1960年代の英国ジャズや、セロニアス・モンクやユセフ・ラティーフやドン・チェリー他の往年のUSジャズ・マンの掘り起こし作が注意を引いたが、今は英国の若手やアブドゥール・イブラヒム(2020年にメール・インタヴューしたら、かなり同社に信頼を置いている感じがあった)やチャールズ・トリヴァーやザ・クッカーズ(現メンバーはビリー・ハーパー、エディ・ヘンダーソン、ドナルド・ハリソン、ジョージ・ケイブルズ、セシル・マクビー、ビリー・ハート)など有名どころの新録作を出すようになってもいる。一方で、純ジャズ外のプロダクツもリリースもしだしてもいる同社を舵取りする社長/プロデューサーのダレル・シァインマンとはいかなる人物であるのか。また、ギアボックスはどういう方向を標榜しているのか。この5月に来日していた、シァインマンに話を聞いた。とても好漢、楽しくインタヴューできたことを付記しておく。
――日本にはよくいらっしゃっているんですよね。
「そうだね」
――それらは、ビジネスと観光を兼ねるという感じなのでしょうか。
「両方だ。2002年以降、ギアボックスを始めていたころから三菱商事との商談とかで何度も来ている。2004年以降は毎年来ているけど、それは僕が武神館武道体術という武道をやっているからなんだ」
――今、ギアボックスに所属するアブドゥーラ・イブラヒムも日本の古武術を長年学んでいますよね。
「彼は空手の古武道をやっているよね」
――あなたは、音楽以外の立派なビジネス・キャリアをお持ちなんですよね。
「かつてはね。モルガン・スタンレーでトレイダーを12年間やっていた。その後、衛星を使って船のトラッキングをする自分のビジネスを始めたんだ。『キャプテン・フィリップス』という船が海賊にハイジャックされてしまう実在の話を基にした映画(2013年作。主役はトム・ハンクス)があるんだけど、その船は僕のクライアントだったものの経費節減で僕のトラッキング・サーヴィスを利用するのをやめたら、ハイジャックされてしまったんだ」
――そうした一方で、ずっと音楽はお好きだったんですよね。
「8歳の時から自分の音楽を作っていた。ドラムを叩いていて、テープ・マシーンを使い、いろんな楽器を録音していたよ」
――ロンドン生まれですか。
「100キロぐらい北のノース・ハンプトンだ。靴を作ることで有名な街だね。父親がユダヤ系白人の英国人で、母は黒人のナイジェリア人。2人が出会った1960年代には白人と黒人の交際が歓迎されず、2人が結婚した際に父親は勘当されたんだけど、僕が1965年に生まれた途端に問題は解決した。父がジャズ好きで、両親はジャズがきっかけで付き合うようになった」
――ナイジェリアというとフェラ・クティですが、何度も行っています?
「6歳の時に行ったきり。両親は11歳の時離婚してしまったしね。僕は寄宿舎学校に入っており、それはラグビーという名前で、それこそラグビー発祥の学校で、だから僕はラグビーもやっていて大好きだ。今はラグビーのコーチをしているよ」
――話は戻りますが、自分で音楽を重ねていた際には、どういう音楽を作っていました?
「パンクだね。パンク・ロッカーだった。最初に買ったレコードはデイヴィッド・ボウイの『ジギー・スターダスト』。グリーン・カーネーションというパンク・バンドをしていて、モヒカンだったこともあった(笑)。父が“テイク・ファイヴ”をかけていたのでよく口ずさんではいたんだけど、ジャズを聞くようになったのは18歳。パンクとジャズは似ているところがあって、表現に自由があるところとか、ルールがないところなどは共通している」
――ぼくはオーネット・コールマンのプライムタイムを、パンク・ロックとして聞いていました。
「うんうん、彼はジャズのパンク・ロッカーだからね」
――では、大学に入ってからはジャズ一直線みたいな感じだったんですか。
「いや、いろいろ聞いていた。ウェザー・リポートなんかも聞いたし、ファンクにもはまったね。今もファンクを演奏するのは好きだ」
――好きなドラマーはどんな人ですか?
「ピーター・アースキン。彼はすごい。あとは、カーター・ボーフォード。(米国広角型ロックの)デイヴ・マシューズ・バンドのドラマーで、僕は好きだな。あとは英国人の若いドラマーで、リチャード・スペイヴン(トーキング・ラウドが送り出して広く知られた4ヒーローで叩いていた新世代ドラマーで、ホセ・ジェイムズの来日公演に同行したこともある)」
――なるほど、やはりいろんな音楽を聞いているんですね。それはギアボックスのカタログを見れば分かりますが。
「そうだね。その中でもジャズは自分の“声”であって、誰かに曲をかけてあげる場合はやはりジャズになる」
――そう言えば、DJはしないんですか?
「ラジオでやっている。かつてはクラブでもかけていて、そのときはアシッド・ジャズ系もかけた。SOIL & “PIMP” SESSIONSもね。昔はオスロに遠征して、DJをしたこともあった。今はソーホー・ラジオという局で、“ギアボックス・キッサテン”という番組をやっていて、月に一度好きな音楽をかけている」
――では、昔のトーキング・ラウドとかも好意的に聞いていましたか。
「トーキング・ラウドはすごくいいアーティストを出していた。ユナイテッド・フューチャー・オーガニゼイション(U.F.O.)や松浦俊夫もいいよね。(トーキング・ラウドをやっていた)ジャイルズ・ピーターソンはライバルとも言えるけど、いい関係を持っている。彼はDJでもあるけど、ギアボックスのことをすごくよく扱ってくれている」
――ギアボックスを設立した際、目標にしたレーベルはありました?
「ブルーノートだね。オリジナル・ブルーノートのコレクションをしていたりもしたので、ジャケットの写真のクオリティの高さとか、素材の良さとかすごく好きで、ギアボックスではそれを意識している」
――僕はもう少し新しい時代のレーベル名が出てくるのかと思いました。
「(英国ロック・レーベルの)ドミノ・レコードはそうだね。アートワークはブルーノートだけど、音楽面ではドミノとも言える。ドミノのオーナーとは知り合いで、その目の付けどころ、若い人たちの興味の拾い上げ方とか、音楽出版をやっているところとか、共感を持っている」
――ギアボックスのイラストを用いた作品(バディ・リッチの『Just In Time The Final Recording』など)は、ケニー・バレルのブルーノートのそれを想起させたりします。
「うん。何人かイラストレイターを使っているんだけど、ブルーノートを意識してもらっていた。でも、今は逆に真似をしないようにしている」
――ブルーノートへの憧憬があると、やはり音にもこだわりたくなりますよね。
「まったく、そう。僕はオーディオファイルでもあって、レコーディング機材にもこだわりを持っている」
――では、ギアボックスにはルディ・ヴァン・ゲルターみたいな人はいますか?
「はは。僕だけじゃなく、キャスパーというエンジニアがいるんだけど、2人合わせてルディに向かっている感じかな。ルディ・ヴァン・ゲルダーは、僕のヒーローだね。去年出たザ・クッカーズのレコーディングは、彼のスタジオを録っている」
――現在、ギアボックスは何人でやっているのでしょう。
「7人だ」
――それは、日本のオフィスも含めて?
「そう。日本に2人、5人が英国だ」
――英国以外に支部があるのは日本だけですか。
「そうだね。ギアボックスの一番大きなマーケットは米国で、2番目が日本なんだ。日本で成功するためにはオフィイスを置いた方がいいと思ったのと、僕が日本好きだからだね」
――ギアボックスって、当初はかつてのジャズ・アーティストの掘り起こし作のリリースから始まったという印象があります。最初はそれがとっかかりやすかったという感じですか。
「レーベルを始めたのは2009年だったんだけど、その頃には全然業界の知り合いがいなくて、僕も知られていないなかったからね。そこで、目をつけたのがそうしたジャズとヴァイナルで、ここから始めようとなった」
――その後、チャールズ・トリヴァーとかアメリカの実力者のアルバムも出すようになりましたが、それは活動と共に知名度が増していったからでしょうか。
「そのとおり。今となっては、ギアボックスとやりたいというレーベルも出てきている。インディ・ロック界のドミノの、ジャズにおける同様の存在になりたい。アート・ブレイキーが出せることになったのはうれしかった。それは、チャーリー・ミンガスのデビュー・レーベルとつながっていた人がいて、音を売ってくれた。今となってはブレイキーの遺族ともつながったし、デクスター・ゴードンやバディ・リッチも同様で、今後は直接やりとりできると思う」
――では、アメリカにも結構行っているんですね。
「うん、父の再婚相手がアメリカ人で、今はニューヨークに住んでいることもあり、よく行っている。僕の元妻もアメリカ人で、子供はハーフ・アメリカンなんだ」
――プロデューサーとしての哲学を教えてください?
「僕は(デジタルではなく)テープにレコーディングすることにこだわっていて、そして1テイクか2テイクしか録りたくない。ちゃんとリハーサルをしてもらった後でね。それはこだわり。オーヴァーダブはしたくない」
――他に、ギアボックスの作品においてこれは外せないという要件はありますか。
「僕はレコーディングを写真と同じように考えている。写真のように、その日その時のスタジオのムードとかを、鮮やかに切り取りたいんだ。それにはこだわっている」
――たとえばECMのマンフレート・アイヒャーは音楽性に口を挟むと言われますが、あなたの場合は?
「僕はリラックスさせることを心がける。リック・ルービン(ヒップホップが出た1980年代以降、米国でもっとも成功したプロデューサーの1人)のやり方が好きなんだ。口出しはせずに、そのアーティアストにとってどうするのが一番心地いいかを考える。口出しして欲しいなら口を挟むし、ピザを買ってきて欲しいなら、買いに行く(笑)」
――テオ・マセロも対象をおだてて木に登らせて録る人のようですね。
「彼もそうだね。アーティストによってはアドヴァイスを求める人もいる。でも、アブドゥーラ・イブラヒムを録った際にはそれは必要なかった。プロデューサーとして重要なことは、ミスを求めるということ。ミスを残したいと、僕は思っている」
――エレクトロ/アンビエント(ギアボックスは日本人の畠山地平の作品もリリースしている)、アメリカーナのアルバムとか、今ギアボックスは作品傾向の間口を広げていますよね。それは予定通りの動きなのでしょうか?
「それはいい質問だな。最初は想定してなかった。ギアボックスは本来ピュア・ジャズで行くはずだったんだ。でも、ジャズ以外にもいい音楽があって、放っておけなかった」
――では、今は自分の耳に引っかかったものは、素直に出しちゃおうという感じですか。
「まったくそのとおり。やりたい音楽は常に出していきたいと思っている。とはいえ、心にはいつもジャズがあって、ギアボックスはジャズ・レーベルと思っていただいて構わない。ジャズってそもそも広くて、幅広いもの。ヒップホップとジャズが融合したものもジャズと言われるし、だからこそ面白いとも思うよね」
――ところで、どうしてギアボックスと命名したのでしょう。
「二つの理由がある。一つは僕がクラシック・カーが好きだから、変速機という名前がいいと思った.。2番めはターンテーブルって、ギアボックスと呼べるものだよね、33回転、45回転、78回転と変えられるでしょ。その二つが僕は好きだし、その二つに共通するのがギアボックスだった」
――ちなみに、車は何台お持ちですか。
「3台。うち、二つはクラシック・カーで、一つは古いランドローヴァーのディフェンダー。そしうて、1979年のフェラーリ」
――趣味は、幅広そうですね。
「うん、フライ・フィッシングも好き。森に行ってきのこを取るのも好きだ」
――ぼくはギアボックスのカタログを見てしなやかだなと思うと共に、音楽一直線ではない経歴や趣味の幅広さが反映しているとも感じます。
「うん、僕は常に新しいものを模索していたいんだ」
――そうでありつつ、録音にこだわり、ヴァイナルにもこだわるというのはクールですよね。
「それがなかくなったら、なにも残らない」
――ギアボックスはCDや配信もありますが、現在そこらへんはどういう比率になっていますか。
「それもいい質問だ。20はデジタル。そして、ヴァイナルとCDが40づつという感じだね。確かに今、デジタルは伸びてきている。一方で、ヴァイナルもね。CDは伸びていない」
――こうやって話を聞いていると、レコード会社という巨大な玩具を手にして、子供のように嬉々としてことにあたっているようにも思えます。
「(笑)それは正しい。趣味として始めたものだからね。2012、3年ごろから本格的にやるようになったものの、まさに玩具みたいなものだ。でも、玩具とはいえ、今は生活もかかっているのでシリアスになっているけどね」
――今カタログ数って、どのぐらいになりました。
「80枚出している」
――今のジャズの動きやジャズ界についてどう感じています?
「ギアボックスは最近のジャズの前を行こうとしているレーベルでもあるので、今の流れについては支持をしている。たとえば、ダンスやアフロ・ビートがまじっているのもいいと思う。もともと僕が考えているのは売れる音楽というのは、ダンスできる音楽であるということ。近年のジャズはダンスに合うような音楽が出てきていて、それによりジャズを聞かなかった層がジャズを聞くようになり、フォロワーが増えていくんじゃないかと思う」
――やっぱりジャズを知らない層に、ジャズを送り出したいという気持ちはありますか。
「うん、本当にそう思う」
――それで、ぼくはギアボックス新録ものを聞いて思うのは、リズムが立っているものが少なくないということです。それは意識するところで、あなたがドラマーだった視点が投影されているのか、とも思います。
「それは正しい。僕はドラムに詳しいので、どうしてもそういう方に注意は向く。だから、ドラムを意識したブツが増えちゃっているかもしれない」
――アメリカのジャズを送り出す一方、若い英国人のジャズも外に発信したいという気持ちもありますよね。
「そうだね。それは目標にしているところだ。最近だと、ビンカー&モーゼズとかスィオン・クロスとか。彼らは、英国以外でも注目を浴びている。
――今、また英国のジャズがおもしろくなっているとも思います。トゥモロー・ウォリアーズ(もともとは、1980年代からコートニー・パインのベーシストを務めていたゲイリー・クロスビー主宰のジャズ・ウォリアーズが発展した音楽教育機関)流れであるとか。
「うん、ギアボックスを一緒に立ち上げたアダム・シーフという人がいるけど、彼はもともとトゥモロー・ウォリアーズの先生をしていた。それで、そこからビンカー&モーゼズと知り合えるようになった。この若者たちのムーヴメントというのは興味深く、米国でもフライング・ロータス、ケンドリック・ラマー、カマシ・ワシントン、サンダーキャットなどがいて、その二つのシーンが今クロスオーヴァーしているのはすごく興味深い」
――そういうものに興味を持つ人にも、ギアボックスは今後注目のレーベルになりそうですね。
「そうだね。100パーセント、そう思う」











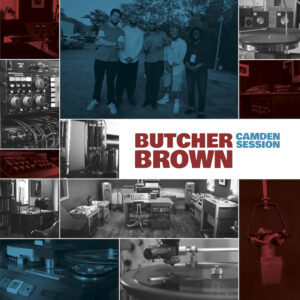
GearBoxからアルバム『First Light』をリリースした Village of the Sun(サイモン・ラトクリフkey、ビンカー・ゴールディングsax、モーゼス・ボイドds)が、2023.5.20(土)と5.21(日)六本木ビルボード・ライヴで2ステージ(16:30~/19:30~)のショーを予定。