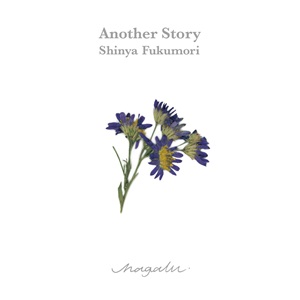インプロヴァイザーの立脚地 vol.20 蒼波花音
Text and photos by Akira Saito 齊藤聡
Interview:2024年5月14日 月花舎・ハリ書房(神保町)にて
静寂と静寂とのあわいにいるような蒼波花音(あおなみかのん)の演奏は、多くのリスナーを驚かせ続けている。彼女は自分自身について「つねづね遅れを取るけれど、その先に良いことがある」人生だなと感じているという。
クラリネット
特に音楽に熱中していたわけではない。ピアノを習ってはいたが、好きではなかった。だが、小学5年生のとき「サックスを始めよう」と決めてしまった。テレビで見たのだったか、見た目がカッコよくてピンときた。そして、卒業文集には中学に入ったらサックスをやると書いた。
中学で吹奏楽部に入部したら、サックス担当がたくさんいて、先輩にクラリネットはどうだとそそのかされた。そんなに自己主張が強いほうではなかったし、部活以外で演奏するという選択肢は思いつきもしなかった。そんなわけで、3年間はクラリネットを吹いた(普通のタイプと、小さいエス管の2種類)。クラリネットはアンブシュアが固めであり、このときに作った自分の音色がサックスに持ち替えてからも大きく影響することになる。もちろん当時は思いもよらないことだった。
サックスを始めた
高校で吹奏楽部に入り、彼女はようやく念願のアルトサックスを始めることができた。あとで振り返ってみて運が良かったなと思うのは、市川豊という素晴らしい顧問がいたことだ。市川は、日本におけるクラシックのサックス四重奏のさきがけともいうべき東京サクソフォン・アンサンブル(*1)を脱退したあと教員に就いた人だった。誰よりも早く朝練に来ており、蒼波もその音を聴きながら練習することができた。
彼女は真面目に練習したし、アンサンブルコンテストに出たりもした。だが、クラリネットの音色が抜けず、他の人のようにサックスを吹くことができなかった。そのことでずいぶん悩み、自己嫌悪にさいなまれたりもした。
ミュージシャンになろうとは思わなかった
高校生のとき、将来ミュージシャンになろうなどと考えていたわけではない。音大に入るというつもりもなかった。むしろ「人並みの人生」を送り、大学を出ないと社会で認められないとしか考えていなかった。彼女は普通大学に入るのだが、そのときも「なにも考えていなかった」。
ところが、彼女は急に「おかしくなった」。これまで本気でやってきたのはサックスだけなのだと気づいてのことである。それに至るきっかけのひとつは、友人からフィル・ウッズのアルバム『Warm Woods』を借りたことだ。ちゃんとジャズを聴いたのはそれがはじめてのこと。ウッズのサックスソロにすごいと思わされてしまった(自分自身の音とはまったく異なるとしても)。
蒼波は2年生で大学をやめた。そして悩んだ結果、洗足学園音楽大学に入ろうと決めた。洗足音大には受験生のためのコースが用意されており、彼女もそれを受講した。音楽理論に触れたのはそのときがはじめてだ。
大学
彼女は退学後1年間勉強して、洗足音大のジャズ科に入った。とはいえ、大学に入ったのも「ヤケクソ」。ともかく、まず目指すべきは即興演奏(=ジャズのアドリブ)ができるようになること。だが、ジャズ科同期の松原慎之介の演奏を聴いて、びっくりしてしまった。「意味がわからないくらい上手かった」。こういう人がいるんだと思い知らされ、絶望した。
そんなこともあって、彼女は自分自身について理解した。実はジャズの演奏に対する情熱がないこと。それは自分の中から出したいものではないこと。自分が同世代のすごい人たちのようになるリアリティがないこと。そして、この人たちがいれば自分は要らないのだという開き直りに至った―――自分に嘘をつくよりは良いだろう。
「ジャズっぽい音」を指向して音色を変えてみようともした。その結果は「迷走」である。「めちゃめちゃ下手」になり、何を信じていいのかさえもわからなくなった。
転機は、4年生のときに講師の山田拓児(サックス)の指導を受けたことだ。彼女にとっては、自分に合った吹き方を見つめ始めるきっかけになった。そして、苦しいところから一歩抜け出すことができた。
もうひとつの転機は、やはり4年生のときにライヴを観たことである。メンバーは福盛進也(ドラムス)、佐藤浩一(ピアノ)、ソンジェ・ソン(サックス)、イェウォン・シン(ヴォーカル)。場所は永福町のソノリウムだった。とても印象的な演奏で、彼女は感動した。その頃までドラムスの音があまり好きではなかったのだが、それは「ぜんぶ壊してくる音」だと捉えていたからだ。ところが、福盛の音は音階のある楽器と同じ土俵に立つようなものであり、彼女ははじめてドラムスを音楽だと感じることができた。
自分の中に変化が起きていた。そして、「十年後に福盛・佐藤と共演できるようにしよう」と決意した。
本格的な活動を始めた
「十年後」といいながら、卒業後すぐの2020年夏には福盛のアルバム『Another Story』に参加している(佐藤も参加)。twitter(X)に音源をアップしていたところ、それを聴いた福盛がDMをくれたのだった。録音にあたり、福盛は参加メンバーに「ジャズっぽい演奏だけはしないで」と指示した。蒼波にとって、音色や間など、その感覚が示唆するものは多かった。これも大きなきっかけになり、いまの彼女は音楽に対して「嘘をつかない」立ち位置にいる。
遠藤ふみ(ピアノ)とも共演するようになった。2021年11月に神保町試聴室でライヴをやったとき、西嶋徹(コントラバス)が聴きに来てくれた。西嶋は蒼波とも遠藤ともすでに知り合っていたが、ふたりの共演を観るのはこのときがはじめてだ。西嶋から「なにかやろう」との言葉を得て、それが翌2022年1月の「幽けき刻」初演につながった。
「幽けき刻」は西嶋、遠藤、蒼波のトリオであり、共演を重ねている。蒼波は「ふたりに支えられていて、私はなにもしていない」と話す。そして「かなりの自然体でいさせてもらっている」とも。ここでの成果もあってか、蒼波は、大きな音を出さないこと、音量以外のものに対して理想を追求することを大事に考えている。「正解はまだわからない」が、悩んだりも焦ったりもしていない。
インプロヴァイザーたち
沼尾翔子(ヴォーカル)とはじめて共演したとき、蒼波は、その声と調和したと感じた。蒼波は、自身のアルトサックスをいかに肉声に近いものとするか、それによってしか自分自身の音は作れない、と考えている。だから、演奏後に沼尾から「どっちの音かわからない瞬間があった」と言われたとき、嬉しさを覚えたという。
徳永将豪(アルトサックス)については、ここまで音色に特化した人がいるのかと驚いたという。楽器のコントロールがとても巧い。なにを考えているのだろうという不思議な存在である。
蒼波が好きなアルトサックス奏者は、一番にリー・コニッツ、二番は「いない」。だから大事にするものはアルトの声、そして旋律。ジャズ的に密度の高い音は苦手だ。「一音で蒼波花音だとわかる」と言われたい、と話す。
ディスク紹介
(*1)1980年7月に結成されたサックス四重奏グループ。結成時メンバーは、下地啓二(ソプラノサックス)、宗貞啓二(アルトサックス)、市川豊(テナーサックス)、佐々木雄二(バリトンサックス)。
(文中敬称略)
フリー・インプロヴィゼーション, 蒼波花音