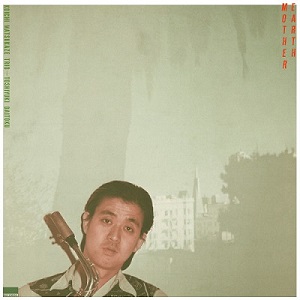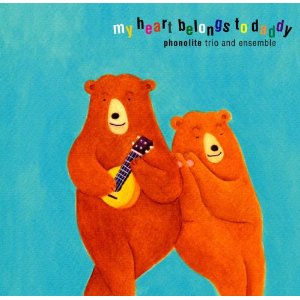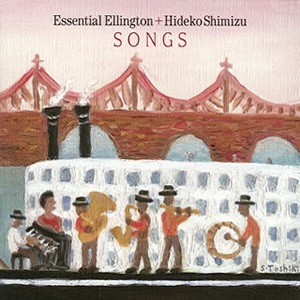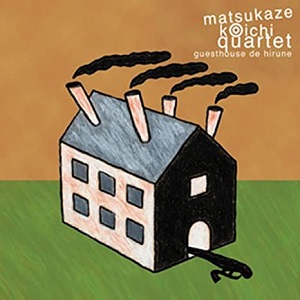Interview #247 松風鉱一
Text and photos by Akira Saito 齊藤聡
Supported by Naoko Saito and Fumi Yoshida 齋藤直子、吉田ふみ
Interviews:
2021年8月28日(土) 秋葉原・ホットミュージックスクール
2022年4月10日(日) 武蔵野市・井の頭恩賜公園
マルチリード奏者・松風鉱一(1948年、静岡市生まれ)。現在は自身のカルテット、渋谷毅オーケストラ、エッセンシャル・エリントン、サックス・ワークショップ、今村祐司グループなどで活動している。2018年に『Earth Mother』(1978年)、そしてこの2022年に『At The Room 427』(1975年)がロンドンのBBEレーベルから再発され、海外からも再評価の光が当てられている。あまりにも独創的なサウンドの魅力は昔もいまもまったく色あせていない。だが、本人はいまなお「ジャズの道が国道1号線だとしてもすごく細かった。だから色々やっていた。いまもその道が太くなったわけじゃない。何にも満足せずやってきた」と話す。
■ 大学
1968年、国立音大サックス科に入学。同期には梅津和時(サックス、クラリネット)、原田依幸(ピアノ)、大森明(サックス)、小宅珠実(フルート)、大井孝志(のちの貴司)(ヴァイブ)、板橋文夫(ピアノ)らがいる。古澤良治郎(ドラムス)、本田竹広(ピアノ)、中村誠一(サックス、クラリネット)、吉田憲司(トランペット)は大学の先輩にあたる。
2年生になって、板橋、津田俊司(ドラムス)とベースなしのトリオでジャズの練習をはじめた。その後他大学のジャズ研の仲間とバンドを組み、大学の芸術祭、新宿ピットインの朝の部、渋谷のオスカーなどで演奏した。十代の渡辺香津美(ギター)がバンドに入ったりもした。
中村誠一の紹介で、すでに国音を卒業して活躍していた山下洋輔(ピアノ)のところに行ったこともあった。松風は後年になって山下と共演するが、その頃はまだ「ペーペー」であり、一緒になにかを演る場所には立っていなかった。渡辺貞夫(サックス)が1965年にアメリカから帰国し、バークリー音楽院で学んだジャズの方法論を日本に持ち込んだことは有名だ。多くのジャズミュージシャンがそれを教わりに通っており、大学の先輩が教材を松風に見せてくれた。
当時、大学の授業はクラシックであり、ジャズなどという「不良の音楽」は教えていない。だが、不思議なことに「みんな上手かった」。個性というアーティストにとって不可欠な要素を育てるには、大学という機能はなくてもよかったのかもしれない。松風は、「変な癖がついては困るという発想」が浸透した日本の教育システムと対照的なものとして、アメリカの文化を引き合いに出す。かれも参加したゴダイゴのトミー・スナイダー(ドラムス)は、幼少期にタップダンスもピアノもギターもフルートも学んでいて、音楽表現に厚みがあった。日本のシステムと違い「これ一本」ではないということだ。
■ ソウルバンド、ロック、ポップス・・・
「これ一本」でないのは、なにも教育の話ばかりではない。松風は二十代から三十代のころの10年くらい、エボニーウエストというソウルバンドなどで活動した。サックスに加え、ギター、ベース、キーボード、ドラムス、それにヴォーカルが2、3人。ディスコのはしりと言ってもよい赤坂MUGEN(1968~86年)や、立川、福生、横浜、三沢でも演奏した。それらは米兵が繰り出す街でもあって、かれらが踊る前で、対バンのアメリカ人バンドたちと深夜の2時や3時まで演奏を続けた。「ディスコバンドがジュークボックスの代わり」だったのである。
クリエイションの竹田和夫(ギター)、外道の加納秀人(ギター)、もちろんゴダイゴのミッキー吉野(キーボード)といったロックのミュージシャンたちとも共演し、親密に付き合った。ポップス歌手の梓みちよのディナーショーでの演奏もある。
ジャズだけを聴いていると驚くべき幅広さのようにも思えるのだが、なにも特別なことではなかった。生計のことは置いておくとしても、これがやはり音楽になにか大事なものを与えている。だからこそ、松風は大学でジャズの方法論を学んでそれを続ける若い人たちに対して「ジャズだけを演っていてはだめだ」と言うのだろう。
■ 音色、奏法、楽器
現在使っている楽器は、アルトサックス5本(ヤマハ、セルマー2本、クランポン、ヤナギサワ)、テナーサックス3本(ヤナギサワ2本、セルマー)、ソプラノサックス2本(ヤナギサワ2本)、バリトンサックス1本(渋谷毅オーケストラでのみ使用)、クラリネット4本(ヤマハ2本、クランポン、セルマー)、バスクラリネット1本、たくさんのフルート、それにバンブーサックス。とても多いが、職人がしっかりと調整したものばかりであり、それぞれの違いを大事にしている。
松風鉱一のサックスはささやくようで、かすれてささくれた独特の音色をもっている。だが、本人はその音色について「ねらっているわけじゃない。高倉健がいくら好きだって似たようにはしゃべれないだろう?」と言う。つまり、このようになろうと思って出す音色ではなく、訓練によって獲得した自分自身の声なのだ。かれはR&Bのサックス奏者キング・カーティスの明るい音が好きだと話すが、当然ながら、だからといって松風鉱一の音色はカーティスの音色ではない。自分の声だから時間とともに変化もする。二十代後半のときの初リーダー作『At The Room 427』(1975年)で聴くことができる「ガサツな音」はもう出ないそうでおもしろい。音色が自分の音楽の生命であり発想の源ということである。
フルートもつねに使う楽器のひとつだ。特に初期の録音からはエリック・ドルフィーの影を感じるのだが、実際にヒントを得てもいた(たとえば、森山威男『Smile』に収められた松風のオリジナル<Step>)。ドルフィーの跳躍するフレージングは、マルセル・モイーズ(多くの練習曲を書いたフランスのフルート奏者)のメソッドが影響していたにちがいないと松風は指摘する。フルートはタンポ間の距離が短くてとくに運動性が高く、跳ぶと、それによりリズムが出るんだ、と。なお、ドルフィーが現代音楽に傾倒していたことは、イタリアの現代音楽のフルート奏者セヴェリーノ・ガッゼローニから取った<Gazzelloni>という曲からも推察できる(『Out to Lunch』に収録)。
■ アメリカ
かつてアメリカに移り住む機会もあった。
同級生の原田依幸と梅津和時がロフトジャズ全盛のニューヨークに渡り、ベースのウィリアム・パーカーらと『生活向上委員会ニューヨーク支部』(1975年)を吹き込む。(余談だが、梅津が現地でサニー・マレイのバンドに参加したとき、前任者がデイヴィッド・マレイ、そして梅津のあとがケシャヴァン・マスラク(現ケニー・ミリオンズ)だった。)一方、日本に残って「生向委」の名前を借りた松風は1976年に『生活向上委員会ライブ・イン・益田』を録音する。「生向委」にはギターの渡辺香津美が入ったこともあったという。
実は、原田には一緒に渡米しようと声を掛けられていた。松風は誘いを断った。曰く、「アメリカには上手い人がたくさんいるし、自分はのんびりやるし、ヘドロの中でもがいてやろうとは思わない。もし行ったとしたらとっくに音楽をやめていただろうね。3年を30年でやるのでいい。好きなことはゆっくりやるのがいちばんだ」と。
■ 人のつながり
大学では「ひとり、ひとりと共演する仲間が増えていった」、「先輩たちはやさしかった」と松風は話す。今よりも横と縦のつながりが濃密だったのだ。それは卒業してからもずっとそうだった。
当時、草野球も宴会も頻繁にしていたという。近くの港で買ってきた魚で手巻き寿司を作ったり、ゴダイゴで中国ツアーをしたとき食べた味が忘れられずチャーシューを仕込んで肉まんを作ったり。仲間のおのおのが得意な料理を持ち込んだ。演奏旅行のブルートレインでも宴会。「同年代の仲良しがそのままみんな歳を取った感じだよ」と笑う。
渋谷毅(ピアノ)との接点もゆるやかなつながりの中でできた。『Earth Mother』(1978年)の録音のとき、川端民生(ベース)の家に泊まった渋谷が、その翌日に二日酔いで録音を見にきたのだった。松風自身はそのことを覚えていないというのがまた愉快である。
仲間の中には国安良夫(サックス)もいて、森山威男(ドラムス)に松風を紹介した。それが森山のアルバム『Smile』(1980年)への参加、そして逆に松風の『Good Nature』(1981年)への森山の参加につながった。
サックス・ワークショップはその時期、70年代後半~80年代前半に活動していたグループだ(1982年の演奏が『Sax Workshop』としてリリースされている)。3人のサックス奏者として松風、梅津和時、沢井原兒に加え、松井洋(ギター)、清水くるみ(ピアノ)、山崎弘一(ベース)、宮沢高史(ドラムス)というメンバーであり、最近も基本的に同じメンバーでまた活動している(ドラムスが宮坂高史から本田珠也に変更されたのみ)。これもまた、我が道を行く同じ面々で続けることが重要だということにちがいない。内田修氏(※ジャズ愛好家として知られた医師)がおもしろがって実現した合歓ジャズイン(三重県)のステージでは、大森明も加わりサックス4人で<Lover Man>なんかを演ったという。
■ 渋谷毅オーケストラ
やはり内田修氏により、1986年、浜松で「高柳昌行の世界」公演が企画された。肝心の高柳昌行(ギター)は体調不良で演奏できなかったが、これが渋谷毅オーケストラ(渋オケ)の原型となった。アレンジが渋谷毅、アルトサックスは森剣治、トロンボーンは松本治、ドラムスは山木秀夫(※このステージでベースを弾いた齋藤徹によればドラムスは山崎比呂志であり、ふたりの記憶が食い違っている)。松風はその前に高柳とシャンソンのバックで共演したことがあり、もちろんそのときの演奏はフリーではなかった。
翌1987年11月、新宿ピットインで正式に渋オケが発足した。当初は武田和命(サックス)や吉田哲治(トランペット)が入り、ギターは廣木光一と石渡明廣のふたり、のちに石渡ひとりとなった。林栄一はいちど辞めてまた参加し、途中でサックスの臼庭潤や峰厚介、津上研太が加わった。そして亡くなった川端民生のあとに上村勝正、古澤良治郎のあとに外山明が入り、現在につながっている。
エッセンシャル・エリントンは、渋オケとは異なるサウンドを指向するものとして、渋谷、峰、松風、さらに関島岳郎(チューバ)を加えた4人を中心に結成されたグループである。
最近ではメンバーも演奏される曲もほとんど変わっていない。しかし、聴くたびに素晴らしさに震えてしまう。それが渋オケである。
■ フリー、方法論の探求
松風鉱一自身が「フリージャズ」や「自由即興」を標榜することは皆無である。その一方で、ライヴでは「いつもぶちこわしているから、フリーといえばフリー」だとも言う。たとえば、三拍子のオリジナル曲<w.w.w.>の終盤なんてそうだろう、踏みはずすのが愉しいんだ、と。
こうなるとどう呼ぶかなど本質的ではないことに気付かされる。
方法論の探求を中央線の路線にたとえたりもする。定められた音階ばかりを使うのは中央特快のようなもの、東中野駅を飛ばしている。寄り道がおもしろいんだし、間の音をどのように使うか。敢えて決まっている中で出鱈目に近い音を効かせることもある。
探求は若いときばかりではない。かれはコロナ禍の中でもいろいろと試し、コードとスケールの新たな関係を作ったので広めたいなあと話している(実際に聴く機会が楽しみでならない)。半世紀近く前に吹き込んだ初リーダー作『At The Room 427』をいまになって聴き返してあらたなアイデアを発見したり、既存の方法論は大体間違えて解釈するからおもしろいとまで言ってのけたりもする。こういった、行きつ戻りつの蛇行もまた松風鉱一の音楽哲学にちがいない。
かれは、若いときに誰もが指向する「より強く、より速く、より高く」よりも、長い目でみればマイペースで血肉化するほうがよいと話す。
■ トリオからカルテット、そして+1
1990年前後にクリヤマコト(ピアノ)、水谷浩章(ベース)、小山彰太(ドラムス)とのカルテットで2、3年間やったあと、クリヤが辞めてトリオになった(『A Day in Aketa』、1993・94年録音)。南博(ピアノ)もときどき参加している。
同時期には板谷博(トロンボーン)のギルティ・フィジックでも活動しており、2枚のとてもユニークなアルバムを残した。しかし、1996年に板谷が自死を選び、新たなサウンドが作り続けられることはなかった。
トリオにギターの三好功郎を加えて吹き込んだアルバムが『万華鏡』(1997年録音)である。三好とはギルティ・フィジックで一緒に演っていた。ギターとの共演は新しい試みではなかった。もともと渡辺香津美とも演っていたし、松宮幹彦とも活動している。津村和彦や加藤崇之とのコラボレーションはそのあとである。
ドラマーが小山彰太から外山明に変わったとき、意外にも、松風は「最初はすごく演りにくくて、ちょっとカルチャーショックだった」という。だから「悔しくて続けた」ことが、いまの松風鉱一カルテットに欠かせない音と化しているのは、やはり愉快なことにちがいない。
カルテットに石田幹雄(ピアノ)を入れたのは、渋オケでサッポロ・シティ・ジャズに出たときがきっかけだった。主催者に薦められて、瀬尾高志(ベース)、竹村一哲(ドラムス)とのトリオでピアノを弾く石田を観た。松風は「いいピアノだ」と思った。
このカルテットでは、2005年に『Private Notes』と『Guesthouse De Hirune』を吹き込んで以来アルバムを作っていない。今後やるとしたらライヴの吹き込みだろうと松風は断言する。ライヴこそが一期一会で良いサウンドを提供するのだという自負であろう。
【参考資料】
『季刊・ジャズ批評別冊 私の好きな一枚のジャズ・レコード』(ジャズ批評社、1981年)
寒川光一郎「ジャズ人―寒川光一郎の東方JAZZ見聞録 松風鉱一(前編、後編)」(『JAZZLIFE』、1994年10月号・11月号)
望月由美「音の見える風景 Chapter 33. 松風鉱一」(『JazzTokyo』、Vol. 199、2014年6月)
田村睦『ジャズから見る国立音大の風景』(自主出版、2020年)
(文中敬称略)
生活向上委員会, エッセンシャル・エリントン, 渋谷毅オーケストラ, 松風鉱一, 板谷博ギルティ・フィジック, サックス・ワークショップ