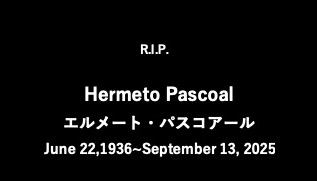Pascoal作品回想 by 徳永伸一
いきなりタイトルからズレるのだけど、エルメート・パスコアールが亡くなって、真っ先に思い出すのはやはり、自分が体験した3回の来日公演の強烈な印象だ。1度目は2002年によみうりランド・オープンシアターEASTで開催されたTrue People`s CELEBRATIONというイベント。1979年のライブアンダーザスカイ以来、23年ぶりの来日だったらしい。
当時の映像がYouTubeにアップされていた。
みんなで筒を持ってパカパカやって、御大はヤカンを吹く。これぞパスコアール!
トリのMedeski Martin & Woodの1つ前だったが、自分としてはパスコアール目当てだったし、お腹いっぱいという感じになって最後までは残らず会場を後にしたのを覚えている。イベント終了後は駅の混雑が大変なことになるから、というのが大きな理由だが、それにしたって、安くないチケットを買ってそんな気になったのは初めての経験で、それだけ生パスコアール初体験のインパクトが大きかったのだと思われる。
2回目は2年後の2004年。
こちらも映像があった。
ウネウネと続く摩訶不思議なフレーズをボーカルとアコーディオンのユニゾンで。これもまた、パスコアールならではの世界。
3回目は少し間が空いて2017年。当時のインタビュー記事が残っていた。
https://www-shibuya.jp/feature/007419.php
若い頃から白髪で年齢不詳のパスコアールだが、80歳と聞いて驚いた記憶がある。意外にも?洗練されたバンドサウンドのカッコ良さもさることながら、ステージ上で飛び跳ねるように演奏していたパスコアールを観て、音楽の妖精だと思った。
遡ると、パスコアールの音楽に初めて触れたのは、1980年代半ばのことだ。当時の自分はフュージョンからジャズに興味が移行しつつ、フランク・ザッパを聴き狂っていたので、CDショップで「ブラジルのザッパ」と書かれたポップに惹かれて購入した。乱暴なキャッチコピーだが、あながち間違ってはいない。複雑だけどポップ。もちろん気に入った。ただ、そのままCDを買い集めようという気になるまでには至らなかった。予算に制約がある中で、最優先で聴きたくなるミュージシャンではなかったということだ。続々とCD化されるザッパの旧譜を揃えるだけで手一杯だったこともある。
というわけで、自分は熱心なパスコアールのリスナーであったとは言い難い。パスコアールの音楽との関わり方、という観点であらためて振り返ってみると、より大きいのは作曲家としてのパスコアールである。実際、本人の演奏より、他の奏者が演奏するパスコアール作品に触れた量の方が圧倒的に多い。
作曲家としてのパスコアールを初めてきちんと認識したのが、こちらの演奏だ。
ブラジルが誇る世界最強クラシックギターデュオ、アサド兄弟が1985年にリリースしたメジャーデビュー作に収録。自分が買ったのは1987年くらいだろうか。渋谷のWAVEでクラシックギターのCDを漁っているときに見つけた。他の収録曲にも目を向けると、目玉はなんと言ってもピアソラが彼らのために作曲した「タンゴ組曲」の世界初録音だろう。しかし当時のピアソラはクラシック業界ではそれほど有名ではなかったから、国内盤はそれを強くアピールしている風ではなくて、アルバムの邦題はヒナステラ作品から取られた「たそがれの牧歌」である。ヒナステラとてさほど知名度があるとは思えないが、他はブローウェル、ニャタリ、パスコアール、セルジオ・アサド(アサド兄弟の兄のの方)らの作品ということで、当時の日本で相対的にもっとも知られていると見なされたのだろうか。自分としては、ピアソラも気になったが、やはり録音が少なかったブローウェル作品を収録していることが決め手になって購入した。
ちなみにピアソラについては、モントリオールジャズフェスティバルへの出演が1984年、ゲイリー・バートンとの共演で注目された来日公演が1986年。今や大御所のクラシックギタリスト、福田進一がアルバム「21世紀のタンゴ」にピアソラ作品を収録したのが1987年だ。1980年代後半には、すでにジャズファンやクラシックファンの間でも知る人ぞ知る存在ではあった。時折り、「生前(1992年没)はほとんど無名だった」などと主張する人を見かけるが、単にその人が知らなかっただけである。
さて肝心のパスコアール作品「Bebe」は、このアルバムの中でやや異彩を放っている。ノンサッチというレーベルならではなのだろうが、一応「クラシック音楽」にカテゴライズされるアルバムの中に、パスコアール作品が収録された例は貴重で、おそらくメジャーレーベルではこれが初めてだったろうし、その後もわずかではないか。
美しい旋律はアレンジ次第でクラシック作品として成立しそうではあるのだが、アサドはオリジナル版のメランコリックなイメージを吹っ飛ばすような軽快さで駆け抜ける。南米音楽特有のグルーヴとスピード感、そして一糸乱れぬ精緻なアンサンブルの共存が彼らの持ち味だ。「タンゴ組曲」にしても、その演奏速度と完璧な技巧により、他のギタリスト達がしばらく手を出しづらくなってしまったほどである(本人達も速すぎたと思ったのか、後の再録音では少しテンポを落としている)。
編曲を担当するアサド兄は作曲家でもあるから、「Bebe」終盤のフレーズなどはほぼ創作だろう。即興的にも聞こえるが、彼らはステージ上ではあくまでクラシック奏者として振舞い、ジャズミュージシャンのような即興演奏はしない。楽譜通りの演奏で、聴衆を熱狂させるのだ。
「Bebe」の演奏は彼らが最速だろうと思っていたが、アンドレ・メーマリとアミルトン・ジ・オランダが記録更新した。2011年、アルバム「gismontipascoal」での演奏だ。
こちらはテクニシャンどうしが勢いに任せて弾いたらこうなりました、という雰囲気。アルバム全体を通しての印象も、即興的要素が多めに感じられ、アサドとの対比が興味深い。どちらのアプローチも許容する、パスコアール作品の「懐の深さ」 を表していると言えるだろう。
その流れでもう一つ紹介したいのが、ヴァイオリニスト木村まりの演奏だ。
ピアノ伴奏のように聴こえるが、ピアニストではなく、即興演奏システムMAXとの共演である。サブハーモニクス奏法(G弦開放より低い音を発する技法)など現代音楽の高度な技法を駆使した即興演奏で知られる彼女ならではの演奏だ。一度だけ彼女のリサイタルを聴く機会があったが、怒涛の超絶技巧と笑顔を絶やさない軽いノリのMCのギャップが印象的だった。シリアスなプログラムなのに遊び心すら感じられ、パスコアールに近い精神性を備えた音楽家のようにも思われる。
パスコアール作品における1つの重要な側面は、ある種の身体性ではないかと思う。本人のユニークなパフォーマンスにも通じるのだが、楽曲そのものに、演奏者のフィジカルな衝動を呼び醒ます要素が散りばめられているように思われる。わかりやすく顕著なのが、幾多のミュージシャンにカバーされているChorinjo Pra Eleだ。個人的に最も気に入っている演奏が、かのリシャール・ガリアーノとブラジル人バンドリン奏者アミルトン・ジ・オランダによるこちらである。
ぜひ最後までじっくり聴いて、呆気に取られて欲しい。ガリアーノは中途半端にピアソラをカバーする一方で(アルゼンチンのトップ奏者達の演奏や、日本の精鋭を集めた鬼怒無月キンテートなども聴いてみて欲しい)、南米の凄腕奏者達と共にこうした素晴らしい演奏を繰り広げていたのだ。同じ動画の中で共演しているベネズエラ人ヴァイオリニスト&パーカッショニストの演奏も必聴だ。Chorinho Pra Eleについては、盟友ミッシェル・ポルタルとのデュオでも凄いテンポで演奏しているのだが、ブラジルの血が加わった演奏は一味も二味も違うと思わせる。
というわけで、アミルトンがパスコアール本人と共演したヴァージョンも確認しておきたい。
パスコアールとアミルトンに挟まれて比較的地味な役回りに徹しているマルコ・ペレイラもブラジルの名ギタリストで、優れた作曲家としても知られている。これ以上ない組み合わせによる王道の演奏だ。
とはいえ、ブラジル人だけがパスコアール作品の魅力を最大限発揮できる、とは思わない。パスコアール作品はもっとグローバルで自由で、豊かな包容力をを備えている。最後に、個人的な大好きな演奏をもう1つだけ紹介しておきたい。saigenjiのライブを初めて観たとき、ローマ字表記だし日系ブラジル人だろうか、と真剣に思ったが、純然たる日本産(+香港在住経験があるらしい)である。この何気なさが良いのだ(最後はやっぱりスリリングだけど)。弾き語りでこんな風にさらりと表現することも可能なんだ、と率直に驚嘆した。パスコアールのマインドに共振するミュージシャンは世界中にいて、これからも果てしなく、名演が生み出されていくのだろう。
エルメート・パスコアール, ピアソラ, フランク・ザッパ, Saigenji, 木村まり, アサド兄弟, アンドレ・メーマリ, アミルトン・ジ・オランダ, リシャール・ガリアーノ, マルコ・ペレイラ