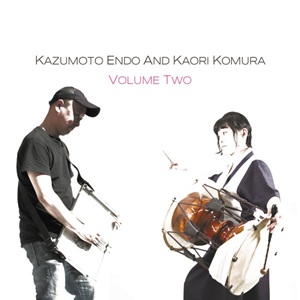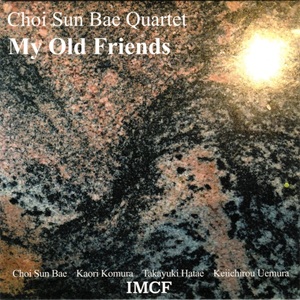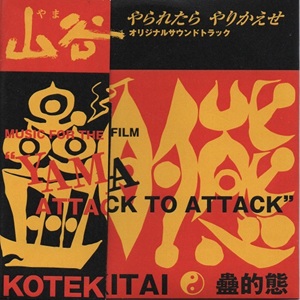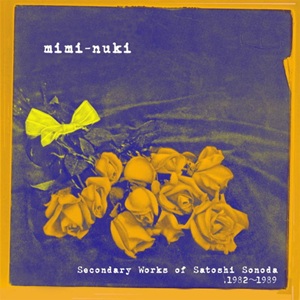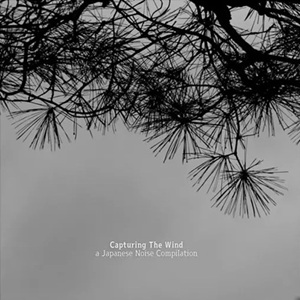インプロヴァイザーの立脚地 vol.33 香村かをり
Text and photos by Akira Saito 齊藤聡
Interview:2025年6月17日 サムライ(新宿)にて
香村かをりは即興演奏をすることで渇望を鎮めているという。だから、彼女は自分自身のことをミュージシャンだとは思っていない。
学園祭バンドからハードコアパンクバンドへ
十代のときにドラムを始めた。「学園祭バンド」である。中高一貫の女子高でドラムを演る人なんて、あまりいなかった。やがて大学生たちとの交流が始まり、慶応大の人に声をかけられてバンド「闇射(あんしゃ)」を結成した。リーダーは上智大生の大熊ワタルであり、まだ19歳。のちにチンドンの演奏やシカラムータなどで知られるようになる大熊だが、当時はまだクラリネットではなくキーボードを演奏し、バンド・絶対零度での活動を開始したばかり。その縁があって、香村は吉祥寺マイナーではじめてライヴを演った。いわゆるアンダーグラウンド音楽であるが、当時の呼称は商業主義へのアンチテーゼとして「マイナー音楽」。そして、このバンドは寺山修司の天井桟敷にインスパイアされた「どろどろした暗い曲」をもとにしており、半分はフリーで即興の要素があった。自分たちだけでなく、白石民夫(サックス)、灰野敬二(ギター等)、山崎春美(ヴォーカル)など、吉祥寺マイナーにはそのような人が多かった。出てくる音を自由に出すのは、彼女にとって自然なことだった。
やがてバンドは解散し、香村はフリーとなった。その頃、日比谷野外音楽堂でイヴェント「天国注射の昼」が3回開かれた(1981、83年)。主催は新宿ゴールデン街にあったバー・HAVANA MOONと雑誌『HEAVEN』。香村もHAVANA MOONに出入りしていたし、ステージの端ッコにも立つことができた。HAVANA MOONには竹田賢一(大正琴)が毎日のように顔を出し、さまざまな分野の人たちが出入りする場だった。余談だが、ボトルキープが3か月を過ぎたウイスキーをひとつのボトルに集めて「救済ボトル」と呼び、ママが認める「貧乏アーティスト」だけが飲んでいい決まりがあった。認定されたのは石渡明廣(ギター)や今井次郎(ベース、劇団時々自動等)といった人たちだ。
まだ香村は高校生だったが、このような活動を変だとは思っていなかったし、そのために浮いてしまうような校風でもなかった―――もっとも、あとになって、最初の学園祭バンドの仲間が「どうしてあんな不良と付き合っているのか」と他の生徒から言われていたと知るのだが。
高校は進学校だが、卒業するとき、親に「みんなが行くからなんていう理由なら大学のカネは出さない」と言われ保留した。進学しなかったのは学年で香村ひとり。
そのころ、HAVANA MOONで知り合った横山茂久(のちのSAKEVI)(ヴォーカル)に「バンド作ったんだけどドラムがいないからやってくんない?」と声をかけられ、G.I.S.M.に入った。のちに世界的にも有名になるハードコアパンクバンドだが、香村がいたのは最初の1年だけだ。ドラムを演ったのもこのあたりまで。香村はひとりになった。
サムルノリ
二十歳のころから、香村のなかで自身の音楽に対する疑問が大きくなってきていた―――自分の即興とは、ただ滅茶苦茶を演っているだけではないのか。形あるものを壊すにしても、もとより壊すものを持っていないのではないか、上手くもないのに。それよりも別のものを追求すべきではないのか。自分の根源とはなんなのか、と。
香村が聴くようになったのは民族音楽だ。身体と直結する音楽を探そうとしていた。日本人であることを意識して和胡弓を習ったりもしてみた。そんなときに出会ったのが、韓国打楽器アンサンブルのサムルノリだ。1983年公演のポスターが、HAVANA MOONにずっと貼ってあり気になっていた(*1)。念願かなって観ることができたのは86年のこと。世田谷美術館開館記念のライヴには満員の観客。香村はなにがなんだかわからないままに呆然と観た。そして一晩寝て起きたら、頭の中がサムルノリの音でいっぱいになっていた。毎日、寝ても覚めてもサムルノリ。六本木Waveで探したらCD(*2)が見つかった。朝から晩までそればかりを聴いていた。
香村は、民族音楽を知りたければ韓国に行くのが当たり前だと考えた。演奏家になりたいわけではない。好きだから行きたい、音の中にひたっていたい。2年間貯金してようやく渡韓できたのは、ソウルオリンピック直前の1988年、25歳になる年である。
「その時の衝撃は、今も忘れることが出来ない。その日以降、寝ても覚めても『サムルノリ』の音が離れず、あの地(韓国)に行かないと病気になる、そんな気しかしなかった。そしてカバン一つもって海を越えた。」(*3)
韓国で音大の伝統音楽科に入って打楽器を学んだことも、大学院に進んだことも、第一の目的はビザを取って滞在することだ。通訳や翻訳で生活費を稼ぎ、ビザが取れなくなってからは観光ビザを使って日韓を行き来する生活をつづけた。
金徳洙
渡韓前にも、サムルノリのリーダー・金徳洙(キム・ドクス)が来日時に開くワークショップに出たりもしたが、やはり韓国でも金徳洙のもとに足を運んだ。もとより放浪芸人の出身、カネを取ってのレッスンなどはしない人である。旅に同行する中で芸を受け継いでゆくのが伝統、一緒に演る者はすべてプロという前提。集まる人たちはなにかできることを演り、上手くできなければ端ッコにいる。肩車の子どもですらなにかに出演すればギャラが出る。香村も金徳洙のいる場に出入りした。気が向けばなにかを教えてくれた。
1993年になり、金徳洙を中心とする集団が法人化することとなった。金が「チャンゴのバチ一本まで法人の財産として登録した。サムルノリを世界的な位置にまで引き上げる過程において、団体の運営をガラス張りにすることは必要不可欠なステップなのだ」(*4)と書いたように、すべてが登録されたが、そのために稽古場はプロとなるべく登録された正式な弟子以外自由な出入りができない場となってしまった。先生たちも散り散りになった。香村は正式な弟子になる道を絶たれ、落胆した。(金徳洙から個人的に弟子と認めてもらえたのはあとになってのことだ。)
もとよりサムルノリは固有のグループ名だが、人気が出るにつれて音楽のジャンルとして認知されつつあった。また金徳洙の周囲の先生たちがそれぞれグループを作り、その傾向がさらに強くなった。しかし、香村にとって大事だったのは「ポール・マッカートニーが聴きたいんじゃない、ビートルズが聴きたいんだ」だったのだ。
それでも香村は韓国の音の中にいたかった。韓国各地のシャーマン儀式を追いかけ、東海岸別神クッの金石出(キム・ソクチュル)(ホジョク、打楽器)にかわいがってもらい、儀式中の宿舎に寝泊まりするなどしたのもこの時期だ。
だが、三十代も後半になって、観光ビザで日韓を行き来する生活に疲れてしまった。ふたたびビザを取るには結婚するしかないと考えた。それはあくまで手段のはずだったが、割り切って結婚に合意してくれた友人との間に子どもができてしまった。計画になかったとはいえ香村はうれしかった。里帰り出産するつもりで日本に帰国したところ、夫も貿易の事業を始めるといって日本に来た。これではビザを取ることができない。香村はふたたび落胆し、韓国音楽どころか韓国ということばを口に出すことすらできなくなった。ようやく落ち着いてきたのは、子育てを続けて数年が経ってからのことだ。
結局、韓国には2000年までの12年間滞在した。
ふたたび韓国音楽
2011年になり、再会した金徳洙が「かをり、趣味でもいいからチャンゴを演りなさい」と言ってくれた。調布に住んでいた香村は、近所の市民会館の音楽室を借り、ひとりでチャンゴの練習を始めた。それも味気ないのでチラシを撒いたら、興味を覚えた人が次々と集まってきた。2014年にサークル「調布サムルノリ」ができたのはそのようなわけだ。楽しくなり、現在まで11年も続いている(*5)。
サークルは練習の場だが、一方で香村自身も在日本大韓民国民団のイヴェントや、旧知の風巻隆(パーカッション)がたまに呼んでくれる場で演奏も始めていた。2019年にトランペットの崔善培(チェ・ソンベ)が来日する際にライヴを企画したのは、韓国でかわいがってもらったことへの恩返しだった。5か所のブッキングに加え、カバン持ちと通訳をこなし、裏方に徹するつもりだった。ところが、崔がとつぜん「かをりも一緒に演奏しよう」と言い出した。かつてサムルノリのエージェント「セカンド・ウインド・ミュージック」の社長を務めた稲岡邦彌(本誌編集長)のあと押しもあり、Bitches Brew(横浜)での共演相手は、崔、大友良英(ギター)となった。大友は韓国フリージャズを作った姜泰煥トリオの崔さんだからと言って、多忙な中で駆けつけてくれたのだった。演奏後に「おもしろいから続けてみれば?」と大友に言われたことで、香村は「調子に乗ってしまった(笑)」。
これを機に店主・杉田誠一の理解もあり、1年間、Bitches Brewでライヴを演ると決心した。月に1回異なる相手を決め、デュオで即興演奏を行うわけである。即興演奏が、サムルノリを演ることができない心の空洞を埋めてくれた。だから、香村にとって崔、稲岡、杉田、そしてその気にさせてくれた大友は恩人だ。
デュオシリーズを続けているうちに、演奏のオファーも入ってくるようになった。
即興演奏
香村自身の音楽的素養はサムルノリのみ。一方で即興演奏に使われるものはほとんど西洋楽器であり、理論がまったく異なる。香村は「わからない」ところから始めた。杉田には、ライヴのたびに叱られた。香村が共演者の音を「聴いていない」からだ。
だが、ライヴを重ねていくうちに杉田にも「よくなった」と声をかけてもらえるようになってきた。2022年の崔のツアーの始め、旧知の梅津和時(リード)は演奏後に「これなら(ツアーで回る技量として)大丈夫だと思った」と、また初めて共演した井野信義(ベース)は驚くようなタイミングで銅鑼の音が入ることを「おもしろい!」と言ってくれた。
あとになって、杉田の言いたいことがわかるようになってきた。サムルノリを演れない自分自身は飢えるような状態にあって、湧き出てくる渇望に衝き動かされているだけだった。それが、回を重ねるごとに人の音が聞こえるようになり、返したり合わせたりできるようになった。求められていることを察することもできる。だが、「上手になってしまった」。それでいいのか、いまも迷いがある。「まるでミュージシャンみたいだ(笑)」。
香村の原点は渇望であり、思う存分なにかを吐き出したい。依然として渇望は感じている。満たされていないから、いまでも演奏を続けることができている。「得体の知れないどろどろしたもの」があって、演奏をすることで落ち着くことができる。すなわち、音で渇望を鎮めているわけである。だから、香村は自分自身のことをミュージシャンだとは思っていない―――ただ「音を出す人」だ。
アルバム紹介
(*1)サムルノリの初来日公演は1982年のことであり、翌83年には「サムルノリ」名を冠したコンサートが開かれている。(四物遊撃『サムルノリ宣言』、リットーミュージック、1988年)
(*2)サムルノリ『四物遊撃』(CBS/Sony、1986年)
(*3)香村かをり「韓国伝統打楽器演奏『サムルノリ』―異国の音楽はいかに日本に広まったか」(2018年度放送大学卒業研究論文)
(*4)キム・ドクス『世界を打ち鳴らせ サムルノリ半世紀』(岩波書店、2009年)
(*5)サークルの活動がきっかけとなり、香村は2019年からプンムル(農楽)にも参加している。サムルノリがプンムルから「舞台音楽化」した過程とは逆ヴェクトルの動きである。(拙稿「プンムルと追悼―演奏を通じた加害の歴史の語りなおし」、『オフショア』第三号、2023年)
(文中敬称略)
香村かをり, フリー・インプロヴィゼーション