”ジャズの楽園 日本”の謎
ジャズはなぜ日本人の心に響くのか?
text: Atzko Kohashi 小橋敦子
photo above: courtesy of Tony Overwater
このエッセイは、2025年7月6日、米web-magazine All About Jazz (AAJ) に掲載されたものです。AAJとの提携により翻訳、転載するものです。原文は;https://www.allaboutjazz.com/why-is-japan-a-jazz-paradise-or-why-the-japanese-feel-at-home-in-jazz

なぜ日本はこんなにもジャズ好きな国なのか?
ブルーノート、リバーサイド、プレスティッジ――これほどまでに多くのクラシックなジャズ・アルバムを再発してきた国は、世界でも日本をおいて他にありません。名盤の数々が、澄みきった音質でリマスタリングされ、紙ジャケット仕様やSHM-CD、SACDといった超高音質フォーマットで次々と蘇っているのです。中には、アメリカ本国ですら長らく廃盤になっていた作品が、日本でのみ復刻されるケースさえあります。
たとえば、ビル・エヴァンスの名盤『ワルツ・フォー・デビィ』や『サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード』は、何度も再発されてきましたが、この秋にもUHQCD版として再リリースされる予定です。
しかも話はレコードだけにとどまりません。日本ではジャズに関する書籍の種類も驚くほど豊富です。伝記の翻訳、百科事典、演奏理論の解説書、さらには『教養としてのジャズ』のようなタイトルの本まで並んでいます。ここまでくると、ジャズはもはや「一部のマニアの趣味」などではなく、確かな文化的存在感をもっていると言ってよいでしょう。
ジャズ喫茶やライブハウスは、地方の小都市にまで存在しており、東京には90〜100軒ほどものジャズクラブがあるとされます。全国的に見れば、ジャズの生演奏が楽しめる場所は数百にのぼるとも言われており、これは世界的に見てもかなり突出した数字です。
さらに日本では、ジャズはクラブやコンサートホールだけで流れているわけではありません。ショッピングモール、百貨店、レストラン、カフェ、果てはラーメン屋にまで――日常のあらゆる場面で、ジャズは当たり前のように流れています。横浜の小さなラーメン店でコルトレーンの<マイ・フェイヴァリット・シングス>が流れているのを耳にしたときは、さすがに驚きました。でも、周囲の誰も気に留める様子はなく、ジャズがむしろ空間に自然に溶け込んでいるようでした。それを本当に「聴いて」いたのかどうかはともかくとして。
では、なぜこれほどまでに日本でジャズが生きているのでしょうか?
なぜ日本のリスナーは、ここまで深くジャズとつながっているのでしょうか?
日本人に本当にジャズが理解できるのか?
――そんな疑問を抱くのも無理はありません。というのも、日本は江戸時代(1639年~1854年)に200年以上もの間、鎖国によって西洋文化からほぼ完全に隔絶されていたからです。その時代、西洋音楽などほとんど存在しませんでした。
西洋音楽が本格的に日本に入ってきたのは、19世紀後半の明治維新以降のこと。クラシック音楽を皮切りに、やがてジャズやポップスも日本人の生活に少しずつ浸透していきました。
『カインド・オブ・ブルー』と日本の水墨画
私がニューヨークに住んでいた1994年から2001年の間、アメリカ人からよくこんな質問を受けました。
「なぜ日本ではそんなにジャズが人気なんだ?あんな遠く離れた島国の人たちに、本当にこの音楽が理解できるの?」
私の答えはとてもシンプルでした。
「ジャズと日本の美意識は、深いところで通じ合っているからです。」
『カインド・オブ・ブルー』のライナーノーツの中で、ビル・エヴァンスはこう書いています。
「日本の視覚芸術に、水墨画というものがある。そこでは、芸術家は常に即興を求められる。彼は特別な筆と黒い水のような絵の具で、薄く張られた和紙の上に一気に描かねばならない。少しでも不自然だったり、筆致が乱れたりすれば、線が崩れたり、紙が破けたりしてしまう。消したり、修正したりすることはできない…」
彼が描写しているのは「墨絵(すみえ)」――一筆一筆に全身全霊を込めて描かれる、日本の伝統的な表現芸術です。そこでは、一瞬の迷いすら許されません。すべての線に意図が込められなければならないのです。
その精神は、まさにジャズの即興演奏に通じるものです。やり直しのない、その場限りの真実。録音の「一発撮り」こそが、魂の叫びなのです。
白い紙に黒い墨だけで描かれる簡素な構成は、『カインド・オブ・ブルー』を代表とするモード・ジャズの削ぎ落とされた美学とも響き合います。
私たち日本人は、そうした感覚をよく理解していると思います。 私たちは「今、この瞬間」に生きている。 そしてジャズも、まさにそうなのです。
一期一会とエリック・ドルフィー
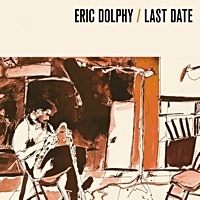
「音楽は、演奏が終わると――空中に消えてしまう。そして、二度と捉えることはできない。」
――エリック・ドルフィー
この言葉を聞くと、私は日本の「一期一会」という概念を思い出します。
「一度きりの出会い」――禅の精神に根ざしたこの言葉は、今この瞬間が二度と訪れないものであることを教えてくれます。そして、その一瞬一瞬を大切に生きるよう私たちに促します。
ジャズの即興演奏とは、まさにこの一期一会そのもの。 たとえ同じ曲を、同じメンバーで演奏したとしても、まったく同じ感覚を再現することはできません。それこそが喜びであり、美しさであり――それがジャズなのではないでしょうか。
間――空間の芸術
日本に住んでいるオランダ人のドラマーの友人が、あるときこう言いました。
「最近、ドラムを演奏しながら “間(ま)”を研究しているんだ。」
“間”とは、物と物のあいだにある空間を指します。ただの「沈黙」ではなく、そこに確かに存在する「気配」や「意味」を含んだ、能動的な余白です。
音と音のあいだの静けさ、フレーズとフレーズの間の呼吸、動きと動きのあいだに漂う緊張感――それが “間”です。
西洋音楽でいう「休符」とは異なり、“間” は耳を澄ませるための時間です。
尺八や箏など、日本の伝統音楽において“間”は、その演奏者の技量を測る鍵となるものです。そして、それはジャズにおいても同じ。「沈黙」や「遅れ」のタイミングによって、スウィングやグルーヴの感覚が生まれるのです。
ほんのわずかにビートの後ろに置かれた音――それは、動きの中にある“間”なのです。
守・破・離とジャズの道
日本には、古くから伝わる「守・破・離(しゅ・は・り)」という考え方があります。
守:型を守る
破:型を破る
離:型から離れる
14世紀の能楽において初めて体系化されたこの思想は、熟練への道を示すものです。
まずは型を忠実に学び、次にその型に挑戦し、やがてその型すら超越して自由に至る――それが「道」を極める流れなのです。
ジャズ・ミュージシャンたちは、本能的にこのプロセスを辿っています。
ジョン・コルトレーン、オーネット・コールマン、そして現代の若きアーティストたち――誰もが、先人たちの音楽を吸収し、それを打ち破り、そして自由を求めて新たな音を探し続けています。
――それこそが、ジャズの本質ではないでしょうか。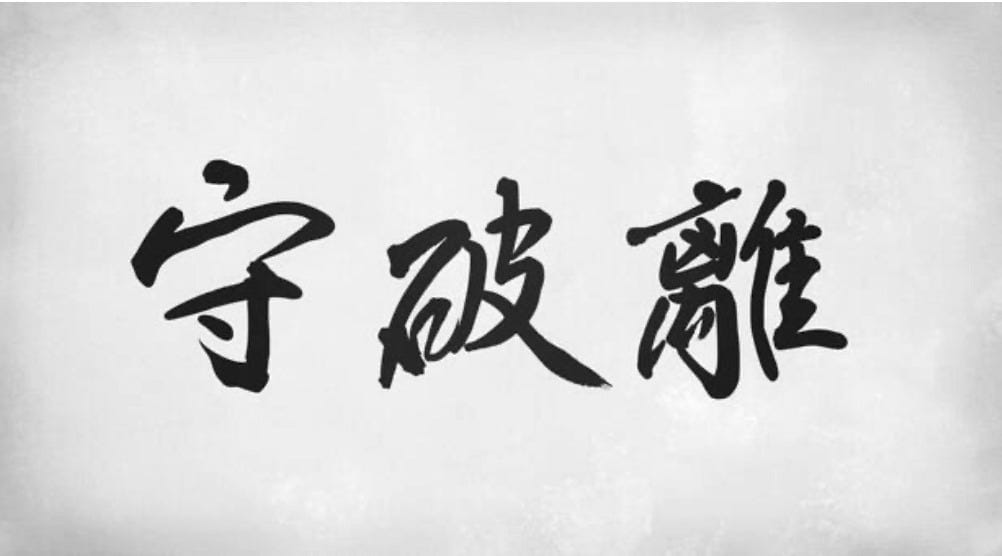
結びに
これまで読んでくださった方には、きっとご理解いただけたのではないでしょうか――
なぜジャズが、日本人の精神に深く響くのかを。
“間(Ma)”、 “一期一会(Ichigo-Ichie)”、そして “守・破・離(Shu-Ha-Ri)”。
これらの概念を通して、私たちはジャズの中に、実はずっと昔から自分たちの中にあった何かを見出しています。
そして――おそらくそれこそが、日本が「ジャズの楽園」と呼ばれるようになった理由なのかもしれません。
もちろん、ジャズを演奏することは決して簡単ではありません。
けれど私たちは、心を込めて、魂をこめて、そして、一瞬一瞬への深い敬意の念を持って――今日もジャズに向き合っています。
小橋敦子, Bill Evans, Eric Dolphy, All Aout Jazz, AAJ, Kind of Blue, Ma, Shu-Ha-Ri, Ichigo-Ichie


