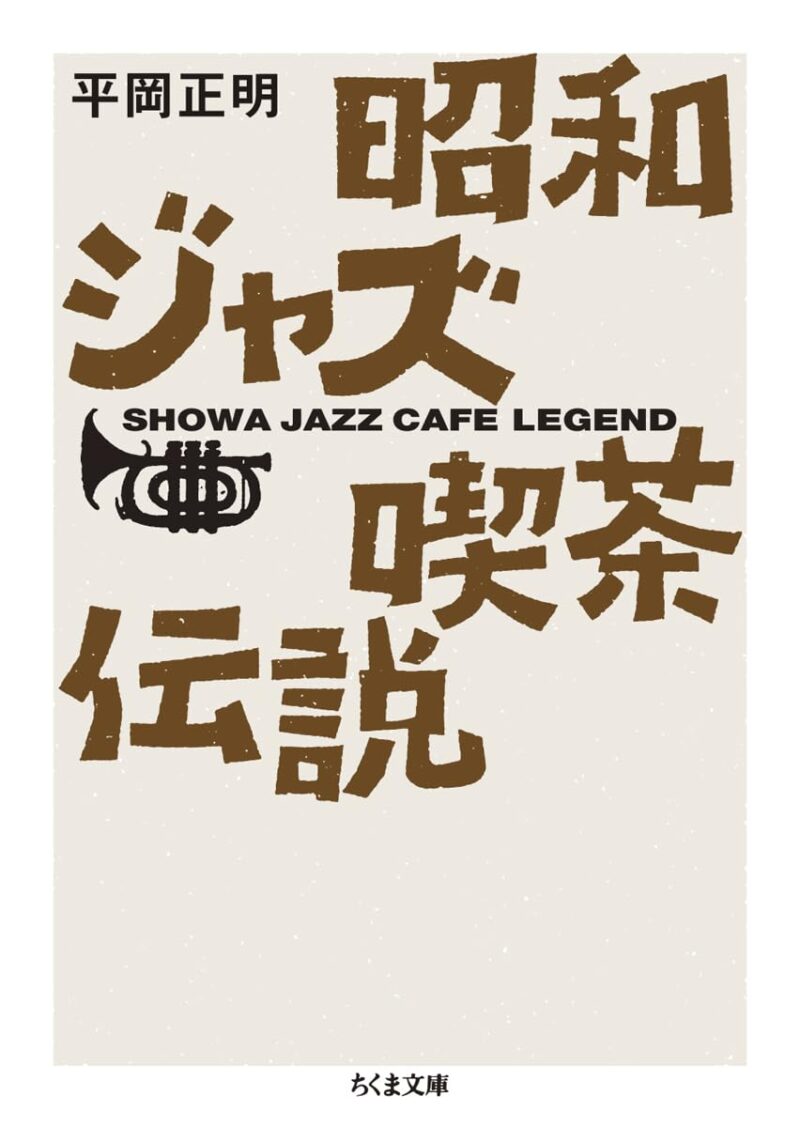#142 平岡正明『昭和ジャズ喫茶伝説』
text: Kenny Inaoka 稲岡邦彌
著者:平岡正明
書名:昭和ジャズ喫茶伝説
頁数:340頁
判型:文庫本
初版:2025/02/06
版元:筑摩書房
その夜、筆者は旧友の杉田誠一(当時、白楽のジャズ・バー Bitches Brew for hipsters onlyの席亭)に誘われて、電通の菊地雅章の担当の一人であった伊藤某と横浜のジャズ・クラブ「ファースト」へ藤井郷子のソロ・ピアノを聴きに行くことになった。伊藤は渋谷橋のオフィスから恵比寿駅に向かう途中、八丈島を謳う料理屋があり、明日葉の天ぷらが旨いなどと言い出す輩も居て小腹を満たしていくことになった。横浜駅からタクシーを飛ばしてファーストへ向かった。まばらな客の中にテーブルに付くひとりの男性客がいた。伊藤が「電通の伊藤です。よろしくお願いします」と名刺を差し出した。男は無言で名刺を受け取ると名刺に目をやることもなく細かく引きちぎり灰皿の中に捨てた。筆者は杉田を残し、伊藤と別のテーブルに向かった。平岡正明との唯一の出会いだった。杉田に1時間待ちぼうけを食わされた平岡の堪忍袋の緒が切れたらしい。
昭和100年の今年、昭和を振り返る企画本がいろいろ刊行されている。これもそのひとつらしい。本書は2005年に平凡社より刊行された単行本を増補したもの、との但し書きがある。ボーナストラックと称する増補は平岡自身による一編と山下洋輔の弔辞、それに遺された奥方の惜辞である。
結論から言えば、平岡が「あとがき」で触れているように「60年代と70年代前半の東京ジャズ喫茶シーンを俺一人称で描き出したところが、世相風俗資料としての本書の値打ち」である。思い返せば当時の若者にとってジャズ喫茶がジャズの学校だった。60年代から70年代前半。それぞれがそれぞれのテリトリーがあり、その中でさらに行きつけの店があった。オヤジの顔が見える店とそうでない店。筆者は地元吉祥寺を中心に、新宿、渋谷界隈だったが、平岡のテリトリーは東京全般と横浜などの近郊。筆者とだぶる店もあるが多くはない。驚くのはオーディオについての記述。当時競ったのは輸入盤のコレクションとオーディオ装置だった。平岡は行きつけの店のシステムをユニット名を上げながら詳細に記し短評を加えている。それも資料として確実に値打ちのひとつになるだろう。在学時代にオープンした中平穂積のDIGのオーディオ装置が、平岡の行きつけのストリップ小屋の装置と同じだったという指摘には目を向いた。その後すぐにDIGのシステムは更新されたらしいが。
博覧強記の平岡のこと、学生運動を中心に政治から、映画、風俗まで話のネタの数々はとどまるところを知らない。当時を知るものは思わず顔を綻ばせ、知らない若者は羨望の眼を向けることだろう。彼の軌跡を辿ろうにも多くのオヤジ、店は廃業あるいは業態を変えている。「伝説」と称する所以である。(文中敬称略)