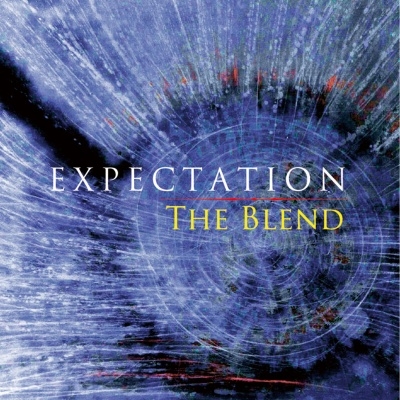#2400 『鈴木良雄 The Blend / EXPECTATION』
text by Masahiro Takahashi 高橋正廣
鈴木良雄 The Blend『EXPECTATION』
Friends Music WAGE-14005 3,000(税込)
- MIXED DONUTS
- EXPECTATION
- BACKSTAGE
- FISH MARKET
- RUN RUN RUMBA
- CHIN SAN
- BURNING POINT
- MONA LISA
- SHINJUKU
The Blend:
鈴木良雄 (bass)
峰厚介 (tenor sax)
中村恵介 (trumpet)
ハイ・エイキム (piano)
本田珠也 (drums)
Recorded by Nagato Sugawara at Studio Orpheus, Tokyo, March 3 & 4, 2025
モダンジャズの屋台骨を支えるのはビバップ期の昔も21世紀の今もベースだ。
古い皮袋に新しい酒を注ぐという寓話を、筆者は古い皮袋の中でワインの新酒が熟成してゆくという新旧のベストマッチのことだと思っていたが、実はこれが大間違い。とある中東起源の宗教の聖典には、ぶどう酒とそれを入れる皮袋に関する有名な「たとえ話」があり、それは「新しいぶどう酒を古い皮袋に入れてはいけない、そんなことをすると、新しいぶどう酒は古い皮袋を破って流れ出てしまう」というのがこの寓話の真実だそうだ。
新酒はさらに発酵が進むのに対し、古い皮袋は固く伸縮性がなくなっており、それ以上膨張しないので破れてしまう、というのが文字通りの意味とか。筆者は真逆の意味に曲解していたのだ。しかしワイン作りには古いオーク樽にワインの新酒を収蔵して樽からの香り付けをして熟成を深めるという製法もあるのだから話はややこしい。
鈴木良雄は文字通りジャパン・ジャズ界のレジェンド中のレジェンドと断言して良いベースの巨人。その華々しいキャリアは鈴木良雄の自伝「死ぬまでジャズ」(2024年1月刊)の紹介文によれば『1946年3月21日生まれ、長野県木曽福島町(現・木曽町)出身。幼少よりバイオリンやピアノに親しんで育ち、早稲田大学に進学してモダンジャズ研究会に所属する。大学在学中にピアニストとしてプロ活動を開始し、のちにベーシストへ転向。渡辺貞夫や菊地雅章のバンドに参加したあと、1973年に渡米し、スタン・ゲッツやアート・ブレイキーらのレギュラー・ベース奏者として活躍する。1985年に帰国。MATSURIやイーストバウンス 、BASS TALK、Generation Gap、THE BLENDといった自身のリーダー・バンドなどで精力的に活動する。2016年には竹書房よりジャズ入門書『人生が変わる55のジャズ名盤入門』を出版し、ベストセラーに。”チンさん”の愛称で親しまれ、日本ジャズ界のリーダー的存在である。』とある。
さて本アルバムはリーダー鈴木良雄が2019年に結成したThe Blendによる第2作。その長いキャリアの中から幅広い音楽観を有する鈴木はそれまでBASS TALK、Generation Gapといったバンドを編成してユニットごとに異なったスタイルで日本ジャズ界に異彩を放っていたが、それらを一旦解き放って新たに結成したのがThe Blend。メンバーには鈴木の2歳年長でテナーサックスの大御所峰厚介とGeneration Gap で活動を共にした1977年生まれの中村恵介のトランペットの2人をフロントに据え、バンドの要となるピアノにはハクエイ・キム(1975年京都出身)という同世代では一頭図抜けた存在を起用。キムはGeneration Gapのメンバーでもあった。更には本田竹広を父に、チコ本田を母に持つジャズの申し子にして清水くるみ(p)のZEK3での活躍も目覚しい本田珠也(1969年生まれ)がドラムに坐る。正に熟達のベテランと中堅の精鋭が合流いや“ブレンド”したユニットが誕生したのだ。
このThe Blend が指向したのが、紛れもないネオ・ハードバップというのが何とも痛快。レジェンド鈴木が長い逆旅の最終コーナーを廻って到達したのがオーソドックスなハードバップの世界だったということはジャズの未来を暗示しているのかもしれない。フロントにサックスとトランペットの2管を据え、ピアノトリオがバックを固めるというハードバップが“発明”した永久不滅のフォーマット(つまり、これこそが古い皮袋かもしれないが)がクール、アヴァンギャルド、フュージョン、M-Baseといった各時代の音楽的潮流を貪欲に吸収し如何様にも受容して、破綻することのない柔軟性を発揮してジャズを革新していく姿を我々ジャズ・ファンは知っている。鈴木の志向するジャズの未来とはThe Blendという柔軟な革袋の中で馥郁とした吟醸香を熟成していく作業に違いない。
さて3年前のライヴ作品『Five Dance』での衝撃のデビューを飾ったThe Blendにとって初のスタジオ作品となったこの第2作では9曲中6曲を鈴木が提供してリーダーとしての立ち位置を明確にしている。そして各曲には鈴木がそれぞれ短いコメントを寄せているのでそれを紹介しつつ鑑賞してゆきたい。
01.<MIXED DONUTS> 「2つの世界が交錯する新曲」とは正にこのThe Blendそのものの立ち位置ではないか。骨太のベースにいざなわれ、50年代ハードバップを彷彿させる2管アンサンブルと鮮烈な21世紀型ソロ・パフォーマンスを発揮する中村とハクエイの跳躍力が見事だ。途中、ブギウギのリズムとなってから繰り出される峰のテナーの存在感は聴き逃せない魅力的なものだ。
02.<EXPECTATION> 鈴木は「先行きが見えない今の人間社会」としつつも「でもきっと素晴らしく輝く明るい未来が待っている」と人間味に溢れた情感をもってこの曲を作ったに違いない。豊潤な低音で支える鈴木のベースがどこまでも優しくメンバーを包み込んでいる。鈴木のベースだけに耳を傾けても良いくらいの感動が押し寄せる。アルバム・タイトルとしたのも納得の1曲。
03.<BACKSTAGE> 鈴木が40年前に作ったという曲。1980年代にNY から帰国したばかりの鈴木にとっては輝かしい前途を託したナンバーではないか。当時より格段の技量で演奏するThe Blendのメンバーに驚嘆しつつ頼もしくバッキングする鈴木の笑顔が見えてくるような爽快な1曲。
04.<FISH MARKET> ピアノのハクエイ作。ユニークなメロディセンスそのままにステレオタイプ的なハードバップとは明らかに一線を画していて印象的なナンバーで、鈴木の弾くベースソロは全く古さを感じさせない。こらが79歳を迎えて尚旺盛な創作意欲を持ち続けていることの証左だろう。
05.<RUN RUN RUMBA> 昔流行ったルンバのリズムで作ったと鈴木。皆んな楽し気にソロを取っているのが伝わって来る。テナーとトランペットの掛け合い、ベースとピアノの掛け合いも実に陽気なルンバらしい雰囲気が醸し出される。
06.<CHIN SAN> 鈴木の旧友だったという故今井尚氏の曲。曲名は勿論鈴木の渾名。峰のTBMにおけるセカンド・アルバムでも演奏されたというから鈴木ばかりか峰にとっても思い入れの深い曲。峰のディープなブロウが沁み、ハクエイの伸びやかなソロも。
07.<BURNING POINT> 鈴木の1stアルバム「Friends」に収録された1972年の旧作の再演。その時のメンバーの一人が峰であり、本田珠也の父である本田竹広に村上寛(ds)という顔ぶれ。鈴木にとってはこの曲もまたThe Blendという新しいユニットで再構成(再醸造)を試みたのだろうか。それに応えた中村のトランペットとハクエイのピアノが秀逸だ。本田のドラムも父のパッションが乗り移ったのかと思う程の素晴らしい切れ味を披露する。
08.<MONA LISA> スタンダードの名曲は鈴木とハクエイの珠玉のデュオによって綴られてゆく。アルバム全体の流れの中で一服の清涼飲料のような涼やかな印象を聴き手に与えている。鈴木のアルコが緩やかな大河のように深々とメロディラインを奏でてゆけば、それに応えるハクエイのピアノが実にヴィヴィドなカウンターメロディで美しさが増幅されてゆく。一度このディープな世界に浸ったら抜け出せないのではとすら思わせる。
09.<SHINJUKU> 鈴木自身が「Very Special!」と絶賛するラスト・チューンは鈴木にとって4度目の吹込みという。掉尾を飾るだけあって中村のトランペット/峰のテナーによるヴァイタルな2管によるテーマが雄大にして勇壮極まる。ハクエイの一心不乱のピアノの疾走感、中村のブリリアントなトランペットの熱い咆哮は全て鈴木の野太く背骨を掻きむしるようなベースに支えられている。そして後半の鈴木のピチカート・ソロはどこまでも熱く哀しい。全員が一体となった演奏の凄まじい風圧が一気に耳を襲ってエンディングを迎える爽快感がこのアルバムの成功を印象付けている。
鈴木がユニット名として「The Blend」と名付けたことは、正に正解と言わざるを得ない。裏ジャケットに並んだメンバー達をバックにしたリーダー鈴木良雄の自信に溢れた表情が本作品の出来をそのまま物語っているのだ。それは古い皮袋であるはずの鈴木が精鋭たちの清新なエキスを包容する中で自身のテイストをグループ内へ浸潤させてゆくという、ヴィンテージ・ワインの醸造プロセスを見るような展開に他ならない。
そして冒頭に掲げたアジテート・コピー『モダンジャズの屋台骨を支えるのはビバップ期の昔も21世紀の今もベースだ。』という筆者の確信は本作品の出現によって更に深まったと言えるだろう。
本田珠也, ハクエイ・キム, 鈴木良雄, 峰厚介, The Blend, 中村恵介