JazzTokyo
Jazz and Far Beyond

-

#76 第16回 東京JAZZフェスティバル
クラブ(WWW、WWWX)演奏も注目を集めたことなどを含めて、渋谷に移転しての東京JAZZフェスティバルは第1回としては成功裏に再出発したといってよいだろう。
-

Reflection of Music Vol. 56 クリス・ピッツィオコス
クリス・ピッツィオコスが来日し、JAZZ ART せんがわに一陣の風が吹き抜けた。彼のソロ演奏は、未知の領域を探究するようなサウンド構成だった。会場を圧倒するほどの凄みはなかったもののその片鱗は確かに観ることができた
-

Reflection of Music (Extra) Vol. 55 JAZZ ART せんがわ 2017
「JAZZ ART せんがわ」がスタートしたのは2008年、今年遂に10周年を迎えた。商業主義とも単なる街興し的なお祭りとも一線を画した独自の路線を持つフェスティヴァルが続いたことは嬉しい。おめでとう!
-

連載第26回 ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報
ニコール・ミッチェルが彼女のユートピア的世界観たる『Mandorla Awakening II: Emerging Worlds』、「ジャズ」をその文脈から引き離し、粉砕して、その壊れた欠片により流れと混乱の組み合わせを創り上げた『Hearts and Minds』。
-

ニューヨーク:変容する「ジャズ」のいま 第17回 マット・ミッチェル〜注目すべき対象と曖昧な始発点の交差する場所〜
ニューヨークで今最も勢いのあるピアニストの一人、マット・ミッチェルの新しいアルバム、『A Pouting Grimace』。木管楽器、パーカッション、リズムセクションとエレクトロニクスという総勢12人の変則的アンサンブルに、指揮者としてタイショーン・ソーリーが加わったプロジェクト。El Intrusoマガジンによるマット・ミッチェルへのインタビューも。
-

#973 2017年9月のニューヨーク
2017年9月のニューヨーク・ジャズシーン報告。
-

ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #23 <Happy Fire>
面白いのは、マイルスやコルトレーンやエヴァンスやオーネットはラッセルのこの理論に深く耳を傾けたことだった。それがモードジャズの誕生だ。
-

ある音楽プロデューサーの軌跡 #38「日野皓正・元彦さんとの仕事」
元彦さんは皓正さんを「兄貴」と慕い、皓正さんは元彦さんを「トコ」と何かにつけ目をかけていた。二人はとても生真面目で真摯に音楽に立ち向かい、自らを厳しく律していた。
-

#6 星降るサハラ砂漠を目指して
砂漠に出たら、すでに旅人や住人が砂上に横たわっているではないか...。見習って仰向けに寝たら大地の懐は涼しく身体を抱きしめてくれるのだった、あ〜何といい気持ちなんだ。
-

ジャズ・ア・ラ・モード #3. アニタ・オデイのブラックドレス
アニタ・オデイ、というとほとんどのジャズファンが1958年のニューポート・ジャズフェスティバルでブラックにホワイトのオーストリッチのついたドレスを着て<Sweet Georgia Brown >と<Tea for Two >を歌う姿を思い浮かべるのではないだろうか?
-

LIVE EVIL #29「Bitches Brew for hipsters only 10 周年記念コンサート」
とりあえず、10年間お疲れ様でした。機会があればまたレコード・ジャケットの撮影をお願いしたいね。
-

Live Evil #28「日米友好コンサート / 米国空軍太平洋音楽隊・アジア」
バディ・リッチで幕を開け、ベイシーで閉じる、アメリカの豊穣なジャズ文化だ。白人隊員中心の軍楽隊だが、アフリカン・アメリカンのバリサックスもいる、女性隊員のトロンボーンとヴォーカルもいる。
-

#1451『TON-KLAMI / Prophecy of Nue』
このCDは、非イディオマティックな即興演奏という、音楽生成のあり方において最上の記録のひとつであることは論を待たない。それを理解するには、聴くという方法以外には無い。
-

#1450 『Racha Fora / Happy Fire:New Kind of Jazz』
自他ともにマイルス・フリークとしてしられるヒロ・ホンシュクであるが、本アルバムではさらに飛躍してジョージ・ラッセル(p,comp,arr)、マイルス・デイヴィス(tp)、ビル・エヴァンス(p)そしてヒロ・ホンシュク(fl,EWI)がサイクリカルに巡っている。
-

#1449『Todd Neufeld / Mu’U』
ジャンルやスタイルに回収できないニューフェルドの音楽は、決して聴き易いものでもなければ、わかり易いものでもない。しかし、そこに定着された、潜勢や気配から発すべき音を掴み取り、無から有へ跳躍するその瞬間の生々しさには抗し難い重力、強度が宿っているのだ。
-

#1448 『Vijay Iyer Sextet Far From Over』
静と動、ダイナミックとフローティング、めっちゃカッコいい表題曲「Far From Over」、ジャズイズカミングバック!
-

#1447 『Avishai Cohen / Cross My Palm With Silver』
伸びやかなトランペット・トーンの陰影を含んだECM独特のヨーロッパ詩情、これに尽きる名盤だ、
-

#1446 『Cortex / Avant-Garde Party Music』
北欧から登場したネオ・ハードバッパー、コルテックス。政府の援助を受け、自ら前衛を名乗り、往年のフリージャズを装いながら、シーンの内側から革命を模索する音楽闘士が奏でる『アヴァンギャルドなパーティ・ミュージック』は新たな創造性へのプロテスト・ソングである。
-

#1445『Talibam! / Endgame of the Anthropocene』『Talibam! / Hard Vibe』
2004年から活動を続けるアヴァンユニット・Talibam!の新作2枚。仮想のSFサウンドトラック、サイケデリックなロック。まるでタイプの異なることこそ彼らの真骨頂か。
-

#1444 『Racha Fora / Happy Fire』
そんな新しいリズムの探求に貪欲な若い世代のジャズ・リスナーにとっても、この本宿宏明(ヒロ・ホンシュク)が提示する“New Kind Of Jazz”は相当刺激的に響くはずだ。
-

#1443 『Racha Fora / Happy Fire:New Kind of Jazz』
永遠の師マイルスの “常に新しい方向に進め” という教えをモットーに、ヒロとそのバンドは “今までに聞いたことのないグルーブ感”、すなわち21世紀型のハイブリット・ミュージックを探求、その創出・深化の過程にある。
-

#1442『Todd Neufeld / Mu’U』
ウェルメイドな楽曲を手がけるギタリストが数多くいる現代のジャズ・シーンのなかで、演奏家としてオリジナルな響きを生み出すことのできるミュージシャンはほとんどいないように思う。
-

#1441『Todd Neufeld / Mu’U』
菊地雅章が身を挺してこじ開けたインプロジャズは、胚胎しその種子となった核がいたるところに内在していることが聴きとることができる、しかしながらそれは、卓抜した演奏者、ここの5にん、トロンボーンを繰るタイションも含む、によってでしか到達できない結果として、だ、もとよりジャズは奏者の力量がものを言う、
-

#1440『TON-KLAMI / Prophecy of Nue』
姜泰煥、高田みどり、佐藤允彦による唯一無二のグループ、トン・クラミ。22年を経て陽の目を見る圧倒的な演奏である。苛烈なエネルギーを放出した『In Moers』よりも多彩であり、ショーケース的な『Paramggod』よりも一期一会の迫力に満ちている。
-

#1439『TON-KLAMI / Prophecy of Nue』
即興演奏、いやアジアのコンテンポラリーな音楽の新たな地平を拓いた歴史的なユニット「トン・クラミ」(姜泰煥、高田みどり、佐藤允彦)のライヴ録音がCD化された。
-

#972 ランドフェスVol.9 仙川
街のなにげない場所を即興の舞台に変え、普段とは全く異なる状況下に置かれたダンサーとミュージシャンの丁々発止のやり取りをリアルタイムかつ至近距離で目撃できるのが、このイベントの醍醐味だ。
-

#971 JAZZ ART せんがわ 2017
記念すべき第10回目となるローカル国際音楽フェス『JAZZ ARTせんがわ 2017』は、過去最長5日間の開催となった。海外からの個性はアーティストも参加し、ジャンルと国境を越えた交流が生まれた。これからも多くの音楽家やファンが「JAZZ ARTせんがわ」で縁を結ぶことになるだろう。
-

#970 音のカタログ Vol. 7~作曲家グループ<邦楽2010>
このグループは邦楽器を扱う作曲家の集まりだが、彼らが洋楽畑出身であるところに大きな特徴がある。私のようにジャズの分野での執筆活動を続けてきた人間が、趣味で親しんでいた邦楽の分野でも執筆をするようになったことと共通しているといえなくもない。
-

#969 「注目すべき人々との出会い」を求めて
このデュオ演奏、ぴったり予定通り20分だった。じつは最近、予定時間通りの演奏ができている。時間芸術としての音楽において、これは非常に大事なことではないか?しかも楽曲ではなく、即興演奏のアンサンブルでそれができるということは?
-
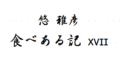
#968 食べある記 XVlll
しばらくの間ご無沙汰していた「食べある記」の扉をを久しぶりに開けて、今回は「食べある記」を振り返りつつ、食べ歩きをひとしきり楽しむことにする。
-

#381 『Todd Neufeld / MU’u』
楽器の特徴、演奏の表現を見事なサウンドで聴かせたディスクだ。
-

#380『TON-KLAMI / Prophecy of Nue』
その中でピアノと打楽器が、遠いサウンドスケープを造っている。筆者仰天の仕掛けである。
-

#379 『Gary Peacock Trio / Tangents』
当然ながらゲイリー・ピーコックのベースの重々しさの表現力は、脱帽の録音。
-

#378 『Racha For a / Happy Fire : New Kind Of Jazz』
フルートを含めたエフェクトが録音のバランスで生きてくる様は感服。ミックス、マスタリングはNY在住の内藤克彦氏。最後の仕上げに巨匠が現れた。
-

#377 『Bill Frisell|Thomas Morgan / Small Town』
録音・ミックスはJames A. Farber。Bill Frisell。Manfred Eicher。サウンドに命を掛けた面々。
-

#376 『Tom Rainey Obligato / Float Upstream』
遠くの印象を伝えるサウンドと切り込むサウンドを描く。ミックス技術の素晴らしさが表れる。
-

#375 『横田明紀男/Love at Christmas』
トラック11に素晴らしい空間感たっぷりの綺麗なサウンドが聞ける。
-

INTERVIEW #163 ヒロ・ホンシュク
我々のウリである、まず今まで聞いたことがないようなグルーヴ感と、変幻自在なジャズのインプロを楽しんでいただきたいですね。
-

#163 橋本孝之(.es)インタビュー:確かな「心」の芽生えと「自己」の消失の先にあるもの
テン年代に大阪の現代画廊から登場したコンテンポラリー・ミュージック・ユニット.es(ドットエス)のサックス奏者・橋本孝之。ソロ活動やジャンルを超えたコラボも精力的に行い、日本の前衛音楽シーンの最先端を更新する橋本の、穏やかなマスクの下に隠された秘密を炙り出すロング・インタビュー。生れてから最新サックスソロ作『ASIA』に至る異端の表現者の素顔が今初めて明かされる。
-

#10 10/26~11/5 ハシャ・フォーラ日本ツアー
本誌で「楽曲解説」を好評連載中のフルーティスト、ヒロ・ホンシュク(本宿宏明)率いるハシャ・フォーラRacha Fora が来日、10月から11月にかけて日本をツアー!
-
#09 10/12~22 オカベ・ファミリー日本ツアー
オランダを中心に活動している岡部源三をリーダーとするオカベ・ファミリーが10月に日本ツアーを行う。オカベ・ファミリーは今年第3作目となるアルバム『Disoriental』(Challenge Records Intl.) をリリース。また、岡部は、オランダの有力ジャズクラブが選出する2017年度の Young Vips(最優秀新人賞)に選出されている。
