風巻 隆 「風を歩くから」Vol.22 「HET APOLLOHUIS」~アイントホーフェン(オランダ)
text & photo by Takashi Kazamaki 風巻 隆

猥雑なエネルギーの溢れるアムステルダムから、電車で1時間半、南オランダの中核都市・アイントホーフェンは、モダンな地方都市だ。教会と新しいビルが高さを競い、駅前のオシャレなショッピングエリアから、古いレンガ作りの倉庫街を抜けると、ゆったりと水をたたえる運河に跳ね橋がかかっている。19世紀にタバコ工場だった場所を改装した「HET APOLLOHUIS (アポロハウス)は、1980年から、現代美術の展覧会やインスタレーション、現代音楽や即興音楽の演奏会、パフォーマンスやレクチャー、書籍や5年ごとの活動記録の出版、カセットテープやLP、CDの製作などを継続していた。
「HET APOLLOHUIS」は、自身もサウンドアーティストであるポール・パンハウゼンと、奥様のヘレーネ・パンハウゼンのお二人によって運営されていて、そこで演奏した日本人ミュージシャンは、NHKの「きょうの料理」のテーマ音楽を作曲したマリンバの 安倍圭子(1985)、ご存じ、現代音楽の巨匠、小杉武久(1987)、サンフランススコ在住でミニマル・ミュージックのヨシ・ワダ (1987)、オランダやスペインを拠点に薩摩琵琶や声明を演奏する上田純子(1988)、「音具」と呼ぶ自作の楽器で演奏/パフォーマンスする鈴木昭男(1990)と数少ないなか、ボクは1988年10月にソロを行うことになった
「HET APOLLOHUIS」は、床が石造りで、壁がレンガ、天井近くに太い木の梁がよこたわって、冬場に使うスティームの上に、明かり取りの小さな窓がいくつか並んでいる。87年の半年をニューヨークで過ごしたボクは、88年の秋に、初めてヨーロッパへ出かけ、いくつかの場所でソロのコンサートをすることができたのだけれど、その後の展開も含めて成功したと断言できるのはゲントの「LOGOS」と、アイントホーフェンの「HET APOLLOHUIS」だろう。「LOGOS」の翌日に行われた「HET APOLLOHUIS」のソロには34人の観客が集まってくれ、石の床の上に立ったまま熱い視線を投げかけてくれた。
コンサートのチラシにはこんな紹介がされていた。「タカシ・カザマキは、彼独特の一風変わった打楽のスタイルを、とても表現豊かでダイナミックなものに発展させてきた。彼は、たった3つのドラムの小さなセットを立ったまま叩き、多くの革新的なテクニックを使いこなすことで、豊かでヴァラエティーに富むサウンドを作り上げている。彼はインドでタブラを習い、近藤等則、竹田賢一、小杉武久と共演、84年と87年にはニューヨークを訪れ、ビリー・バング、ジョン・ゾーン、トム・コラ、ペーター・コヴァルト、サムベネット、ジーナ・パーキンス、ネッド・ローゼンバーグ、エリオット・シャープと共演した。」
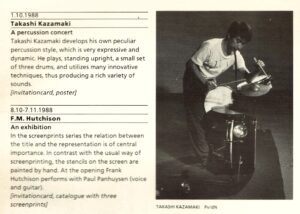
この時点で、ボクが自分の音楽をどこまで自覚していたかは、よくわからない。日本では、即興演奏は音楽のはみ出し者のような扱いで、初めて自主製作したLP『風を歩く』は、「これは音楽ではない」と雑誌のレコードレビューでこきおろされていたし、ニューヨークでは、バンドや、プロジェクトとして形を作っていくことの方が、即興演奏でセッションを重ねることよりも今風に思われていた。ただ、ヨーロッパでは、ジャズの伝統からも離れ、日本の伝統音楽からも離れ、ヨーロッパの即興演奏のイディオムからも離れたところで、誰もやらない形で音楽を作ろうとしていることに多くの称賛が集まった。
10月1日の土曜日、長い夏休みの後、88年秋から89年春にかけてシリーズで行われるコンサート/インスタレーション等の最初の企画ということもあって、夜9時からのコンサートには多くのお客さんが詰めかけてくれ、石やレンガでできたスペースに細かい音のニュアンスが響き渡る。「HET APPOLLOHUIS」でのボクのソロは休憩をはさんで2部構成で行われ、まず、「Thank you very much for your coming…」と英語で挨拶をして始まり、1部2部ともに30分弱、ニューヨークでのレコーディングのときのような細切れの演奏ではなく、 長尺の音楽をその場で即興し、構成し、形を作っていった。
ゆらいだりズレたりしながら語りかけるようなリズム、風が吹いたり川が流れるようにどこへ行くのかまるで見当がつかない構成、シンバルと革のタイコがぶつかるときに湧きおこるノイズ…、そうした非西洋的なエレメントが多ければ多いほど、また個の表現というものを突き詰めれば突き詰めるほど、ヨーロッパでは「アーティスト」として認めてくれる。多くの聴衆の「こいつは何者なのか」という視線を受けながら一人で演奏するのは楽しい。この人達は、ボクが何をしようが、どんなことをしようが、それを音楽と受け止めてくれる…、そう思うと、音楽からのはみ出し方がだんだん半端なくなっていく。
まず初めに提示したのは、肩掛けのタイコとシンバルをスティックで押さえてマレットでシンバルを叩く重低音のシンバルの音だ。シンバルを叩いた音がスティックを伝わってタイコの革や胴を鳴らす。おそらくそれだけで、「この打楽器奏者は自分の音を作っている」ということを感じてもらえただろう。また革のタイコの音色は、ヨーロッパの耳には東洋的な響きに聞こえたに違いない。とくにバスドラの重低音は、ドラムセットのバスドラを聞き慣れている耳には、エキセントリックな響きに聞こえただろう。一つのリズムに、別のリズムがズレて挿入されてくる感覚も、おそらく全く異色のものだったろう。
音楽と非音楽の境界線をすり抜けていくという独特の立ち位置に居て、ジャズのグルーヴを土台に、エスニックテイストの音色と、リズムにおける語る要素や、自分の演奏をもう一人の自分が異化していくような「New Music」的なアプローチ、そして何より打楽器の演奏であるにもかかわらず、さまざまな倍音がきらびやかに輝いていく…、そんな音楽。肩掛けのタイコをシンバルの下にかませ、うなるようなノイズをさまざまにコントロールしながら、ヴォイスと口笛を同時にだす…、最後にはそんな部分も作ってその日の演奏は終わる。観客の暖かい拍手が、「HET APOLLOHUIS」に響き渡った。
終演後、いかにもジャズミュージシャンといった風貌の長身の男が挨拶に来て、ボクの演奏をとても気に入ったと言ってくれた。彼はアド・ペイネンブルグというバリトンサックス奏者で、ジョン・チカイらと「SIX WINDS」というサックスアンサンブルを行っているバリトンサックス奏者だ。自分のレコードを渡したいから、明日会えないかと言う。彼は、アイントホーフェンのジャズクラブ「EFFENAAR」で行われる「ZUID-NEDERLANDS JAZZ FESTIVAL」のオーガナイザーで、その後、ボクは1992年には彼のフェスティバルに招待されて出演し、翌年には彼が来日し、新宿ピットインなどでライブをすることになる。
ヨーロッパのジャズフェスティバルのいくつかは、「新しいジャズ」を指向していて、ボクのような即興演奏とも親和するところが多い。ただ、「HET APOLOHUIS」にジャズミュージシャンは出演することはなく、現代音楽としての独自性を持っているか、自分の音や新しい演奏方へのアプローチを持っているかが選考の基準になっているようだ。ヨーロッパでは、即興演奏は現代音楽とジャズの中間領域だと考えられているようで、個の表現を追求する点では現代音楽に、即興でアンサンブルを作り上げる点ではジャズに近しいものと考えられている。いずれにせよ即興演奏は作品へと向かっていく。
1995年10月、「HET APOLLOHUIS」15周年に「NowHere」という2か月間に及ぶサウンド・インスタレーションや現代美術、パフォーマンスのイベントが、神田のギャラリーサージと「HET APOLLOHUIS」の国際交流企画としてあり、そのオープニングでボクは、近くの工場跡の「SCHELLENS BUILDING」で、再びソロの演奏をすることになる。だだっ広い部屋へと通じるエントランスのような場所に楽器をセットし、その演奏を観客は思い思いの場所でおもに立って眺めている。今ここのNow Hereと、どこでもないNowhereのダブルミーニングのタイトルは、近未来へのまなざしを持っているようだ。
その翌日、ボクは「EFFENAAL」での「ZUID-NEDERLANDS JAZZ FESTIVAL」に出演し、梅津和時さんとオランダ在住のベーシスト、ラウル・ファン・デア・ヴァイデとのトリオで演奏する。梅津さんとは87年にニューヨークの「THE KITCHEN」で共演して以来、たびたびデュオで演奏をしていたけれど、ベーシストを加えたトリオでの演奏はこの時が初めてだった。ニューヨークのダウンタウンで活躍していたアコーディオンのガイ・クルセヴェックや、ジョン・ゾーンとの共演で知られる津軽三味線の佐藤通弘さんも、その日出演していた。ヨーロッパのジャズも、その頃、ニューヨークシーンを意識していた。
「HET APOLLOHUIS」は、その後も現代音楽と現代美術がオーバーラップするような独特の立ち位置で、多くのアーティストを紹介し、さまざまな作品を発表していったのだけれど、助成金が止められてしまったこともあって、多くに惜しまれながら2001年9月で閉館した。88年、初めてのソロ・コンサートの夕食に、一口大のバケットの上にオイルサーディンを載せたスナックを、ヘレーネさんが作ってくれたことを、ボクは今でも覚えている。あれは、SUSHIだったのではないだろうか…、初めてヨーロッパを旅する若い音楽家を、彼らは心からもてなしてくれたのだと、今でも懐かしく思い返している。
梅津和時, 風巻隆, 風を歩く, LOGOS, HET APOLLOHUIS, アポロハウス, ポール・パンハウゼン, ヘレーネ・パンハウゼン, アド・ペイネンブルグ
