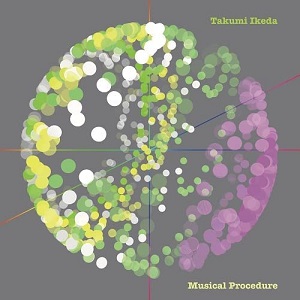インプロヴァイザーの立脚地 vol.7 遠藤ふみ
Text and photos by Akira Saito 齊藤聡
Interview:2023年3~4月 水道橋、有楽町、神楽坂にて
遠藤ふみは、この数年間の即興シーンにおいて大きな注目を集めるピアニストとなった。静寂を引き寄せて音を発するスタイルは、気の合う人との関係をゆるやかに深め、次の関係へとつなげてゆく中で得られたものだ。
ジャズ研、大きな変化
1993年、東京都練馬区生まれ。3歳のときからクラシックのピアノ教室に通い始めたが、楽器を蹴るほど練習が嫌いだった。中学まで続けて、レッスンを受けるのを止めた。高校生のとき、なにかの本を読んでいたらチック・コリア(ピアノ)のことが書いてあって、父親のCD棚にあった『Friends』を聴いたりもしたし、名曲<Spain>を自分で弾いたりもしていた。
東京農工大学ではジャズ研に入った。大学時代に目立った演奏活動をしていたわけではない。外部のセッションにもほとんど出ていない。
大きな変化が遠藤に生じたのは、大学を出てからのことだ。大学院(情報工学専攻)に進んだがすぐに通わなくなり、退学した。その後、アルバイト先で正社員になったものの、自身の問題と職場環境のために無理が生じてしまった。遠藤は携帯電話の電源を切り、旅に出た。福山、尾道、松崎、倉吉、鳥取。店でピアノを弾いたりもした(このとき、鳥取の個性的なサックス奏者・武信ゲバラ雄次に出会ってもいる)。彼女は元気を取り戻し、東京に戻った。
知らない人との共演が怖かったはずが愉しくなったのも、大きな変化だろう。彼女はセッションに片っ端から出るようになった。ナカノピグノウズでは宅シューミー朱美(ピアノ、ヴォーカル)や加藤崇之(ギター)がホストを務めるフリーインプロ・ジャムセッションに参加し、良い経験になった。
違和感から独自の発展へ
セッションなどの場で、ジャズスタンダードをオーソドックスに演っていた。その一方で自由即興を開始したのだが、はじめのうちは(いわゆる)フリージャズの延長だった。彼女自身はそれを感情の発露のように思い込んでいた。それは速度を伴うし、大きな音を出さないと場に届かない。そういった表現を自分が演ることに違和感を覚え、演奏が終わったあとに「それで何なのか」と感じるようになっていた。ただ、遠藤はそのような即興演奏しか知らなかった。(もちろん感情の発露を主軸にした演奏を否定的に感じているわけではない。川島誠のサックスソロを2022年に聴いたとき、遠藤はその考えをあらためた。)
そうではない音楽との接点は、ナカノピグノウズでの体験以外にもあった。
たとえば、下北沢のApolloで須川崇志(ベース、チェロ)やロッテ・アンカー(サックス)といった人たちの演奏を観たこと。六本木のSuper Deluxeでウィリアム・パーカー(ベース)のソロを観たこと。
あるいは、22歳のときに知り合った伊集院正之助(サックス)に柳沢耕吉(ギター)のことを教えてもらい、2019年に東北沢のOTOOTOに柳沢と細井徳太郎のギターユニット・合わせ鏡一枚を、また不動前のPermianに柳沢と池田陽子(ヴィオラ)とのデュオ演奏を観に行ったこと。
柳沢、阿部真武(ベース)とはスタジオで曲を演奏するようになったものの、コロナ期に入り、柳沢の発案で深夜にリモートでのセッションをすることにした。それではどうしてもタイムラグが出てしまうため、曲よりも即興を演ろうと決めた。彼女は、このときの自分の演奏が「フリージャズの延長」であり、「なにかをねらう作為的なもの」でもあったと振り返る。演奏そのものよりもふたりとのおしゃべりの時間が長く、愉しかった。柳沢から教えられることは多く、その中で「Ftarriで演奏するということはどういうことなのか、よく考えたほうがいい」と言われてもいた。2020年の9月、ふたりとのトリオでFtarriに初出演した。
それまで自分が知っていた即興演奏ではない形を探らなければならない。
自由即興の開始
自身の中でこれまでとは異なる回路が開通するきっかけは、他にもあった。
スタジオで試行した音を録音し、soundcloudにアップしてはいた。いま聴くとジャズ的ではあるが、たしかに現在につながる芽ではあった。スタジオの古いアップライトを弾いてみたところ、「ハンマーの音がする」と思えて、その状態を維持したまま録音した。それまで気にしたことのない音だった。遠藤自身は、「鍵盤を押したら鳴る」ようなものではない、なにかを求めていた。
そんな経緯があって、2021年に入り、Ftarriのオーナー・鈴木美幸が池田陽子と遠藤とのデュオを企画した。鈴木には、デュオだけでなくソロも演ろうと言われ、はじめて人前で自由即興のソロを弾く機会が与えられた。池田のソロ、遠藤のソロ、そしてデュオ。
このとき、遠藤は慎重に音を出したかった。ピアノでそれを行うにはどうすればよいのか。彼女自身は「安易に反応してパタパタと焦ってしまった」と反省を口にする。(だが筆者も目撃したそのピアノ演奏は極めて繊細なもので、その時点から表現者としての個性が傑出していたことは確かである。)
人とのゆるやかな関係が音楽の発展につながった
はじめてFtarriでソロ演奏をしたあと、やはりFtarriに徳永将豪(アルトサックス)とすずえり(ピアノ、自作楽器)とのデュオを観に行った。ここでもFtarriの鈴木が遠藤のことを「気が合うかも」と言って徳永に薦めてくれた。3月に開始されたデュオはサウンドを発展させ、アルバムとなって結実している。
蒼波花音(アルトサックス)の演奏を2021年1月にはじめて観て感動した。Ftarriにライヴを観にきた蒼波を鈴木に紹介し、それが6月のkajon(ヴォイス)、蒼波、遠藤のトリオによる演奏につながった。7月には神保町試聴室で「ぶくぶく6」と題したライヴを遠藤自身が企画した。メンバーは、蒼波、Jasmine(トランペット)、伊集院(テナーサックス)、阿部(ベース)、長澤洋平(ドラムス)、それに遠藤であり、ややジャズ的なサウンドである。
グループ「幽けき刻」は西嶋徹(ベース)、蒼波とのトリオである。西嶋の演奏はすでに観ており、好きだった。西嶋も遠藤の演奏を観に来てくれた。そして年が明けて2022年1月、「幽けき刻」初演となった。筆者を含め、多くの聴き手にとって蒼波の音は驚きであったにちがいない。それは静寂と静寂のあわいで震えるものだった。
宮野裕司(アルトサックス)の音は以前より好きだった。西荻窪のアケタの店で定期的に演奏している宮野のクインテットを頻繁に観て、このテンションで音楽を演りたいと思っていた。Ftarriでのソロの模索とこのようなジャズのサウンドの指向性とが混じり合って、遠藤のいまが形成されているという。
遠藤がかみむら泰一(サックス)の音に見出す特徴は、ことばを慎重に扱うこと、考え抜いて新しい形を作ろうとすること、そういった探求心や妥協のなさ、音色のすばらしさ。阿部がかみむらの近所に住んでいたこともあって練習に加わる機会を得たりもして、2021年5月にかみむらと初共演した。そのグループは「Prime Leaf」と名付けられた。
沼尾翔子(ヴォーカル)のことは、甲斐正樹(ベース)がアップしていたsoundcloudでの共演によって知った。2021年の夏に神戸まで足を運び、生の声を聴いてみたら「透明人間だと思った」。人間の匂いがしない声、音だけがあって実体がない声。沼尾もその年の冬に遠藤の演奏を聴きにきてくれた。お互いにネット上にアップしている音源を聴きまくっていたことがわかり、ふたりは意気投合した。翌2022年には沼尾、遠藤に阿部、白石美徳(ドラムス)の4人で演奏し、「Uquwa」という名前のバンドになった。
長沢哲(ドラムス)とは神保町の試聴室で2回共演した。遠藤にとって、それまで即興演奏を多く行なっていたFtarriは「即興演奏とは」という問いと切り離せないエクスペリメンタルな場であり、またそれ以外の場ではあまり即興演奏を行う機会がなかった。長沢との共演には、試聴室の場の力と相性の良さの両方があった。長沢の音にはすみずみまで神経が行き届いており、打楽器にもかかわらず音階があった。だから、長沢との共演を「ピアノとドラムスとのデュオ」と思ってはいない。いまは、長沢とお互いに呼応するかたちで一緒に音楽を作りたいと思っているという。もちろん共演者に合わせるありように違和感を抱いてきたのだし、そうしたいわけではない。
山㟁直人(パーカッション)の「Ensemble 響む」への参加は衝撃的な経験となった(2023年)。それまで「響む」のようなアンサンブルのかたちで即興演奏に取り組んだことがなかったこともあり、いつもの音を出すプロセスと異なることに戸惑った。遠藤に与えられた役割は「こもれびの光」であり、山㟁から森の中に日が射したり陰ったりする動画が送られてきた。もとよりソロであっても、心象風景を音にするわけではない。あるとすれば形のイメージであり、考えて聴いては進むものだ。それとは異なり、このときは「自我がない」存在となった。新しい体験だった。
すずえり(ピアノ、自作楽器)の音楽は接したことのないキュートで儚い世界だった。個展にも足を運んだが、一緒に演奏するとは思っていなかった。これもFtarriの鈴木の発案で、トイピアノを使ってのデュオを演ることになった。すずえりの演奏に共通する感覚を竹下勇馬(機械化楽器)にもみており、はじめて観たときにはカルチャーショックを受けている。演奏においてスイッチを入れたり切ったりするオンオフの感覚がどうもわからないのだという。通常の楽器を演奏する人に感じるなんらかの流れと異なる体感で、竹下もすずえりも流れをいきなり切ったりする。
曲の表現
こうみていくと、ジャズを出発点としながらもまったく異なるコンテキストでの即興演奏を追求してきた遠藤が、一周回って曲の世界にも自然に入っていることがわかる。ただ、ストーリーや展開があるものを良しとするわけではない。
これまでのアプローチが、曲の世界の際を攻めたり出入りしたりするものであったとして、いまの遠藤が試みているのは「曲を通して潜ってゆく感じ」。むしろ、曲を通して知らないなにかをみたいのだという。
(文中敬称略)
アルバム紹介