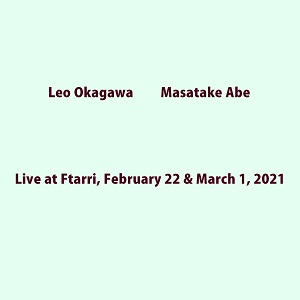インプロヴァイザーの立脚地 vol.9 阿部真武
Text and photos by Akira Saito 齊藤聡
Interview:2023年6月13日 高田馬場にて
阿部真武はさまざまなタイプのプレイヤーとしなやかに共演するベーシストである。演奏を行う場、演奏を介した関係の構築、それらは演奏家として自分自身に意識的にフィードバックされているようだ。
楽器が好き
1993年、福島県生まれ。小学4年生のときピアノ教室に通い始めた。嫌いなわけではなかったが、特に熱心に続けていたわけでもなかった。その後、中学では吹奏楽部でトランペットを吹き、2年生のときにはエレキベースを始めた。これには音楽好きの両親だったことも影響している。父親は学生時代にビッグバンドサークルに入っていて、またこのとき初めて弾いたベースは軽音楽部の経験がある母親の持ち物だった。ドラムも叩いてみたりもしたし、地元のお祭りで和太鼓と篠笛を担当したりもしたし、なにしろ楽器をいろいろと演ってみることが愉しかった。
日本大学に進学した阿部は、キャンパス近くの千葉大学のジャズ研に入り浸った。当時は2学年上に柳沢耕吉(ギター)がいて、その上には大熊紺(ベース)もいた。もう少し年上の落合康介(ベース)も阿部と同じように他大から千葉大に遊びにきていたと聞いた。阿部は都内のジャムセッションに足しげく通い、音楽理論の勉強はおもにネット経由。織原良次にフレットレスベースのレッスンを受けたりもしていた。そのころの音楽への動機は、とにかく「出来ないことが悔しい」という感情だったという。
いまも使っているリッケンバッカーのベースは、2016年に勤務先の健康診断のあと大久保の楽器店に立ち寄って目に止めたものだ。もとよりアンデルス・クリステンセンが使っていて、気にはなっていた。かれは夢中になって1時間も試奏してしまった。スティーヴ・スワロウのようなニュアンスも、またウッドベースのような音色も、両方出せておもしろいと感じた。
楽器から音楽へ、即興嫌いから即興好きへ
とはいえ、楽器が上手くなることとおもしろさとは別の話である。「楽器好き」が環境に左右される一方で、「音楽好き」は自分の中のものに他ならない。阿部も自分自身が次第に「音楽好き」へと変わってきたことを意識している。
ベーシストでいえば、中高生のころからジャコ・パストリアスやレッド・ホット・チリ・ペッパーズのフリーが好きで、大学生のころはとくにジャコの流動的な雰囲気を演奏で実現したいと思っていた。憧れたのは、パット・メセニー(ギター)がジャコやボブ・モーゼス(ドラムス)と組んだ70年代のトリオだ。
大学を出て音楽活動を始めてからは、チャーリー・ヘイデン、ゲイリー・ピーコック、ベン・ストリート、トーマス・モーガン、アンデルス・クリステンセンといった、ポール・モチアン(ドラムス)との縁があるベーシストを好んで聴いた。またトニー・シェールからはパートとしてのベースの愉しさを感じ取っていた。
その一方で、大学に入るころまでは整っていない音や不協和音が苦手で、それゆえ即興もフリージャズも嫌っていた(とはいえ、即興とフリージャズのちがいも意識していなかった)。だが、その意識も次第に変わってきた。きっかけのひとつは好きなジャコの活動。メセニーとのトリオでオーネット・コールマン(サックス)の曲を取り上げていたり、ポール・ブレイ(ピアノ)やアルバート・マンゲルスドルフ(トロンボーン)と共演していたりして、ジャコの根底にあるフリーを意識したことによる。もうひとつは、モチアンや、フリー色が強くなったマイルス・デイヴィス(トランペット)の中期以降などのサウンドをたくさん聴くようになったこと。
多彩な即興演奏家からの刺激
2016年ころから、同い年の細井徳太郎(ギター)の演奏をよく観に行くようになっていた。細井はいろいろな音楽を教えてくれたり、おすすめのミュージシャンを一緒に聴きに行こうと誘ってくれたりもした。細井が参加するライヴには、ジャズも完全即興も、またその中間的なものもあって、阿部には学ぶところが多かった。細井は同い年ではあるが、面倒見の良い先輩のように感じることもあるという。 また伊集院正之助(サックス)が山本陽一(ギター)、大熊、長澤洋平(ドラムス)とフリーなスタイルでジャズを演るバンドをやっていたことにも影響された。
遠藤ふみ(ピアノ)とは同じライヴに出かけるとばったり出会ったり、阿部の演奏をよく観に来てくれたりもして、仲良くなった。
そんなわけで、阿部は細井や遠藤らと下北沢のApolloに出入りするようになった。アクセル・ドゥナー(トランペット)、ジャック・ディミエール(ピアノ)、ヨナス・コッハー(アコーディオン)からなるDDKトリオに齋藤徹(ベース)が参加したときも観たし、千葉広樹(ベース)や、アダム・プルツ・メビュー(ベース)とジュリア・リーディ(ギター)のデュオ、細井とヨアヒム・バーデンホルスト(リード)、シセル・ヴェラ・ペテルセン(ヴォーカル)とのトリオなども衝撃的なものだった。店内で流されていたフレッド・フリス(ギター)のサウンドも印象に残り、それをきっかけにプリペアド奏法を始めた。
柳沢に教えてもらい、ラファエル・マルフリート(ベース)、トッド・ニューフェルド(ギター)、カルロ・コスタ(ドラムス)のトリオを稲毛のCandyに観に行った。かれらは図形譜面の曲などをもとに即興演奏をやっており、エレキベースで弓を使う手法を始めて目にした。海外旅行のときに観たダン・ピーター・サンドランド(ベース)もまた弓の使い方が上手く、阿部も自身のリッケンバッカーで試してみた。だがかれらのようには上手くいかず、独自奏法を研究することになった。
自身の即興演奏
初めての即興的な音楽活動としては、2016年に、ポール・モチアンのエレクトリック・ビバップ・バンドのコピーバンドのようなものを始めた。メンバーは阿部に加えて伊集院と田尻智大(サックス)、岩本次郎(ドラムス)、細井と山本陽一(ギター)である。それまで事前のアレンジに基づき演っていた「予定調和」の世界とはちがい、その場で音を作り出してゆくものだった。また、細井、岩本とのトリオも組み、スタンダードやオリジナルを演った。
大熊に勧められたこともあって、2017年、中野のナカノピグノウズで宅 Shoomy 朱美(ピアノ、ヴォーカル)や加藤崇之(ギター)がホストを務める即興セッションに参加してみた。ジャズを演っているときにはだんだんと息苦しくなってゆく感覚があったのだが、即興演奏は愉しいものだった。また、翌2018年になって、江古田のFlying Teapotで細井、高橋直康(ベース)とも共演した。これが、最初から最後まで即興演奏をした初体験だ。Flying Teapotでは、その後もtani(ギター)、金子由布樹(エレクトロニクス)と定期的に即興のトリオで出演していた。
2018年に勤め先を辞職してニューヨークやヨーロッパをひと月かけて回り、さまざまなライヴを観たこともいい経験になっている(本当はカーラ・ブレイのトリオを3回観るつもりだったのに、カーラが体調を崩し叶わなかったという)。なにより旅の収穫は、振り返ってみて、日本に素晴らしい音楽家がたくさんいることが分かったことだ。
だから、阿部にとって即興の世界はApolloなどの場や海外即興演奏家の鮮烈なサウンドによって拡げられたということができる。さらに、水道橋のFtarriにおいて、さまざまな日本国内の即興音楽家を知ることができた。
即興演奏への次のキーとなったミュージシャンは、柳沢、秋山徹次(ギター)、岡川怜央(エレクトロニクス)らである。
ニューヨークから帰国した柳沢は、岡川と北千住の古い日本家屋でデュオを演ったり、「種まき種まかせ」という集団即興のシリーズを展開したりしており、阿部にかなりの感銘を与えた。また、2018年に観た秋山と細井とのデュオにはたいへんな衝撃を受け、秋山の作品をよく聴くようになった。20年ころからエフェクターをいろいろと導入してみたのも、秋山の影響が大きい。さらには、音楽をMIDI的にとらえていた阿部にとって、質感で音楽を構成してゆく岡川の演奏はとても驚きがあった。
阿部は柳沢、遠藤のふたりとスタジオでジャズスタンダードや柳沢のオリジナルを演り、その帰りに柳沢の提案でFtarriに立ち寄ったところ、店主の鈴木美幸が「出てみますか」と提案してくれた。それで、かれらは2020年に出演して即興演奏を行った。
もちろん、多大な影響を受けた柳沢耕吉の存在は大きい。また、宮坂遼太郎(ドラムス)については、意図的な音のようでありつつ意図を感じないという不思議なつかめなさを覚えている。
「ジャズを演っている」という意識で音を出すバンドも継続している。阿部は藤原大輔(サックス)に音楽理論を習っていたこともあって、藤原に頼んで藤井信雄(ドラムス)も誘い、トリオを始めた。また、「曲と即興の境界線があいまいな音楽」の比重が自身の活動の中で高まってきた。阿部は、いまでは自分の音を出すことが大切だと思っている。
即興演奏の場
共演者の影響はとても大きい。事前にどのような音楽を展開するかを考えること、あるいはどのような音楽が展開される結果を迎えることは、共演者や場所の影響によるものが大きい。その影響に期待してバンドを継続してみる意識もある。一方、個人としての興味はいかに自分自身が予期しない音を出せるかにあって、それはシンプルな音楽のほうが実現できる。即興とはその探求を人に伝える意識であり、手法でもある。音に華があれば愉しいが、それよりも、即興演奏という状況で音を出せるかどうかが重要だ。
そのような探求ができたのもFtarriという場があったからだ。いまも阿部にとって特別な場であり、鈴木の言葉にも共感できるものがあるという。他によく演奏する場所は、神保町の試聴室、不動前のPermian、東北沢のOTOOTO、渋谷の公園通りクラシックスなど。ジャズの演奏場所はまた別である。
サウンドは響きや機材などにより場所に影響を受けるものであり、逆に言えばその場所でないと実現できないサウンドがあるということだ。即興演奏を始めたころは場所によらず同じようなことを演ろうとしていたが、阿部自身もその場に応じて音を出せるようになってきたと話す。
アルバム紹介
(文中敬称略)
フリー・インプロヴィゼーション, 阿部真武