#01 ユージン・スミスと「ジャズ・ロフト」、そしてモンク
text by Kazue Yokoi 横井一江
写真家ユージン・スミスといえば、日本ではまず「水俣」だろう。そこで撮影した写真、とりわけ「入浴する智子と母」などはユージン・スミスという写真家を知らない人でも水俣病の実態を捉えた写真の一枚として記憶のどこかに残っているに違いない。
だが、彼がジャズ・シーン、それも音楽創造の場の証人だった時期があることはほとんど知られていない。
11月ベルリンに向かう前、ジャズ祭のプログラムの中に『The Jazz Loft According to W. Eugene Smith』(2015) の上映があることに気がついた。しかし、『ライフ』誌のカメラマンとして名を成し、水俣を撮ったあのユージン・スミスと「ジャズ・ロフト」が結びつかない。ジャズファンにとってロフトといえば70年代の「ロフト・ジャズ」だが、時期的に異なっている。それにユージン・スミスが撮影したジャズ・フォトがなかなか思い浮かばない。私の中でモダンジャズ黄金期を撮影したジャズ写真家といえば、チャック・スチュワート、ボブ・パレント、ビル・ゴッドリーブである。それゆえにそのドキュメンタリーへの興味が増し、メインホールの演奏ではないにせよこれは絶対に見逃せないと思ったのだ。
その日はまずグローブ・ユニティ・オーケストラのサウンド・チェックでのフォト・セッションへと出かけた。私が到着した時は、十数名のカメラマンが既にその場に居た。何人かは顔見知りであり、旧交を温めるというか雑談をいろいろ。ひと仕事を終えて、そのドキュメンタリーが上映されるホワイエに向かった。気がついたらサウンド・チェックの場に居た皆もそこへ移動しているではないか。この時ばかりは商売道具であるカメラをバッグにしまい込み、皆じっとスクリーンを見つめていた。
ユージン・スミスは、1957年に家族と別居し、マンハッタンの6番街821番地の「ロフト」に居を移す。その時期のスミスは未完の「ピッツバーグ」プロジェクトを抱え、経済的にも厳しい時期だった。「ロフト」には画家のディヴィッド・X・ヤングや作編曲家でジャズ・ピアニストのホール・オーヴァートンが住み、そこを去来したミュージシャンなどに又貸ししていた。オーヴァートンがその一部をリハーサル・スタジオとして使用できるように改装したことから、ミュージシャンやボヘミアンの溜まり場となっていたのである。パーティで撮影した写真には、画家サルバドール・ダリや作家ノーマン・メイラーなどの姿も写っている。出入りしていたミュージシャンもビバップからディキシー、60年代に入ってからは初期のフリージャズまでさまざまだった。
そこに引っ越したスミスは、「観劇を楽しむように、我がスタジオの窓から混沌とした都市を眺め、その都市の凝縮した場面をカメラに収める」(*)。彼が撮影したのは窓の外の眺めだけではなかった。「ジャズ・ロフト」と呼ばれたオーヴァートンのスタジオでの光景を撮り続けたのである。しかも撮影するだけではなく、あちこちにマイクを置き、ワイヤーを張り巡らせ、自室のテープレコーダーに繋ぎ、リハーサルの様子だけではなく会話なども録音していたのだ。元々音楽好きだったことが高じてこのような行動になったのだろうか。少なくとも「ジャズ・ロフト」でのミュージシャンの日常に多大な関心があったことは間違いない。この一種ののぞき見趣味は自身の生活にも向けられ、電話や会話、ラジオの音声なども録音していたのである。そして、膨大な数のネガとプリントと録音テープを残したのだ。ちなみに2001年にディヴィッド・X・ヤングが亡くなった時のニューヨーク・タイムス紙の記事によると、ヤングとスミスはロフト・シーンについての本を書くことを計画していたようである。
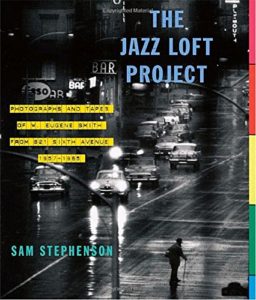
そのスミスの残した「ジャズ・ロフト」での記録にスポットを当てたのが、彼の研究者であるサム・ステファンソンで、その成果を『The Jazz Loft Project: Photographs and Tapes of W. Eugene Smith from 821 Sixth Avenue, 1957-1965』(2009) として出版している。この本は、写真集ではないもののスミスが「ロフト」の内外を撮影した写真も多く掲載され、ステファンソンによる解説、また残されたテープを文字起こし、当時を知る人々へのインタビューなどを加えたもので、当時の資料として貴重なものである。ただし、レイアウトや編集作業にもとことんこだわったスミスにとって満足のいくものかどうかはわからないが。「ロフト」でスミスはありのままを撮っている。演出も何もないその外連味のなさが返ってドキュメントして当時の状況をダイレクトに伝えているように思う。ジャズ史は録音された音盤を第一の資料として語られることが多いが、創造的な行為が行われていた場について語られることはあまりない。そういう意味でもジャズ史の中での「ジャズ・ロフト」をいかに位置づけるべきか、さらなる歴史研究を期待したいところである。
出版に合わせて、ニューヨークのラジオ局WNYCのプロデューサー、サラ・フィッシュコが『The Jazz Loft Project』をラジオ番組のシリーズとして取り上げた。そのサラ・フィッシュコがプロデュース、監督したフィルムが『The Jazz Loft According to W. Eugene Smith』だったのである。
『The Jazz Loft According to W. Eugene Smith』では、スミスの遺した写真や録音を繋ぐだけではなく、研究者や評論家、当時を知るカーラ・ブレイ、スティーヴ・スワローをはじめとするミュージシャン、学生の頃出入りしていた作曲家スティーヴ・ライヒへのインタビュー、当時の映像を交えながら「ジャズ・ロフト」を現出させる。また、スミスのそれまでの仕事、暗室作業をしている時の映像なども交え、その作品はいかに手を加えて創られたのか、その人となりや仕事ぶりも浮き彫りにしていた。
だが、やはりこのフィルムのハイライトは、セロニアス・モンクとホール・オーヴァートンによるタウンホール・コンサート、後に『The Thelonious Monk Orchestra at Town Hall』(Riverside, 1959) としてリリースされたそれに向けた準備とリハーサル風景だろう。3週間に亘ったそれをスミスはまるごと撮影、録音していたのである。モンクが語ることを譜面上に反映させようと必死に書き記すオーヴァートンの姿が印象的だった。フィルムでは、音盤でも白眉の演奏だった<リトル・ルーティ・トゥーティ>を取り上げていたが、モンクのピアノをオーケストレーションするというオーヴァートンのユニークなアイデア、それを具現化させるためのリハーサル風景もフィル・ウッズやロバート・ノーザン(ブラザー・アー)へのインタビューも交えながら捉えられている。
ちなみに、タイトル上に使用した『Monk.』(Columbia, 1964) のジャケット写真は、「ジャズ・ロフト」でのタウン・ホール・コンサートのためのリハーサル中にスミスが撮影したショットを大きくトリミングしたものだった。それを知ったのはフィルムを観ている最中で、その見覚えのあるモンクの横顔を写したショットが出てきた時である。
オーヴァートンの仕事について、何度もモンク作品に取り組んでいるアレクサンダー・フォン・シュリッペンバッハはかつてこう言っていた。
「モンクの曲をビッグバンド用にアレンジした先例としてはホール・オーヴァートンやオリバー・ネルソンのレコードがありますが、私はオーヴァートンのほうが好きですね。ネルソンの方は型にはまっているというか、カウント・ベイシーにも近いありふれたビッグバンド・サウンドですが、オーヴァートンはモンクのアイデアにより近い。驚かせるようなサウンド、驚かせるようなヴォイシングなど普通でないところはモンクの音楽、意味、アイデアにフィットしていますね」
時代性を考えると尋常ではないビッグバンド・アレンジがどうして出来たのか、やっと謎が解けたのである。このオーケストラのための編曲作業は一種の共同作業であったのだ。それがフィルムを見てわかったのである。
連写した写真を映しながら、バックに会話やリハーサルの音源を流しているためか、あたかもその場に居るようなリアルさを覚えた。ミュージシャンは自身の作業に没頭していて、写真を撮られていることを全く感知していない。スミスもまたその世界に入り込んでいたに違いない。彼はその場に居たミュージシャンの中にとけ込み、空気のような存在だったのだろう。これは私にとっての理想でもある。
よく言われるとおり、自分が納得するまでとことん仕事をし、自分の思うところに沿わない写真記事の掲載には徹底的に抵抗するスミスの仕事ぶりは、ある意味ミュージシャンの音楽創造への意識に近いものがある。彼自身もジャーナリストであると同時に表現者(アーティスト)でなければならないと考えていた。だからこそ、その場を共有出来たに違いない。
フィルムの最後に、スミスは「水俣」プロジェクトで「世界を変えるフォト・ジャーナリストとして復活した」ことが字幕で出たが、「水俣」での仕事がこれだけの記述であったことは何とも残念だった。なぜなら、環境汚染という問題は現在もなお世界のあちこちで起こっている今日的な問題であるからだ。もしかすると権利関係のこと、「入浴する智子と母」の著作権所有者であるアイリーン・美緒子・スミスが、「智子を休ませてあげたい」という被写体の両親、上村夫妻の気持ちに答え、その写真使用の決定権を「お返し」したことも関係しているのかもしれない。それはそれとして、「水俣」について数行ののみというのにはいささか不満が残った。
『The Jazz Loft According to W. Eugene Smith』をきっかけに、ユージン・スミスの仕事を改めて見直しながら考えたのは、今日の写真表現についてであり、フォト・ジャーナリズムについてである。スミスは『ライフ』誌でフォト・エッセイという手法を確立した。それはテレビもない時代である。説得力のある写真と文章は人々の気持ちを動かした。
しかし、昨今はどこもかしこも画像や映像が玉石石石石石混淆、溢れかえっており、情報は濁流のように流れている。上手い写真、キレイな写真は多いが、ココロに引っかかるものは少ない。つまり上手いピアニストは多いが、モンクのように頭の中に残るピアニストは滅多にいないのと同じである。スミスは徹底した仕事ぶりで知られていた。テーマを決めて撮影に取り組む前にそれについて可能な限り勉強し、考えた。だが、今はどうだろう。何事も一見簡単に、また誰でも出来るようになりすぎた。そして、流されすぎてはいないか。感覚が麻痺してはないだろうか。戦争の残虐さや災害の悲惨さを伝える画像や映像は溢れているが、まるで映画のようで現実感がどことなく薄い。思考することが、そこに流通する事実や価値観、あるいは表現手法を批判的に見ることが忘れられてはいないか。そして、リアルとバーチャルの区別が曖昧になってしまった現代における表現とは、と逡巡したのだった。
奇しくも2017年はセロニアス・モンク生誕100年にあたる。
歴史上のジャズ・ジャイアンツは数多くいるが、これほどの異能は珍しい。私はなによりもピアニストとしての表現の独創性に惹かれる。その作品もまた創られてから数十年経つにもかかわらず、確立されたジャズに対峙し続けているように思える。だからこそ、ヨーロッパの前衛達も含め、多くのミュージシャンを惹きつけているのだろう。単なる「モンク祭り」には興味がない。だが、この機会にさまざまなモンク再考がなされることを2017年のひとつの愉しみにすることにしよう。
* 「窓の下のドラマ」というタイトルで1958年3月10日号『ライフ』誌に掲載時、彼が書いた序文より
『The Jazz Loft According to W. Eugene Smith』はオンデマンドで映像を入手できる。
http://www.wnyc.org/jazzloftthemovie/
参考文献
Sam Stevenson, The Jazz Loft Project: Photographs and Tapes of W. Eugene Smith from 821 Sixth Avenue, 1957-1965. New York (Alfred A Knopf) 2009
『ユージン・スミス写真集 1934-1975』岩波書店、1999年
土方正志『ユージン・スミス 楽園へのあゆみ』偕成社、2006年
http://www.nytimes.com/2001/06/03/nyregion/david-young-dies-at-71-painter-and-friend-to-jazz-artists.html


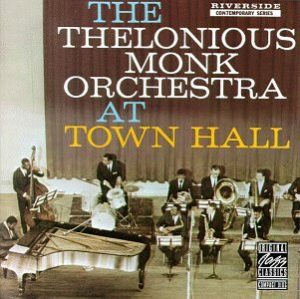
TV東京の「お宝鑑定団」を観ていたらユージン・スミスのオリジナル・プリントが出品された。
出品者の父親がミノルタに勤務中、カメラを紛失したスミスにカメラを提供したお礼にスミスからもらったもの。写真はスミスの代表作「楽園へのあゆみ」。出品者の希望額50万に対し、専門家の評価は500万円。今後さらに根が上がるだろうとの見方。プリントする際、細工が施され、スミスの署名入り。
スミスのキャリアが紹介されたが、残念ながらジャズとの関わりについては触れられなかった。何れにしても偉大なカメラマンだった。
http://www.tv-tokyo.co.jp/kantei/kaiun_db/otakara/20170718/02.html
現在、東京都写真美術館で「生誕100年 ユージン・スミス展」が開催されています。1/28まで。
http://www.crevis.co.jp/exhibitions/exhibitions_084.html