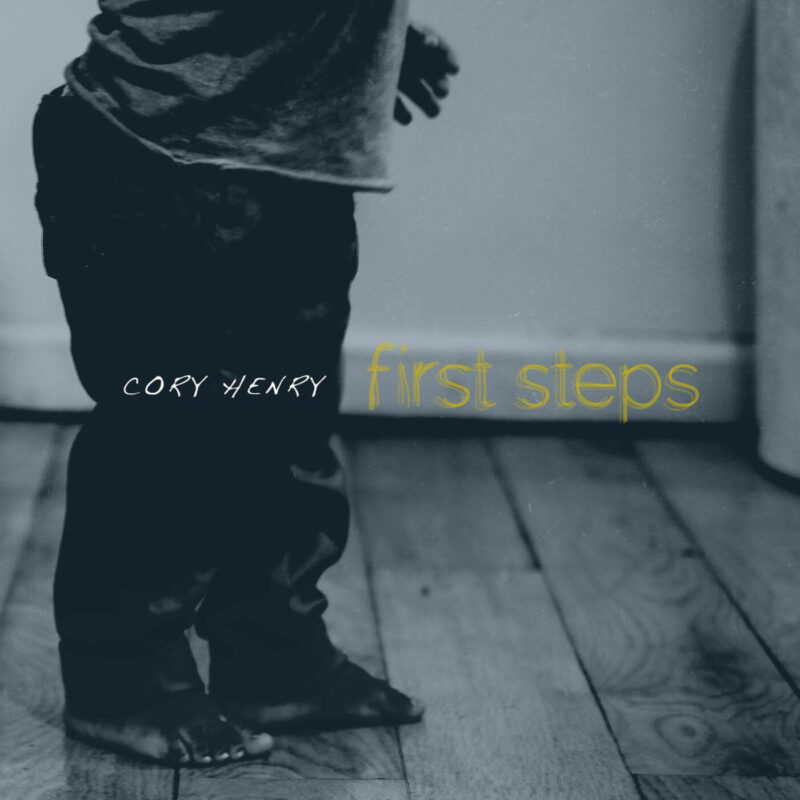ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #94 Cory Henry<Switch>
先日8月14日に念願のCory Henry(コーリー・ヘンリー:日本ではコリー)のライブを観に行った。ハモンドB3奏者として追従を許さないスタイルを築いたコーリーは、シンセサイザー奏者としても半端なくすごい。その彼がなんとソロピアノ及び弾き語りでのツアーということで、実はどんなライブになるのか気になってはいた。それが、予想以上の感動のライブで興奮未だに冷めやらず、といったところなのだった。


通常のジャズ・ファン同様、筆者も彼を知ったのは2014年に発表になったSnarky Puppy(スナーキー・パピー)の『We Like It Here』の最終トラック、<Lingus>での彼の演奏にぶっ飛んでからだ。正確には、その演奏の映像を観て顎落ち状態になってからだ。本誌No. 268、楽曲解説#57で触れたので参照頂くと良いと思う。まずはその映像をご覧頂きたい。この10分強の動画、コーリーのソロが始まるのは4分20秒付近からだが、ぜひ最初からお楽しみ頂き、4分20秒に戻ってコーリーのソロをもう一度観ると感動がさらに増すかも知れない。筆者はこの彼のソロを何度繰り返して観たことか。
神童コーリー・ヘンリー
この<Lingus>が録音/録画された2014年当時、1987年生まれのコーリーは27歳。コーリーのことがもっと知りたくてネット検索したが、なかなか情報は入手出来なかった。しかし、彼のプロとしてのキャリアは4歳にして始まっていた。
コーリーの母親は著名な教会音楽家だった。ピアノ、オルガン、ベース、ドラム、サックスの全てを演奏し、NYブルックリンにあるペンテコステ教会の聖歌隊のディレクターをも務めていた。コーリーが2歳のある日母親が礼拝の音楽の準備をしていると、自分が弾く音を全てコーリーが完璧に真似して弾くのに気がつき、<Amazing Grace>を弾いて見せると即座に習得した。2歳でだ!そこで母親が始めたのは、<Amazing Grace>を違うアレンジで覚える、という遊びだったそうだ。ゴスペル、ソウル、ファンク、ジャズ、サンバ、ロック、フォーク、全てのスタイルを試したそうだ。その度にコードまで変えて、と語っていた。今回筆者が観たコーリーのライブでも、「母が最初に教えてくれたこの曲から始めるね」と言って心に沁みるゴスペルでこの曲を聴かせてくれた。
上記の動画でわかるように、4歳にしてすでに彼は鍵盤を見ないで演奏しており、教会の会衆から「マスター・ヘンリー」と呼ばれる。この「マスター」とは「巨匠」または「師匠」の意だ。5歳にして5組の違う聖歌隊の伴奏をするほどの忙しいスケジュールをこなし、6歳であのアポロ劇場にまで出演した。あちらこちらで同じ曲を弾くことに飽きて来、母親に教えられたように色々なスタイルをアレンジして讃美歌を弾いてみたところ、教会の会衆から強い反感を受けたそんなある日、ラジオでOscar Peterson(オスカー・ピーターソン)が<Take The A Train>を、Duke Ellington(デューク・エリントン)のオリジナル録音と全く違う雰囲気で演奏したのを聴いた。それに習って讃美歌で試すと大絶賛を受け、これだ、と確信したそうだ。Art Tatum(アート・テイタム)なども聴くようになり、ジャズのイディオムも身につけ始める。さて、ここで突然母親が亡くなってしまう。コーリーはまだ6歳だ。そして父親も13歳の時に亡くなってしまう。原因は公表されていない。育てたのは祖母だそうだ。
コーリーのインタビューは断片的にしか見当たらず、また、あまり家族のことは語らないようなのだが、「父親がB3をバンの荷台に乗せてハーレムのあちらこちらでの演奏を助けてくれた。」という記述があったので、裕福な家庭ではあったのだと思う。母親に次いで父親をも亡くしてからより音楽に没頭したようだ。学校をサボり、マンハッタン48番街の「Manny’s (マニーズ楽器店)」と34番街の「Sam Ash (サム・アッシュ楽器店)」に入り浸ってひたすらピアノの練習をした。どちらのお店もコーリーを追い出すことはしなかったので、いつまでも練習に没頭出来たそうだ。
高校生になるとコーリーは130番街(注:ハーレム)にある「Village Underground」というクラブに入り浸る。残念ながらこのクラブ、今では音楽をやめてコメディー・ショーのみの上演となってしまったが、当時はB3がハウス・バンドの一部という珍しいクラブだった。コーリーにとってここが初めての、教会の外での音楽の場だった。ここでコーリーを目にしたのがKenny Garrett(ケニー・ギャレット)で、即座にツアーに雇われ、3年間世界中をツアーすることになったわけだ。これが2005年頃、コーリー18歳だ。それまでゴスペル系の音楽を中心に演奏していたコーリーは、ギャレットの演奏スタイルを即座に吸収してモダン・ジャズのスタイルをも消化してしまった。これがなければあの<Lingus>の演奏はなかったのだと思う。
残念ながらコーリーのケニー・ギャレット・ツアーバンドでの演奏の録音も映像も探せ出せなかった。正確には、ひとつだけお・し・る・し程度に出てきたのがこれだ。ギャレット・バンドで名を馳せたコーリーは、あちらこちらから声がかかるようになり、なんとBruce Springsteen(ブルース・スプリングスティーン)のバンドにも参加する。2010年に自己プロデュースの『Christmas With You』をリリースし(正式リリースは2020年)、プロデュース能力にも注目されるようになり、翌年Kim Burrell(キム・バレル)の『Love』でグラミー賞のノミネートやStellar賞などを受賞した。そして2013年にスナーキー・パピーに参加して<Lingus>以降は周知の通りだ。そうそう、そう言えばQuincy Jones(クインシー・ジョーンズ)に惚れ込まれ、2019年に『Soundtrack of America』というイベントでフィーチャーされたということもあった。
コーリー・ヘンリーの作品の歴史
正式には2014年発表の『First Steps』が最初のアルバムとされているが、『Christmas With You』の後にもう一枚ある。2012年の『Gotcha Now Doc』だ。この「(医者の)先生、今わかったぜ」という、よく意味のわからないタイトルのアルバムは2012年6月6日にNYCのRockwoodでのライブを録音したものだ。YouTubeにこのアルバムのプロモーション動画がある。このアルバムは筆者のお気に入りのひとつだ。<Donna Lee>、<Green Dplphin Street>と、ご機嫌なスタンダードで始まり、次にお馴染みの<Danny Boy>で得意なゴスペルを披露し、次にタイトル曲の<Gotcha Now Doc(後にタイトルからDocが外されて<Gotcha Now>でいきなりプログレッシブ・ロック!この後はソウルとファンクだ。ちなみに、2016年にスナーキー・パピーのGroundUpレーベルからリリースされた『The Revival』はB3とドラムのデュオ・ライブアルバムで、このアルバムが筆者の一番のお気に入りだ。このアルバムの8トラック目はなんと<Giant Steps>が収録されており、これがともかく素晴らしい。また、10トラック目には今回のボストンのライブでも披露したゴスペル風<Yesterday>が収録されている。
これに比べると正式な第一作目(事実上は三作目)である『First Steps』は、よくある「色々なアイデアがあり過ぎて」感がある。最初の曲はスナーキー・パピーの延長、次の曲はアフロ・キューバン・ジャズ、他の曲は、例えばChick Corea(チック・コリア)エレクトリック・バンドのサウンドがしたり、Herbie Hancock(ハービー・ハンコック)のヘッド・ハンターズのサウンドがしたり、色々なスタイルのブラック・コンテンポラリー風の曲や、プログレッシブ・ロック風などが散らばっている。但し、それでも筆者としてはかなり満足な出来のアルバムだ。何せどの曲もグルーヴが素晴らしい。確認は取れなかったが、Carlin White(カーリン・ホワイト)と思われるドラムがともかく気持ちいいいし、ドラム・グルーヴのアイデアも素晴らしい。もうひとつ特筆すべきは、なんとコーリーはB3にフォーカスせず、ピアノやMoogにフォーカスしている。<Lingus>の映像でもわかるようにコーリーはかなりのシンセサイザー使いだ。言い換えれば、彼は正真正銘のGear Head(機材オタク)なのであり、機材を操る優れた耳の持ち主なのだ。天は彼にいくつもの才能を与えたのだ。
さて、ここに来て2018年発表の『Art of Love』でコーリーは「Cory Henry & The Funk Apostles」を結成して変貌する。なんと70年代のソウルのサウンドに集中するようになったのだ。本人の話によると、Stevie Wonder (スティービー・ワンダー)、 Marvin Gaye (マービン・ゲイ)、Donny Hathaway (ドニー・ハサウェイ)、P-Funk、James Brown (ジェームス・ブラウン) などの音楽をやりたかったのだそうだ。ちなみに「Apostles(アパスルズ)」とは、聖書にある12弟子のことだ。このバンドは現在も活動している。
ところで、コーリーはJacob Collier(ジェイコブ・コリアー)同様Harpejji(ハーペジ)奏者としても半端ない。スティービー・ワンダーの影響らしい。この動画を是非ご覧頂きたい (YouTube →)。
コーリー・ヘンリーのスタイル

もちろんコーリーのスタイルは何と言ってもゴスペルが基盤になっている、が、前述の様にかなり広範囲に色々なスタイルをカバーしている。だからこそライブ録音の様に楽器を限定された方が本領を発揮する。スタジオでプロダクションの時間を費やして色々なスタイルの音楽を構築するより、限られた楽器編成のライブ現場で色々なスタイルの音楽を演奏した方が面白い結果が得られる。今回のライブでも、チック・コリアの<Spain>をゴスペル風に演奏して思いっきり盛り上がった。ところで、今回のライブでは3割がソロ・ピアノで、残りの7割は弾き語りだったのだが、弾き語りと言ってもガンガンにグルーヴする曲ばかりでゴキゲンだった。コーリーの歌い方のカッコいいことったらありゃしなかった。また右足にキック・ドラムを置き、これをむちゃくちゃ効果的に使っていた。興味深かったのは「Four On The Floor」、つまりバックビートの2拍目と4拍目を踏むのではなく、4分音符を全拍踏んでいることが多かった。つまり古いスイングジャズのスタイルだ。
コーリーの凄いところは、彼はB3、ピアノ、シンセサイザーのそれぞれを全く異なった楽器とはっきり認識しているところだ。例えば、ピアノ専門の人がRhodesを弾くとボイシングが汚くなったりする。クラシックではピアニストが本物のパイプオルガン(鍵盤が電動スイッチ化されていないという意)を弾くと全くパイプの音がしなかったりする。コーリーはインタビューでそれぞれの楽器の練習方法は全く違うと語っている。だからこそ彼のピアノの音色が素晴らしい。あれだけ強く叩くのに音色が全く痛くない。ピアノの下に向かって抜ける音なのだ。
B3は電子楽器ではない。実際に歯車の振動で音が出る有機的な楽器だ。コーリーのB3のドロアーの操作も、右足のペダルの操作も通常のB3奏者より遥かに細かい。また、左足のベースラインは、スイングでしっかりオン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブする。左手でベースラインを弾くB3奏者と違い、足でこれをやるのは簡単なことではない。どこかで見た動画で、彼がゲストとしてステージに上がって、弾き出してから左手で左の靴紐を解き、器用に左だけ靴を脱いでベースラインを始めるというのがあった。
コーリーが<Lingus>で操るシンセサイザーは 往年のKingKORGだ。このモデリング・シンセサイザーをコーリーはガンガンに弾きまくりながらモジュレーターをリアルタイムで巧みに操作しているのが映像でよくわかる。驚かされるのは、B3のドロアーもシンセサイザーのモジュレーターも、はたまたピアノの左手の演奏も右足のキックドラムも全てオートクルーズ状態、つまり全く意識と切り離すことが可能らしい。今回のライブでも左手でグルーヴし、右足でキックドラムを踏みながら聴衆と会話したり、今回取り上げた<Switch>では、グルーヴを維持しながら右手は完璧にルバートで演奏するという芸当を見せてくれた。二つのマーチングバンドが街で交差するというCharles Ives(チャールズ・アイヴス)の交響曲、<Three Places in New England>を思い出した。この曲では舞台に指揮者が二人上がる。コーリーの場合は一人でやってのける、二重人格状態だ。
話は逸れるが、このスタイルというものは実に不思議なものだと思う。筆者の個人的な意見では単純な音楽スタイル、例えばロック、ブルース、ゴスペル等は不変のスタイルで、いつの時代も万人が好きだ。つまり、廃れないスタイルというものが存在する。何か人間の本性に訴えかけるものがあるのではないだろうか。それに比べて70年代、80年代、90年代の音楽は時代と共に廃れて行く。ジャズ同様当時の素晴らしい録音を楽しむか、または当時のアーティストが健在で演奏するのを楽しむもので、その時代に育っていないアーティストが過去の時代のスタイルの曲を演奏してもどうも聴く気にならない(もちろんグルーヴ良ければ全て良しなので、言い切ることはできないが)。そう言えばオールデイズ、グループサウンドなども時代と共に消えたスタイルだ。いや待てよ。レゲーやサンバも不変だ。つまりその国の文化から発生したスタイルが全ての基盤を作るから、それを演奏することは基本に戻っているということだけなのかも知れない。何かものすごく大きな力を感じる。
『Live At The Piano (2023)』
このアルバムは今年の5月24日にリリースされ、7月から9月まではそのリリース・ツアーだ。筆者にとっての楽しみは、コーリーが以前に発表した曲の数々がゴスペル/ブルース調の弾き語りで聴けるということだ。筆者としてはどうしても70年代ソウルバンド風よりこちらの方が好きなのだ。っと言いながら、この記事が書き終わったらもう一度コーリーの70年代ソウル風のアルバムの数々を聴き直してみようと思っている。
このアルバムでは披露していないが今回観たボストンのライブで、彼はなんとB3奏法特有のグリッサンドをピアノ上で再現することを可能にしていた。B3でよく聞く長いドラマティックなグリッサンドではない。左手のグルーヴの間で溜めて短くビャアっと入れるあれだ。これがむちゃくちゃカッコいい。ピアノではあるまじきサウンドが出ていた。一体どうやってそんなことが可能なのか一生懸命彼の手を見た。B3では手のひらを押し付けてやるが、打楽器であるピアノでそれは不可能だ。どうやら彼は一瞬にして指を1点に集めて嘴のような形を作ってやっている様だったが、あまりの速さで自信がない。ともかくテクニックが半端ない。だが、なんと言ってもコーリーの演奏は「楽しい」の一言に尽きる。今回のライブではソロパフォーマンスだからこそのアドリブでコミカルな雰囲気も満喫させてくれた。ある意味で今回取り上げた『Live At The Piano』よりも素晴らしい演奏だったと思う。彼は「音楽に国境はなく、言葉が通じない国でも自分の演奏を楽しんでもらえるのが生き甲斐だ。だからやめられないんだ。」と語っている。ちなみにコーリーは今回のピアノソロ・ツアーを期にプロデュースなどのビジネス関係の仕事をやめ、演奏に専念するのだと発表している。
<Switch>
何せゴスペル系の単純な曲が多いので、どの曲が楽曲解説に向くのか迷った末、結局一番お気に入りのこの曲を選ぶことにした。ライブで「この曲は失恋して書いた曲なんだ。失恋って最低な気分になるよね」と言って演奏し始めた。12小節フォームではないが、これは正真正銘のブルース曲だ。
Used to be my angel then you switched
ぼくの天使だったのにすっかり冷たくなったね
I miss the way we was before(注:ここでのwasは黒人英語)
昔の二人に戻りたいよ
You flipped the switch and never flipped back
急に冷たくなって二度と戻って来ないんだね
You’ve done me damn wrong
ひどい仕打ちをしてくれたもんだ
And now all my money’s gone
こっちは一文なしになった
And now all my hope is gone
こっちは希望のかけらもなくなった
And only pain remains
残ったのは苦痛だけだ
この抜粋の最初の行に登場する「Switch」は「入れ替える」の意味で、他の男のところに行ってしまったことを示唆している。残りの「Swich」は全て電源のスイッチと被せている。つまりOFFにされてしまったという意味だ。急にバチンとフラれたことを示唆する。
曲のオープニングは、調性のB♭のブルース色強く、テンション#9であるC#音を交えて不安感を高めるアルペジオだ。ところがかなりアウトな響で別物のアルペジオが挿入される。採譜した。

ご覧の様にG7(13)という全くB♭ブルースと関係ないコードと、さらには同じB♭ルートでありながら#11というブルースとは程遠い響のコードのアルペジオが被さる。注目すべきは、G7(13)コードもB♭7(#11)コードも、どちらもトップ音がルート、ボトム音が♭7に配置されている。そしてどちらもモーダルな4度ボイシングを基盤にしている。これが何を意味するのか。コーリーは耳で適当にやっているのではない。モードジャズのボキャブラリーが身体に染み付いているからこういうサウンドが自然に出せるということだ。
56秒付近からこの曲のテーマであるオスティナートが始まる。このグルーヴがむちゃくちゃカッコいい。採譜した。

この録音ではご覧の様に最初1回目で「焦らし」を入れて2回目からグルーヴが固定する演奏になっている。それが今回のボストン・ライブではピックアップのC#を装飾音扱いにし、ダウンビートをもっと強く出してグルーヴ感を12倍にしていた。まあその気持ちいいこと。
さて、筆者がこの曲を特に気に入っている部分が1分33秒で登場する。”’Cause you don’t treat me like you should” と歌った直後のブレイクでダウンビートに一発ガンとくるB♭(#9)コードだ。このコードの演奏の仕方がすごい。言葉で説明するのは難しいが、ものすごい重力を持ったサウンドなのだ。しかも、これだけ打ち付けているのに全く痛い音がしない。サウンドが綺麗に下に抜けて行く。ちなみにこの重力感はもちろんキックドラムでパンチを効かせているからだ。このアイデアがまた素敵だ。この先このブレイクは何度も登場するが、毎回この素晴らしいダウンビートをお見舞いしてくれる。ワクワクものだ。
2分45秒の位置で俗に言うシャウトのセクションが挿入される。採譜した。

E♭7はブルースの4度コードなので普通だが、その4小節フレーズのターンアラウンドに登場するG7コードが実に新鮮だ。俗に言うロックの6度セブンコードとも考えられるが、続くのはドミナントの5度コードのF7ではなく、E♭7に戻るSubVコードであるE7コードなので、G7の存在が非常に新鮮なのだ。ちなみにこの曲では5度コードであるF7が一度も出てこないことも特筆されるべきだろう。こんなに単純そうな、よく耳にするブルースサウンドなのに、細かいところでかなり新しいアイデアが盛り込まれているのだ。コーリー・ヘンリー恐るべし。
それにしてもここからのコーリーのコミカルで表情豊かな歌い方の素晴らしいこと。本当にすごい人だと思う。続くのはコーリーのピアノソロだ。このグルーヴのすごいこと。この録音でのピアノソロは2分半程度だが、筆者が見たライブではその2倍以上だった。筆者がiPhoneで録画したその映像をご覧に入れよう。この曲が登場するのは5分49秒付近からだ。そして前述の右手がルバートになる二重人格は13分10秒付近からだ。ぜひお楽しみ頂きたい。
https://youtu.be/uUKIuYsDdbQ?si=vbOdNEv_yk0NKUBS
ハモンドB3, Charles Ives, KingKORG, ハーペジ, Harpejji, Soundtrack of America, The Funk Apostles, カーリン・ホワイト, Carlin White, キム・バレル, Kim Burrell, ブルース・スプリングスティーン, Bruce Springsteen, Village Underground, Lingus, Hammond B3, コリー・ヘンリー, アート・テイタム, Art Tatum, Cory Henry, Oscar Peterson, Snarky Puppy, スナーキー・パピー, チャールズ・アイヴズ, Quincy Jones, コーリー・ヘンリー, クインシー・ジョーンズ, オスカー・ピーターソン