#27 アルバート・アイラーとの五時間
text & photos by Kenny Inaoka 稲岡邦彌
アルバート・アイラーとの五時間
2021年2月3日 19:30~24:30 Dommune / youtube
企画/司会:細田成嗣
■19:30-20:30 TALK 1「ESP期アイラーの即興性またはエモーショナリティ」
出演:松村正人 渡邊未帆 大西穣
■20:30-21:00 LIVE 1「AAに捧げるソロ・インプロヴィゼーション」
出演:山田光(as)
出演:纐纈雅代(as)
■21:00-22:00 TALK 2「Impulse!期アイラーのポップ性またはスピリチュアリティ」
出演:柳樂光隆 imdkm 後藤護
■22:00-22:30 LIVE 2「AAに捧げるデュオ・インプロヴィゼーション」
出演:吉田アミ(voice)吉田隆一(bs)
■22:30-23:30 TALK 3「ジャズ /音楽/批評」
出演:佐々木敦 菊地成孔 大谷能生
■23:30-24:30 LIVE 3「AAに捧げるコレクティヴ&ソロ・インプロヴィゼーション」
出演:本藤美咲(bs)本藤達朗(tp)小幡颯人(as)阿部真武(el-b)林頼我(ds)宮坂遼太郎(perc)
出演:大友良英(g)林頼我(ds)
締め切りをとうに過ぎた今、レポートに代わる走り書きのメモで済まさざるを得ないことをたいへん遺憾に思う。
ジャズ・フェスで延べ5時間、あるいはそれ以上という体験は一度ならずあるが、ひとつのイベントをネット経由のストリーミングで5時間視聴しつづけるというのは初めての体験だった。しかし、コーヒーを飲んだり日本茶を飲んだりチョコをかじったりしながら苦もなく5時間が経過した(アルコールを控えたのは、アイラーと出演者に対するリスペクト、さらには感性にバイアスがかかることを恐れたためである)。新型ウイルス感染予防のためのステイ・ホームで、所属するふるさと未来研究所の月例会が1時間、つづくフォーラムが2時間、アフターアワーズが1時間の計4時間のZOOM会議で毎月鍛えられているからかも知れない。こちらは運営、出演のひとりでもあるから4時間の拘束が終わるとかなりの疲労感を覚えるというのが正直なところだ。しかし、今回のイベントは終わってみると5時間が経過していたということで、それだけ内容が充実していたということだろう。トークとライヴを交互にという構成が巧みだったこともあるだろう。トークの合間にはCDの演奏もあった。
1月23日の刊行以来話題を呼んでいる『50年後のアルバート・アイラー』、その刊行にちなむイベント『アルバート・アイラーとの五時間』。五時間は50年後にこだわったのだろうが意味のあるこだわりだった(単にDommuneの放送枠にはまっただけとは思いたくないほど)。自粛要請を受けてのDommuneスタジオからの無観客youtubeライヴ。7時開始の予告にもかかわらず一向に始まる気配がなくチャットが騒ぎ出した7時30分、30分押しでスタートした。24時に演奏を始めた大友良英が「わがままを言ってすみませんでした」と詫びを入れたところを見ると、大友のスケジュールに合わせた30分押しだったのだろう。結果的にはこの大友の豪胆な演奏が5時間のイベントの大団円となったのだから30分押しで大友を待った甲斐があったというわけだ。
上記のプログラムにもある通り、トークとライヴが3パートずつ、企画と司会は書籍の編著者でもある細田成嗣で、弱冠32才の細田が見事な腕の冴えをみせた。出演者の多くは書籍の執筆者だがトークの内容が執筆内容とどのような関わりがあるのか、書籍を未読の今、詳細に触れることはできない。
冒頭、アルバム『マイ・ネーム・イズ・アルバート・アイラー』(Debut 1964) から<サマータイム>がかかり、いきなり胸を突かれる。 このアルバム、Debut原盤を買い取ったロンドンのアラン・ベイツがFreedomレーベルから再発、日本では僕が勤務していた旧トリオレコードが1975年に国内盤をリリースしたのだ。先行したのは『Spirits』(Debut 1964)で、Freedom盤では『Witches & Devils』に改題の上、1972年国内盤リリース。もう1枚、Freedomからは『Swing Low, Swing Spiritual』(Osmosis 1971)が『Goin’ Home』と改題されて届いたが、このアルバムはニグロ・スピリチュアル(黒人霊歌)に焦点を当てた内容で、企画会議を通らず国内リリースを断念、Freedomの契約が徳間ジャパンに移行した後、1994年にリリースされたようだ。
TALK 1では、名曲<Ghosts>の由来について、スカンジナヴィアの民謡をネタにしたのではないかと該当すると思われる民謡との聴き比べなど。他にフランス国家を下敷きにした『Spirits ReJoice』(ESP 1965)なども話題に上がった。
LIVE 1は、アルトの山田光と纐纈雅代がソロを10分ずつ披露。山田のサーキュラー・ブリージングを駆使しながらのメロディアスな演奏に対し纐纈はあくまでフリーキーな演奏に徹し両者がアイラーのそれぞれの側面を対称的に聴かせた。纐纈が演奏後咳き込みながら「My Name is Masayo Koketsu」と名乗ったのは「My Name is Albert Ayler」のギャグではなく、進境著しい彼女のパフォーマンスに対する自負の表明であると理解したい。
TALK 2はインパルス期のアイラーの特徴をアルバム『New Grass』(Impulse 1969)を中心に解析。このアルバムについては渋谷のジャズ喫茶「Mary Jane」でも賛否両論が沸騰したことを思い出す。当夜も、ジャズ・プロパーの出番は少なく、imdkm(いみじくも)がテクノロジー的側面から電気楽器の導入や録音、ミックスを解析、後藤護が制作スタッフやグラフィックスの側面から興味ある解析を試みた。
LIVE 2は吉田隆一のバリトンサックスとヴォイスの吉田アミのデュオ。吉田のサーキュラー・ブリージングを挟みながらもメロディアスな演奏に対し吉田の喉を手でチョークしながら発するヴォイスとのコントラストが際立っていた。
TALK 3は、のっけから菊地成孔と大谷能生のコンビが暴走、楽屋の雰囲気をそのまま持ち込むありさま。間に挟まった佐々木敦がなんとか本来のテーマに持ち込もうともがくものの「トーク・セッションでは声の大きな者が場を制す」の言われ通り爆笑までマイクで拡声する菊地にまったく歯が立たず司会の細田もなす術を見出せず立ち往生。楽屋オチの連発からやっと、菊地がプレイヤーの立場からアイラーがテナーのマウスピースにバリトンサックスのリードを使っていたのではないかと実演を開始。『New Grass』のジャケットをかざして説得力を持たせた。菊地のデモ通りヴォリュームは大きくなるが音程がやや不安定なアイラーのゴーストが現れた。大谷がアイラー本の他に去年は『スティーヴ・レイシーとの対話』(月曜社)も刊行されたと言及、菊地が阿部薫の『僕の前に誰もいなかった』(文遊社)と合わせてサックス奏者の本が3冊揃ったと締めて終わった。
LIVE 3はエレキベースとパーカッションが加わった新世代による6人編成のユニットが風通しの良いコレクティヴ・インプロヴィゼーションを聴かせた。
24時に「予定」扱いされていた大友良英が無事登場、後半ドラムスの林頼我とデュオでパワープレイでアイラーを3曲演奏、オマージュとした。大友の豪胆な演奏でTALK 3の悪酔いを吹っ切ることができたのは幸いだった。
総じて、とくに企画者の細田成嗣につながる新世代のトークとライヴに脳のシワにたまった澱(おり)をきれいに洗い流すことができた。
最後にひとこと。画像で分かるように出演者にマスクを着用する者としない者が混在していたが、無観客配信とはいえトーク・セッション(それぞれかなりの熱弁を振るっていた)ではマスク着用は必須ではないだろうか。仮に、非着用者が抗体を持つ者であったとしてもだ。1000人に近い視聴者に対する「非言語メッセージ」を考慮する必要もあったのではないだろうか。アートに前衛は必要だが、人格に前衛は無用だと思うのだが..。
♪ 関連記事
中上健次『破壊せよとアイラーは言った』
https://jazztokyo.org/reviews/books/post-61890/












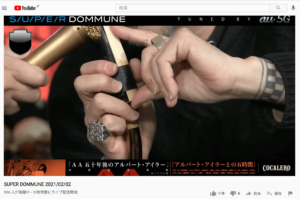





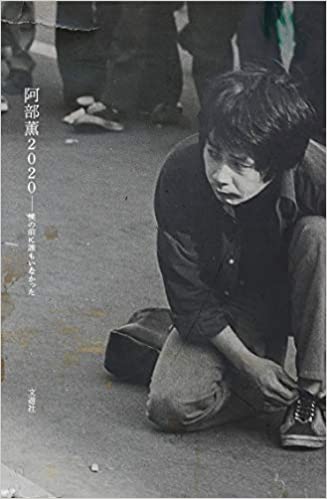


当夜メディア側から示されたマスク着用のルールは、隣り合わせに座るどちらか一方が着用すれば良い、というものだったようだ。