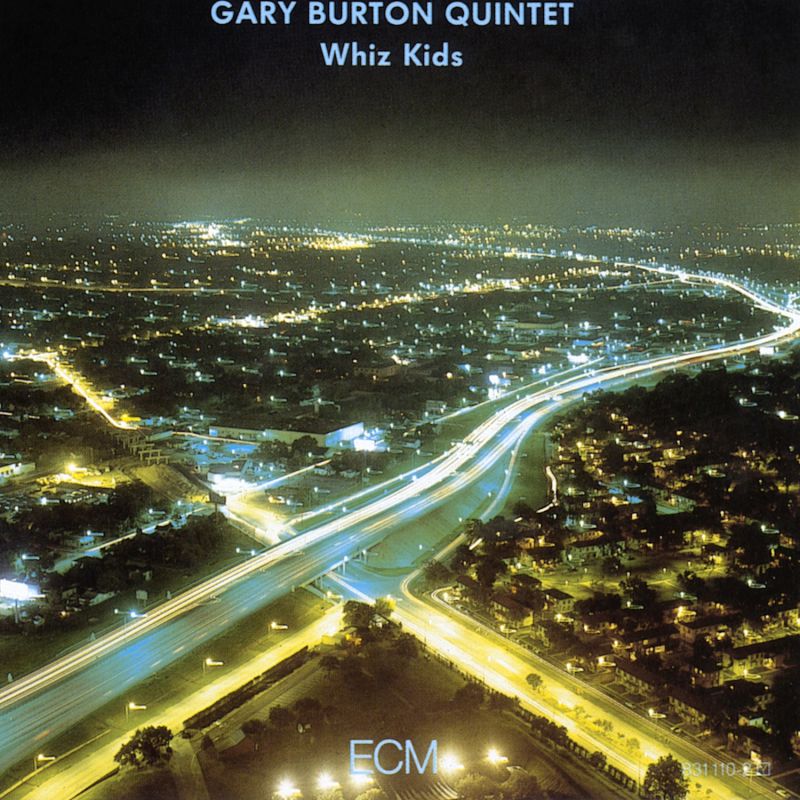中西光雄『Gary Burton Quintet / Whiz Kids』『ゲイリー・バートン・クインテット/神童』
1986年、ECMからリリースされたゲイリー・バートン・クインテットの『Whiz Kids』。
最初にお断りしておかなければならないが、私はこのアルバムのリアルタイムのリスナーではない。私にとって小曽根真に出会うことは、ジャズに出会うことと等しいが、それは2000年のことであった。もちろん、同世代の天才的なピアニストとして、小曽根真を知らないわけがなく、FMラジオから彼の名と演奏はたびたび聴いたことがあった。私はジャズボーカルが好きで、歌に対してはある程度の関心と好みとを持っていたが、ジャズ特有なインストゥルメンタルな掛け合い、インタープレイについては、むしろ小曽根真から全てを教えられたといってよい。2000年以降、小曽根は音楽のボーダーを超え、クラシック音楽にも果敢に取り組んで行くわけだが、私にとって、彼の師ゲイリー・バートンとのレコーディングは、小曽根のルーツを辿る中で出会ったということになる。
“Whiz Kid”とは、若くしてなにごとかを成し遂げたブリリアントな人物のこと。しかし、邦題の「神童」は、ジャズアルバムのタイトルとしてはなんだかダサく感じられ、当初は食指が動かなかった。ゲイリーの来日によって、彼と小曽根との親密な豊穣のセッションを聴くに至って、どうしても聴かずにはいられなくなったのである。そして、結論から言うと、私は恐ろしいほどの衝撃を受けたのである。「神童」“Whiz Kids”とは、ピアノの小曽根真と、スコットランド出身でサックスのトミー・スミスのこと。トミー・スミスは録音時18歳である。今ならさしずめ「ギフティッド」と呼ばれるに違いないこの「神童」たちが、全く遠慮のない師ゲイリー・バートンの挑発に乗って、誰も見たことのない音楽的世界を出現させるという壮大な物語。その過程が、収録された一曲、一曲に見事に実現している。「神童」たちを見出し、ステージという対等な場に連れてゆくことで深い音楽的経験を与えるかつての「神童」。それがジャズの「スコラ=学校」である。そのことが手に取るようにわかる。
L: 『Real Life Hits』(ECM1293) R: ファーストアルバム『OZONE』(CBS)
ゲイリー・バートンと小曽根真との出会いは、小曽根が留学したバークリー音楽大学でのこと。1984年には大学卒業直後の小曽根をピアノに迎えて『Real Life Hits』(ECM1293)を録音し、1985年にリリースしている。このアルバムの中に収録されたスティーヴ・スワロウの名曲〈Ladies in Mercedes〉は小曽根真の天才を世界に知らしめた。ゲイリー・バートン・カルテットの、ニューポート・ジャズ・フェスティバル・イン斑尾 (1984) でのこの曲の演奏は動画として残されているが、今なお新鮮な感動を呼ぶ。
Gary Burton Quartet / Ladies in Mercedes (YouTube動画)
『Whiz Kids』はその続編にあたるが、トミー・スミスの加入によってリファインされたといってよい。
ゲイリーは小曽根と出会った際、ピアノのテクニックに集中する小曽根に自分の曲を書くように勧めた。その話は有名だが、このアルバムでも、小曽根とトミーのオリジナル楽曲が演奏されている。小曽根の〈Yellow Fever〉は最近でもしばしば演奏されるが、若書きの作品とは思えない洗練された曲で、今日までの小曽根の音楽的成熟の道のりを予感させる。小曽根は若い頃、楽曲のタイトルをつけるのが苦手で、この曲のそれもベーシストのスティーヴ・スワロウに任せたのだという。小曽根のアジア人としてのアイデンティティを考慮して、〈Yellow Fever〉と名づけられたのだが、のちにそれが「黄熱病」と同名だと気づいた。でも、後の祭りだった。小曽根はユーモアを交えながら、楽しそうにこの曲を演奏するのが常だ。しかし、決してシンプルとは言えないこの曲は演奏が進むに従って熱くなる。燃え尽きるほどのインタープレイは、このアルバムの演奏に淵源を持つと言ってよい。
このアルバムを聴けば、ゲイリー・バートンの引退公演ツアーで、ゲイリーが小曽根真をパートナーに選んだ意味が誰にでもわかると思う。そして小曽根が、スコットランドを拠点に活躍するトミー・スミスと「ラプソディ・イン・ブルー」のオーケストラ版を作り上げた理由もわかる。音楽とは、「神童」が一切の余剰物を捨てて、それに向き合う時にしか達成できないものだからである。過酷だが喜びしかない世界。その世界に参入できる幸せを、私は感じないわけにはいかない。
ゲイリーとのセッションを終えた小曽根真は、深夜までゲストたちと語りあった翌朝でも、朝9時から練習を始めていた。ニューヨークでのことである。「神童」たちはいつでも「ただの人」になりうる。だが、真の「天才」は努力の人であり、今日の自分を日々書き換えているのである。
ECM 1329
Gary Burton (vibraphone, marimba)
Makoto Ozone (piano)
Tommy Smith (saxophone)
Steve Swallow (bass)
Martin Richards (drums)
Recorded June 1986, Tonstudio Bauer, Ludwigsburg
Engineer: Martin Wieland
 中西光雄 なかにしみつお
中西光雄 なかにしみつお
古典講師(河合塾元専任講師) 、音楽(唱歌・讃美歌)・国学研究。著書『蛍の光と稲垣千頴』、共著『唱歌の社会史』。小曽根真『Reborn』(2003)ライナーノーツ、兵庫県芸術文化センター・オーチャードホール公演(2019)・プログラムノート「小曽根真のあくなき挑戦」など。