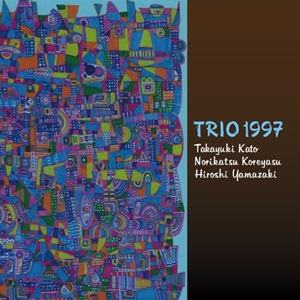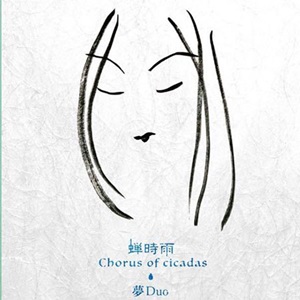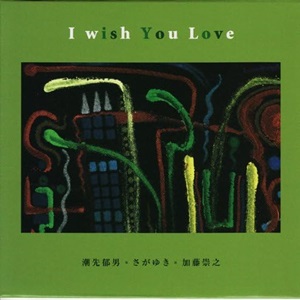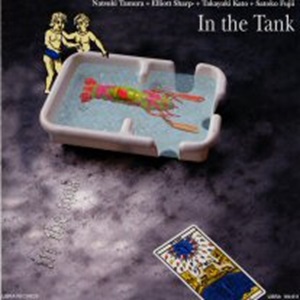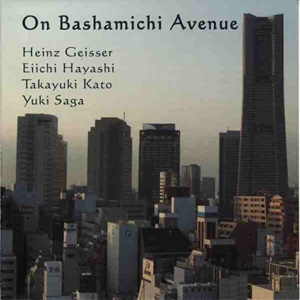インプロヴァイザーの立脚地 vol.24 加藤崇之
Text and photos by Akira Saito 齊藤聡
Interview:2024年9月1日 阿佐ヶ谷にて
加藤崇之は大ヴェテランでありながらまったく同じ場所にとどまろうとしない。音に対して自分を開き、つねに衝動やひらめきを大事にする人である。
気合です
とにかく、十代でプロになるのだという思い込みがあった。きっかけは中学3年生のときセルジオ・メンデス、ジョアン・ジルベルト、バーデン・パウエルらブラジルのミュージシャンたちを知ったことだ。中3の文化祭では、「全日本ライトミュージックコンテスト」で優勝した横倉裕(ピアノ)の姿を目にして、雷が落ちたように感じた。
そのあとクラシックギターを1年半習い、潮崎郁男のもとに4回通ってジャズギターを教わったりもした。それよりも大きかったのは、中学3年生から高校2年生までの3年間、ギターを「めちゃくちゃ弾いた」ことだ。必死だった。それで、「なんとかなる」と思った。「気合です。」
高校3年生のとき、ジョージ大塚(ドラムス)の教室に行ってみた。なんどか合宿にも参加し、志賀高原のスキー合宿ではじめてジョージさんに褒められた。「俺の弟子と演らないか」との誘いがあり、田中文彦(ドラムス)のグループに参加した。程なくして新宿ピットイン朝の部にも出ることができた。それもジョージさんの力があってのことである。大学1年生、19歳になっていた。
その後もジョージさんとの縁は続いた。田中文彦グループに参加して半年が経ち、同い年のギタリスト・秋山一将が、加藤をジョージさんに紹介してくれた。ジョージさんは、「あの加藤なら知っているぞ」と驚いたという。加藤はジョージさんのグループに入り、夏のジャズフェスなども含めて全国を回った。オフの日に与論島の海で遊んでいると、ボートの上にいるジョージさんから「上がってくるんじゃない」とオールで殴られたりもした。そういった世代特有の上下関係からくる問題もあったが、それだけではなかった。まだ「生半可な気持ち」だった。1年ほどして、ぼろぼろになってジョージさんのグループを辞めてしまった。
インプロが好きだった
加藤はあとで自分自身を振り返ってみて、高校生のころにはすでにインプロが好きだったのだなとわかったという。ハービー・マンの『Memphis Underground』をよく聴いていたのだが、特に好きだったのはふたりのギタリストのうち「ラリー・コリエルではないほう」、つまりソニー・シャーロックだった。急にハウリングを効かせて「バキューン、キュイーン」とやったりして、強く惹かれた。マンのコンサートを観にいったところ、共演者のダニエル・ユメール(ドラムス)がスティックでタムに穴を開けるなど破壊しており、仰天してしまった。
それにマイルス・デイヴィスの『Jack Johnson』や『Bitches Brew』にハマっていたし、ビートルズであればサウンドコラージュの<Revolution 9>(『The Beatles』に収録)や『Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band』のヘンな部分ばかりを聴いていた。オーネット・コールマンも嫌いから好きに変化し、クラシックでもラヴェルの『ダフニスとクロエ』やドビュッシーの『海』を聴きまくっていた。
そんなことを二十代の終わりころに自認するようになって、音楽活動への動機が生まれた。それはたとえば「破壊衝動」だ―――俺たちは日本人なのに、アメリカのジャズが正しいものだとしていつまでもお手本みたいにするのはおかしくないか? だからソロが回ってきても反旗を翻し、期待されるような音は出さなかった。頭が固いジャズファンを怒らせたくもなった。「アジア人としてのジャズをやろうよ!」
濃密な二十代
とにかく二十代は何でもやろうと思った。ブラジル人とのサンバのバンドもやったし、アメリカ人とディスコバンドを組んで米軍基地で演奏もした。向井滋春(トロンボーン)や益田幹夫(ピアノ)のフュージョンバンドも、それにもちろんジャズも。
当時はミュージシャン同士の評判でつながっていく世界だった。だから、ジョージ大塚のグループを辞めたあともすぐに声がかかった。オマさんこと鈴木勲(ベース)のグループに誘われたのも、ジョージさんのときと同じく秋山一将の推薦によるものだ。秋山はすでにブレイクしており、渡辺香津美のあとの大スターと目されていた。
菊地雅章(ピアノ、キーボード)のバンド「東風」にひと月ほど参加したのも二十代のときである。ときどき再来日する菊地さんに、ジョージさんが「しごいてやってくれ」と加藤を紹介したのだった。加藤は渡辺香津美の都合が悪いときなどに入った。菊地さんの曲は変拍子でとても難しく、わけがわからなかった。ジョージさんでさえもついていけず、ドラムスに村上ポンタ秀一が入ったりもしていた。ヤマカンやバクチが効かない世界だった。
濃い日々だった。
自分の方向性
リーダーになるという発想はなかなか生まれてこなかった。昔気質というのか、人に認められるのが先という考え方だったからだ。すなわち「免許皆伝」。チラシを作って自分から宣伝するようなことも好きではなかった。ところが、二十代の終わりころになってリーダーとして活動したくなった。方向性は3つ。ジャズのギタートリオ、インプロ、ソロだ。
ギタートリオは、早川哲也(ベース)、安部正隆(ドラムス)と一緒に始め、3年目に是安則克(ベース)、藤井信雄(ドラムス)とのトリオに落ち着いた。1年後にはリーダー作『Guitar Music』(1989年録音)を出すことができた。
インプロは金井英人(ベース)の誘いでデュオを始めた。もともと井上叔彦(サックス)が金井さんに「おもしろいギターがいる」と薦めてくれたからだ。息が合った。銀座のギャラリーで現代美術を前に演奏したりして、ずいぶんと盛り上がった。そして、ここからも世界が拡がった。1年ほど井野信義(ベース)、馬場たかもち(ドラムス)との演奏を経て、1991年、グループ「渦」として金井・馬場とのトリオで『渦』の第1作を吹き込んだ。馬場は空間をうまく使ったし、なにより加藤には「バクチ的」なやり方がぴったりきた。高柳昌行(ギター)が山崎比呂志(ドラムス)に「加藤が良いよ」と薦めてくれたから、山崎さんを「ニュー渦」に迎えることもできた。人の縁があって次の音楽が生まれた。
同じころ、神奈川県のライヴハウス足穂のマスターから「フェダインがマンネリ化しているから壊しに来て」と誘われた。不破大輔(ベース)、川下直広(サックス)、大沼志朗(ドラムス)によるトリオである。加藤にはなにしろ破壊衝動があった。さっそく参加して爆音を鳴らすと、メンバーも喜んでくれた。
渋さ知らズに加わりもした。「いつものように演って、でかい音で壊そう」と臨んで思い切りハウリングを効かせたりしたところ、最高の結果になった。そして、これが渋さ知らズのスタイルと化していった。1998年に初めてメールス・フェスティヴァルに出演したときには、<天城越え>の演奏が最高で涙が出てしまったという。そして3回目の出演のときには「散々楽しんだから卒業しよう」と考えていた。
ソロを始めたのは28歳のときだ。きっかけはエグベルト・ジスモンチの初来日公演を観たことだった。セルジオ・メンデスのステージでフィーチャーされるギターもよかった。よし、ガットギターでソロを演ろう、できなきゃダメだ。人の真似をせず、独自に。
インプロのひらめき
日本人としての意識は強い。実際、たとえばパーカッションであっても感覚がまるで異なり、その方向で他国に手本となるような人はいない。もちろんそれだけではなくさまざまな人がいる。もともとジャズはどう演ってもいいものだ。古くからの「武士道精神」を体現したようなフリージャズの人もいるし、そんなものとは無関係に平和的な人もいるし、パンクだってなんだっている。時代性と無縁ではないだろう。しかし、そんなことよりも外に出ることが大事なのだ。だから、若い人ともつねに「音の出しっこ」をして、なにかをもらっている。自分自身だって、インプロを演っているときにはつねに衝動やひらめきがある。
ジャムセッションのホストをやっていると、上手い人も下手な人も来る。パット・メセニーのコピーを演る人が来て嫌だったことがある。そんなことよりも、そこにいる「人」と演ることが大事なのだ。上手ければいいというものではないし、のっけから「自分」を出してジャズの方法論なんかで進めたら誰もが死んでしまう。皆、なにか音は出せるのだし、一緒になにかいいことができるはずだ。たとえば、擦ってみたり、叩いてみたりする。「どうやろうかな」という意識をもって演れば、相手も自分も生きる方法が見つかるはずだ。―――加藤はそのように考える。
絵描き
むかしから画家になりたかった。二十代の終わりに新宿ピットイン夜の部3デイズをやったとき、チラシを作ってみた。生まれて初めてだ。一枚一枚手で描き、百枚作った(コピーではない)。とにかく描きたかったし、調子に乗ってくると止まらなくなった。印刷会社を使う発想はなかった。
いったんは絵を描くことをやめて気持ちをしまい込んだが、アケタズ・ディスクからCDを出すときにオーナーの明田川荘之(ピアノ)にジャケットを描いてと言われ、応じた。それからまた描き続けている。
共演者たち
松風鉱一(リード)のカルテットにはずっと在籍した。かれの曲は大変な研究の成果であり、理解して演れるまでには時間がかかる。「最初は、コルトレーンの『Giant Steps』をはじめて演らされたトミフラ状態だったよ」と。ただ、それは難解なだけのものではなかった。最終的にはなんの音を出してもいいよ、という感覚で受け入れてくれたという。
ビリー・ホリデイの本を読んだところレスター・ヤングとの関係がとても印象的で、自分でもそれに重ね合わせる音楽ができそうな人を探していた。3人目の手合わせをしたのが宅シューミー朱美(ピアノ)で、アケタの店(西荻窪)、りぶる(市川)、横濱エアジン(関内)なんかにも連れていって共演した。すべてがバラードのようで、さらりとした指遣いで音楽が始まる。
音に対して自分を開くこと
加藤はいまの若い音楽ファンやミュージシャンに言いたいことがあるという。マニアックなのはいいが、その一方で情報が偏っていて共通の話題にのみ進んでしまう。情報が先行するあまり、たとえば目の前で石田幹雄や原田依幸といった素晴らしいピアニストが演奏していても反応ができない。それよりも事前に知った名前のほうに寄せられてしまう。
これはライヴハウスの変化とも無縁ではないだろうという。たとえば新宿ピットインの朝の部で演り昼まで長居すれば縁が生れた。別ジャンルのライヴもあった。ところが朝の部が消え、人気の出る特別公演のような企画が増えた。
大事なのは幅広く自分を開くことではないか。インプロを演る現場では宴会の二次会ノリでも面白がられ許されている人もいる。知らないものを持つ人と演れば、なにかがわかるものだ。気概も、これまでなにをやってきたかも、耳が良いかどうかも。
2024/11/10には、自分自身の音楽活動50周年記念ライヴを行う(新宿ピットイン)。
「この数年の間に出会った中でおもしろいと感じた人を中心に声をかけさせていただきました。」
ディスク紹介
(文中敬称略)
加藤崇之, フリー・インプロヴィゼーション