悠々自適 #81「The Lost Album よみがえったジョン・コルトレーン」
tsxt by Masahiko Yuh 悠 雅彦
The Lost Album よみがえったジョン・コルトレーン~コルトレーンに明け暮れた日々がよみがえる
はじめに。
去る7月初め、広島、岡山など西日本一帯を急襲した豪雨の犠牲になられた方々に、慎んで哀悼の意を捧げます。
…………………………………………………………………………………………………………
ジョン・コルトレーンの『THE LOST ALBUM』のニュースが最初に伝えられたときは、驚いたのはもちろんだが、それ以上に当初はまさかという気持の方が強かった。コルトレーン全盛期のスタジオ録音がなぜ今頃になって市場に飛び出して来たのかと。たとえ未発表作品でも ”コルトレーン” と名がつけば飛ぶように売れるレコード(盤)が、なぜ今になって突然に姿を表し、世を(ジャズ界にとどまらずという意味)騒がせているのか。
このニュースを聞いた瞬間、私はもう55年以上もまえ、大学(早稲田)に入って間もない(恐らくハイソサエティ・オーケストラに入部したころ)1960年代初め、あるジャズのレコードに衝撃を受け、徹夜して繰り返し聴いた時のことが脳裏によみがえった。そのLPレコードこそ、コルトレーンがプレスティッジからアトランティックに移籍して吹き込んだ移籍第一弾『ジャイアント・ステップス』だった。めまぐるしい、息継ぐ暇もないほどのフレーズを矢継ぎ早に織り成していくコルトレーンのプレイが “シーツ・オヴ・サウンド” と形容されて流布し始め、その形容がコルトレーンのプレイを特徴的に際立たせていることを多くのファンが納得し始めたころだった。
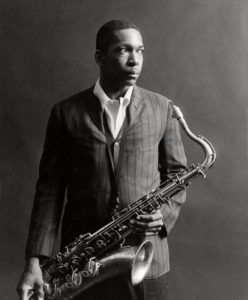 夜中遅くまでジャズのレコードを聴いた経験はビリー・ホリデイやミルドレッド・ベイリーなど幾つかあるが、正真正銘の徹夜は後にも先にもコルトレーンだけだった。それほどまでに『Giant Steps 』でのトレーンのテナー奏法は衝撃的で魅力的、かつ新鮮だった。いうまでもないが、コルトレーンの愛聴曲はほかにもたくさんある。とりわけ1957年に吹き込まれた彼の初リーダー作『コルトレーン』(プレスティッジ)の1曲 <Violets for Your Furs コートにすみれを> は今でも聴くことがある愛聴曲だし、むろん当時のジャズ界を代表するテナー奏者としての実力の一端を開示した『Blue Train』(ブルーノート)や『Soul Trane』(プレスティッジ)も飽きることなく繰り返し聴いた。それ以上に、それこそすべて口ずさめるほどに聴いた『ライヴ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード』(インパルス)の <Softly As in a Morning Sunrise 朝日のように爽やかに> でのソプラノ演奏やテナーでの <Chasin’ the Trane> 。思い出しただけでも往時の熱気がよみがえる。コルトレーンをめぐるそんな思い出が突然,『The Lost Album』での彼の演奏に触れた瞬間、火花のように弾け飛んで来たのだ。そして、60年代に入って結束を固めた彼の黄金のクヮルテットによるアルバム作りが当時のインパルスのプロデューサーだったボブ・シールの手で進められたことは周知の通り。その中でも『バラード』、『デューク・エリントンとジョン・コルトレーン』、『ジョン・コルトレーンとジョニー・ハートマン』は異例ともいえるヒットを記録した作品を含む、コルトレーン・ファンにとっては聖典ともいうべき彼の最盛期を飾る傑作群であることは言うまでもない。
夜中遅くまでジャズのレコードを聴いた経験はビリー・ホリデイやミルドレッド・ベイリーなど幾つかあるが、正真正銘の徹夜は後にも先にもコルトレーンだけだった。それほどまでに『Giant Steps 』でのトレーンのテナー奏法は衝撃的で魅力的、かつ新鮮だった。いうまでもないが、コルトレーンの愛聴曲はほかにもたくさんある。とりわけ1957年に吹き込まれた彼の初リーダー作『コルトレーン』(プレスティッジ)の1曲 <Violets for Your Furs コートにすみれを> は今でも聴くことがある愛聴曲だし、むろん当時のジャズ界を代表するテナー奏者としての実力の一端を開示した『Blue Train』(ブルーノート)や『Soul Trane』(プレスティッジ)も飽きることなく繰り返し聴いた。それ以上に、それこそすべて口ずさめるほどに聴いた『ライヴ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード』(インパルス)の <Softly As in a Morning Sunrise 朝日のように爽やかに> でのソプラノ演奏やテナーでの <Chasin’ the Trane> 。思い出しただけでも往時の熱気がよみがえる。コルトレーンをめぐるそんな思い出が突然,『The Lost Album』での彼の演奏に触れた瞬間、火花のように弾け飛んで来たのだ。そして、60年代に入って結束を固めた彼の黄金のクヮルテットによるアルバム作りが当時のインパルスのプロデューサーだったボブ・シールの手で進められたことは周知の通り。その中でも『バラード』、『デューク・エリントンとジョン・コルトレーン』、『ジョン・コルトレーンとジョニー・ハートマン』は異例ともいえるヒットを記録した作品を含む、コルトレーン・ファンにとっては聖典ともいうべき彼の最盛期を飾る傑作群であることは言うまでもない。
 今回初めてCD化された『Tha Lost Album』は1963年3月6日に行われたと記録されているが、実はこの翌日の3月7日には上記アルバムの『ジョン・コルトレーンとジョニー・ハートマン』の録音が行われたことになっているのだ。事実、ジョニー・ハートマンとのアルバムには今回の『The Lost Album』の収録曲<Villia> が入っているのだ(最初は『 The Definitive Jazz Scene vol. 3 』に収録されていた)。つまり、今回の『The Lost Album』の録音曲である <Villia> がなぜジョニー・ハートマンとのアルバムに追加されたかの理由は今となっては不明としか判断のしようがないが、これによって今回の『The Lost Album』が発売を前提として挙行されたものか、 あるいは後日もう一度録音し直した結果で発売するか否かを決定しようとしたのか。後者であることも充分に考えられるのではないかということだ。
今回初めてCD化された『Tha Lost Album』は1963年3月6日に行われたと記録されているが、実はこの翌日の3月7日には上記アルバムの『ジョン・コルトレーンとジョニー・ハートマン』の録音が行われたことになっているのだ。事実、ジョニー・ハートマンとのアルバムには今回の『The Lost Album』の収録曲<Villia> が入っているのだ(最初は『 The Definitive Jazz Scene vol. 3 』に収録されていた)。つまり、今回の『The Lost Album』の録音曲である <Villia> がなぜジョニー・ハートマンとのアルバムに追加されたかの理由は今となっては不明としか判断のしようがないが、これによって今回の『The Lost Album』が発売を前提として挙行されたものか、 あるいは後日もう一度録音し直した結果で発売するか否かを決定しようとしたのか。後者であることも充分に考えられるのではないかということだ。
ほかにも不可解なことがいくつかある。
まず、この『The Lost Album』と題されたセッションは、当時コルトレーンが吹込契約を交わしていたインパルスのプロデューサー、ボブ・シールがセッティングした公式の録音であった。私は70年にニューヨークで生活したが、そのおり会う機会があったボブ・シールは饒舌なほど気さくに話してくれる男だった。その彼が公式の録音でモノラル録音のリファレンス・テープをコルトレーンに渡し、正規のステレオ録音をスタジオに保管していなかったなんて常識では考えられない。私たちがユニバーサルの会議室で初めてこの演奏を聴いたときの説明では、コルトレーンは当時の妻だったナイーマに持ち帰ったテープを渡したというが、ナイーマの死後このテープを保管していた彼女の遺族が改めて見つけ出したことで、今回のCD化が可能になったということだった。私の記憶ではこの直後コルトレーンとナイーマの関係は破綻し、入れ替わるようにアリス・マクレオド(当時はマクロードと表記していた。コルトレーンと所帯を持ってアリス・コルトレーンを名乗るようになった)がトレーンの恋人としてクローズアップされたことで、私などは個人的な感情でナイーマに同情したことを思い出す。してみると、コルトレーンはアリスとの関係を深める過程でナイーマに預けたテープのことは忘れてしまったのだろうか。あるいは、正規の吹込セッションがもう1回あることを前提にしたコルトレーンの行為だったのだろうか。私は個人的には、この『The Lost Album』のコルトレーンのプレイが曲によっては極めて優れた内容を示している反面、別の曲の演奏では必ずしもコルトレーン的な満足度が得られなかったとトレーン自身が感じるところがあったからこそ、彼がナイーマに預けたテープに大した関心を示さなかったのではないかという気がしてならない。ライナーノーツを書いているのはアシュリー・カーンだが、彼が引用したラヴィ・コルトレーンの感想は私にはうなづけるものだった。彼は「これは、小手調べといった感じの試験的なセッションじゃないかな。僕にはそういう風に聴こえるね」。
 小手調べをラヴィは英語でなんと言ったか知らないが、少なくとも私にもこれがレコーディングの最終セッションであるとはやはり感じられなかった。ここに集められた全トラックにはアシュリー・カーンが書いているように「編集やミキシング、あるいはマスタリングといった、アルバム化に伴う作業が一切行われなかったということは判明しており、当然ながらカタログ・ナンバーの割り当てもカヴァー・アートもない」。とはいっても演奏者は天下のコルトレーンであり、曲によってはトレーン自信が認めたOKテイクといって何らおかしくない演奏もあったことは間違いない。私は個人的な意見として、アシュリー・カーンが解説文の冒頭に書いた「疑問の余地はない。ジョン・コルトレーンの他界から51年以上の歳月を経て新たな音源が発見されれば、その事実だけで歓喜に値する」という一文に賛同する。
小手調べをラヴィは英語でなんと言ったか知らないが、少なくとも私にもこれがレコーディングの最終セッションであるとはやはり感じられなかった。ここに集められた全トラックにはアシュリー・カーンが書いているように「編集やミキシング、あるいはマスタリングといった、アルバム化に伴う作業が一切行われなかったということは判明しており、当然ながらカタログ・ナンバーの割り当てもカヴァー・アートもない」。とはいっても演奏者は天下のコルトレーンであり、曲によってはトレーン自信が認めたOKテイクといって何らおかしくない演奏もあったことは間違いない。私は個人的な意見として、アシュリー・カーンが解説文の冒頭に書いた「疑問の余地はない。ジョン・コルトレーンの他界から51年以上の歳月を経て新たな音源が発見されれば、その事実だけで歓喜に値する」という一文に賛同する。
それはともかく、ジョン・コルトレーンというミュージシャンはファースト・テイクか、せいぜいセカンド・テイクでアルバム収録曲の演奏を終えるのが常だったと言われている。彼はそこに現れるエネルギーの新鮮さを第一の重要な要素にあげたことがある。もし彼のそうした発言に従えば、この『The Lost Album』のセッションはもしかすると、これら演奏の最良のテイクをピックアップして構成すれば良いと考えていたのかもしれない。<Villia > の演奏の1テイクを、ジョニー・ハートマンとのアルバムに挿入することに彼が抵抗しなかったとすれば、これはこれで彼には納得のいく演奏だったからかもしれない。
初めてコルトレーンの <Villia ヴィリア> を聴いたときは不思議な感じだった。その昔、ポール・ホワイトマンやとりわけアーティー・ショウ楽団の演奏がラジオから何度も流れるのを10代のコルトレーンは耳にしていたと見え、その親近感を素直に表現したのだろうか。フランツ・レハールというと日本では喜歌劇「詩人と農夫」や、かつて浅草オペラ全盛時に一世を風靡した喜歌劇「ボッカチオ」や「金と銀」で有名なオーストリアの作曲家(生まれはハンガリー)であり、ヨハン・シュトラウスと並ぶ人気作曲家だった。「ヴィリア」はレハールの有名な喜歌劇「メリー・ウィドウ」の中で歌われる最も有名なアリアだが、コルトレーンは余程気に入っていた曲と見え、珍しくテイクを5回も重ねて吹き込んだ。CD1(マスター・テイク)に入っているテイク3がかつて『ジョン・コルトレーンとジョニー・ハートマン』に加えられた1曲である。
しかし何にも増して、この『The Lost Album』の<デラックス・エディション>での聴きものは、曲名のついていない①「アンタイトルド・オリジナル」、③「アンタイトルド・オリジナル」、⑤「インプレッションズ」、⑦「ワン・アップ・ワン・ダウン」であろう。
ブルース進行に基づく①でのソプラノ・サックス、およびマッコイ・タイナーの各6コーラスのソロ、各8小節のAABA形式作品③における10コーラスのソプラノ・サックス・ソロ、続く同じ10コーラスのピアノ・ソロ。この二つのトラックを聴いたら、とても ”小手調べ” などという悠長な言葉は消し飛んでしまう。それほどコルトレーンのソロは彼の想念や闘志が彼の音楽的アイディアと一体となって前へ前へと前進する。とりわけ③でのソロは彼の最良の音楽的充実の一端を示すものだ。⑥の <Slow Blues>と⑦ <One Up, One Down>を続けて聴くと、タイトルの『The Lost Album』の lost が「失われた」ではなく、「よみがえった」と解釈すべきではないかとさえ思えてくる。 <Slow Blues> での2回にわたる全11コーラスの充実ぶりもさることながら、32小節の中の8小節をアドリブの核心として怒涛のような 14コーラスのソロとエルヴィンとの8小節交換を続けざまに演奏してマッコイにバトンタッチするトレーンのプレイは、<One Up, One Down> の聴きものというより本作の核心的演奏ではないかと聴いているうちに昔の熱さがよみがえってくるような思いだった。なお彼が来日する前の年(65年)、「ハーフ・ノート」でのライヴやニューポート・ジャズ祭での演奏でコルトレーンは <One Down, One Up> というタイトルの曲を演奏している。これを彼が正確に認識した上で演奏しているとすれば、コルトレーンとは見かけによらぬユーモリストということになるかもしれない。66年の彼の来日演奏時のステージや発言からは、そんな素振りは皆目見せることはなかった。だが、アシュリー・カーンは同じ増三和音を活用していることから同一曲で、現在は「ワン・アップ、ワン・ダウン」として統一されていると説明している。
本稿は演奏解説ではないので、①「ヴィリア」に始まる別テイク集(CD2)に触れることは差し控える。アシュリー・カーンによれば、コルトレーンが自筆で書き残したメモには正式なタイトルをつけずにいた2つのオリジナル曲(先に示した①と③)の候補題名として「トライアングルズ」と「サン・シップ」の名があったという。無論周知のように「サン・シップ」はのちに彼の死後発売されたアルバムのタイトルとなった。
いかに辛口の評価を下そうと、ジョン・コルトレーンの残した音楽は不滅であり、半世紀以上も前の演奏がこうして世界中のジャズ・ファンの注目を浴びる彼の偉大さをいま改めて思わずにはいられない。(2018年7月19日記)
ジョン・コルトレーン, ナイーマ, Giant Steps, エルヴィン・ジョーンズ, マッコイ・タイナー, ジミー・ギャリソン, Lost Album, ヴィリア, トレーン
