JazzTokyo
Jazz and Far Beyond

-

#69 小さなホールで出会った喜びと驚き
♩テクニックといい、表現術といい、演奏スケールといい、まさに舌を巻かざるを得ないソロ・サックスの妙技に酔った2時間余であった。(上野耕平:サクソフォン)
♩6歳を数えた2016年4月、<邦楽2010>が大きな春を迎えたといっていい小ホールでの出来事だった。(音のカタログ Vol.6) -

ナナ・ヴァスコンセロス ECM
唯一無二のブラジルの打楽器奏者、シンガー、ベリンバウの名手、ナナ・ヴァスコンセロスが故郷、ブラジルのレシーフェで亡くなった。享年71。(今年、エグベルトとナナはコラボを復活させ、4月には極東ツアーが組まれていた)
-

フォト・アーカイヴ ロベルト・マゾッティ(Roberto Masotti)
♩ Click any picture
-

フォト・アーカイヴ ノーマン・シーフ (Norman Sheef)
ノーマン・シーフ Norman Sheef
1939年、南アフリカ・ヨハネスブルグ生まれ。
サッカー選手、医者のキャリアを捨てて、69年、映像の世界を追求するためNYに移住。渡米直後マンハッタンに生きる人々の写真で認められ、音楽家、映画俳優を撮影するチャンスに恵まれる。 -

Nana meets Akiko Yano 上原 基章
『Tokyo Music Joy ’91 / 矢野顕子 with ビル・フリゼール、ナナ・ヴァスコンセロス』。往時「Live Under The Sky」と並んで私たちに音楽の「喜び」と「驚き」を体験させてくれたフェスティバル「Tokyo Music Joy」。そのラインナップの中でも一際異彩を放っていたのが、この公演だった。
-

ナナ・ヴァスコンセロス、自然へ還る
ナナを突然失ったご家族、仲間、ファンの悲しみは計り知れない。でも、不思議と森の中へ、風になって空と海へ、ビリンバウを背負ったまま還って行ったような爽やかな印象を残す。今年のラ・フォル・ジュルネのテーマ「la nature」にしても、自然と人を媒介する存在としての音楽の素晴らしさと不思議さに気付かされる。まさにナナはそのために世界に遣わされた存在なのかも知れない。
-

R.I.P. ナナ・ヴァスコンセロス
ナナが大地に還った。
3月9日。突然。4月20日の東京での一夜限りのコンサートを控えながら。
上海のECM ジャズ・フェスではエグベルトとのデュオの録音が予定されていたという。デュオのライヴ・アルバムも惜しいとは思うが、『Dança das Cabeças』(輝く水 ECM1089 1976)以上の演奏とはどういうものなのだろう。 -

AAOBB on TV – Archives
AAOBB-All Night All
-

プリンスを失ったことの痛み
マイルス:『プリンスは例の教会的なことをやるんだ。プリンスはギターもピアノも最高にうまい(筆者:ドラムもベースもとんでもなくうまい)。だがヤツの教会的なサウンドがヤツを最もスペシャルにしてる。例のオルガンサウンドもだ。黒人のものだ。白人のものじゃない。プリンスってのはオカマ用教会みたいなもんだ(筆者:意味不明)。ヤツの音楽は夜10時11時に遊びに出かけるヤツらのための音楽だ。プリンスはビートと共にやってきて、そのビートの上で演奏する。プリンスってのはきっとセックスの時ラヴェル(筆者:近代フランス作曲家)じゃなくてドラムを頭の中で鳴らしてるに違いない。だからプリンスは白いヤツじゃないんだ。ヤツの音楽は新しく、しっかりトラディションを理解し、88年、89年、90年っとしっかりと時代を映し出す。ヤツはこのまま行ったら次世代のエリントンだぜ。』
-

殿下と帝王と、そしてプーさん
マイルスとプリンスが交錯した時期、同じマイルスDNAの継承者である菊地雅章もプリンスを強く意識していたことは非常に興味深い。プーさんもその意味で、私にとっては to be continued….な存在だ。マイルスを軸としたプリンスと菊地雅章のトライアングル。未知の音への興味は尽きない。
-

追想 冨田勲 オスカー・デリック・ブラウン
私にとって冨田勲の音楽は覚めて欲しくない夢のような存在だった。
真の天才 ”冨田”。 -

連載第12回 ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報
チェス・スミス Ches Smith『The Bell』、マイケル・フォスター Michael Foster+レイラ・ボルドレイユ Leila Bordreuil『The Caustic Ballads』
-

ニューヨーク:変容する「ジャズ」のいま 第3回 境界を越える―ダリウス・ジョーンズ
ダリウス・ジョーンズのNYストーンでのレジデンシーがあった。彼にとって声の可能性とは何か、「フリー」の定義とは何か。
-

#1299 『アフリカン・ドリーム/明田川荘之~楠本卓司~本田珠也』
ピアノとツイン・ドラムという異色の顔合わせがホットでスリリング、三者入り乱れてのリズムの応酬の中からセンチメンタルなアケタのオーラが湧きたっている。
これまでにアルバムを出すたびに自己ベストの演奏を更新してきたアケタこと明田川荘之であるが本作『アフリカン・ドリーム』(AKETA’S DISK)にもアケタのベストが記録されている。 -

#1300 『矢沢朋子 / Absolute-MIX』
今回このアルバムを聴いて、矢沢朋子の素晴らしい音色と弧を描くタイム感でこんなにもミニマルミュージックを楽しめるものなのかと思ってしまった
-

#1298 『Christoper Zuar Orchestra / Musings』
ギル・エヴァンス(p,kb,arr)、ブルックマイヤー、サド・ジョーンズ(tp,arr)らからの強い影響を語るズアーだが、先人達をリスペクトし、クリストファー・ズアーは今、コンテンポラリー・ジャズ・ビッグバンドの新たな扉を開く。
-

#1297 『Grégoire Maret / Wanted』
トゥーツ・シールマンス(harmonica)の後継者と目されるグレゴア・マレのリーダー第2作。マレ自身とテリ・リン・キャリントン(ds)の卓越したプロデュースによって、けっしてオールスター顔合わせセッション的作品ではなく、ビッグ・ネームが適材適所に起用された、コンセプチャルかつ、現代音楽シーンの縮図がみえるアルバムとなった。とキャリントンの卓越したプロデュースによって、けっしてオールスター顔合わせセッション的作品ではなく、ビッグ・ネームが適材適所に起用された、コンセプシャルで現代音楽シーンの縮図がみえるアルバムとなった。
-

#1296 『Ryan Keberle & Catharsis / Azul Infinito』
現代ニューヨーク・ジャズ・ビッグバンド・シーンにおいて、マリア・シュナイダー・オーケストラを始めとする重要ビッグ・バンドに於いてメイン・ソリストを務めるファースト・コール・プレイヤー、ライアン・ケバリー(tb)のユニット、カタルシスの第3作目。本作では自らが演奏してきた南米音楽からの影響を受けた音楽で、リスナーにとっての“審美的なイヴェント”をもたらしたいと抱負を述べる。
-

#1295 『Marika Hughes / New York Nostalgia』
異能のチェリスト/ヴォーカリスト、マリカ・ヒューズのサード・アルバム。このアルバムは「自らの出身地、ニューヨークへのラヴ・レター」と語っている。ヒューズの多彩な音楽こそ、人種と文化の坩堝、ニューヨークを象徴していると言える。
-

#1294 『齋藤徹+かみむら泰一/Choros & Improvisations Live』、『齋藤徹+喜多直毅/Six trios improvisations with Tetsu & Naoki』、『ダンスとであって/矢萩竜太郎10番勝負!』
齋藤徹による春の刺激、3作品
-

#1293 『菊地雅章/黒いオルフェ』
Live Report で「僕の胸を締め付けたのは<オルフェ>と<リトル・アビ>であった」と特筆した2曲が収録されているのは殊の外嬉しい。さらに嬉しいのは、<リトル・アビ>こと愛娘・菊地あびさん撮影のスナップが9点もブックレットに使用されていること。これはこれで立派な菊地さんのフォト・ストーリーになっており、父娘共演の珍しい1作となった。
-

#1292 『ジャック・ディジョネット/イン・ムーヴメント』
こういう紹介文を書くと、年寄りが能書きを垂れるから若者がジャズから離れていく、としたり顔で若者寄りの意見を吐く御仁がいるが、ジャズはもともと社会と密接な関係を持ちつつ発展してきた音楽だ。ロックやフォークだってそうだった。バーミンガムの教会爆破事件やコルトレーンを知らずにこのアルバムを聴くとその意義は半減するだろうし、ミュージシャンが意図するメッセージも充分に受け取ることができないだろう。
-

#888 「京都フィルハーモニー室内合奏団/第203回定期公演」三陸のうた 祈り
私たちのあの悲劇への痛切な思いが、このときの演奏と合体した。少なくとも私はそう思って身を震わせた。汗を噴き出しながら指揮した斎藤の胸中に何が去来したのか。久保摩耶子は最後に書いている。<この「三陸のうた」を聴いて自然の大惨事の風景をそこに探そうとするならば、それは間違いです>、と。
-

#887 Swing MASA 爆音JAZZ
野宿者・失業者を支援する山谷労働者福祉会館において、大阪やニューヨークで活動するサックス奏者・Swing MASAのソロライヴが行われた。
-

#886 白石雪妃×類家心平DUO
類家心平のバンド「RS5pb」(Ruike Shinpei 5 piece band)によるニューアルバム『UNDA』のリリースを機に、書とジャズとのコラボレーションが実現した。
-

#885 喜多直毅クアルテット2016「挽歌」〜沈黙と咆哮の音楽ドラマ
境界を自在に駆け巡る異才ヴァイオリニスト、喜多直毅。そのメインプロジェクトであり、今年で活動開始から5年目を迎える「喜多直毅クアルテット」が、ティアラこうとう・小ホールでライヴを行った。
-

#884 JAZZ非常階段~ニヒリスト・スパズム・バンド来日公演
人は年を取ると子供に戻ると言われるが、子供の心を持ったまま活動してきたニヒリスト・スパズム・バンドにとって18年ぶりの日本は人生の最後の一幕というよりも、地元のギャラリーでの月曜日の演奏への新たな刺激になったに違いない。
-

Chapter43 ソニー・ロリンズ
ソニー・ロリンズは大の親日家で1963年の初来日から2010年の80歳記念ツアーまでしばしば日本を訪れている。 写真は1968年、2度目の来日時のもので、まだこの頃はサックスにマイクを着けていなかったので生の音が聴けた。ロリンズは興が乗ってくるとステージ中央のマイクから離れ、舞台の端から端まで吹きながら歩くのが常であったがノン・マイクでもロリンズのテナーは美しい音で客席を満たしてくれた。
-

ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #5『Purple Rain』
プリンスの看板曲、パープル・レインの解説。映画との関連、この曲が発表されたライブと1年後のリリースなどにも触れ、プリンスの天才的な曲の構成、コードのヴォイシング、コード進行等を解説。
-

#273 『矢沢朋子ピアノ・ソロ/Absolute-MIX』
音響の光線軸を明瞭に捉えた録音。エフェクトのオーバーダブの空間感とピアノ・ソロの軸。空間処理と録音時の緻密な計算が窺える
-
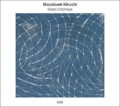
#272 『菊地雅章/黒いオルフェ』
東京文化会館小ホールでのライブ録音。大きな波動を感じさせるマイキングで捉え臨場感が見事。奏者の特徴的な高音部における連打が、肉厚に感じられ、これは従来の菊地雅章録音にはなかった収録の技。
-

#271 『田中鮎美トリオ/Memento』
トリオが均一な音像構成。リアルな効果的なサウンド造りと、空間感にヨーロッパ録音の特徴を聴ける。
-
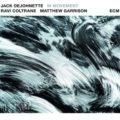
#270 『Jack DeJohnette / In Movement』
ドラムのリアルな音像展開を示した空間に、覆い被さるサックスの巨大音像が、聴く者を仰け反らす。
-

#269 『平林牧子+ボブ・ロックウェル/ゴング』
デッドな空間のリアルな直接音で迫るサックス。オンマイクのピアノが音場を濃厚に支配。若干のリバーブ効果が装飾音となっている。
-

#32 Pooさんの靴
帰り際、さすがに申し訳ないと思ったのか僕に靴とフランネルのパンツをくれた。新品ではなく菊地さんのお古。当時、菊地さんは最新流行のReebokのスニーカーを愛用していた。靴は茄子紺といったら良いのか本革のセミブーツ。お洒落好きの菊地さんらしい逸品である。
-

#650 『ミルバ&アストル・ピアソラ/ライヴ・イン・トーキョー1988』
今やピアソラの音楽とミルバの歌が結合した時の真価に開眼。もし、ピアソラがミルバを念頭にオペラを作っていたら、21世紀に新しいオペラの水脈がひとつ生まれていたかもしれない。
