JazzTokyo
Jazz and Far Beyond

-

#71 食べある記 XVI
16回目の今回は、ニューヨーク・リコリッシュ・アンサンブル、Satoko Fujii Quartet、くりくら音楽会~二台ピアノ大作戦、ニコール・ヘンリー(Nicole Henry)を食べ歩く。
-

RIP ルディ・ヴァン・ゲルダー
生涯に録音したアルバムは2000作を超えるという。その足跡を辿ることはモダンジャズの歴史を紐解くことになろう。
-

ルディ・ヴァン・ゲルダー 追悼
多くのエンジニアが挑戦したであろうルディ・ヴァン・ゲルダー・サウンドは、これで終わった。真似しても真似できなかった。
-

Farewell to Mr. Rudy Van Gelder
2016年8月25日、ルディ・ヴァン・ゲルダーが逝ってしまった。1989年4月25日に初めて、その伝説的なスタジオで撮影をするチャンスを頂いて以来の日々が、走馬燈の如く駆け巡った。最後にお会いしたのは、2014年のジャズ・アット・リンカーン・センターのディジース・クラブ・コカコーラで開催されたプレステッジ・レコード創立60周年記念パーティで、ヴァン・ゲルダーの90歳のバースディ・イヴェントでもあった。側近のドン・シックラー夫妻に付き添われ車椅子に座っていたが、相変わらず眼光鋭く矍鑠となさっていた。長年のご厚誼に感謝し、ご冥福をお祈りしたい。
-

#149 ルディ・ヴァン・ゲルダー 〜インパルス・イヤー、クリード・テイラーを語る〜
インパルス・イヤーは、とても重要だ。それは、コルトレーンのレコーディングが出来たことに尽きる。コルトレーンと共にモダン・ジャズ史に輝く作品を創りあげることが出来たのは、大きな自信となり、とても感謝している。コルトレーンが私を選んでくれ、共に過ごした時間は何にも代えがたい。私のキャリアにおいて、比類のない経験だった。
-

ルディ・ヴァン・ゲルダーの思い出
最後の音が消えフェーダーが下された瞬間、緊張から解放されたバンドから大きな笑いがはじけ、ずっと神妙な表情を続けていたルディの顔から初めて笑みが漏れた。ケイコさんと僕は拍手で彼らの健闘を称えた。ラッカー盤にルディが自分の名前を刻み込んですべてが終わった。
-

#086 「ヴァン・ゲルダー決定盤 101」
ジャズ喫茶で名盤に耳を傾け、新譜を追いかけたファンにはあの肉迫するスリリングでダイナミックなヴァン・ゲルダー・サウンドがまざまざと蘇ってくるだろうが、ヘッドフォンやイアフォン主体のデジタル世代の若者にはゲルダー・サウンドはどのように響いているのだろうか。
-

RIP トゥーツ・シールマンス
ギターと口笛のユニゾンは評判をとったが、晩年ますます味わいを増したハーモニカがやはりトゥーツのトレードマークだった。
-

巨匠トゥーツ・シールマンス逝く
ジャズを愉しむ余裕のあるファンならば、ほぼ例外なくこのハーモニカ親父(爺さん)の愛称を持つ名匠(口笛の名手でもある)の音楽が好きで、ぼくの周辺で彼を嫌いだなどという輩には、まだお目にかかったことがない。
-

追悼 : Toots Thielemans
photo & caption
-

ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #10『Obi』
トゥーツ・シールマンズが逝ってしまった。ブラジル音楽をこよなく愛したトゥーツの『The Brazilian Project』、その中からジャヴァンの名曲のひとつ、<Obi>を解説。ジャヴァンの卓越した作曲法と、トゥーツのハイレベルなブラジル音楽の理解度に焦点を当ててみた。
-

トゥーツ・シールマンス @ベルリンジャズ祭2004
2004年のベルリン・ジャズ祭、リシャール・ガリアーノのニューヨーク・トリオのゲストがトゥーツ・シールマンスだった。色彩感溢れ、どこまでも情感豊かに聴かせる息のあった名コンビぶりからは、とても2度目の共演とは思えない。演奏の合間にシールマンスがベルリン・ジャズ祭にまつわる思い出として語ったのは、ジャコ・パストリアスのことだった。
-

#1341 『生活向上委員会ニューヨーク支部 / SEIKATSU KOJO IINKAI』
パンクとフリージャズ、どちらも革命の拠点のニューヨークに赴き直に体験したミュージシャンが持ち帰り、自ら革命戦士となることで、日本の音楽シーンに変革をもたらしたという事実は興味深い。
-

#1340 『生活向上委員会:In NY支部』
ともあれ、祝CDリリース! 待ち望んでいました。おまけに、ドン・モイエまでが来日し、生活向上委員会と共演するとは! 一体どんな演奏が繰り広げられるのか。ぜひともライヴ録音をリリース願います。
-

連載第16回 ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報
ジャズ・シーンに復活したピーター・キューンの新旧のレコード、歌手フェイ・ヴィクターのスペシャルナイト。前者は経験豊富なクリフォード・アレンが執筆。
-

ニューヨーク:変容する「ジャズ」のいま 第7回 フリン・ヴァン・へメン~音楽らしい音楽、のすべて~
フィールド・レコーディングや詩の朗読などのあらゆるマテリアルを用いて、驚く様な仕掛けがちりばめられた渾身のデビュー作。その静かで魅力的な音楽的たたずまいの真髄にせまるインタビュー。
-

#1339 『The Fred Hersch Trio / Sunday Night at the Vanguard』
センシティヴなタッチとリリカルなプレイで、ヴァンガードのハウス・ピアニストと言える地位を確立したフレッド・ハーシュのヴァンガード・ライヴとしては4作目。Sunday Nightと銘打っているが、実際は金曜から日曜日の夜のベスト・テイクを現代ジャズ録音の名匠ジェイムス・ファーバーがヴィヴィッドに捉えた作品。
-

#1338 『Chris Pitsiokos Quartet / One Eye with a Microscope Attached』
クリス・ピッツイオコスたちにとってポップとアヴァンギャルドの境界は存在しない。ジャズもパンクもヒップホップも前衛もすべて等しく「音楽」でしかないという生まれながらに血肉の中に刷り込まれた感覚を武器に世界を撹拌するからこそ、彼らの音は限りなく「リアル」なのである。
-

#1337 『加藤真亜沙/アンモーンの樹 』
ニューヨークのジャズ・シーンに、また新たな才能溢れるピアニスト/コンポーザー/アレンジャーが登場した。斬新な4ホーンズのアレンジと、ユニークな作曲、エッジの効いたピアノ・プレイで、加藤真亜沙(p,kb,vo)は処女作とは思えない完成度の高いリーダー・アルバム『アンモーンの樹』で、鮮烈なデビューを飾った。
-

#1336 『The Cookers / The Call Of The Wild And Peaceful Heart』
中堅トランペッターのデヴィッド・ワイスが、9年前にヴェテラン・プレイヤーを結集して結成したオールスター・グループ、ザ・クッカーズが、レーベルをスモーク・セッションズ・レコーズに移籍して5枚目のアルバムをリリースした。ワイス自身が、最もスピリチュアルで、激しいプレイと自負する快作である。
-

#1335 『渋谷毅 市野元彦 外山明/Childhood』
渋谷と市野が弾くメロディーは遠い幼い頃の記憶を思い出させてくれるようなどこかで聴いたことがあるようなメロディーが次々と湧いてくるので、初めて聴いても昔から聴いていたような錯覚におちいる曲である。
-
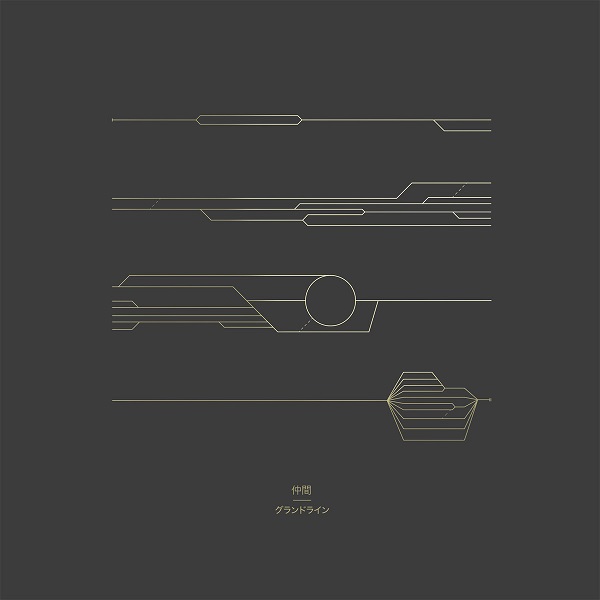
#1334 『Nakama / Grand Line』
Nakamaによる二枚目のアルバム『Grand Line』は、音楽の「形式」と「内容」の相互作用にフォーカスしたユニークな試みだ。それは北欧のローカルな音楽情況にとどまることのない、かつてなく魅力的な実践である。
-

#907 ブルーノート東京オールスター・ジャズ・オーケストラ directed by エリック・ミヤシロ with special guest イヴァン・リンス
イヴァンは、ステージ上でも「キラー・ビッグバンド」と絶讃し、演奏を終えて、再度の共演を希望し、「一緒にツアーに出たい」とまで言ったらしい。それは簡単ではないにしても、その言葉に値する演奏だった。
-

#906 マイク・スターン・トリオ with special guest 渡辺香津美
二人のプレイとソロをたくさん聴かせてくれたこの公演に会場のギターフリークはしっかり満足したに違いない。比較すると、マイクは2〜3コーラス以上の長い時間の流れの中でフレーズが生まれ、ハーモニーを創り出すのを感じるのに対して、渡辺は各コーラスのそれぞれのパートで自在なテクニックを活かした高速フレーズを繰り出して来る。どちらが優れているということではなく、音の生まれ方の違いがわかって面白い。
-

Chapter 45 ポール・デスモンド
ポールのフレーズをなぞらえるミュージシャンは結構いるがポールのニュアンスまでも引き出すことは出来ない。
常に唯一無二の存在であり続けたポールの音は永遠に不滅である。 -

#20 Norwegian cool jazz trio +one
天候の懸念もあり1stセットでB♭を後にしたが、この時代に東京の赤坂でノルウェーの若い世代が牽引するクール派ジャズを堪能できるとは夢にも思わなかった。
-

#296 『Miroslav Vitous / Music of Weather Report』
ミックスにも細心の注意が払われたと観察。録音終了後のミックス技術に相当な時間を要したと思う。
-

#295 『Mats Eilertsen / Rubicon』
アンサンブルに、カッコ良くヴィブラフォンが乗っかる。ベースの音像も小音量時も明確な音像だ。美しい音色のピアノがたまらない。ドラムもギターも。
-

#294 『Glauco Venier / Miniatures~Music for Piano and Percussion』
ホール中央にピアノが置かれた周辺を時々遮る打楽器の遊び、これを想像する。
-

#293 『Jim Black / The Constant』
ピアノの自然さに対するベースとドラムが迫り来る音像は、このグループの印象を強める効果なのかも知れない。
-

#292『Peter Erskine John Taylor Palle Danielsson / As It Was』
このサウンドを聴いていると、ジャズの分野でのハイレゾ録音の可能性を感じ取る。
-

#291『Dominique Pifarély Quartet / Tracé Provisoire』
リバーブ処理を上手く使って空間に泳がせる表現に、現実の演奏の輪郭がドサッと展開。
-

#290 『Sinikka Langeland / The Magical Forest』
私自身、今まで経験しなかった録音とミックス技術を尽くした録音表現作品だと思う。
