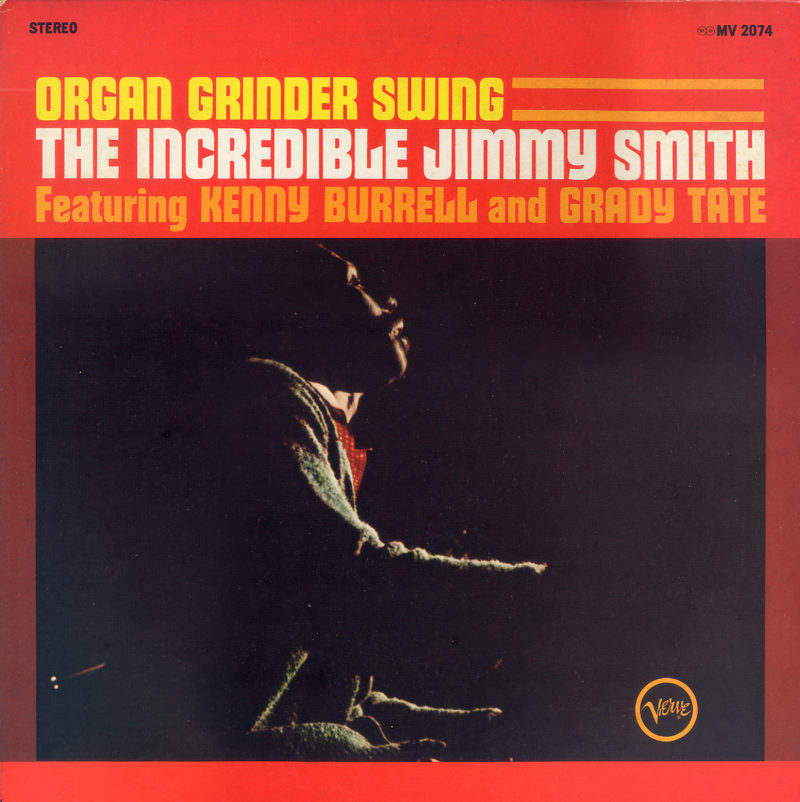ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #24 Grady Tate <Satin Doll>
筆者率いる「ハシャ・フォーラ」の新譜『ハッピー・ファイヤー:ニュー・カインド・オブ・ジャズ』発表ツアーのため筆者は昨夜来日(帰国?)し、この連載に穴を開けないようなんとか努力中。今月は8日にグラディ・テイト(Grady Tate:正確にはグレィディ・テイト)が亡くなった。85歳だったそうだ。原因はDementia(ディメンチャ)、日本では認知症を言うらしいが、正確には脳障害であって認知症などと言う精神障害的な診断名が付くのがどうも解せない。筆者の親分、ジョージ・ラッセルもこれで亡くなり、常々「脳器質障害」とか呼んで欲しいと思う。今回は楽曲解説と言うよりは、演奏者解説になる。

NYTimes
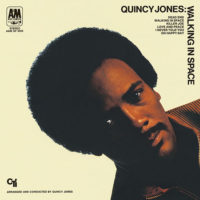
どれだけのジャズ愛好家がテイトのことをご存知だろうか。彼は誠に特殊な演奏家なのだ。ヴォーカリストとして成功したドラマーだからではない。彼のヴォーカルは痺れるほどかっこいいが、彼の地味なドラミングのグルーヴは失神するほどかっこいい。
クインシー・ジョーンズの『Walking in Space』(1969)に収録されている、あの超有名な<Killer Joe>、レイ・ブラウンのオン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブするベースラインに対し、レイドバックした心地の良いドラム・スタイルなのに、喰いつくように攻撃的にドライブするテイトのタイム感が彼を一躍有名にした。このドライブ感が唯一無二で、オン・トップ・オブ・ザ・ビートに聞こえないオン・トップ・オブ・ザ・ビートとしか言いようがないタイム感なのだ。このオン・トップ・オブ・ザ・ビートとビハインド・ザ・ビートの言葉の意味はこちらの記事を参照されたい(→)。
テイトはNYCのファースト・コールで、実に沢山のアルバムに参加している。Wikipediaにはサイドマンとして120枚もリストされている。その多くは聞いたことのあるアルバムだが、派手にテクニックを披露するようなことをせずただひたすらグルーヴするスタイルなので、テイトだと気がつかなかったアルバムがほとんどだ。ただ筆者は個人的にケニー・バレルが好きだったので、バレルのアルバムや、バレルがよく共演していたジミー・スミスのアルバムで馴染みがあった。そんなテイトがある日テレビで中継中の、サイモンとガーファンクルのマディソン・スクエア・ガーデンでの再会ライヴでドラムを担当していたのを偶然見て驚いたものだった。それと、アメリカでもっとも視聴率が高かったジョニー・カーソンのトゥナイト・ショーに6年間もドラマーとして毎晩お茶の間に現れていたらしい。70年代のことだ。 そして、デイヴィッド・リンチの代表作、『トゥイン・ピークス』のオリジナルとリブート・バージョン両方のサウンド・トラックで演奏したことでも有名で、なんとそのトラックの一つは<Grady Groove>というタイトルがつけられているのだ。つまり、彼は商業的に相当な成功を納めていた。60年代の終わりにすでに歌手として成功していたのに、だ。そんな彼のドラミングの秘密はなんであろうか。余談だが、何かの番組でテイトが『ムーン・ダンス』を歌っているのを見たときはあまりのかっこよさに痺れまくった、と同時にこんなすごい歌手だと知らなかった驚きを今でも覚えている。
グラディ・テイトの特異なキャリア

テイトは60年代半ばにクリード・テイラーがプロデュースするレコーディングのお抱えドラマーとして活躍した。その相方のベースは、これも超オン・トップ・オブ・ザ・ビートのロン・カーターだった。クリード・テイラーは良くも悪くもジャズの歴史を変えた貢献者の一人である。ジャズを70年代にイージー・リスニング系に移行させ、ジャズファンを増やし、数多くのジャズミュージシャンの名前を一般に浸透させた。ジョージ・ベンソン、フレディ・ハバード、スタンレイ・タレンタイン、チェット・ベイカー。数え上げればきりがない。筆者はウエス・モンゴメリーの『A Day In The Life』を初めて聴いた時に、まだ頭の硬い若造だったので、大好きなウエスにこんなコマーシャルなことをさせたテイラーを恨みさえした。しかしマイルスにジャズは博物館に展示する音楽ではなく、常に発展しなくてはいけないと教えられて耳を傾けてみると、まずドン・セベスキーのオーケストレーションに感銘し、そのサウンドを他の多くのアーティストたちの作品にも反映させたテイラーのプロデュース能力に感心した。テイトのレコーディングのタイムラインを見ると、テイトはテイラーに見出されてクインシー・ジョーンズに出会ったと勘違いをしていたが、色々調べているうちに今回全く逆だったと学んだ。
グラディ・テイトの特異なスタイル
テイトの得意な演奏スタイルは彼の性格と大きく関係すると思われる。彼は以前「Modern Drummer」誌のインタビューで、ドラムソロは大嫌いだと言っていたのを思い出す。彼は自分はグルーヴを提供するドラマーと心得ていた。また、同インタビューでセッションの進行を妨げるような行動を取らないこと、例えばセッションに遅れるなどは絶対しないと強調していた。さて、彼のキャリアを見てみると意外と受動的なのに驚かされる。
高校卒業後空軍楽隊に入る。アメリカの軍楽隊のレベルは異常に高く、独学だったテイトはここで初見などの技術を身につけた。退役後大学で英文学を専攻し、ワシントンDCに引っ越して高校の先生を始める。ドラムは全くやめていた時期に、発散のためセッションで1曲叩いたのを聞いたバンドに速攻で雇われ5年ツアーする。急に思い立ちNYCに引っ越し、今度は俳優になるべく大学の演劇科に入る。ここで旧友の一人がテイトのドラミングの才能を惜しみ、クインシー・ジョーンズにテイトを引き合わせテイトの本格的なキャリアが始まるわけだ。軍楽隊で鍛え上げられたテイトは、譜読みと仕事に対するプロフェッショナリズムに加え、追従を許さないタイム感で一挙にファーストコールになった。
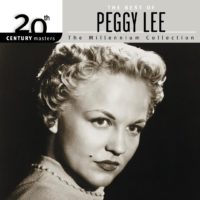
同様に彼は別に歌手になりたいと思っていたわけではなかったらしい。彼はあくまでも趣味で歌っていたのに、サポートを勤めていたペギー・リーに強く勧められてペギーの舞台で歌って、そこから彼の歌手としてのキャリアが始まった。つまり彼のキャリアは他人が彼の才能を惜しんで彼を押し出した形で成り立っている。控えめな性格だが周りが放って置けない才能、いや、驚くほどの才能だが控えめな性格だから周りが助けたいと思うのかもしれない。いずれにせよここでいう彼の「才能」だ。すごいテクニックで見せつけるようなことは絶対にしない。彼は70年代のR&Bをドライヴさせたというような形容詞をどこかで読んだ記憶があるが、よく聞いてみれば彼は他のR&B系のドラマーのようなタイトなビートは決して刻まない。ちなみにここで言うタイトという意味は、ベーシストとキックドラムが一糸乱れず同期し、その間のポケットにスネアがバックビートでグルーヴするという意味だ。テイトのバックビートは、なんとR&B系ではありえないオン・トップ・オブ・ザ・ビートなのだ。
彼のオン・トップ・オブ・ザ・ビートは、トニー・ウイリアムスなどがライドで攻撃的に追い上げるようなわかりやすいビート感では全くない。無理やり彼のビート感を説明しようとすれば、例えばフィリー・ジョー・ジョーンズのようなよだれが出そうなビハインド・ザ・ビートのドラミングを録音して、480割のMIDIティックでパルスより20ティック前に移動したような、と言うような説明がわかりやすいかもしれない。筆者は今ツアー中で、自分のスタジオで実際何ティック前なのか検証できない状態なので、この20は想像で言っていることをお許し頂きたい。ここで面白い発見をした。テイトは1974年にガトー・バルビエリの『チャプター・スリー』と言うアルバムにロン・カーターと参加している。1年以上前に解説した『Fenix』(→)と違い、ロン・カーターはタイム感の合うテイトとの演奏なので、持ち前のオン・トップ・オブ・ザ・ビートでラテンのリズムにそれほど違和感のあるサウンドを出してはいないのはありがたいのだが、困ったことにテイトはロン・カーターとぴったり同期してしまっている。ラテンなのだからもっとオン・トップ・オブ・ザ・ビートの位置にいないとドライヴしないのに、だ。つまりテイトのオン・トップ・オブ・ザ・ビートのタイム位置は生まれ持ったもので、トニー・ウイリアムスのように自由自在に変えられると言うものではないらしい。
『Organ Grinder Swing』

ハモンドB3オルガンの王者、ジミー・スミスのオルガン・トリオだ。もちろんこのフォーマットを築いたのはウエス・モンゴメリーだ。しかしそのサウンドは天と地との差がある。ウエスのトリオはオルガンにMelvin Rhyne(メルヴィン・ライン)、ドラムにPaul Parker(ポール・パーカー)、3人ともビハインド・ザ・ビートでグルーヴするタイプだし、メルヴィン・ラインのペダル・ベースはメトロノームのようにオンの位置にあり、ベースがドライヴしない分、普段ビハインド・ザ・ビートが売り物のウエスがドライヴするコンピングを刻む。これが結構危険で、終わった時に始めより速くなってしまった曲などあったことを思い出す。これに反しジミー・スミスのオルガントリオは全く逆だ。まずケニー・バレルだ。ジャズ・ギタリストにはとても珍しい、驚くほどオン・トップ・オブ・ザ・ビートの奏者だ。本人から聞いたのだが、彼は1/4アメリカ・インデアンの血が混ざっているそうで、その辺りが彼の特異なタイム感を生み出しているのかもしれない。そしてジミー・スミスだ。彼のペダル・ベースはジャズのご機嫌なベーシストのようにオン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライヴするのに対し、手のコンピングはご機嫌にビハインド・ザ・ビートでスイングし、インプロする右手は縦横自在にオン・トップ・オブ・ザ・ビートとビハインド・ザ・ビートの間を駆け回る。そしてグラディ・テイトだ。
このアルバムでのテイトは非常にわかり易い。ライド・シンバルはジミーのオン・トップ・オブ・ザ・ビートのペダル・ベースのギリギリ前のもっとオン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライヴするのだが、一つ一つのライドの音の間には十分スペースがあるので、まるでレイドバックしているように聞こえる。つまり彼自身のビートがパルスよりも前にあると言うことだ。これは筆者がレイ・ブラウンを目の前で見た時の発見の感動と同じだった。テイトのスネアやフィル(おかず)はほとんどオン・ザ・ビートの位置にあるが、同じく幅があるのでレイドバックして聞こえる(注:前述したようにテイトのバックビート・スネアはオン・トップ・オブ・ザ・ビートだ)。これに対してハイハットが異常にオン・トップ・オブ・ザ・ビートで、彼のドラム・パーツ全てがレイドバックして聞こえるのに、ハイハットだけが唯一常に喰いついて聞こえる。こんなドラマーが他にいるだろうか。もう一度言うが、スイングでも、R&Bでもソウルでも、テイトが入るとレイドバックサウンドなのに、エキサイティングなサウンドになるのだ。驚異的である。
<Satin Doll>
今回は楽曲解説の楽理の部分をすっ飛ばさせて頂き、大スタンダード、<Satin Doll>、ウエスのバージョンとジミー・スミスのバージョンを聴き比べて頂きたい。
https://youtu.be/uQrORPnJHMM
ジミー・スミス, Ray Brown, Tonny Williams, ペギー・リー, Peggy Lee, Creed Taylor, Quincy Jones, ウエス・モンゴメリー, Wes Montgomery, ケニー・バレル, Kenny Burrell, Jimmy Smith, グラディ・テイト, Grady Tate, レイ・ブラウン, トニー・ウイリアムス, クインシー・ジョーンズ, Ron Carter, ロン・カーター, クリード・テイラー