Hear, there and everywhere #10 「 I ❤ Vinyl」
text by Kenny Inaoka 稲岡邦彌
リトアニアとオランダから2枚ずつLPが送られてきたので、どうせならハイエンドに近い再生装置で試聴しようと、休業中の白楽のカフェ・バー「Bitches Brew」を開けてもらった。オーナーは本誌でフォト・エッセイを連載中のジャズ・フォトグラファー杉田誠一である。リトアニアのNoBusiness Recordsから届いたのは、バール・フィリップスと吉沢元治のベース・デュオ『Oh My, Those Boys!』(NBLP111)と姜泰煥(カン・テイファン)のアルトサックス・ソロ『Live at Café Amores』(NBLP113)で、共に300枚の限定生産だ。NoBusinessからは、防府のChapChap Recordsとの原盤供給契約に基づき、すでにポール・ラザフォード(tb)と豊住芳三郎(ds) のデュオ『The Conscience』(NBLP102)と沖至(tp)と井野信義(b)、崔善培(チェ・ソンベ、tp) のトリオによる『Kami Fusen』(NBLP103) のLPがリリースされているが、何れも300枚の限定生産(ChapChap Seriesではもう1点トン・クラミがCDのみで発売)。オランダのRhapsody Analog Recordingsから届いたのは、Carmen Gomes Inc の『Sings Belafonte』(RAR-17-001)と、Denise Jannah (vo) と小橋敦子(p) のデュオ『Lost & Found』(RAR-17-002)の2枚。NoBusinessはタイトルによってはCDもリリースする場合があるが、Rhapsodyは社名にもある通り、アナログ一本槍である。
Rhapsody盤のジャケット裏には以下のコメントが記されている。少々長いが引用してみよう;
人生自身がアナログです。だから、他の方法がありますか?音楽とオーディオ業界で長年経験を積んだ結果、アナログは本当の音楽体験をつくるのに唯一言及しているものであるという最終結論に達しました!音楽がつくられた瞬間の精神を捉え、ライヴ・パフォーマンスの本質的な品質、魔法のリアリズムに最も近いものです。Rhapsodyアナログ・レコーディングの使命は、この探求された「アナログ・サウンド」をつくり出すことです。
人生自身がアナログです。確かにその通りだ。人生はデジタルのように標本化されたり、断続的な数値として捉えることはできない、連続的なものである。だから本来連続的に変化する音楽もアナログで捉えるべきである。お説ごもっともで返す言葉はない。ある知り合いに「CD (Compact Disc) は音楽の一部の情報しか反映していない。“CDの音が良い”というのは音楽的な意味ではなく、“S/N比が良い”ということを意味しているにすぎない」、と伝えたところ、「それではあなたはCDが世の中に出た時どのように評価したのか?」とやや気色ばんで問い返された。僕の答えはこうだ。「音楽を自由に外へ持ち出せるようになったこと(wikiによると、初代CDウォークマン=ディスクマンが発売されたのは1984年)。キース・ジャレットの長大なピアノ・ソロ・インプロヴィゼーションを切れ目なく聴けるようになったこと」。キースのソロをLPのA面最後でフェイドアウトし、B面頭をフェイドインして聴く、これは甚だ感興を殺ぐリスニング体験だった。ECMから届いた最初のCDのテスト・プレスはキースの『ケルン・コンサート』だった。感興の赴くまま、イマジネーションの溢れ出るまま紡がれていく音楽を演奏された通り切れ目なく体験できる喜びは、はるかに予想を超えるものだった。
ジャケット裏の表記に戻る。さらにスペックとして以下の表記がある;
・100% analog
・ live to 2-track
・ 180 gram vinyl
・ 100% virgin black vinyl
・ HQ pressing at –Record Industry -, The Netherlands
1と2は録音手法に言及するもので、すべてアナログ機器を用いて録音されデジタル回路を経ておらず、直接2トラック・テープに録音され、マルチ・トラックに録音し2トラック・マスターにトラックダウンされたものではないことを意味している。これは音楽の鮮度を保つために最適な手法である。3と4は製造に関するもので、再生原料を一切使わず100%生の原料を使用し、しかも通常の130g以上の180gの原料を使っている重量盤である、という意味である。
ディスクの重量を増すとターンテーブルの回転の安定性や、カートリッジのトレーサビリティが増し音質の向上に寄与すると言われているが、この物理的貢献が聴感上どのような効果をもたらすか正直なところリスナーの好み次第というところだろう。
アナログ全盛時代には、製造コストを下げるためにシングル盤や一部LPは返品されたLPなどを潰した再生原料を混合してプレスされることがあった。この場合、再生原料には不純物などが混入することがあり音質に悪影響を及ぼすことが想定された。再生原料については忘れられない思い出がある。1970年代の2度にわたる「オイル・ショック」の時だ。日本が石油不足に陥り、不要不急の石油商品であるレコードは製造を控えるようにお達しが下った。慌てたレコード業界は、苦肉の策として評論家からサンプル盤を回収することを思い付いた。回収したサンプル盤を潰して再生しようという魂胆である。本来サンプル盤は貸与したものであるからという理由で実際に社員総出で回収に走ったものだった。いま考えると大した量にはならないと思うのだが、レコード業界存亡の危機と捉えられたのだ。トイレットペーパー買い占めに走った庶民を笑えない実話である。もうひとつ。当時われわれがプレスを依頼していたポリドールレコードの工場には再生原料混合ラインと100%純生原料ラインの2ラインがあった。純生ラインは当然コストが高くポリドールでもクラシックのドイツ・グラモフォンしか製造されていなかった。クオリティを重視するECMは当初からその純生ラインでプレスされていたのだ。当時アメリカのポリドールから輸入されたLPの音質が悪く不評だったが、おそらく再生原料を使ってプレスされたものだろうと想定される。最後は、オランダの「Record Industry」というプレス工場でHQ=High Quality、高品質製造された、という意味であることはお分かりの通り。
デニス・ジャナーと小橋敦子の『Lost & Found』。ヴォーカルもピアノも非常にナチュラルな音色、人肌の温もりが演奏者をとても身近に感じさせる。曲が終わって拍手が来るまでライヴとは思えぬ静寂さに包まれていた。デニスは演奏後、目に涙を浮かべていたと原盤ライナーにあるが、抑制の効いたピアノとの相性も良く満足し切ったのだろう。ふたりの円熟した女性が醸し出す安定感が純度の高い音色と相まってとびきりの多幸感をもたらす。もう1枚のギター・トリオをバックにしたヴォーカル・アルバム。ベースとドラムスのオフ感がやや残念だが、ライヴのリラックスした雰囲気が横溢。『ベラフォンテを歌う』という企画は珍しく、貴重。姜泰煥のアルトサックス・ソロ。多彩なテクニックを駆使した演奏が究極のディテールまでくまなく捉えられているが、空気感に溢れた録音で刺激臭に神経を逆撫でされることがない。姜泰煥の真摯な人間性まで伝わって来るようだ。バール・フィリップスと吉沢元治のベース・デュオ。真剣にふたりが渡り合うスリルと緊張感がたまらない。これも新鮮で切れ味鋭い鮮烈な音色だが無機的な色合いがまったくなく、アコースティック・サウンドの極地を聴く心持ち。僕がECMと最初に契約した4枚のうちの1枚、バール・フィリップスとデイヴ・ホランドのベース・デュオを思い出した。吉沢さんのベース・ソロ・アルバムも2枚制作している。遠く70年代のことだが、ベースは僕がもっとも好きな楽器である。
ちなみに、I ❤ Vinyl のVinylは「ヴァイナル」と発音し、アナログレコードのこと。欧米では一般にアナログレコードの原料がビニール樹脂であることからVinyl ヴァイナルと呼ぶ。
最後に、試聴に使用した「Bitches Brew」の再生装置のラインナップは以下の通り;
1.Pre Amp McIntosh C-11 (1968年)
2.Power Amp McIntosh MC-30 (1953年)
3.Player System
TD-124 Thorens (1965年)
Torn Arm SME3009(1975年)
Cartridge Shure M-44G(1975年)
TD-124 BASE(1978年)
4.Speaker System (Altec)
416A Woofer(1950年)
806A Driver(1950年)
811A Horn(1950年)
Enclosure FKJr.38 Realoaded(1978年)
Universal Tweeter 800/5000N/W



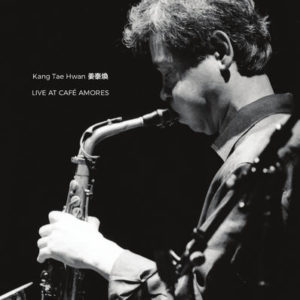
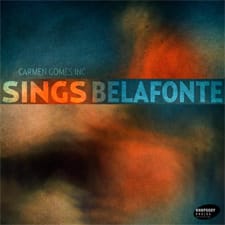






バール・フィリップスの久々のソロ・アルバムが6月、ECMからリリースされるという情報がバールからもたらされた。『Barre Phillips / End to End』(ECM2575)。楽しみだ。