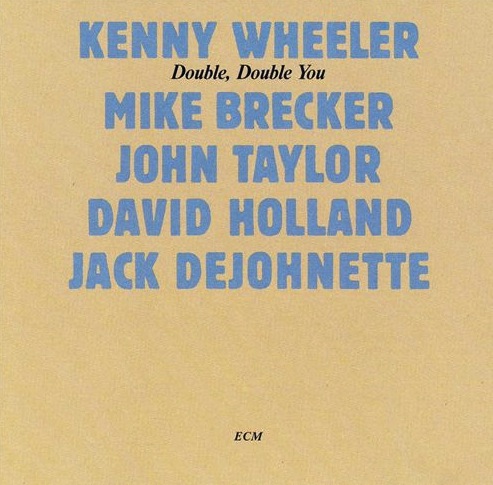ジャズ・ヒッピーの精神を自らの音楽に昇華することに成功したレジェンド・ドラマー/アーティスト by 池長一美
text by Kazumi Ikenaga 池長一美
◾️バップドラミングとの距離感
ジャック・ディジョネットのドラミングをエルビン・ジョーンズとトニー・ウイリアムズを足して2で割ったような、と表現する人がいる。エルビン、トニーとくれば、誰もが認める巨匠だから、時代を考えればそう言いたくなる気持ちも分かる、でも私は少し違ったポイントから考察してみたい。
最初に、ジャックに縁のあるドラマーでイノベータの3人を挙げてみよう。
まずはエルビン・ジョーンズ。ジャックに関わらず当時全ての先進的ドラマーが影響を受けた誰もが認める巨人。
エルビン以前と以後ではバップドラミングの基準は大きく変化した。特にコルトレーンとのモーダル音楽でドラムの地位を大きく向上させた。
そんな彼だが、デビュー当初は多くの批評家や保守的なミュージシャン達に酷評されたようだ。
話は簡単で、それまで誰も聴いた事のないドラミングをやったから、伝統からはみ出したと見られたのだ。
そしてもう一人、同時期にジャックと同じ音楽的土俵で語られることの多い、ポール・モチアン。ビル・エヴァンス・トリオでのスコット・ラファロとの出会いを経て、ドラムスの表現力を更に高い次元に引き上げ、これまでにないオリジナルのフリーアプローチを確立する事になるのだが、自身のドラミングスタイルには晩年までビバップの精神を継承し続けた。
最後は、ジャックとECMレーベル全盛期を支えたもう一人の雄、ヨン・クリステンセン。彼はアメリカン・ジャズの歴史に敬意を表しバップドラミングを試みていたが、そのキャリアの中で自らの北欧人としての表現を一生涯追求し続けた。
このように、如何に強烈な個性を放つドラマーであっても、バップドラミングの流れを無視することはできない。
彼らの経歴を振り返ればそれは明らかだし、音楽がコール&レスポンスのダイアローグ(対話)である限り、避けて通ることはできないのである。
さて、いよいよジャック・ディジョネットだが、彼も然り!と言いたいところだが、彼はバップドラミングには敬意を払いながらも、それに固執する事をせず、引きの視点から音楽全体を見つめていた印象がある。何故なら独自のドラミングを、若きデビュー当時既に見出していたからだ。
具体的にはエルビンのイノベーションの一つである不定分割法(雪崩のようなフレージング、緩急を使った表現)にヒントを得たものだが、彼の場合メロディや音楽のケーデンスを尊重したアプローチで、本来彼がピアニストであったという事実と無関係だとは思えない。
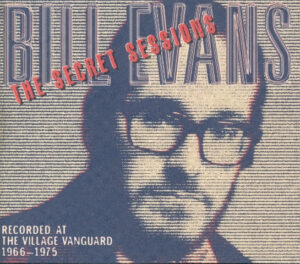 彼の20代中盤での若々しいプレイ、流れるように斬新で刺激的なプレイをこのアルバムで聴くことができる。
彼の20代中盤での若々しいプレイ、流れるように斬新で刺激的なプレイをこのアルバムで聴くことができる。
「Bill Evans the secret sessions 」
これは1966年〜75年 NY バンガードでの非公式録音集でフィリー・ジョーやマーティ・モレル、私の師ジョー・ハントを始め総勢7人のドラマーが登場する。その中でもジャックのプレイ(1968年)はこれまで誰も聞いた事のないもので、会場の誰もが驚きを持ってそのパフォーマンスを見つめているのが分かる。
まるでピアニスト(ビル)と対等に会話をしているかのよう。それまでのドラマーのサポートの常識から大きく飛躍したもので、ここまで叩いても大丈なのか?と思わせるギリギリのライン。
彼はこの音楽性をどのようにして育んできたのか?にとても興味が湧く。
◾️ジャックのピアノプレイとドラムプレイの関連性

1985年にリリースされたピアノアルバム
「The Jack Dejohnette Piano Album」は当時のドラマーたちの間でかなり話題になった。
ジャックのピアノプレイが一体どの様なものなのか?
ここでは、それぞれの楽曲に秘められた、彼の音楽性の一端に触れることができる。
どのような経緯でこのアルバムがリリースされる運びになったかは不明だが、これがドラマーか?と思うと、もう全然ピアニストじゃん!ということになるのだが、演奏を聴く限りピアニストとしての技術は、どちらかというと大味で、見方によっては(彼の共演ピアニスト達と比べると)少しスラッピーな印象さえ受ける。
ルバートやバラードは良くても、アップテンポや速いパッセージになると、不器用な動きだったり、フレーズの末尾も流れ、トメ、ハネが緩い。
名手たち(E・ゴメス、F・ウエイツ)のサポートが完璧なので、自分はフワッとで良いか?みたいな印象さえ受ける。
彼の作曲に関しては、後に本人名義のグループで多く演奏される楽曲を聴いても、T・モンク、E・ドルフィー、O・コールマンなどのジャズアバンギャルズに影響を受けたようなメロディであったり、意表をついた構成など、ジャズの本流ではない独自のスタイルを持つ、ある意味ヒッピータイプ(?)の先人たちの影響を多く受けていることがわかる。
彼のドラミングに視点を戻すと、そういった異文化的、雑多な要素をうまくドラム表現に取り入れている。
かつて、80年代にフュージョンブームがあって、フュージョンドラマーという表現があったが、
そういった意味でジャックも広義のフュージョンドラマーの一人といえるかもしれない。

CTIレーベルでの数多くのレコーディングがそれを物語っている。
「Freddie Hubbard / Stanley Turrentine In Concert 」
ファンクドラマーばりにグルーヴに徹しているジャックが聴ける。
しかしソロは、ザックリと大まかに捉えて、ケーデンスポイントはしっかりキメにかかる。
彼のピアノとドラムスではこの部分が異なるのが興味深い。
ドラマーは饒舌になり過ぎると、コンビネーションやタイムもしっかりし過ぎて、フロントのミュージシャンが何かを起こすキッカケを奪うストッパーにもなりかねない。
ただ、ジャックが並でないのは、そのタイム感が抜群で、常に緊張感を孕みながらも凄まじいスピード感でグルーヴしていくところだ。(前述のCTIレコーディングを参照)
晩年は更にどっしりと構え、まるでロールスロイスのシートに座っているかのように安定して前へ前へと進んで行く。
そしてケーデンスのアクセントは、彼のドラミングのトレードマークといっていいくらいにカッコいい。
◾️まるで音楽監督、演出家のようなドラミング
個人的な逸話になるが、私がバークリー音大の学生だった(1990年)頃のある日のこと、友人が興奮してロビーに居る私に向かってダーッと走って来て、言った。
「今会場に居なかったの? いや〜、マジで凄かった!」彼がいうには、校内の表彰式にジャック・ディジョネットがゲストで招かれていて、学生代表バンドとセッションしたらしい。つい先ほど、隣接する音楽ホールで現場を目撃したとのこと。
聴衆が彼に「ドラム叩いて!」と何度もコールし続けたので、しかたなく壇上に上がったジャック大先生。
その学生代表バンドにはカート・ローゼンウインケル(Gt)、マーク・ターナー(Ts)、クリス・チーク(Ts)など、後のNYジャズシーンを牽引するメンバーたち。
そしてドラムスは当時若干19才くらいのエイブ・ラボリエルJr. (現ポール・マッカートニーのバックドラマー)
そして、ドラマーがジャックに変わった瞬間、その場でステージが強い輝きを放ち始め、バンドが全く別次元になったというのだ。それに聴衆全員が息を呑んだという内容。
曲中でソロイストがチェンジするたびに、ジャックはバッキングのアプローチを変え、さまざまな世界観をドラマチックに作ってゆく。要するにバッキングするソロイストの音楽性を、瞬時にキャッチして、それぞれが活き活きプレイできる環境を作ってしまう。
話を聞いて、その場に居なかった自分を悔いたが、この友人の興奮も手伝ってその情景が手に取るようにイメージできた。
学生代表メンバーのカートやクリスなどは、何度もセッションしていたので、どれだけ素晴らしいかはよく知っていた。
巨匠ジャックがそのメンバーで音楽をどう料理したか、その報告を聞くだけで十分鳥肌ものだった、、
そのイメージは私の頭の中で膨らんでいき、いつしか自分の理想にもなっていった。
彼の状況を見抜く並外れた直感力とドラマチックに音楽を進めていく力は、その後、ジャックの生演奏の機会に触れる度、深く心に刻まれることになった。
本来ドラマーというのは、音楽全体を左右する影響力がどの楽器よりも大きいということを、かなり高い次元で再認識させられる事象だったと思う。
実際に彼のステージをさまざまな編成で7、8回は聴いている。毎回その地を這うような重厚な音にショックを受けるのだが、彼が大きめの編成で演るときと、ピアノトリオで演るときとでは、ダイナミクスもスタイル的にもかなり異なる。
80年代キース・ジャレットのスタンダーズではかなり音量を抑えながら要所要所をキメる印象だった。フィリー・ジョーさながらのバップフレーズも出てきたりして、その洒落っ気に思わずニヤけてしまう。
一方、管楽器が入る大きめの編成になると封印されていたジャック節が炸裂する。重低域豊かなドイツ製ソナーのセットをカランカランのハイピッチにチューニングして叩きまくる。
このように野生全開の状態であっても、インテリジェンスを感じるところがジャックならでは。
それを理解して頂ける音源をECMの録音2作品で挙げたいと思う。
「Kenny Wheeler / Double, Double You」「George Adams / Sound Suggestions」
◾️先人達からの計り知れない恩恵
先日亡くなったアル・フォスターがある動画で、彼がプロとしてまだ駆け出しの頃に、ある現場でシカゴから上京したばかりのジャックに出会って、その演奏に衝撃を受け、それから何十年もかけて自身も独自のモノ(ジャックに対して強く感じた彼独特の音楽性)を持ちたいと努力してきたと言う内容を語っていた。
マイルスに見出されて、個性とは何かを追求し続けたアルの人生と、ジャックのそれを比べてしまうと、アルは努力型のプレイヤーになるのかも知れない。
愛らしい人で、役者のようなお茶目さが演奏にも表れていて大好きなドラマーの一人だった。
ジャックのような天才タイプの人からも吸収しようとしていたんだなと、NYのアーティストのその層の厚さを感じざるを得ない。
偉大なロイ・ヘインズ、アル・フォスター、ときてジャック・ディジョネット、、、、
私以外にもこの流れに感じ入っているドラマー、音楽家は多いと思う、、
こういった真のアーティスト達と同時代に生きていられた事に感謝すべきだ🙏
ジャック・ロスはしばらく癒えそうにないが、彼の残した数多の作品たち、、これからも我々が人生を賭けて噛み締めて学んでいくに有り余る程の価値があると私は思う。
RIP Jack Dejohnette🙏
 池長一美 いけながかずみ
池長一美 いけながかずみ
ドラマー。京都市出身。‘80年代後半に鈴木勲、金井英人ほかと活動後、’89年にバークリー音楽大学の全額免除奨学生として渡米。’91年に米国政府から滞在芸術家としてアイオワ州のルーサー総合大学の特別講師として招聘される。5年の米国滞在を終え1994年に帰国。中牟礼貞則、石井彰、中川昌三、山口真文など国内の実力派ジャズアーティスト達と活動する傍ら、バート・シーガー、マグナス・ヨルト、クリスチャン・ブーストなどアメリカや北欧のアーティストとのレコーディングやツアーを重ねる。欧米各地のジャズフェスティバルにも多数出演、参加CDは50作品以上。国際的に活動している。現在は自己のグループやその他のセッションなどで活動を継続中。2002年より洗足学園音楽大学の非常勤講師として後進の指導にあたっている。2021年ジャズドラムの歴史書『52nd street beat』(ジョー・ハント著) を翻訳出版。
公式ウェブサイト graphic-art.com/ikenaga/。Facebook:池長一美。ライブ情報/全スケジュール