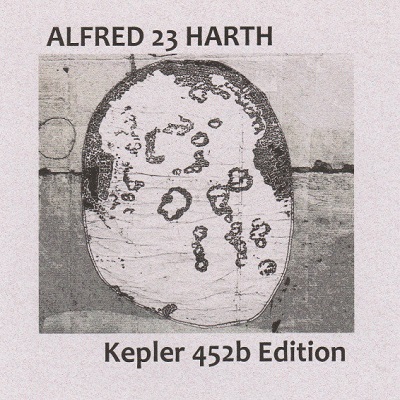#2152 『Alfred 23 Harth / 55 Quintets』
Text by Akira Saito 齊藤聡
Photos provided by Alfred 23 Harth
Interview with Alfred 23 Harth by Akira Saito 齊藤聡
https://alfred23harth.bandcamp.com/track/55-quintets
Choi Sun Bae 崔善培 (trumpet, harmonica, electronics)
Alfred 23 Harth (alto sax, Kaoss Pad, synth, prepared CDR+Numark CDX, composition, production, mix)
1. 55 Quintets
Recorded live at LaubhuetteStudio Seoul 04/2004
Photography by Choi Sun Bae 崔善培
Portrait by A23H taken at Drawing Space Saalgoo, Seoul
今般、アルフレート・23・ハルト(Alfred 23 Harth、略称A23H)の音源『55 Quintets』がデジタルリリースされたことを機に、ハルトに話を聞いた。
ハルトは、作曲家・ピアニストのハイナー・ゲッベルス(Heiner Goebbels)と70-80年代に組んだサンプリング音楽によって世界に衝撃を与えた。大友良英(ターンテーブル、ギター、作曲)も大きな影響を受けたひとりであり、かれのバンド・Ground-Zeroの第2期はゲッベルス=ハルトのアルバム『Frankfurt/Peking』(Riskant、1984年リリース)に収録された「Peking-Oper」をリ・サンプリングするために作られたほどだった。それによりGround-Zeroは『革命京劇』(Trigram、1995年リリース)という傑作をものしている(*1)。
その後もハルトは大友や原田依幸(ピアノ)らとのコラボレーションを展開してきたのだが、最近の活動はさほど認知されていない。その理由のひとつは、今世紀に入りハルトが拠点を韓国のソウルに移したからでもあるだろう。先鋭的な即興音楽のプレイヤーが登場してきてはいるものの、日本において知られてきたのは、金大煥(キム・デファン、パーカッション)、姜泰煥(カン・テファン、サックス)、崔善培(チェ・ソンベ、トランペット)らフリージャズ第一世代が中心だった(*2)。
だが、ハルトはなおソウルにおいて刺激的なサウンドを創り続けている。アートの祭典・光州ビエンナーレ(2001年)にイ・スンジョ夫人が出展したときに、ハルトも韓国に渡り、姜泰煥や朴在千(パク・チェチュン、パーカッション)らとソウルで初めてのコンサートを開いた。ニューヨークでも活動していたが(この時期にベースのウィルバー・モリス、ドラムスのケヴィン・ノートンと組んだトリオ・ヴィリディタスでもアルバムを作っている)、同年に移住先として選んだのは補助金が出たソウルだった。2001年9月11日に同時多発テロ事件があり、2002年にはモリスが他界し、ハルトは、もうニューヨークに残る意味が見いだせなかったのだとかつて語っている(*3)。
2002年にソウルにラウブヒュッテ・スタジオを作ったハルトは、8月には崔善培とのデュオ『08 + 15 Celebration』(Laubhuette Productions)を録音し、いきなり、ふたりのさまざまな楽器によるコラージュ的なサウンドを描き出してみせた。翌2003年に崔らと録音した『eShip sum』(1000cd)はマイルス・デイヴィスへのオマージュであり、「Someday My Prince Will Come」のイントロを執拗に引用するなどかなりの異色作だ。また、この年には、ソウルを拠点にロックの領域で活動する佐藤行衛(ギター)が月例の実験的音楽イヴェント「プルガサリ」を主催し始め、かれと崔もレギュラーメンバーとして出演し続けた。ヘーグム(奚琴)とプク(鼓)を加えたアンサンブル・ネイルによる『Live At SCUM 2003 06 15』(Laubhuette Productions)は、一転してシンプルに韓国伝統音楽への関心をかたちにしはじめたものだ。
そして2004年に録音された本盤『55 Quintets』は、ふたたび崔とのデュオとなった。もともと2008年に『Ballet Music』(Laubhuette Productions)に収録されたものだが、聴いた者は極めて少ない。『08 + 15 Celebration』や『eShip sum』と同様にハルトと崔の楽器とエレクトリック・サウンドが奇妙に混淆しており、かれらのおもしろさを認識していないと当惑することになるだろう。崔も伝統的なプレイヤーかつ韓国フリージャズ創始者にとどまらず、このようなアプローチも悠然と選ぶことができる人なのだ(突然スタジオにエレクトロニクスを持ち込み、ハルトを驚かせたという)。『08 + 15 Celebration』における諸々の要素が長い演奏にコラージュ的に詰め込まれ、ユートピアのように愉快であり、ディストピアのように不穏でもある。自然とつながったような崔のトランペット、ハルトの管による擦音や共鳴、それらが息づく場に別の世界や別の時間からの音の火薬がばら撒かれている。どこに連れていかれるのかわからない30分弱であり、録音から20年近くが経ったいま聴いても、混沌が厚みを増してゆくさまに興奮させられる。まさにゲッベルス=ハルトのサウンドの発展形が韓国においてハルト=崔によって提示されているわけなのだ。
ところで「55」とはタイトルを付ける直前にハルトが55歳になったからであり、デュオにも関わらず「Quintets」とは多要素をさまざまなクインテットになぞらえたからだという。これに限らず、ハルトは数字遊びが好きな人だ。2017年の来日時、ミドルネームの「23」は現在につながる音楽活動を開始した1985年から作った「マジック・ナンバー」だと愉しそうに教えてくれた(1+9+8+5=23)。またその年から18年後の2003年に『eShip sum』が録音されたわけだが、「1」と「8」は「Alfred」と「Harth」の頭文字の順番、そして「23」を韓国語で読むとタイトルの「イーシップサム」、これは録音年にもちなんでいる(20+0+3=23)。どこまで冗談なのか頭がくらくらする感覚もハルトの音楽性と共通するものがある。
ハルトと崔は、2007年に原田依幸が渡韓した際にトリオで『Homura』(off note)を吹き込んだが、これは原田のスタイルのこともあってか伝統的なフリージャズの様態であり、そのみごとなエネルギーの燃焼ぶりがかれらの幅広さを示している。そして同年10月には原田がヘンリー・グライムス(ベース)、トリスタン・ホンジンガー(チェロ)らと共演した「Kaibutsu Lives!」コンサートが韓国でも開かれ、崔とハルトも客演した。
もちろん、ハルトがソウルにおいて発展させてきたのは崔とのコラボレーションだけではない。たとえば、2016年に吹き込まれたソロ作品『Kepler 452b Edition』(Kendra Steiner Editions)もまたおもしろい。ケプラー452bとは地球程度の大きさの太陽系外惑星であり、ハルトは出自の西洋からみてまったく異なる東洋に住む自分自身に重ねているようだ。これもまたスタイリッシュで猥雑なハルトのサウンドである。
ハルトは最近では2017年に来日し、水道橋のFtarriでは、楽器で壁を擦り、向かい側にある小さな稲荷神社に向けて「Hi fox, …」と語り掛ける愉快な即興演奏を行った。ダダイズム的な表現の多彩さも突破力もいまなお健在だ。
(*1) 大友良英「アルフレッド・ハルト」(『大友良英のJAMJAM日記』、2005年1月15日)
(*2) 齊藤聡「阿部薫の他国への伝播と影響」(『阿部薫2020―僕の前に誰もいなかった』、文遊社、2020年)
(*3) クリフォード・アレン「Alfred Harth: Forty Years Of Synaesthetic Improvisation」(『All About Jazz』、2009年1月5日)
(文中敬称略)