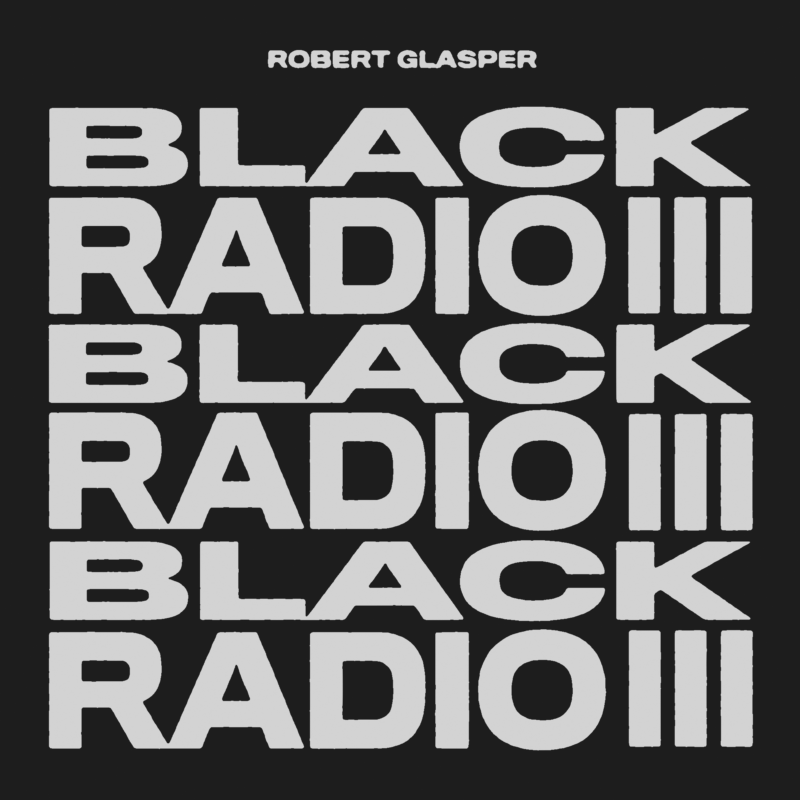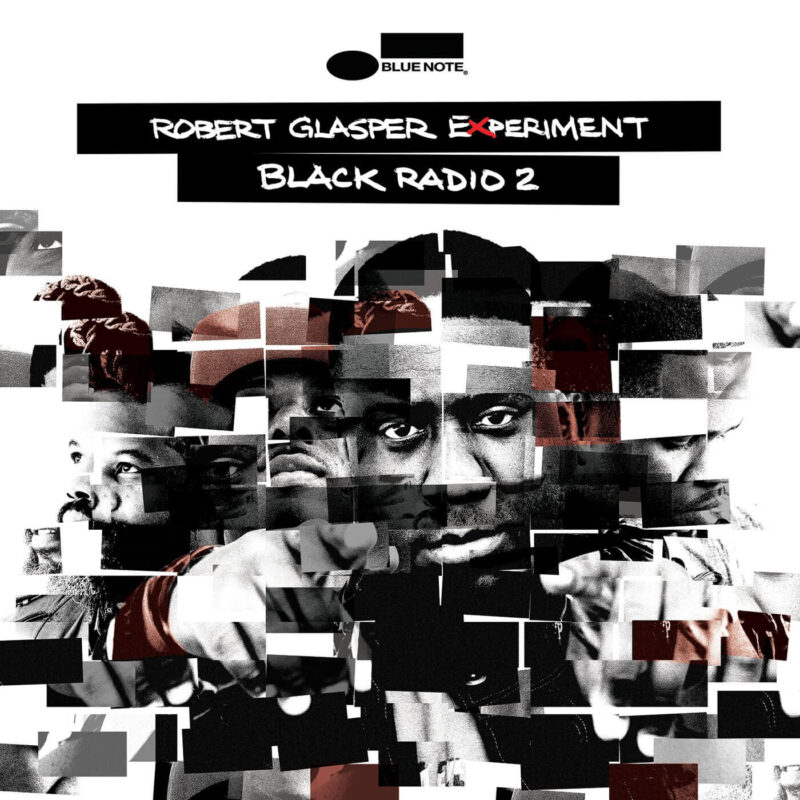ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #76 Robert Glasper <In Tune>
この2月25日にロバート・グラスパー(Robert Glasper)の待望の新譜、『Black Radio III』が発表された。グラミーを受賞した『Black Radio』の1作目からちょうど10年だ。グラスパーはこの楽曲解説の第一回目に筆者が取り上げてから、Theo Croker(シオ・クローカー)と並んで筆者が注目しているアーティストだ。筆者が今までに取り上げて来たグラスパーの記事は:
- このパフォーマンス2021(海外編)#01 Robert Glasper『Electric Trio+1』【ライブ配信】
- 楽曲解説#65 R+R=Now <How Much A Dollar Cost>
- Concerts/Live Shows #1041 R+R=Now: ロバート・グラスパー @Blue Note NYC
- 楽曲解説 #31 R+R=NOW <Change Of Tone>
- 楽曲解説 #9ロバート・グラスパー<Maiysha (So Long)>
- 楽曲解説 #1 ~『ロバート・グラスパー・トリオ/カヴァード』
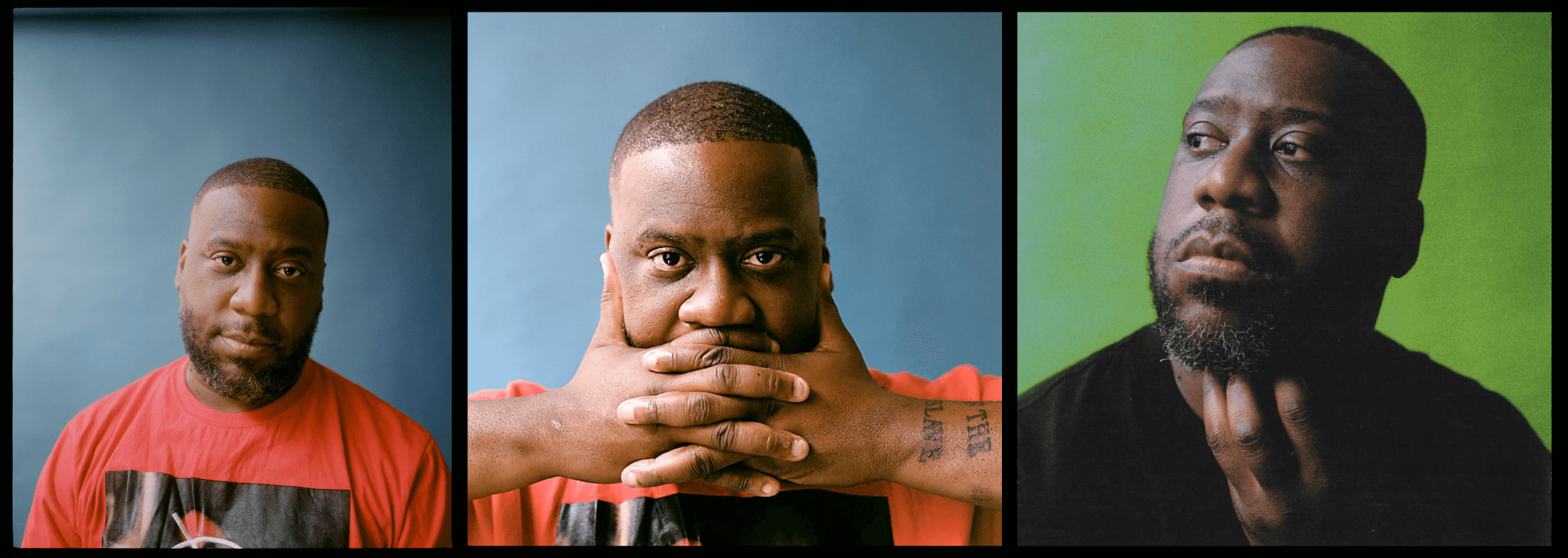
Black Radioとは
Black Redioとは、黒人向け音楽ラジオ番組をアルバムとして作成するというプロジェクトで、グラスパーが数多くの詩人やラッパー、歌手などを招聘して作成される。ここに本人のインタビューからの抜粋を紹介する。
“When I’m working on Black Radio, I’m not interested in who’s the hot new artist at the time,” Glasper says. “It’s more about people who are open to pushing the music. I’m interested in, ‘Are you actually talented? Do you actually work on your craft?’ Black Radio has become a bar. If you’re on Black Radio, you have to be a certain thing. Who really has something to say?”
Black Radioに誰を招聘するかと考えている時、ホットな新人を起用するということには全く興味がない。音楽(の限界)をプッシュするチャレンジ精神が欲しいんだ。「本当に才能があるのか?創作過程に労力を厭わないのだろうな?」Black Radioはバーみたいな場所になって来たんだ。ある条件を満たしていなければBlack Radioに居られない。それは、伝えたいことをはっきり持っているアーティストという条件だ。
このバーとは、昔のヨーロッパに栄えた芸術家や哲学者たちが論議をする場という意味だと理解する。
第1作目は2012年に発表されてグラスパー初のグラミーを受賞、翌年2013年に第二作目がリリースされて一旦幕を閉じた。ファンから続投をせがまれるもグラスパーは既に前進していた。マイルス同様同じ事を続けることを嫌ったのだ。それが3作目の作成に至った理由は、コロナによるパンデミックでライブ活動を阻止され、ファンからのBlack Radioの要望がさらに強まり、使命感に駆られたそうだ。まず昨年2021年5月にシングル<Better Than I Imagined>をリリースして『Black Radio III』の予告をした。そしてアルバムリリースまで1年を費やした。グラスパーがアルバム制作にこれだけ時間を費やしたのは初めてだそうだ。通常はスタジオで即興的に構築して行くことを好み、今回もバンド演奏はスタジオでのライブ演奏なのだが、招聘したフロントのアーティストたちとはリモートコラボという初体験をしたと語る。
ちなみに、この<Better Than I Imagined>(YouTube→)はH.E.R.(Having Everything Revealedの頭文字:隠し事はないという意味)のボーカルとMeshell Ndegeocello(ミシェル・ンデゲオチェロ)の甘い語りによる昔別れた恋人同士のストーリー展開で、遠く離れたミッシェル演じるキャラクターがH.E.R.演じるキャラクターの留守電に「Stay inside」という、コロナ・パンデミックを象徴するメッセージを入れているところが印象的だ。イントロからグラスパー印満載の強力な曲だが、まず驚くのがH.E.R.とグラスパーのグルーヴ感だ。今までに聴いたことがないような、言葉で説明できないようなビハインド・ザ・ビートでグルーヴしているのだ。それにしても、14歳でメジャーデビューし、この録音当時22歳のH.E.R.の才能には実に感嘆させられる。
続いて2021年10月にD Smoke(Dスモーク)とTiffany Gouché(ティファニー・グーシェ)をフィーチャーした<Shine>(YouTube→)がリリースされ、今年1月に<Black Superhero>(YouTube→)がリリースされた。両曲とも黒人の生活に希望を与える内容になっている。<Shine>は最近のグラスパーにしては珍しくB3のサウンドから始まるが、やはりグラスパー印満載。それに対して<Black Superhero>は、おっ、と思わせるその理由はゴスペルシンガーたちが歌うラインが斬新なのだ。いや、そんな簡単な言葉では片付けられない。まず「空を見ろ。鳥か?飛行機か?」というスーパーマンのオープニングが子供たちの声で入り、次にジョージ・ベンソン風のオクターブのラインがギターで入り、それと別世界のようにグラスパー印のピアノのテーマが入ったその後にゴスペルのラインが半端な位置から登場する。自然なように聴こえてやはり自然ではない。グラスパーのラインもいつになくリラックスしたサウンドで耳を引く。歌詞はどこの黒人の街角にもヒーローがいるといった内容で、黒人社会を賞賛しているものだ。この曲を楽曲解説で取り上げようと考えていたのでグラスパーの美しいボイシングとゴスペルの入りのタイミングを採譜した。
ご覧の様にゴスペルシンガーたちが歌う第二テーマはグラスパーの第一テーマより2小節遅れて入り、2回繰り返されるその真っ只中で突然中断される。この不自然なフォームを全く自然に聴かせるのもグラスパー・マジックのひとつだ。ちなみにグラスパーの演奏するこの美しい第一テーマ1小節目後半のコードは、DマイナーコードというよりはC/Dというボイシングだが、続くベースラインは明らかにDマイナーを提示していることに注目頂きたい。この単純なコード進行とボイシングでこれだけグラスパーにしか出せないサウンドを出せる、これが他の追従を許さないグラスパーのアートだと思う。

この曲をもって楽曲解説を進めるつもりだったのだが、入稿の期日をとっくに過ぎてしまった25日にCDが届いて、その1曲目である<In Tune>を聴いて凍りついてしまった。それは、冒頭いきなり、詩人Amir Sulaiman(アミア・スレイマン、日本ではアミール・スレイマン)の聴衆を鷲掴みにするような声で語り始めた言葉だった:
I heard him call out
I heard him call for his mother
2020年5月に公衆の面前で9分間ミネアポリスの警官から暴行を受けて亡くなったGeorge Floyd(ジョージ・フロイド)のことだ。「ママ、ぼくはこのまま殺されちゃうんだよ」という彼の言葉のことだ。この事件は、この26日に十周忌を迎えた当時17歳のTrayvon Martinが殺害された時と違い(トレイボン・マーティン射殺事件)、現場にいた警官4人全員が有罪になり、そのニュースがつい先日報道された。決め手は、近くにいた少女が携帯で一部始終を撮影した映像がネットに流れたからだ。この映像のおかげで歴史的な「Black Lives Matter」運動がアメリカ全土で勃発したのだ。
グラスパー特有のピアノのボイシングがこの冒頭の一行目の後から始まり、淡々と繰り返すそれをバックグラウンドにしてスレイマンの言葉は徐々に高揚し、聞く者の胸を掴んで離さない。このトラックが頭から離れなくなってしまった。もう締め切りが過ぎてしまったこの時点でどこまで書けるか疑問だし、いったいどこまで楽曲解説ができるのかも怪しいが、我慢強くお付き合い頂ければ幸いと思う。
<In Tune>
楽曲解説なので、まずグラスパーのユニークなサウンドの解説をする。グラスパーのピアノサウンドは非常にユニークだ。彼のピアノの音色の美しさも、単純で短いのに恐ろしくキャッチーなテーマを創造する力量にも感嘆するが、彼のシンプルなボイシングもかなり斬新だ。この曲のテーマを採譜してみた。これはコラールだ。

まず、なぜ4分の4拍子ではなく4分の2拍子表記にしたかと言うと。彼の演奏ではっきりとそういうフレージングが聴こえるからだ。作曲法に於いて、フレージングの最後を明確にするという基本作業がある。もし4分の4拍子で8小節フレーズなら、必ず2小節または4小節でフレージングの切れ目が必要になるが、ここではそれがない。D♭メジャーのブロックとG♭メジャーのブロックに分けたところの、それぞれの8ビートフレーズ(日本で言う8ビートというバックビートの事とは違い、4分音符8つという意味)に注目して頂きたい。始めたコードを最後の2ビートで再現している。フレーズの区切りをビート数で表してみよう。普通なら2、2、3、1(切れ目)となるが、譜面をご覧になって分かるようにここでは3、1、2、2で切れ目がないのだ。グラスパーのすごいところは、この8ビートフレーズを4回繰り返した後に3拍子を2小節挿入してフレーズを完結させているところなのだ。
次にボイシングだ。最初のコード、D♭Maj7の左手はパワーコードと同じ5度ボイシング、右手は殆どFマイナーだ。メジャーコードなのに暗いサウンドが響くようにボイシングされている。次の小節でCメジャーが聴こえて初めて最初のコードはCに対するモーダルインターチェンジ、つまりクラシックで言うところの「ナポリの六度」コードだとわかる。では、その中間にある1小節目4拍目のコードはどう解釈すればいいのか。解決感のある進行だが解決に必要なトライトーンは存在していない。音は3音中2音が2度ボイシングなので、どちらかはコードトーンではない。GーB♭ーCだ。こういう場合前後のコードスケールを考える。すでにD♭Maj7はモーダルインターチェンジと判明しているので、コードスケールはLydianだ。ならば4拍目のコードはD♭Lydianの#11上に存在するダイアトニックコード、G-7(♭5)、つまりGLocrianコードと判明する。言い換えれば、これがコードスケールを共有するコード名だということだ。そしてフレーズ最後でD♭Maj7を1度に見立ててピボットとし、次のフレーズであるG♭Maj7に4度ジャンプし、移調した形でテーマを展開させている。
興味深いのは4小節目の4拍目だ。最初の繰り返しであればC-7(♭5)になるはずだが、そうではなくFに対する他のモーダルインターチェンジ・コードであるA♭Maj7を置き、以前より明るいサウンドを作っている。その直前のG♭Maj7はボイシングに#11音を入れてわざわざ暗くし、意図的に大きな変化を出していることに注目したい。それにしてもなんと美しいボイシングであろうか。ため息が出る。
<In Tune>:Amir Sulaimanの詩
まず英語が苦でない読者にはこれを是非見て頂きたい。スレイマンの語りがトランスクライブされており、聞き取れなくても目で追える。
要約する。最初の1分弱で語られるのは、このアメリカで黒人であることの怯えを語っている。そして第一テーマのリフレインが提示される。
Don’t mind me
If I seem a little off key
Or I sing a little off key
ぼくが少しズレてる様に見えるかもしれないけれど
ぼくのことを少し音痴と思うかもしれないけど
気にしないでくれ
But when we’re on keys
We can unlock things
Souls
Freed
Otherwise held hostage
だが皆がぴったり合わさった時
囚われの身であった魂が解放される
詩なので意訳するしかなかったことをご理解頂きたい。実はこのon/off keyには色々な意味が込められていて、簡単に訳すことができない。音楽の調性に使われる言葉だが、Keyには重要なことという意味もあり、また、ピアノの鍵盤の白鍵と黒鍵に見立てて、白人と黒人間の問題という意味も込められている。
意外だったのは、この次に続く内容はいきなり人種問題から離れて、もう一つの病んだアメリカの重大な社会問題である、痛み止め中毒に話を移している。この痛み止め中毒は麻薬より恐ろしく、実に多くの人が死亡している。この社会問題は依存性の強い薬を生み出した製薬会社の金儲けが原因で、起訴された製薬会社はすでに処分されている。ここからどう繋がるのかと思っていたら、「警官も、盗賊も、奴らは金儲けを信心とする宗教団体だ。いったいどうやって対抗できるというのだ。」
Don’t mind me
If I seem a little off key
Or I sing a little off key
But once we’re IN TUNE だが皆がぴったり合わさった時
We can conduct the Cosmos 大宇宙を指揮することも可能になる
No Captain America キャプテンアメリカなんていない
No Cap in America 平等社会アメリカなんて存在しない
If you’re black おまえの肌が黒ければ
In a finger snap 一瞬にして
Fade to black in Amerika アメリカの暗闇に飲み込まれてしまう
そして強力な第二テーマのリフレインが登場する。
So we don’t play music だから音楽を演奏するのではない
We pray music 音楽を祈るのだ
ここから最後に向かって、音楽によって立ちあがろうと熱弁する、これがすごい。涙が出るほどすごい。是非上記の動画を数回見て頂きたいと思う。ちなみにこのトラックの短縮版がテレビでライブ演奏された。ご参考までにご覧いただきたい(YouTube→)
アメリカの人種問題
筆者は公の場で社会問題や政治的なことに対する意見を公開することを好まない。その理由は、私情を避けることが書き手にとっても受ける側にとっても難しいからだ。言い換えれば、自分の価値観を正当化することであっさりと差別が発生してしまう。差別問題はどこの国にも、どんな社会においても存在する問題だが、アメリカはその銃社会のありさまと人種の多さから症状が重い。人は自分と違う他人を受け入れることが非常に苦手だ。当然自分と同じ価値観の人間と一緒にいる方が楽だからだ。ジャズ界でも、白人を雇うマイルスやアート・ブレイキーが非難されていたのは周知だ。グループ化して差別をするというのも人間の悲しい習性だと思う。
筆者はアメリカのドラマ鑑賞が大好きだ。アメリカの役者の質の高さは半端じゃない。だが筆者が賞賛したいのは作り手の努力だ。白人至上主義が台頭すると、それに対抗する様にまずコマーシャルに登場する人物が必ずミックスになった。白人、黒人、ヒスパニック、アジア系はもちろんのこと、頻繁に同性愛者も含まれるようになった。ドラマでも同性愛者でない役者が同性愛者を見事に演じる。筆者は幸運にも学生時代に同性愛者の友人がいたので偏見はなかったものの、やはり目の前でキスなどをされれると一抹の違和感があった。だが、テレビドラマのおかげですっかり慣れ、今では全く違和感がない。
『Star Trek(邦題:スター・トレック/宇宙大作戦)』を生み出したジーン・ローデンベリー(Gene Roddenberry)を忘れてはならない。白人以外に人権のなかった60年代に、周囲の反対を押し切って黒人とアジア人系をメインキャストに起用した。当然商業的に失敗して短命に終わったが、ご存知の通りそのレガシーは今も生きている。筆者がアメリカに移住した1987年に始まった『Star Treck Next Generation(邦題:新スタートレック)』はもっと進化していた。地球人に育てられたクリンゴン星人、ウォーフ(Worf)士官だ。彼は続くスター・トレックDS9でもレギュラーだが、シリーズを通して自分のクリンゴンとしてのアイデンティティに苦しむ。だが特筆すべきは彼のキャラクターではなく、周囲のキャラクターの対応だ。スター・トレックは、違う価値観をもつ相手を受け入れるというメッセージを送り続けたのだ。クリンゴンの体臭はキツいが、それに慣れなくてはいけない、などという場面もあった。惑星連邦にはPrime Directiveという厳しい規則がある。他の星の文化を自分の価値観で判断してはいけないし、手出しもしてはならない。モームの『雨』を思い出す。筆者がアメリカに来て多くの違う国の人と接し、自分と違う価値観の人たちと接する際にこのスター・トレックのメッセージがどれだけ励みになったことであろうか。
もうひとつ筆者のお気に入りの番組がある。『The Big Bang Theory(邦題:ビッグバン★セオリー)』だ。これはシットコム、つまりシチュエーション・コメディーというアメリカ特有の、200人からの聴衆を前に演じるコメディー番組だ。シェルダンというキャラクターは11歳で大学入学、16歳で博士号を取得するほどの天才だが、自分勝手な迷惑人間で友達は登場人物の4人しかいない。そのうちの一人、同じアパートに住むウエイトレスのペニーというキャラクターは、登場人物中唯一の学問とは関係ないキャラクターで、簡単にシェルダンを受け入れる。シェルダンの頭の中は学問で満杯だから他人のことを考える能力がない人だ、と単純に自分の対応を調整するのである。12年間続いたこのシリーズ、各キャラクターが成長して行くその過程がともかく素晴らしく、最終回でシェルダンがノーベル賞を受賞するその場で初めて自分は皆に助けられて生きて来たことに気が付くその場面に感動した。
アメリカの映画やテレビドラマには耳の不自由な役者も少なくない。共演者は皆手話を学ぶという徹底ぶりだ。ところで、アメリカでは差別意識は家庭で育つと言われているわけだが、アメリカ人の家庭は白人も黒人も驚くほど家族の親密さを重視する。家族より仕事を優先すると非人間呼ばわりされるなどもよく聞く話だ。家族で行動することを大切にし、子供たちは高校を出るまできっちり管理される。それだけに親の子に対する影響力は半端ではない。当然親が持つ差別意識も子供に受け継がれ易い。但し筆者の親しい友人には、親の白人至上主義を恥ずかしいと思っている若者も当然いる。ありがたいことにミュージシャンの間で人種差別を強く感じたことはそれほどないが、筆者は渡米早々「遠い東の国からやって来て、おれたちの音楽が演奏できるようになると思うなよ」と言われたことがある。
さて、前述した「Black Lives Matter」運動に少し触れてみよう。こういう運動で近年成功した例は、セクシャルハラスメントに対する「Me Too Movement」がある。家庭内性暴力被害者のサポートで2006年に始まったこの運動は、その10年後にSNSの力で実を結び、多くの加害者が告発された。2019年に映画化された実話、『Bombshell(邦題:スキャンダル)』を是非ご覧頂きたいと思う。この「#MeToo」運動が成功を納めたのは、告訴された一連の加害者が映画界やテレビ界の有名人たちであったからだと思う。残念ながら「Black Lives Matter」運動はそれほどの成功を納めていない。コロナパンデミックの影響ももちろんあるだろうが、病巣がセクシャルハラスメントと比べ物にならないほど大きいからだと思う。
「Black Lives Matter」とは黒人の命を粗末にするな、という意味になるが、では白人の命は粗末にして良いのか、人間全ての命を粗末にするなと言うべきだろうと反論が持ち上がった。このアメリカでヒスパニックを含む黒人は簡単に射殺されるのに、警官は罪にも問われないからこういう運動が持ち上がるということが一部で理解されていないのだ。大量殺人を犯しても白人ならその場で射殺されず、逮捕されても丁重に防弾チョッキまで着せてもらえるこの社会に抗議しているのだ。犯罪とはまるで関係ない中流階級の黒人は、肌の色が黒いというだけで常に自分や家族の命の心配をして生活をしなくてはならない、それがアメリカの問題だ。
上記のジョージ・フロイド事件の少し前の2020年2月に、ジョージア州で25歳のビジネスマン、Ahmaud Arbery(アマード・アーベリー)がジョギング中に元警官の白人の親子に車で追い回されて、挙句の果てに散弾銃で撃ち殺されるという事件があった。高価なジョギングシューズを履いていて反感を買ったと伝えられている。この事件も犯人の親子とそれを助けた友人、3人全員がつい先日有罪になった。怯えて暮らす黒人に希望を持たせるニュースだったと思う。
筆者はこの『Black Radio III』は歴史に残るアルバムと信じる。グラスパーのメッセージは白人を憎むギャング・ラップとはほど遠い。現代社会を黒人の視点から描写しているだけだ。だがグラスパーの追従を許さないサウンドがこのアルバムの社会的に重要な位置付けを与えていると強く感じる。
何回か以前にも書いているが、筆者はグルーヴを崩さずに単純なパターンを延々繰り返せるミュージシャンをとても尊敬している。特に最近の若手黒人ミュージシャンが操る新しいタイプのレイドバックしたグルーヴでの難易度は相当なものだと思う。このアルバムでは、そのグルーヴを押し殺しているのでさらに難易度が高い。グラスパーはライブだと、必ず1曲か2曲でご機嫌なピアノソロをフィーチャーして堪能させてくれるのだが、残念ながらこういうアルバムだとソロはフィーチャーされない。それでも8トラック目の<Everybody Love>で少しだけソロがフィーチャーされている。コード進行はコルトレーン級の難易度だ。そのうち分析してみたいと思う。ちなみにコード進行は以下の通り:
| D / D#− | F#− / F− | E− | GMaj7 |
もっとソロを堪能させて欲しいというファンは、是非こちらをご覧頂きたい。10トラック目の<Heaven’s Here>のテレビでのライブ演奏なのだが、第一音からすごいピアノ演奏を聞かせてくれる。「顎落ち状態」というやつだ。お楽しみ頂きたい。
ティファニー・グーシェ, ビッグバン・セオリー, The Big Bang Theory, 宇宙大作戦, 新スタートレック, Star Treck Next Generation, スター・トレック, Star Trek, ジーン・ローデンベリー, Gene Roddenberry, 差別問題, 人種問題, アミール・スレイマン, アミア・スレイマン, Amir Sulaiman, Tiffany Gouché, Dスモーク, D Smoke, H.E.R., Black Radio 3, Black Radio III, Meshell Ndegeocello, ミシェル・ンデゲオチェロ, Black Radio, ロバート・グラスパー, Robert Glasper