ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #38 Miles Davis <Rubberband>
本年4月21日にマイルスの未発表曲『Rubberband EP』が45回転12インチEPレコード(vinyl)でリリースされていた。オリジナルの録音に、新たに3つのバージョンが加えられてだ。そしてこの11月16日にそれがデジタル配信としてパッケージされた。今度はさらにリミックスバージョンが追加され、全5トラックになった。1985年、マイルスのワーナー・ブラザーズ移籍第1作に当たるが、名プロデューサー、トミー・リピューマ(Tommy LiPuma)によってお蔵入りさせられたアルバムのタイトルソングだ。リピューマはジョージ・ベンソン、アル・ジャロウ、イエロー・ジャケッツなどをプロデュースしてグラミー受賞も多い。彼の作品は、洗練されたイメージを売りにしており、このアルバムをボツにして名盤『Tutu』を作成したのは自然な流れだったのだろう。マイルスがそれに文句を言ったかどうかは定かではないが、最終的にリピューマの指示に従ったのは事実だ。(追記参照↓)
マイルスは1955年から30年間コロンビアと契約していた。コロンビア最後のアルバムは『You’re Under Arrest』だ。筆者が思うにワーナーへの移籍は金だと思うが、マイルスは新しいことがやりたかったのも確かだ。ワーナー移籍第1作に向け、アイデアを模索し、プリンス等数多くのアーティストに声をかけたと言われている。そのうちの一人がランディ・ホール(Randy Hall)だった。そしてこの『Rubberband』が誕生した。
Randy Hall

ランディ・ホールと言えば『The Man With The Horn』、つまり5年遡った1980年のマイルス復帰作を実現させた歌手兼ギタリストだ。ランディはマイルスの甥っ子であり、アル・フォスターの後釜としてマイルス・バンドに入ったドラマーのヴィンス・ウィルバーンJr.(Vince Wilburn Jr.)と幼馴染で、シカゴであちらこちらのバンドで共演していただけでなく、「AL7」というバンドを一緒に結成していた。その「AL7」の<Space>という曲をマイルスは耳にし、バンドを丸ごとNYCの自宅に呼びつけた。ランディ・ホール若干20歳。この若者たちの音楽がマイルスに復帰を決心させたきっかけだったそうだ。この時のキーボードが後々マイルスバンドで活躍するロバート・アーヴィング3世(Robert Irving III)。多くの曲を提供した。そしてベーシスト、フェルトン・クリューズ(Felton Crews)は『The Man With The Horn』に起用されているだけでなく、1986年のモントルー・ジャズフェスティバルにも出演している。ところで<The Man With The Horn>、マイルスはライブで演奏しなかったもののランディ・ホールは演奏していた。YouTube→
マイルスはよほどランディ・ホールが気に入ったようで、その後も連絡を取っていた。<Decoy>のクレジットはアーヴィング3世だが、もともとはホールがローリング・ストーンズのために書き下ろした<(Let Me Be Your) Decoy>らしい。ホールとホールの相棒であるゼイン・ジャイルスがクレジットされてる曲を、モントルーの10枚組DVDからアルファベット順に書き出して見よう。
- Al Jarreau(ホール、ジャイルス)
- Burn(アーヴィング3世、ホール)
- Carnival Time(ニール・ラーセン、ホール、ジャイルス)
- Maze(マイルス、ホール、ジャイルス)
- Winkle(エリン・デイヴィス(息子)、ホール、ジャイルス)
<Winkle>は最後まで毎回演奏するレパートリーにしていた曲で、毎年テンポが速くなって行くのが実に楽しみだった。その<Winkle>も、<Al Jarreau>と<Carnival Time>と共にこの『Rubberband』に収録されるはずだった曲らしい。
1984年、マイルスはホールにワーナー移籍第一弾のプロデュースを依頼する。製作中の自分のアルバムの共同プロデューサーである前述のアタラ・ゼイン・ジャイルス(Attala Zane Giles)を連れて来た。マイルスは彼らに、ストリートのサウンド、荒削りでラフなサウンド、また色々なジャンルのサウンドを混ぜるというコンセプトを説明したそうだ。結果、ファンク、ラテン、カリビアン、アンビエントなどの要素を持つアルバムの録音が1985年10月17日に始まり、アル・ジャロウやチャカ・カーンの参加が予定された。マイルスはその時録音したファンク、<Rubberband>を非常に気に入り、2週間後の11月1日にはすでにライブで演奏している。YouTube→
『Rubberband』ペケ → 『Tutu』
録音は3ヶ月後の1986年1月に終了し、マイルス、ホール、ジャイルスはアルバムにするだけの題材を確保したと確信したところでトミー・リピューマが却下した。ラフで過激なストリートのサウンドはリピューマが看板にしていた洗練されたサウンドとは程遠かったわけだ。そこでリピューマはマーカス・ミラー(Marcus Miller)と、プログラマーであるジェイソン・マイルス(Jason Miles)を連れて来て『Tutu』の制作に入った。結果『Tutu』はグラミー受賞などの大成功を納めただけでなく、歴史に残るアルバムとなった。またしてもマイルス5年先を行くオンパレード。新しいアイデア満載。筆者のDesert Island Album(離れ小島に流れ着いた時これひとつあれば生き残れるというアメリカの常套句)でもある。歴史はリピューマの決断を肯定しているのだ。

マーカス・ミラーのことは言及しなくてもほとんどの読者にとっては馴染みが深いアーティストだと思う。反対にジェイソン・マイルスのことはあまり知られていないのではないだろうか。70年代にシンセのプログラマーとしてNYCで名を挙げ、80年代ではセッションキーボードプレヤーとして数多くのアルバムに参加している。アレサ・フランクリン、ウイットニー・ヒューストン(日本ではホイットニー・ヒューストン)、マイケル・ジャクソン、チャカ・カーン、ダイアナ・ロス、デイヴィッド・サンボーン等、有名どころばかりだ。ジェイソンは、マイルスには自分の苗字が気に入られたが、内心破裂しそうに緊張し続けたと語っていた。その彼とは面識があったので、何か『Rubberband』がボツになって『Tutu』が始まるに至る逸話でも聞けないかと連絡してみた。筆者が知りたかったのは、マイルスが新しいプロデューサーであるリピューマにどう対峙したのか、3ヶ月かけた『Rubberband』プロジェクトがボツになってマイルスの機嫌はどうだったのか、だ。(追記参照↓)しかしジェイソンは明確な答えをくれなかった。自分で最初に「そのことについては話さない方がいいだろう」と言っておきながら、今回の『Rubberband』のリリースに大いに不満を持っていることが見え見えだった。その不満は、お蔵入りされ続けるべきだったのにリリースされたことが不満なのか、4つのリミックスが気に入らないのか、どちらかの判断はつかなかった。レディシー(Ledisi)の名前を不満そうに出したので後者かもしれない。それに対して筆者は、マイルスはライブで『Rubberband』から何曲も演奏し続けたのに、未だにこのアルバムが公開されていないことから、リピューマに批判的な語調になったわけだが、それに対してジェイソンは、「リピューマがあの時崩壊を防いだんだぞ」と言った。つまりマイルスのあの時の方向は間違っていたという自分とリピューマの意見に自信があるらしかった。そう考えると不満の理由は前者なのかもしれない。
筆者はマイルスを救世主と崇め、その足跡から学び、キリスト教信者が神のなさる業に問いかけをしない(・・はずなのだが、遠藤周作は不遜にも『沈黙』で思いっきり問いかけている、のは、置いておいて)ことと同じようにマイルスのすることは全て受け入れる、だけに、この意見に対して複雑な気持ちになった。ただ盲信はしてはならないので少し考えてみることにした。
確かに『Rubberband』のオリジナルトラック(トラック4)は80年代前半のマイルスバンドから『Tutu』ほどの新しさは聴こえない。特にマイク・スターンを呼び戻してマイク・スターン節を披露しているのは、マイルス本人は新しいサウンドを求めていたといえ、マイルスの神業専売特許であるその時代の音楽を包括して5年先の音楽を創造する、というようには聴こえない。このアルバムに続き1986年のツアーバンドはマイク・スターンを呼び戻しただけでなく、5年前の『The Man With The Horn』のベーシスト、フェルトン・クリューズも呼び戻している。確かにマイルスらしくないかもしれない。それに対して『Tutu』は全て新しく、完璧に歴史を変えた。
『Rubberband』
さて、このアルバムのジャケットはマイルス本人のイカした絵で、内容は前述のように同じ曲5バージョンからなる。
- Rubberband Of Life (Radio Edit)
- Rubberband Of Life
- Rubberband Of Life (Instrumental)
- Rubberband (Original Version)
- Rubberband of Life (Amerigo Gazaway Remix)

まずトラック4のオリジナルバージョンだが、オリジナル録音からかなり変更がある。実は今回初めて知ったのだが、この曲は2010年に英国で『Perfect Way: The Miles Davis Anthology – The Warner Bros. Years』の収録曲として発表されており、ようやっと今日手に入れた。聞いてみるとサウンド的には『Tutu』のプロダクションと同じで、当時のドラムマシーンやシンセ・ベースが使用されているのに対し、今年発表されたバージョンではドラムがサンプラーに置き換えられ、『Doo-Bop』と同じようなトラッシー(ラフ)なサウンドだと言うだけでなく、ベースラインはシンセベースとサブウーファー系のエレクトリックベースとのユニゾンだ。またスネアはオリジナルのようなスナップの効いたレイドバックしたバックビートではなく、現代風の跳ね上げるビートだ。ドキドキする。間奏のシンセのパッドは、オリジナルの曖昧なサウンドと違い、はっきりとしたボイシングでコード進行が形成されている。またオリジナルでイントロに使われているアダム・ホルツマン(Adam Holzman:後々アーヴィング3世のマイルス・バンド番頭役を引き継ぐ)のPPG Waveシンセの演奏は、曲の最後にエンディングとして使われている。つまりオリジナルバージョンと言いながらかなり変更されているのである。 ただ、一つ驚いたのは、Rubberbandという言葉を「ラ・バーン、ラ・バーン、ラ・バーン、」とマイルスがラップ風に連呼しているのは1985年のオリジナルで、これは当時にしてはかなり新しい。また、1985年バージョンも2018年バージョンもベースラインとキックドラムのタイム感は一糸乱れず同期しているのに、そのリズムパターンは同じではない、が、妙に違和感がないだけでなく、スリル感を生み出している。この発想は新しいと思った。フレットレス・ギターの使用も含めてホールのアイデアであろう細部が光る。では『Rubberband』と『Tutu』の決定的な違いはなんだろう。それは、ランディー・ホールは『Rubberband』でマイルスをダンスミュージックにし、トミー・リピューマは『Tutu』でそれを否定したのだ。
オリジナルのトラック4以外は全て半音上がったE♭マイナーに移調してあり、レディシーのソウルフルな歌が加わり、テンポはオリジナルの112BPMよりはるか遅い90BPMに変更してゆったりグルーヴする。それだけにトラック4に到達するとものすごい効果がある。シンセベースが使用されているのはオリジナルのトラック4だけであり、他は全てアップライト(アコースティック)ベースが使用されているのも奇抜だ。トラック5は4月リリースのEPでは含まれていなかった、この11月発表のデジタル配信で新たに加えられたもので、アメリゴ・ギャザウェイ(Amerigo Gazaway)のリミックスだが、これがまた洒落ている。オリジナルのDマイナー一発のコード進行に対しE♭ー7・A♭7・D♭ー7・G♭7と言うギター・リフに変更してゆったり軽めにグルーヴするのが気持ちよくアルバムの幕を閉じてくれる。また、 “If you don’t mind, we’d like to play something for you”(1曲お聴かせしようかと思いますがどうでしょう)というマイルスのナイスな語りが冒頭で入るが、これは映画『Dingo』での一コマからだ。むちゃくちゃオシャレ。
この一連の手の込んだプロダクションは、甥っ子ヴィンスとランディー・ホールとゼイン・ジャイルスの手によるものだ。マイルスのトラックのリミックスと考えて良いだろう。筆者は充分楽しめるのだが、やはりロバート・グラスパーの手が入っていたらもっと斬新だったのではないかという感がある。ところでレディシーの歌う歌詞から想像するに、このタイトル、<Rubberband>の意味は、輪ゴムに縛られて自由になれない、と言ったところらしい。
<Rubberband (Original Version)>
さて、楽曲解説なのでマイルスの演奏など分析したいところだが、やはりどうもその気になれない。筆者は学生時代ウエス・モンゴメリー、コルトレーン、マイケル・ブレッカー、ランディ・ブレッカー等数多くトランスクラブして勉強したが、マイルスだけはトランスクライブできなかった。なぜなら筆者にとってマイルスは神の声だからだ。ジャズを勉強し始めた時、マイルスの1964年のリンカーン・センターでの2枚組、『My Funny Valentine』と『Four & More』だけを1年間聴き続け、ジョージ・コールマンをトランスクライブし、トニー・ウイリアムスを含め全てのパートを歌えるようにしたことがあるが、それでもマイルスはトランスクライブしなかった。
と、言うわけで、恒例のような解説は控えさせていただくことをご了解頂きたい。取り敢えずヘッドを採譜して見た。エレクトリック・マイルスの特徴として、曲のキャラクターはグルーヴとベース・パターンで、マイルスが吹くラインは確固としたメロディーではなく、モチーフだ。この曲のモチーフはFーBーCだ。そして、曲のフォームははっきりと構成されている。

モチーフの最後に1小節クッションが入っているところが実にオシャレ。[C]の直前に赤で示したラインは第2モチーフにあたる。グルーヴ・パターンがDマイナーなのに、マイルスはDドミナントをモチーフとして演奏する、つまりグルーヴ・パターンで提示されてるDの短3度音であるFをDドミナントの#9thとして逆手に取る方法で、マイルスのシグネチャーでもある。これを我々が真似してやっても間違えたようにしか聞こえないのだ。神の真似をしようとするとやけどするのだ。
フォームを2度繰り返したところでインターリュード(間奏)に入る。今回入手した英国版ではこの部分が全く違うのに驚いた。オリジナルでは単純にD♭メジャー・G♭メジャーとコードが進んで行く上でマイルスはA♭メジャーのラインを呟くのだが、今回のバージョンではかなり凝ったコード進行に置き換えられている。

2段目のラインはシンセのトップノートを記載した。マイルスのモチーフは3小節目を除いてそれほど干渉する音列ではないが、それにしても完璧に2階建のハーモニーだ。例外は4小節目だ。ここでは干渉する音はない。但し、録音から聴こえるボイシングはわざと干渉させている。ここのコードは理論的にはE7 (alt) / D、つまりE mixo ♭9、#9、♭13、そして♭5から成立するコードなのだが、なにせボイシングはCのトライアッドが上に積んであるのだ。しかもシンセのトップ音がA♭でコード音のGと干渉しているのに、だ。このあたりがランディ・ホールとゼーン・ジャイルスのマイルスの音楽の理解が正しくされているところだ。何度も言うようだが、このマイルスの演奏しているラインを真似して譜面通りに演奏してみるとどうにも間違ったようにしか聴こえない。これがマイルスの恐怖だ。
このアルバム全曲が早くリリースされないかと切望する。前進し続けるマイルスのアルバムではないが、『Tutu』で大きく前進したマイルスの、その前の時期最後のアルバムとしてリリースされてもよかったのではなかろうか。
== 追記 ==
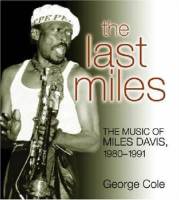
2005年にミシガン大学から出版された、ジョージ・コール(George Cole)著の『the last miles』という本がある。マイルスの復帰後から没年まで、つまり1980年から1991年を解説した本で、かなり詳しく書いてあるらしいのだが、なぜかとっくの昔に絶版になっておりなかなか手に入らない。アマゾンで古本を見つけて速攻で注文したが年内には届かないと諦めていたところ、隣町のWatertownの図書館で見つけ、借りてきた。色々面白いことがわかった。まずマイルスがコロンビアを去った原因は金だけではないらしい。その当時借金を払う金が必要だった事実はあるらしいが、実際はワーナー・ブラザーズがマイルスの出版権を握ったことに不満で、なんと1年後にマイルスはコロンビアに戻りたい意思を示したそうだ。では何が移籍の原因だったのか。それはウィントン・マルサリスだったらしい。コロンビアがマイルスよりウィントンをちやほやしたことに腹を立てたのだ。ウィントンはマイルスのステージに飛び入りして追い出されたことを根に持ち、ジャズを殺したマイルスという非難を拡声していた。そんなウィントンはジャズとクラシックと両方でグラミーを受賞し、天狗状態。コロンビアがちやほやするのも当たり前だったのかもしれない。
次に、知りたかった『Rubberband』のお蔵入りの経緯だ。ワーナー移籍に際し、ラジオ受けの向上への期待があったらしい。ホールがプロデュースした『The Man With The Horn』はラジオ受けがよかったことから、ホールとジャイルスは3ヶ月全てを投げ打って今度もディスコ系のサウンドでラジオ受けを狙った。だがワーナー・ブラザーズはスムーズ・ジャズ系でラジオ受けを狙いたかった。トミー・リピューマは非常に賢く、『Rubberband』制作中に文句を言えば喧嘩になると思い、その製作が終わった時点で「このアルバムからは言いたいことが伝わってこないな」と言い、そして「マイルス、実はマーカス・ミラーとこんなプロジェクトを始めてみたんだよ。ちょっと聴いてみないかい」と言ったそうだ。つまりマイルスはそれを聴いてマーカスのプロジェクトに自分から乗ったというわけだ。名プロデューサーとはこういう手腕のことを言うのであろう。前述の通りマイルスは『Rubberband』からのトラックをライブで何度も演奏していることから、両方気に入っていたのは明白だ。かわいそうなのはホールとジャイルスで、この悲惨な歴史は3度、『The Man With The Horn』、『Rubberband』、『Doo-Bop』と繰り返されたらしいが、ここでは控える。
『Rubberband』がボツになり、『Tutu』が発表された時に『Rubberband』の関係者が口を揃えて言っていることに考えさせられる。全員『Tutu』を賞賛しており、ラフなストリートのサウンドを求めたマイルスの指示に従って作った『Rubberband』は、ワーナー・ブラザーズにとって実験的すぎた、と言っているのである。実は筆者率いる「ハシャ・フォーラ」も、実験的なことが受け入れられるNYC以外では、”very experimental” という良いか悪いか判断がつかないような、いや、多分良い意味ではないような言葉で形容されることがある。我々としてはグルーヴを最も大切にし、実験的なことをしているつもりは全くないのだが、即興演奏が多い部分が実験的なのだろうか。多くの聴衆に聴いてもらうためには実験的ではいけないのかもしれない。いや、待てよ、マイルスの70年代は120%実験的だったではないか。それはマイルスだから受け入れられたのか、またはそういう時代に一般が吸い寄せられる音楽をマイルスが築いたのか、今はもう毎回何が起こるかわからないスリルが受け入れられる時代ではないのか、いずれにしてもマイルスを真似して真似できるようなものではないのであろう。そういう意味でもロバート・グラスパーから学べることは多い。色々と考えさせられてしまう。
ロバート・アーヴィング3世, アダム・ホルツマン, Adam Holzman, ゼイン・ジャイルス, エレクトリック・マイルス, Ledisi, レディシー, ディンゴ, Dingo, Amerigo Gazaway, アメリゴ・ギャザウェイ, Jason Miles, ジェイソン・マイルス, Zane Giles, Robert Irving III, Vince Wilburn Jr., ヴィンス・ウィルバーンJr, ランディ・ホール, Randy Hall, トミー・リピューマ, Tommy LiPuma, マーカス・ミラー, Marcus Miller, Mike Stern, マイク・スターン, マイルス・デイヴィス, Miles Davis


