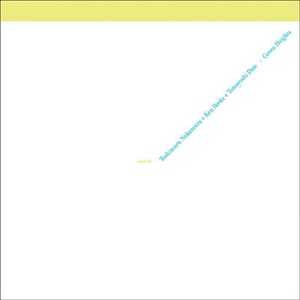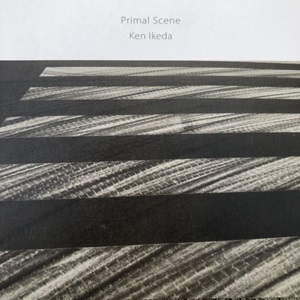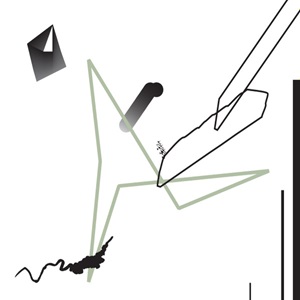インプロヴァイザーの立脚地 vol.23 池田謙
Text and photos by Akira Saito 齊藤聡
Interview:2024年8月6日 神保町・月花舎にて
池田謙は俯瞰の音楽家である。自身の音には確固たる方法論がありながら、自我を表出させることを極端に回避する。現代美術や小説も手掛けるかれの展開するマンダラはどのようなものか。
中心性
池田がバークリー音楽大学で専攻したのはジャズのエレキベースである。そこで、自分自身の音楽的根拠や中心性に疑いを持ってしまった。ばりばりに弾くアメリカの同級生たちを目の当たりにし、その一方で、日本でも演っていたブルースなどを続けている。なぜ自分はそのようなことをしているのか。
かれは電子音楽に移行することにした。90年代に入ってからシンセサイザーなどの機材が安く市場に出てきたこともある。歴史のない音楽をやりたかった。まだバークリーでも譜面偏重で電子音楽を教えておらず、本で独学した。
80年代の終わりころ、いちど日本に戻った。まだ現代美術が流行る前だったが、寺田倉庫(天王洲アイル)やSCAI THE BATHHOUSE(谷中)などが現代美術の展示の場を作りはじめていた。池田もそのあたりに注目した。
そして、かれはニューヨークに移住した。まだ地価がさほど高くもない時代、本格的なグローバリゼーション到来の前である。マンハッタンのイーストヴィレッジの住居も、家賃600ドルに過ぎなかった。同じように若い現代美術のアーティストたちがたくさんいて、展覧会のオープニングレセプションなどで知り合うことができた(かれらが住めなくなってベルリンなどに流れていくのはそのあとのことだ)。一方、90年代あたりからヴィデオ作品が流行りはじめ、池田のもとにも作家から音を付けてほしいとの依頼が入ってきた。自身でもヴィデオ作品を手掛けた。
東洋
当時のニューヨークでは小津安二郎や溝口健二らの日本映画が再評価されはじめており、池田もその機会にはじめて小津の『東京物語』を観た。劇場で涙を流す若いアメリカ人の姿を見て、かれは驚いてしまった。映画に描かれるような「家庭的」なものを鬱陶しいものと感じていたからだ。東洋人としての立ち位置も意識せざるを得なかった。
すでに注目されていた武満徹や坂本龍一も、また現代美術の河原温やナムジュン・パイクも、アジア人であることをその表現に表出させていたし、そのような文脈で評価されてもいた。だから、どうしても東洋―西洋という図式にとらわれてしまう。
ポストモダンの時代にあっては、東洋などはぶち壊すという流れがあった。Y.M.O.(イエロー・マジック・オーケストラ)はオリエンタルな雰囲気を残しつつわざとユーモラスなサウンドに仕立て上げており、池田も影響を受けた。また、カールハインツ・シュトックハウゼンのような現代音楽ではエレクトロニクスを基本としつつポップな要素も効いており、どのように作っていったのか不思議に感じてもいた。モダニズムと東洋性との折り合いをどうつけるのか。
90年代初頭は民族音楽が「ワールド・ミュージック」として大々的に紹介されはじめた時代であり、池田もかなり聴いていた。デレク・ベイリー(ギター)が自身の音楽について現代音楽でなく民族音楽に近い旨を書いていたことがあり、池田にも共感するものがあった。ベイリーは現象的な音のとらえ方をしており、音そのものに向かう姿勢はいわゆるフリーとは違うものだと思った。一方、ジョン・ケージが提唱した反音楽には疑問を覚えた。二元論はかれが学んだ禅の精神とずれるのではないか。むしろ、ベイリーのありようにこそ二項対立ではなく矛盾をひとつにするなにかを見出せるのではないか。それは仏教的でもあるのではないか。―――池田はそんなふうに考えていた。
初期の方向性
だから、自分自身の音楽は「いわゆる電子音楽」にもしたくなかったし、「アンチ音楽」にもしたくなかった。ハーモニーやメロディがあってもいいし、急にそこから外れてもいいだろう。その意味ではブライアン・イーノからの影響もあった。イーノも急にポップなサウンドに変化するような人だったからだ。
はじめは映像に対して音楽を作っていた。横尾忠則、森万里子、デイヴィッド・リンチといった作家の映像に音を付けるよう依頼されたこともあったし、CMやゲームの仕事もあった。もとより池田自身が映画や文学に影響を受けたこともあって、音楽が映像的なものだった。
最初のソロ作品『Tzuki [Moon]』(2000年)もSCAI THE BATHHOUSEで展示するヴィデオのための音楽だった。ギャラリーの担当者がテープをいくつかのレーベルに送ってくれて、英国のTouchレーベルから出すことになったのだ。
2000年代は家で子育てをしなければならなかったから、自宅で依頼仕事をこなす日々。ソロ作品が多かったのは宅録ができるからだ。『Merge』(2003年)、『Mist On The Window』(2007年)、『Kosame』(2010年)をリリースした。
即興演奏の開始
2013年になり、池田はロンドンに引っ越した。Café OTOやIklectik(2024年初頭に閉店)といったライヴスペースに出かけていき、ジョン・ラッセル(ギター)、デイヴィッド・カニンガム(作曲)、デイヴィッド・トゥープ(ギター、フルート等)といったフリー・インプロヴィゼーションのミュージシャンたちの知己を得た。またエディ・プレヴォ(パーカッション)が毎週土曜日に開いていたワークショップにも出て、そこでも友人たちができた。
即興演奏に興味はあったが、それまで、自分自身が演るものとは思わなかったという。シーケンサーに打ち込む音楽と即興演奏とはまったく異なるものであり、池田は、その順序をまったく逆にした。すなわち、即興演奏を行うと同時にその断片を蓄積しておき、それらをもとに作曲を行うという発想の転換である。それはやはり「アンチ音楽」ではない。トゥープも、池田の作る音楽を良いと言ってくれた。典型的なフリー・インプロヴィゼーションではないからだ。
もちろんロンドンでも保守的な「ジャズリスナー」は少なくなかった。シンセサイザーを演奏することに対しても色眼鏡で見られることがあった。だが、良いミュージシャンたちと共演することができた。ラッセルらもそうだし、マッシモ・マギー(アルトサックス等)、ヨシュア・ヴァイツェル(三味線等)、ウテ・カンギーサー(チェロ)、アンガラッド・デイヴィス(ヴァイオリン)、エドワード・ルーカス(トロンボーン)、ダニエル・コーディク(シンセサイザー等)、N.O.ムーア(ギター等)といった面々。日本人でいえば、エレクトロニクスの伊達伯欣、畠山地平、中村としまる、ギターの秋山徹次、オブジェクトの中島吏英といった人たちとアルバムを作った。
個性、自我
池田は自分自身のことを「渡り鳥」になぞらえる。確固たる自分を失くすという感覚である―――それは音楽活動の方向性だけでなく、演奏においても。ソリストのように個性を出してスポットライトを浴びるタイプではなく、いわば舞台美術家だ。バンドであろうとソロであろうと、自我が出ることを非常に嫌悪してしまう。10メートルくらい上から自分を俯瞰するありようがいちばんピンとくる、という。
その意味では、際立った個性をもつ人との共演はとてもむずかしい。伴奏であっても自我の表出になりうるからだ。坂田明(サックス)や木村まり(ヴァイオリン)との共演もそうだった。ただ、自分を追い込むことが好きで、さてどうしようという状況のときウキウキするという。それは「修行」でもある。
もちろん自分の音作りに関しては確固たる方法論がある。サイン波を中心としたサウンドの種を200個ほど持っておき、シンセサイザーを弾いたときに事前に用意した8個の種がランダムに現れるようにしている。自分でも弾くまで何が来るかわからず、常にどきりとしながらサウンドを作ってゆく。だから、ソロであっても自我を出す「シンセサイザーの演奏方法」ではない。サウンド全体のテイストは自分のものだとしても、はたしてそれを即興演奏での「個性」と呼ぶべきかどうか。ひょっとしたら、このアイデンティティのありようは仏教の悟りに近いものかもしれない、と話す。
池田は、そういった自我から離れた場所にある人たちが出てきたことを愉快に感じているという。たとえばサム・ゲンデル(サックス等)など、アメリカ西海岸のLeaning Recordsでサウンドをリリースしている人たち。ニューエイジ的であり、ヒッピーカルチャーと共通するものもある。アンビエントやヒップホップの要素もある。それはかつてのアーティスト然としたありようを良しとした文化とはまったく性質を異にするものだ。
共演者でいえば、トリオ・Phiptを組んでいる遠藤ふみ(ピアノ)、阿部真武(ベース)にもそのような面がある。その場にいるのかいないのかわからない遠藤の佇まいにはシンパシーを感じるし、威圧感がなく前にも出てこない阿部のベースは押しつけがましくない「植物のような感じ」だ。ここにジャズ要素がある山本達久(ドラムス)が入ってくるのもおもしろい。
ロジャー・ターナー(ドラムス)は両方の顔を持つ。秒単位での対応能力がすばらしく、アンビエント的にもフリージャズ的にもなりうるおもしろさがある。
作曲とライヴの方法論
ソロ作品も作り続けており、方法論が最近になって固まってきた。部分としての素材を即興で作り、それを日記のように残しておく。後日それらを使い、ループさせたり、重ね合わせたりする。別の日に作った素材どうしで偶然キーが合ってそれを利用することもあるし、無調となることもある。結果的にそれが作曲ということになる。2023年にデジタルのみでのソロ作品『Sparse Memory』を発表したが、録音時から2年が経ち、その間にも方法論はまた発展しており、また次のソロを作りたいという。
文化人類学のクロード・レヴィ=ストロースは、特定の目的や用途があって部分を作るのではなく、独立したものとして部分を作り、臨機応変につなげていくありようを「ブリコラージュ」と呼んだ。これは「野蛮」ではない。そして、目的を定めて音をコントロールしてゆく西洋音楽のありようとは異なっている。池田が電子音楽でやりたいのは「ブリコラージュ」なのだ。
ただ、この方法論はライヴでは使えない。ライヴは作曲ではなく、「部分」を見せる。いわば裸を見せるようなものであり、いちど出すと修復できない。体調や環境によってもちがうものになる。それはやはり「修行」であって、演っていかないとおもしろくはならない。
ライヴにはリスナーとの駆け引きという要素もある。よく演奏するFtarri(水道橋)はオーナーを含め音楽への理解の深い人が集まり、緊張感がある。またKNOCK(高円寺)はクラブスペースでもあり、テクノの人やDJが「いいですね」と声をかけてくることは意外だったという。池田は、次の世代が新しい対応能力をもっていることの現象だとみている。
池田マンダラ
池田は音楽家であると同時に美術作品も小説の執筆も行う。
美術のテーマも音楽である。これまでは「楽器」を作っていた。たとえば木に釘を打ち込んで弦を張り、その弦に絵具を塗布して震わせることで音が色の集合となる。そして、あらたなテーマは「譜面」だ。譜面は文法であり、時間は同じ速度で進み、音階もきれいなハーモニーを作り出すようにできている。これを崩すとどうなるか。
博物学の南方熊楠が説いた「南方マンダラ」というものがある。ランダムに多くの線が引かれており、それらがもっとも交わる点から見る世界は大日如来的なものだとした。それを解釈するならば、限られた専門分野だけでなくさまざまな追求から交わる点を見つけてゆかなければならないということだ。たとえばキース・ジャレット(ピアノ)のような音楽の天才とはりあいたくはないし、全く別の視点をもちたい。トゥープも決して楽器の演奏が巧いわけではなく、一方で非音楽的感覚ももつ人だ。
池田にとっての小説はそのようなものだ。宮沢賢治などの日本の小説には擬音が多くおもしろいという。そんなこともあって、坂田明とのデュオ作のタイトルは賢治の『セロ弾きのゴーシュ』から取って『Gauche』と付けたし、ロジャー・ターナーとのデュオ作のタイトルは賢治の詩集と同じ『an Asura in Spring(春と修羅)』とした。芥川龍之介の自作朗読もまた音楽のようだ。音として美しいことが池田にとって大事な小説の姿である。
ディスク紹介
(文中敬称略)
フリー・インプロヴィゼーション、池田謙