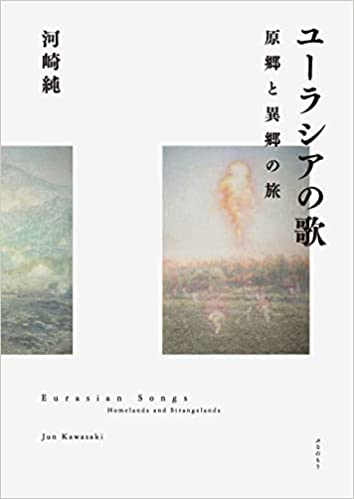#120 河崎純著『ユーラシアの歌』についての冗長なレポート(後編)
text by Yoshiaki Onnyk Kinno 金野Onnyk吉晃
0.
この一文は、2022年12月3日、岩手県盛岡市で上演された、音楽詩劇研究所によるコンサート版ユーラシアンオペラ「響き合う東アジアの歌声」のレビューと平行して、その主宰者、河崎純の著書からインスパイアされた愚考を散文化したものである。
河崎ほど自身の音楽のモチベーションと意義と現在を見つめている演奏家がどれだけいるだろうか。その彼の思索が一冊の本になったのである。
『ユーラシアの歌』は旅の記録、彼の個人史、活動報告、思想のための備忘録ではあるが、それをどれほど読みこんでも分からないものは残るだろう。しかしその分からない所こそが肝だ。
この不穏な世界の「無常」という流れに棹さす『ユーラシアの歌』も、ある種の日記文学とも紀行文学とも読めるのではないか。
1. ポリフォニー理論をもう一度音楽に戻す
前編で記したことを一部繰り返す。
<一人の歌い手が多様な表現をするのは浪曲やパンソリ的な話芸に近く、多数の歌手がそれぞれの役割を果たすのはまさにオペラであるが、今回の上演では一人の登場人物の声を、心情を、複数の歌手が担う。またその人物の舞踊も決して一対一の関係ではない。さらに河崎は、一切装置のない舞台で、背景さえも歌や踊りによって表現しようとしている。
つまり一人の存在の中の複数性、あるいはまた複数の中にある共通要素を、「音/演奏」と「歌/声」の組み合わせ、すなわち実体のない「音楽という現象」によって、鑑賞者に共感を求めているのではないだろうか。>
私はこう書きながら、どこかでこのイメージを既に得ていたと感じた。
それは旧ロシア、ソビエトの哲学者、批評家、ミハイル・バフチン(1895〜1975)の「ポリフォニー理論」であった。
ポリフォニーとは音楽で言う多声音楽であり、近代西欧において発達した楽理の基盤である。
バフチンは文芸批評において、登場人物の思想や心情を実在の人物のように批評・批判する場合や、それらは登場人物に託された作者の思想にすぎないと分析する場合について、どちらも小説のテキスト自体として捉えたものではないと批判した。
バフチンはドストエフスキーの作品分析においてこう考えた。
各登場人物が独立した人格、固有の思想によって振舞うことで、人物相互の間に「対話」が成立し、その関係性において、小説空間の多次元的・多視点的な表現が可能になっていると。
小説を書いた経験のある者からすれば、作者の創造した人格がひとりでに動き始めるのは納得できる。
バフチンは、「真理は、特定の視点からは表現することはできず、さらに複数の限定的な視点を総合的なひとつの視点によって完全に包含して、代替することもできない」とした。真理の絶対性への疑念である。作者は自作世界の神ではない。
彼はまた、芸術の創作における題材やジャンル、プロット等を選択する作者の姿勢や方法の特徴を「詩学」の問題とした。これはまさに河崎の面目躍如ではないか。
バフチンは、(神話文学ではなく)それ以降のヨーロッパ的モノローグ小説とは対照的に、ドストエフスキーの非ヨーロッパ的、まさにロシア的小説では、各登場人物が被造物ではなく作者と対等の存在として設定され、それぞれのイデオロギーや階層といった社会的差異が織りなす、複数の声や意識がテクストとしての小説であるという。これが彼の言う「ポリフォニー」である(これは日本の私小説に適応できるのか?)。
私は、河崎が自ら創作した詩劇に用い、個としての存在の内部にある多数の声(ポリフォニー)を複数のキャストに担わせつつ、あるいは歌わせる事で一人の女性のビジョン、イメージ(つまりコンテクストとしての存在)を形成させたのではないかと思うのである。
あるいはまた、西欧的ロゴス中心主義を問い直すブルガリア出身の記号論学者ジュリア・クリステヴァ(1941〜)は、意味を多数化する<身体のロゴス>として「ポリローグ」という語を用いた。クリステヴァはバフチンに負っているところがあるようだが、まさに存在の複数性という意味では「ポリローグ」という概念の方が河崎の思惑には近いかもしれない。
2. 時には母のない子の…
風景は人がつくるものだという。
そうだ、風景はそれを見入る人があればこそ存在する。河崎が作る二時間ほどの風景は、ありえぬ、あるいはあったかもしれない故地であり、そこに響く「故-響」である。それはまた一瞬毎に失われて行く故郷ではないか。ノマドならば旅が故郷なのだが。
いま、ここに生まれ育った我々は、ノマドではない。またディアスポラーでもない。ましてやレフュジーでもない。一方無思慮に、日本人は単一民族で、言語と国家が一致していると嘯く者もある。
河崎の住んでいる地域は身近にクルド人のコミュニティがあり(既に日本生まれの二世も居る)、居住地からもじって、其処をワラビスタンと呼んでいる。トルコ政府から存在しない部族とされ弾圧をうけてきた彼等との交流のなかで、河崎は国家と暴力と文化の問題を常に感じている(p334〜)。
他人事ではない。中国、インド、韓国、台湾、北朝鮮というアジア全体の政治関係の緊張と再構成。この文はそれを語る場ではないが、世界情勢を常に念頭に置かずには何事も語れない。
私は1957年に盛岡に生まれたが、物心ついて以来子守りはテレビとマンガ雑誌だったと告白しよう。毎日、歌謡曲の番組と子供向け番組とアニメがあり、それらの音楽でプラッギング(耳栓)された。思春期にはラジオの深夜番組や、FMで最新のポップスを覚え、背伸びして現代音楽と民族音楽にのめりこんでいった。つまり私の精神の栄養はマスメディアが用意してくれたのである。
これは特異例ではない。私と同世代の友人達は皆一様に、強くメディアの影響を肯定する。我々は生き生きとした一体感、ライブの音楽生成現場から離れ、学校教育の、音楽教室の「長三和音、モーツアルト、楽音」の世界と、スピーカーから流れる平板な(そう、ディスクからの)商品音楽に聴覚を支配されて育ったのである。そして結局今もその依存から脱していない。
私は、自身をデラシネ、文化的孤児とみなす事を否定できない。
また現在世界中に、アボリジニ(原住民の意味で)に対する憧憬を持つ者達がいる。彼等はアボリジニの文化復興を掲げ、その芸能をリスペクトする。
そのような者達は自らをアボリジニではないと意識しているのか。しかし世界中のアボリジニは、ほんの少しだけそこに先に来ていた、少しだけ長く住んでいた「移住者」ではないのか。
古いアボリジニの多くは文字を持たないからその来歴を絵や歌で記憶する。この歌が専門化していくと、少し前のアフリカ社会にみられたグリオとなるし、アイヌならユーカラとか、語り部になる。文字で記録されない部族の<歴史>は不分明で正確ではなく、権力の都合で装飾と改変がされやすい。川田順造は『無文字社会の歴史』(1976、1990)のなかで、アフリカのモシ族の口承芸能から王統を推定した例を示す。
我々は皆、デラシネの孤児であるだけでなく、少しだけアボリジニでもある。
そして孤児もまたいつか親となり、家族を作る。そこから彼の家系が、物語が始まる。国営放送で、その種の番組が人気なのもよくわかる話だ。
歴史を「勝者の記録」にさせず、個人の記憶の積層と民衆伝承からの抽出とし、政治、権力を(括弧)の中に幽閉しておくこと。民衆自身に語らせる事。
河崎は著書において、自らの生い立ちと想い出を語りだす。
山梨の農村にある祖父母の家で、親戚の子らと枕を並べて寝るとき、高い所に吊り下げられた先祖達の写真に睨まれているような怖さ、真夜中の、振り子時計のカチカチ、ギー、ジーンという、つげ義春のマンガにも出て来るあの音、そして朝には祖母が仏壇に飯を備え、鉦をならす音で目覚めた記憶。これはそっくり私も経験している! …その家は東北大震災の津波で永遠に消えた。
家族での墓参り、祖先への儀礼を提案する母に、消極的な父。しかし河崎は、父の理屈をひっくり返す事は出来なかったと述懐する。おそらく思春期には唯物論的な理性が優位に立ってしまうのはやむを得ないだろう。
その彼が「ユーラシアンオペラ」という作業=work in progressに辿り着くまでの経緯が、この一冊に納められている。前編にも書いたように、ユーラシア大陸の各所での出会いと軋轢と齟齬、歓喜と悲哀と慚愧が記される。
シベリアはシャーマン天国だという。その意味は、部族がシャーマンたる女性を核として多数存在するからだ。しかしシャーマンは行政的な役目はもたない。祭政一致ではないのだ。沖縄でもシャーマン的なノロ、ユタはあるが、これも祈る事を役割としている。彼等は部族の感情面を慰撫する。
「アイヌも…エヴェンキ族と同じく無文字社会だった。そこで口承で語られて来た神話が、女性によって書き留められた、ということにも着目した。男性は文字社会を成立させ、意味や価値を定着、明文化してその原則に依拠してきた。いっぽう女性が積み重ねてきた日々の即興的な営為は明文化されず、意味や価値に束縛されぬしなやかさをもって伝えられてきたはずだ。即興性は口承芸能の特性でもある。少女が書き留めた『アイヌ神謡集』は、即興の痕跡が根付いたままいきいきとしている。」(p134)
『アイヌ神謡集』は、19歳のアイヌ女性、知里幸恵がユーカラのなかから13篇をローマ字で文字起しをして書き上げた。知里は完成したその日、金田一京助宅で急死した。1922年の事である。
(「書かれたことばは、話されることばの一つの弱められた形である。…書かれたことばはそれを語る者があらかじめ姿を消してしまうことを意味する」オルテガ・イ・ガセー、1959)
河崎はアイヌ音楽をポリフォニー化し、カザフスタンの演奏家達と上演した。その報告を文面から想像する限り、舞踊や映像が混入する即興性の強い、敢えて言わせてもらえばユーラシアの「ジャズ」となっただろうか(p179-180)。
しかしこれが「ジャズ」であるか否かは、即断できないだろう。
舞踊や音楽は、かつて儀礼とそのあとの宴に欠かせなかった。ジャズは今そのようなあり方が可能だろうか。可能ではあろうが、どうしても商品として抽出された性格が露出する。そのようにしてしか我々は歌舞に出会えない。
だからこそ大規模なライブに「〜フェスティヴァル」「〜の祭典」という名がつけられる。ユーラシア各地の歳の祭り、季の祭りには共通性がある。そしてそのどちらもが、無文字的、口承的な秘中の秘、つまり神の往来を根底においている。果たして『真夏の夜のジャズ』や『ウッドストック』や『フジロック』はいかなる神を降ろしたのか。
ちょっと面白いのは河崎の、アヴァンギャルド音楽のパースペクティヴを、国や地域別にメモしているページがあることだ(p188-189)。全部紹介したいが、冗長なのでやめておく。一例でも出せば他も書かざるを得ないだろう。とにかく的を得ていて、笑いながら納得してしまった。
3. 肝っ玉おっかーない
今回の駄文のなかでも何度も登場するシャーマン、巫祝の女性的な優位性であるが、またここで母、妣(はは)に関して多少、音楽的な問題に繋がる連想がある。
端的に言えば「お袋さん」の性質について、ということになろう。
前出、クリステヴァは「アブジェクシオン」なる概念を提示する。
「アブジェクション」はもともと精神分析の用語であり、主客未分化の状態にある幼児が、自身と融合した状態にある母親を「おぞましいもの=アブジェ」として「棄却」することを意味する。
そこでプラトンに由来する「コーラ」という観念を援用する。コーラは何かを胚胎する空間なのだ。子宮を持つ母とみてもよい(すなわちオフクロ)。この母は父=ロゴスとは対にならず、息子を保護するものでもない。コーラは、何も生み出さず、母胎でも起源でもない、何かを呼び込む場所だ。
コーラは感覚的でも叡智的でもなく、父なるロゴスの保護を受けない「私生児的」(一種のオーファン)を養う。それは覚醒した意識、智慧、論理ではなく、強力な「夢見、陶酔」の状態でしかない。ある種のドラッグ体験のようなものだろうか。
このようにロゴスの世界と離反して行くコーラ=母=アブジェの語る言葉は、神話でもない。神話/ロゴス、虚構/現実の対性を超越した、あるいは無化するコーラこそが物語を生み出す。それは父=暴力に抵抗し続ける力だ。それはそれで恐ろしい暴力以上の恐ろしさを見せている。家父長的ファロスに対する家母長的アブジェ(なんて適当に二元化しちゃいけないだろうが)。
しかしまた「コーラ」はアンチロゴスとしての音楽をも生成する。
アレックス・ヘイリーの大ヒット作『ルーツ』(1976)の中で、奴隷としてアメリカにやってきたヘイリーの祖先はギターを「コー」と呼んでいたことが分かる。ここに言語的なルーツを感じた著者は、コーを探し求め、それが西アフリカに広く分布するリュートの一種「コーラ」であると推定する。
この名の示すものは、中空の胴、共鳴体を持つ楽器に共通の原理である。それはまさに「何も無い、それ故に神聖な空間」であり、「そこに神を降ろすことによって、音は音楽として鳴りだす」楽器という持ち運び可能な神殿なのである。シャーマンが、自らを依り代、依りましとするために己の中に留まっているロゴスを棄てるように、その結果自身が恐るべきアブジェ=コーラになるように。
クリステヴァはテクストの連鎖に記号生成の謎を探る。そこには<意味になる前の意味>が精子の群れのように蠢いている。この精子は何処に向かうのか。この精子の運動こそ「詩的言語」ではないのか。かくして彼女は構造主義の呪縛を、ソシュール記号論を断ち切る。
詩的言語は日常言語の亜種ではなく、日常言語こそが詩的言語の部分集合であるという逆転現象が起る。
これこそ河崎が、「現代詩の言語は、読み手に沈黙を要求する言語表現であるともいえる。そのような詩的言語に対して、…まずは声をざわめかせてみたいと思った。」(p30)と意図した上演言語の様態ではないか。
4. 狂った星達の天の下、無数のクニとヒト
ニンゲンは生れおちたとき、まだヒトでしかない。その存在は社会という第二の子宮において成長し、他者との関係性を通じて<人・間>になる。一個人の存在は、多数の血筋の結節点、knotであり、社会とはそれによって編まれた網である。
畢竟、河崎の求めるのは仮構の共同体、幻想の部族であろう。それは上演であり作品ではないのだ。
生は意識せずに与えられた。気づけば社会の中にある。そして死は、誰もが迎えるし、その先を知らない。共同体の観念は死者の系譜、先祖を語る事を基盤として成立つ。河崎のテーマ、『終わりはいつも終わらないうちに終わっていく』というコトバの<終わり>を<死>、また<生>に置き換えてみたくなる。
しかしまた共同体とは一体なんだろうか。少なくともそれは国家ではないのだ。共同体と音楽は支えあう。一方無くして他方は成立たない。
音楽は共同体を生きながらえさせ、その成員に確かな死を与え、また新たな生を迎えるためにある。その意味で「春歌」もまた共同体のウタであろう。河崎の春歌への思いは、添田知道から大島渚、そして林光を経由してブレヒト、ヴァイルにまで繋がって行く(p216〜218)。
韓国籍のチェ・ジェチョルがロシア、トルコの再出入国で拘束の可能性もあり、河崎旅団は緊張する。結局、運を天に託し事無きを得る(p116)。島国では海岸線が国境(とはいえないが)だが、地続きの国家群は見えない線を引いて部族を隔離し、共同体を解体する。
誰もが緩やかな連携の共同体を夢み、それは瓦解して行く。原始共産主義からアナルコサンジカリズムまでは数万年かかったかもしれない。しかし人民革命から強権国家に達するまで十年かからなかっただろう。教団も企業も学校も、あらゆる組織は、発足から十年で変容し始める。
さて2015年誕生の音楽詩劇研究所の将来や、如何に。
異郷を求めて原郷から旅立てば、異郷のなかに原郷を見いだす。そしてまた原郷のなかに異郷の人々が居る。異郷と原郷は互いに無限にマトリョーシカの入れ子になっている。その内奥から言葉にならない声が聞こえて来る。そしてユーラシアンオペラは、オーファンのポリフォニーである。 (とりあえず終わり)
河崎純, ジャズ, ユーラシアンオペラ, 音楽詩劇研究所, シャーマン, 響き合う東アジアの歌声, ユーラシアの歌, ミハイル・バフチン, ポリフォニー理論, ポリローグ, アボリジニ, アブジェクシオン, 共同体