JazzTokyo
Jazz and Far Beyond

-

#96 追悼 ガトー・バルビエリ
と、バッタリ、ガトー・バルビエリと出会う。黒いハット、枯れ草色のコットン・ジャケットに、赤白ストライプのシャツ。 「Hi ! ガトー、たったいま『ラスト・タンゴ・イン・パリス』を観てきたよ」 ちょっと、キョトンとしていたけれども、ドン・チェリーの奥さんが、ゆっくりていねいに、伝えてくれる。
-

追悼:ガトー・バルビエリ(1932年11月28日―2016年4月2日)
そして、ガトー独自の他の誰のものでもない音楽がついに完成したのは、1973年から1975年にかけてImpulse! に残された『Latin America』4部作だと思う。
-

RIP ガトー・バルビエリ
ガトーのヴォイスは、コルトレーンの影響は別にして、つねにヤン・ガルバレクの根源に通底するものだ。叙情的な歌い方、刺激的なメロディーと活力に満ちたラインを通して僕らの魂を揺り動かし、とろけさせてしまう。
-

ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #7 追悼 ガトー・バルビエリ〜アルバム『Fenix』を聴く
今回の楽曲解説はいつもの楽理的な立場と少し目先を変えてみたい。筆者がなぜこのアルバムを好んでいないかというと、それはこのバンドのタイム感に対して居心地が悪くてしようがないからなのである。
-

連載第13回 ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報
ライヴに行こう。それによって、誰もが、自分の物語を語りうるようになるに違いない。
-

ニューヨーク:変容する「ジャズ」のいま 第4回 ジェン・シュー:古代と現代を繋ぐ芸能~インターメディア~
土着文化、伝統、実験、革新、都会、舞踏、土、ステージ、儀式、夢、昔話、紡がれる歴史、切り開かれる今、月琴、唄と踊り、ヴィジュアル・アート、自然。ジェン・シューの表現する世界とは。
-

#1318 『ブラッド・メルドー・トリオ/ブルース・アンド・バラッズ』
そこにピアニストとしての、あるいは音で語り、音を織り成していく詩人としてのメルドーの、いわばメルドーらしさが、この新作に息づいているということではないだろうか。
-

#1317 『川口賢哉/雨露~無伴奏尺八即興独奏~』
ここにある尺八の演奏は、サックスやトランペットなどが切り捨ててきた領域をたしかに有しており、楽器のアドバンテージを活かした即興演奏には可能性を感じる。
-

#1316 『平田王子 渋谷毅/LUZ DO SOL アヴェ・マリア』
足かけ10年、つかず離れず程よい距離を保って活動を続けてきた二人のデュオ「ルース・ド・ソル」が練れてとても楽しい局面に入ったことを示している。
(4)<エスペランサ・ペルヂーダ>ではピアノのソロで思わずもれた渋谷のスキャットがなんとも微笑ましい、ついに渋谷がジョビンを歌った。 今回の渋谷はいつになく快活で自作の(7)<彼方へ>ではソロに合わせて口笛もきかれる。 -

#1315 『カルロ・サボーヤ/カロリーナ』
スケール感たっぷりなジョアン・ボスコの<アマゾンから来た女性>、心地良い浮遊感を味わえるジャバンの<アヴィエ―ヴォ(飛行機)>等々、その力量を窺わせるに充分な好ナンバーが並ぶが、なんといっても今作の注目はビートルズの<ハロー・グッドバイ>とスティングの<フラジャイル>という2大ヒット曲。
-

#1314 『Murray, Allen, Carrington, Power Trio / Perfection』
2016年に逝去した、オーネット・コールマン(as,tp,vln)、チャーリー・ヘイデン(b)、マーカス・ベルグレイヴ(tp)に、デイヴィッド・マレイ(ts,b-cl)、ジェリ・アレン(p)、テリ・リン・キャリントン(ds)が結成したパワー・トリオが、豪快で繊細なプレイで、トリビュートを捧げる。先人達の遺志を継ぎ、現代ジャズを新たなステージに、押し進める。
-

#1313 『Theo Croker / Escape Velocity』
アフロ・ビートと鋭いメロディが交錯するタイトなバンド・サウンドで、現代の混沌と希望をコンセプチュアルに描く、トランペットのニュー・スター、セオ・クロッカーの衝撃作。
-

#1312 『New York Standards Quartet / Power of 10』
日本でも精力的に活動しているニューヨーク・ジャズ・スタンダーズ・クァルテットの結成10周年記念作。緊密なインタープレイと、斬新なスタンダード解釈が円熟の境地を描く。
-

#1311 『グンジョーガクレヨン / Gunjogacrayon』
グンジョー色の求道者は、37年間音楽の輪廻を彷徨ったのちに、西から同類の求道者を迎え入れ、創造の神の霊感を再び受けて、音楽シーンに真を問うのである。即ちこれが<西の果てにはグンジョーあり>の理(ことわり)である。
-

#1310 『Yoni Kretzmer / Five』、『Yoni Kretzmer + Jason Ajemian + Kevi Shea / Until Your Throat Is Dry』
イスラエル出身のテナーサックス奏者ヨニ・クレッツマーは、新作2枚においてますます凄みを発散する
-

#1309 『Sergio Krakowski / Pássaros : The Foundation Of The Island』
ブラジルのパンデイロによる越境音楽
-

#1308『Arthur Vint & Associates / Through The Badlands』
アーサー・ヴィントは、アメリカの原点の一つである西部のフロンティア・スピリットを、ジャズ・オリエンテッドな音楽で描くことに挑戦する。
-

#1307 『Will Vinson / Perfectly Out of Place』
インプロヴァイザーとしては高い評価を確立していたウィル・ヴィンソンが、コンポーザー/アレンジャーとしての才能を余すところなく発揮した野心作。
-

#1306 『Anne Hartkamp Quartet / Songs & Dances』(2016: Double Moon)
バンドメンバーも自らの音を知り尽くしたヴェテラン揃い。長年組んできただけあり、抑制の効いた大人のサウンドをじっくりと聴かせる。コルトレーンやマル・ウォルドロンの名曲のなかに”The Moon a Sphere”(track.4)などの自作も遜色なく融け合う。
-

#1305 『Peter van Huffel |Alex Maksymiw / KRONIX』(2016: Challenge Record New Talent)
ピーター・ヴァン・ハッフェルといえば 「Gorila Mask」、ロックテイスト溢れるアナーキーな咆哮がすぐさま思いだされるが、ギタリストのアレックス・マキシミゥ (Alex Maksymiw) と組んだこのデュオアルバムは、一見その対極にあるかのように見える。
-

#1304 『Tamara Lukasheva Quartet / Patchwork of Time』(2016: Double Moon)
故郷のオデッサでは劇場で女優としても活躍していたというだけあり、変幻自在なヴォイスの魔力、あらゆるシーンの演出能力とその引き出しの多さに、音楽を聴いているというよりは舞台芸術を楽しんでいるような錯覚に陥る。
-

#1303 『Pascal Niggenkemper le 7 ème continente / talking trash』
昨年ソロ・アルバム『汝の耳で見よ(Look With Thine Ears)』をリリースし、21世紀の未来派芸術家として異彩を放つドイツ生まれのベース奏者パスカル・ニゲンケンペルの最新作。主戦場であるNY即興シーンの情報誌「New York City Jazz Record」から”NYシーンで最も冒険的で危険なベーシスト”と形容される。
-

#1302 『Ayumi Tanaka Trio / Memento』
ノルウェー音楽に特有の耽美な響きをまといながらも、それらを「日本的感性」とともに表現していく彼女の音楽は、卓越した演奏技術や作曲センスが輝く本盤においても、その特異なありようを随所に聴き取らせてくれる。
-

#1301 『内田修ジャズコレクション 人物VOL.2 宮沢昭』
同時期を生きたスタープレーヤー松本英彦 (1626~2000) の陰に隠れがちだった宮沢昭だが、その実力は衆目の認めるところで、このアルバムのリリースで彼の存在が再認識されるに違いない。
-

#896 東京都交響楽団 第807回定期演奏会
当夜のプログラムはペルトとライヒの作品が2曲づつ。これではいくらクリスチャンへの注目が高まっているとはいっても入りは期待できまいと踏んだ当初の予想は、見事に外れた。
-

#895 Cooljojo Open記念Live~HIT(廣木光一トリオ)
伝説の音楽家・高柳昌行の磁場たる場が開かれた。こけら落としのライヴは高柳の弟子筋にあたるギタリスト・廣木光一。
-

#894 Gilles Peterson presents 『WORLDWIDE SESSION 2016』
90年代に<ジャズで踊る>というムーヴメントが世界各地で盛りあがった。日本では折からの渋谷系ブームとも連動し、深夜のクラブで朝までジャズやレアグルーヴで踊り明かすのがトレンドになった。そんな時代の最先端にいたのがジャイルス・ピーターソンとUnited Future Organizationの松浦俊夫だった。その二人が21世紀の最初の15年が過ぎた今、ジャズを基盤にした”大人のための都市型音楽フェス”を企画した。
-

# 893 Big Phat Band
このBig Phat Band を率いるのはゴードン・グッドウィンズという男だが、普段はピアノの椅子に座ってバンドをリードし、演奏が終わればマイクでファンと交歓しあい、喜々としてメンバーや演奏曲の紹介を通して雰囲気を盛り上げる。
-

#892 パット・メセニー with アントニオ・サンチェス、リンダ・オー&グウィリム・シムコック
ユニティ・バンド&グループで、パットのサウンドコントロールの下でステージとの間に「見えない壁」を感じてしまったのに比べて、新バンドはダイレクトでインタラクティブなエネルギーをしっかり受け止めることができ、新バンドの魅力全開とまでは至らなかったにしても、高いポテンシャルを感じさせた。
-

#891 ディーナ・ヨッフェ 「ピアノリサイタル」
この日はファツィオリ社の主催による、スクリャービンとショパンの『24の前奏曲』計48曲を1曲ずつ交互に織り交ぜて演奏するという実験的な趣向。
-

#890 エグベルト・ジスモンチ・ソロ〜ナナ・ヴァスコンセロス追悼コンサート〜
目を閉じて音楽に聴き入ると、ジスモンチの演奏にナナ・ヴァスコンセロスのビートも聴こえてくる。ジスモンチはナナを意識しながら演奏をしている。すると、演奏が静かになった時、ピアノ以外の音が聴こえてきたような気がした。ジスモンチもピアノの向こうに身を乗り出して何か捜すように演奏をしていたが、いつしか会場の拍手の音にその気配は消されてしまった。
-

#085 「プライベート・マフィア 草兵」
ここに登場するのは、そのスマッグラーの中でもなんら組織を背景としない一匹狼。ノルマや規律にしばられないフリーランスの運び屋だ。草兵、41歳。国際前科4犯。身長180センチ。彼はみずからのことを、プライベート・マフィアと呼ぶ。
-

Reflection of Music vol.46 佐藤允彦
素材としての原曲をいかに料理するのか、編曲転じて新た曲を創る行為そのものを楽しんでいる。「戯楽」という発想そのものがジャズなのだ。
-

49. レジェンド、ジェイ ”フーティー” マクシャン生誕100年
この2016年はカンザス・シティ・ジャズの大御所、チャーリー・パーカーを見いだしたジェイ・マクシャンの生誕100周年にあたる。ジェイ・マクシャンは1930年代にカンザス・シティから生まれたブルースピアニスト、バンドリーダーであり、チャーリー・パーカーの才能を理解した人でだった。彼の人生はブルースと共にあり、2016年の今もカンザス・シティの総てのミュージシャン達の最高の指導者だ。
-
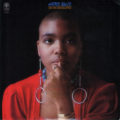
ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #6 『People Make The World Go Round』
70年代初期、ソウルグループ、スタイリスティクスによるヒットソング、<People Make The World Round>は、マイケル・ジャクソンやフレディー・ハーバードなどの手によってもカバーされた名曲。ディー・ディー・ブリッジウォーターは その名曲を自分のデビューアルバムでオリジナルとはかけ離れたモード・ジャズとして披露した。そのアレンジの素晴らしさを解析。
-

#018 ニコラス・レットマン・バーティノヴィック&川口賢哉 デュオ・日本ツアー2016 スペシャル・ゲスト:豊住芳三郎
一転、豊住の二胡の演奏から始まった2ndセットは、すぐNicoがアルコで和し、川口も尺八で寄り添ってアンサンブルとなった。豊住の二胡から旋律めいたものが生まれたので、Nicoが付け、コレクティヴ・インプロヴィゼーションではあったが、うまくアンサンブルと化したのだった。
-

#017 庄田次郎+織茂サブ / 大由鬼山+織茂サブ
“鎌倉の竹林を渡る風”が“野分”に変貌していくさまを目の当たりにして織茂の可能性に驚くとともに、織茂の可能性を引き出した鬼山師の技量と懐の深さに感銘を受けた一夜だった。
-
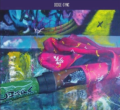
#016 Chapa
一聴、シンセの合成音と聴き紛うかも知れないが、かすかなブレスのノイズにディジリドゥの吹奏だと確認できる。何れにしても民族楽器1本で新しい音楽世界と創り出したChapaに乾杯だ!
-

#276 『Carla Bley-Andy Sheppard-Steve Swallow / Aandante eL Tempo』
多分、ミキシングコンソールのフェーダーはエンジニアの指先の圧力で押さえ込まれ定位置のままでは。
-

#275 『橋本一子 & 中村善郎/duo』
この録音の成功の起因は音質とバランスだ。音像は広げる事なくセンターに厚く集中させたのも音圧を感じさせて心地いい。
-

#274 『Nik Bärtsch’s MOBILE / CONTINUUM』
繰り返される演奏のなかに低音部の歯切れとリバーブ効果が謎めいた空間表現を醸し出す。
-

#147 マーシャル・アレン Marshall Allen (サン・ラ・アーケストラ)
「創造とはスピリット(精霊、魂)の技であり、何かを創造することは、一つのところから別のところへ行って、違う人や違うアイデアをミックスすることなんだ」
