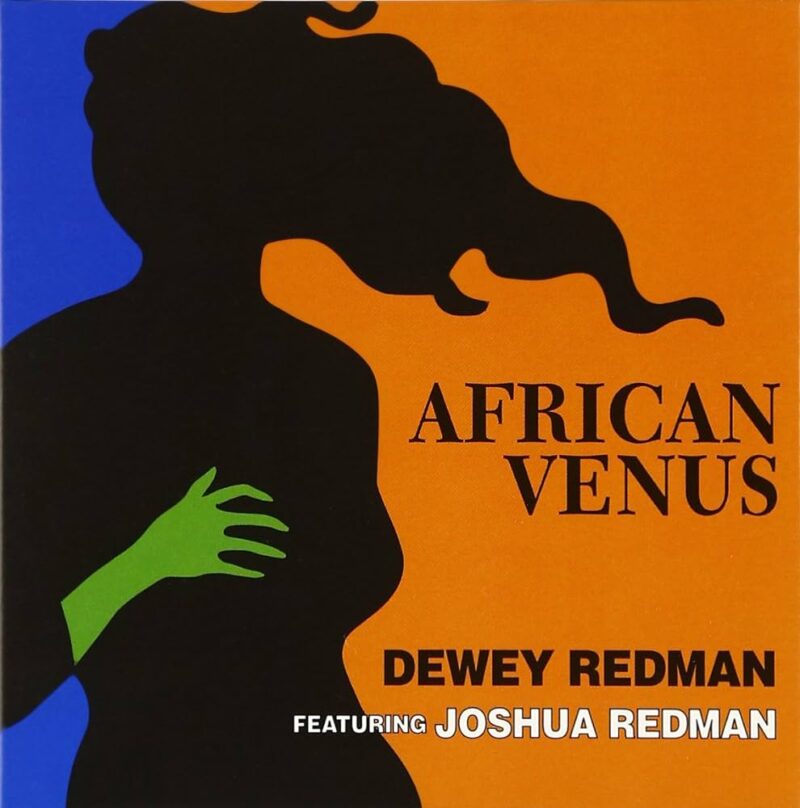ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #95 Joshua Redman<After Minneapolis>
ちょうど1週間前の9月15日にJosha Redman(ジョシュア・レッドマン)の新譜、『where are we』がリリースされた。このタイトルは「Where Are We?」ではない。クエスチョンマークを外しているので答えを求めていない疑問文であり、大文字を使わないことでつぶやきを表しているようだ。このアルバムはアメリカの各地の風景を追っている。あまり聴いていなかったジョシュアだが、このアルバムに興味を持ったのはDownbeat誌今月号の記事を読んだからだ。

筆者にはジョシュアを良く思っていなかったというお恥ずかしい過去がある。カルフォルニア州バークレーに生まれ育った彼は1987年にマサチューセッツ州ケンブリッジのハーバード大学に入学する。筆者が米移住し、ビッグバンドを始めたのもこの年だった。このビッグバンドはテナーのGeorge Garzone(ジョージ・ガゾーン)をフロントにフィーチャーしていた。ガゾーンは筆者がジャズを勉強し始めるきっかけになった人であり、そして筆者の永遠のアイドルだ。渡米1週間目に彼の率いる「Fringe (フリンジ)」のライブを見て、その場で「ガゾーンになりたい!」と決心し、彼の追っかけをして彼をコピーしまくったのであった。そして、最初の目標がガゾーンをフロントにビッグバンドを結成することだった。結局筆者が燃え尽きるまで約6年ほど活動した。そんなある時ガゾーンが他のツアーで不在だったので筆者はジョシュアに連絡をしてみた。彼の父親はOrnette Coleman(オーネット・コールマン)の片腕であり、あのPat Metheny(パット・メセニー)の『80/81』(1980)で素晴らしい演奏を堪能させてくれたDewey Redman(デューイ・レッドマン)だったし、信用できる知人からの推薦でもあった。しかし残念ながらあっさり断られた。その時の印象があまり良くなかったのでちょっと根にもったのであった。
今回この記事を書くに当たってインタビューを探していたところ、この動画に出会って顎落ち状態になった。彼は完璧な別人28号になっていた。当時の彼はちょっと鼻っ柱の強い、自信満々の若造と言ったところだったが、現在は優しい目をし、話す時も下を見て自分の言ったことを細かく言い直しながら話す学者系の人間になっていた。青天の霹靂だった。一体どういう経緯でこんなにも変わったのであろう。次に1994年のアルバム・プロモーションの動画を見つけた (YouTube→)。画面取り込みをした画像で見比べて頂きたい。写真左は彼がNYCに移住し、すでに2枚のリーダーアルバムを出した後だ。右はパンデミック開けの2020年にデューク大学で収録された公開インタビューからのものだ。

1991年、彼はハーバード大学の社会学部を主席で卒業し、イエール大学の法学部の入学が決まっていたが、夏休みにNYCを覗きに行って音楽を本気でやろうと気が変わったのだそうだ。相当の秀才と言ったところだろうが、本人は「自分のやりたいことがわからなかったから、とりあえずハーバード大学を出て弁護士にでもなるか」と思っていたのだそうだ。彼は黒人には非常に珍しいユダヤ教徒で、なぜか弁護士にはユダヤ系アメリカ人が多いという事実もある。また別のインタビューでは、ボストンの思い出はあまりいいものではなかったと言っていた。人種差別が嫌だったと語っているが、これはちょっと意外だった。世界各国からの留学生や研究員が溢れるボストンで、筆者はそれほど人種差別を感じたことはない。むしろ郊外での人種差別の経験の方が多い。と、思ったのだが、そう言えば筆者も大学の授業中での差別感は味わったことがあるのを思い出した。ジャズを勉強する場で東洋人が差別されるように、アカデミックなエリート大学で黒人が差別されるのがわかるような気がした。まあ、筆者はそれに動揺するほど繊細な性格ではなかったのが幸いだったが、ジョシュアは黒人という立場からもっと敏感だったのかも知れない。ちなみに父親のデューイは教育学で大学院を出てどこかで教鞭を取っていたと記憶する。ジョシュアもスタンフォード大学で教鞭を取った。かなりアカデミックな家系だ。だが、興味深いのは、このアカデミックなジョシュアでさえ音楽の勉強は一緒に演奏して学ぶしかない、と強調している。
Joshua Redman

彼はデューイの息子だが、両親は早くに離婚しており、母親に連れて行かれるライブに登場するサックス奏者が自分の父親だという実感はなかったそうだ。それでも母親の影響で父親の演奏やオーネットの演奏を聴いて育った。但しここで興味深いのは、自分にとってのジャズはソシアル・ファンクションではなかった。ここでのソシアル・ファンクションの意味は、仲間と話す話題、または仲間と出かける目的などだ。つまりジャズは自分のアイデンティティとは無関係のものだったそうだ。なぜなら自分の周りでは誰一人としてジャズを聴いている者がいなかったからだ。だから自分にとっての、ソシアル・ファンクションとしての音楽は間口の広い母親のコレクションからのもので、例えばThe Temptations (テンプテーションズ)、Otis Redding (オーティス・レディング)、Aretha Franklin (アレサ・フランクリン)、Earth, Wind & Fire (アース・ウィンド・アンド・ファイアー)、Commodores (コモドアーズ)、Kool & the Gang (クール&ザ・ギャング)、Prince (プリンス)、それに加えクラシック・ロックのコレクションも凄かった。例えばThe Beatles (ビートルズ)、The Rolling Stones (ローリング・ストーンズ)、The Who (ザ・フー)、Led Zeppelin (レッド・ツェッペリン)などをよく聴いた。ヒップホップの時代に育ったので、Public Enemy (パブリック・エナミー)などもよく聴いたし、生まれ育ったバークレー市はスカ・バンドが全盛だったので、The Beat (ザ・イングリッシュ・ビート)などもよく聴いたそうだ。
ジョシュアはNYC移住直後にデューイのバンドに在籍していた。アルバムも残っている。『Choices (1992)』と『African Venus (1994)』だ。どちらも素晴らしいアルバムだ。常に父親がソロ1番手で自分が2番手だった、とジョシュアは回顧する。1931年に人種差別の厳しいテキサス州に生まれた父親から滲み出るブルースが込められた演奏はとても真似することが出来ず、常に自分のソロに苦しんだそうだ。学校で習うテクニックを超えたスピリチュアルな何かを習得することが必要であることを父親から学んだ。未だにそれを追っている、と語っている。だが、ジョシュアの当時の演奏からは父親の影響は聴こえない。むしろ「どんなもんだい」的な演奏が聴こえてしまう。この公開インタビューで、観客の一人が「いきなりNYCに出て来てすぐにヴィレッジ・バンガードに出演し、アルバムをリリースし、と華々しいデビューだったけど、どうやって成功させたと思いますか」という質問をした。それの答えが面白かった。「若者特有の世間知らずさが運よく作用したのだと思う。今だったら考えられないような行動をいっぱい取った(笑)」。彼は自分の当時の振る舞いを認識しているようだ。
余談だが、この公開インタビューでもう一つ興味深い一コマがあった。観客の一人が「自分はトライアッドを使ったアウトの仕方は理解しているが、あなたはどういう方法でアウトするのですか」と質問した。それの答え方がとても彼の今の人柄を表していた。彼の意は、自分はトライアッドを使うとか、アウトしようとして演奏しているのではない、ということを言っているのだが、それをはっきり言わず、例えば「そんな難しいことしないよ」とか「練習では考えるけど、本番じゃあそんなこと覚えていられないよ」などと答えていた。明らかに「くだらない質問だ」と感じているのを隠しているようだったので微笑んでしまった。人間変われば変わるものだ。
そう言えば、筆者同様彼も練習嫌いだそうで、31歳になるまで練習をしなかったそうだ。練習をしないであれだけの演奏をしていたというのは、やはりお育ちが違う。それにしても31歳の頃に何かがあったのは確かなようだ。きっと性格もその時点で180度変わったのではないだろうか。
ところで、上記の1994年の動画がBrad Mehldau(ブラッド・メルドー)、Christian McBride(クリスチャン・マクブライド)、Brian Blade(ブライアン・ブレイド)で録音した『MoodSwing (1994)』だ。まあみんな若いこと。そして19年後にこのバンドが再結成され、『RoundAgain (2020)』と『LongGone (2022)』を録音している。ちなみにブライアンだけは多くのジョシュアのアルバムに参加し続けている。

聴いていなかったジョシュアだったが、実は1枚だけ以前に興味を持ったアルバムがある。2002年録音の『Elastic』だ。このアルバムはジョシュアには珍しく、筆者の好むグルーヴに溢れ、曲も彼の演奏自体も、ミックスさえも相当斬新で今でも愛聴している。彼が33歳の時の作品だ。この作品で聞こえて来る彼の演奏は他の作品と違い、うまく言葉で説明できないが、楽しんでいるサウンド、また、心の底から吐き出すようなサウンドがとても魅力的で、それが聞こえるのが筆者が知る限りこの1枚だけだというのがどうも残念だ。
『where are we』
16作目に当たるこのリーダーアルバムは、ジョシュアにとって「初めての」が多いことに興味をそそられた。まず、これは彼がBlue Noteに移籍して第一作目になる。彼が歌手を起用するのも初めてだが、最も重要なのは、彼にとってこれが初めてのコンセプト・アルバムだ、ということだ。コンセプト・アルバムはパンデミックの間にすっかりトレンドになった。皆篭りきりで暇を持て余したからかもしれない。この楽曲解説でもその多くを取り上げて来た。筆者も含めファンの多くがアルバムにストーリーを求め、ライブで楽しむ音楽とは別の商品を求めている。演奏したい曲を集めてアルバムにする時代は終わったと思う。
起用された歌手はGabrielle Cavassa(ガブリエル・カバッサ)というニューオリンズで活動する29歳のイタリア系アメリカ人だ。サンフランシスコの学校に行っていたので、ジョシュア同様サンフランシスコ・ベイ・ブリッジに想いがあるそうだ。そのサンフランシスコ繋がりで<I Left My Heart In San Francisco>をベースにした8トラック目の<My Heart In San Francisco>に辿り着いたそうだが、「あのベイ・ブリッジがサンフランシスコの看板なのに、あの曲にはブリッジがないんだよ」とジョシュアは笑っていた。

そのガブリエルとの出会いは、ジョシュアのマネージャーがニューオリンズで彼女を聴いてジョシュアに推薦したそうで、パンデミック中綿密に連絡を取り続け、アルバムのコンセプトを二人で練って行った。ガブリエルは参加を求められただけかと思っていたが、これだけプロジェクトに介入させてもらえるとは思っておらずびっくりしたそうだ。11トラック目の<Stars Fell On Alabama>はジョシュアとガブリエルのデュエットで、これが鳥肌が立つほど素晴らしい。是非ご一聴頂きたい。
ロバート・グラスパー、シオ・クローカー、ブラッド・メルドー、ウエイン・ショーター、ドニー・マッカズリン、シシール・マクロリン・サルヴァントなどのコンセプト・アルバムと違い、このジョシュアのコンセプト・アルバムには斬新なアイデアが捻り込んである。それは、それぞれの曲に数曲の関連した曲を混ぜ込んでいる、というかなり凝ったものだ。筆者が気がついたものを書き出してみる。
すぐに目につくのは8、9、10トラックのアラバマ関係の3曲だ。期待通りコルトレーンの<Alabama>をベースにしているが、中間に挿入されているのは1930年代の名曲<Stars Fell On Alabama>だ。コルトレーンのこの曲は1963年の黒人教会爆破事件で亡くなった子供達に捧げたものであることは周知の通りだ。
次に、1トラック目の<After Minneapolis (Face Toward Morning)>はこのアルバム唯一のジョシュアのオリジナルだが、Woody Guthrie(ウディ・ガスリー)の<This Land is Your Land>が挿入されている。このタイトルの「ミネソタ」は2020年の警官によるジョージ・フロイド殺害事件のことで、「Face Toward Morning)」とは喪に伏せるという意味と窒息死させられたということの両方に引っ掛けている。上記の「アラバマ」と合わせ、このアルバムは単純にアメリカの風景を描いているのでないことが瞬時に理解できた。
また、3トラック目の<Chicago Blues>はCount Basie(カウント・ベイシー)の<Goin’ to Chicago Blues>とSufjan Stevens(スフィアン・スティーヴンス)の<Chicago>が掛け合わされている。そして、9トラック目は現代音楽作曲家、Charles Ives(チャールズ・アイヴス)の<Three Places in New England>とBetty Carter(ベティー・カーター)が歌ったことで知られている<New England>が掛け合わされているようだ。
<After Minneapolis (Face Toward Morning)>
この1トラック目に針を落とすと、<This Land is Your Land>がジョシュアのアカペラで始まる。この1940年代に流行ったフォークソングは、1938年に流行った例のアメリカの第二の国歌的な<ゴッド・ブレス・アメリカ>を皮肉ったものらしい。ジョシュアがこの曲を選んだ理由がここにあるのだと思う。「アメリカは白人のためだけの土地ではない」と言ったところだと思う。
ジョシュアが始めたアカペラの演奏は普通の上手いジャズで、いつものように聞き流していると、ジリジリと変化して行った。まるで苦痛の叫びのようなサウンドになり、2オクターブ目のA音に辿り着くと循環呼吸で延ばし、リバーブを強くかけ始めた。これはもう鳥肌ものだ。えっ?これがあのジョシュアなのか、と耳を疑ったほどだ。Jan Garbarek(ヤン・ガルバレク)を思い出した。ジョージ・ラッセルがよく話していたが、なぜヤンがあのような演奏をするのかと言うと、彼は隣の部屋で戦犯として拷問を受ける父親の悲鳴を聞いて育ったからだという。
ジョシュアが延々と続けるA音にピアノが被さって入り、クラスターで音が重なって行き、ガブリエルの歌声が入る。
Keep on neck
Near necked night
Colors cleave
フロイドの首に締め付ける警官の膝と、夜の深いさまを引っ掛けたneckという言葉を強調して始まり、最後に「色が張り裂ける」となっている。なんとも強烈な詩だ。
Fear forms hate
in faithless fight
Love that leaves
「望みのない確執の中で怯えから憎しみが生まれ、心は失われる」
ガブリエルの歌い方が実にいい。この難しい音程のメロディを呟くように歌う。残念ながら時間がないので細かく分析できないが、このセクションのメロディーとコード進行はすごいものがある。ゆっくりとした単純そうなメロディーなのに、不安と怒りと希望を全て表現するようにムードが小刻みに変わり続ける。第一テーマがAメジャーとAをペダルで残したままでのB♭メージャーの繰り返しなので、AベースとB♭トライアッドがぶつかって不協和音を出し不安感を匂わせる。今までジョシュアの作曲作品は少し凝りすぎだという印象があったが、こんな曲を書くのか、と驚いてしまった。採譜してみた。

ご覧のようにコードとメロディが干渉する部分が数箇所あるが、これは故意だ。実に面白い。このフォームの最後、譜面13小節目、録音3分40秒付近で以下の歌詞が歌われる。
Rise up,
Face toward morning bright,
Bravery makes our peace.
「さあ立とう。朝日に直面しよう。我々の勇気が安らぎを導くぞ。」
ここで突然強力に緊張感が満ちたストップ・タイムが入り、モーダルなソロ・セクションに入る。ストップ・タイムの時には気が付かなかったが、ここからなんと5拍子に変化していた。しかもソロの調性は、ヘッド第一テーマの調性のAメジャーではなくAマイナーに変更しているのだが、入れ替えのコードであるB♭/Aは据え置きなので不安感が一挙に煽られる。このセンスの良さには唸った。

実はこのストップ・タイムのコードがかなり特異だ。ハーモニーの構成からF#のハーモニックマイナーから派生しているのは理解できるのだが、ジョシュアはG#を連呼して次のセクションのAマイナーに対するドミナント扱いをしている。ドミナントならばE7の変形か、もしくはSubVの変形と考えるのが妥当だが、例えばE7とするとナチュラル9thと♭9thの両方を含んでいることになるので成立しない。SubVと考えるとA♭7を基盤に考えるが、#9thのC♭と♭5のDは説明出来てもナチュラル13thのFの説明がつかない、とまあ分析泣かせのコードなわけだが、サウンドはむちゃくっちゃカッコいい。なので理論はどうでもいいということになる。この世界、カッコいいサウンドを出した者の勝ちだ。ちなみにコード名というのはそこでどういうスケールを使用するかで決定される。前述のようにここはF#のハーモニックマイナースケールが該当するので、F#を基盤に考えてみるとF#- (Major 7, ♭13) という変則マイナーコードだ。普段お目にかからないコード名になるのだが理論的にはこれが一番正しいということになる。ジョシュア恐るべし。
このアルバムでジョシュアは筆者好みに変身したのであろうか。今後の作品が楽しみだ。
ジョー・サンダース、コモドアーズ、Commodores、アース・ウィンド・アンド・ファイアー、テンプテーションズ、The Temptations、フリンジ、Fringe、ハーバード大学、Kool & the Gang、ガブリエル・カヴァッサ、Joe Sanders、Gabrielle Cavassa、Josha Redman、Charles Ives、The Rolling Stones、Dewey Redman、ジョージ・ガゾーン、コンセプト・アルバム、ベティー・カーター、Betty Carter、スフィアン・スティーヴンス、Sufjan Stevens、ジョージ・フロイド、George Floyd、ウディ・ガスリー、Woody Guthrie、George Garzone、スカ、Ska、パブリック・エナミー、ザ・イングリッシュ・ビート、The Beat、Public Enemy、The Who、クール&ザ・ギャング、led zeppelin、チャールズ・アイヴズ、アーロン・パークス、Aaron Parks、オーネット・コールマン、john coltrane、カウント・ベイシー、ジョシュア・レッドマン、ブライアン・ブレイド、Count Basie、ornette coleman、ジョン・コルトレーン、ブラッド・メルドー、Pat Metheny、クリスチャン・マクブライド、パット・メセニー、Prince、プリンス、ビートルズ、ローリング・ストーンズ、Wind & Fire、Earth、Brad Mehldau、ザ・フー、Joshua Redman、Christian McBride、Brian Blade、デューイ・レッドマン、Otis Redding、オーティス・レディング、Aretha Franklin、アレサ・フランクリン、The Beatles、レッド・ツェッペリン