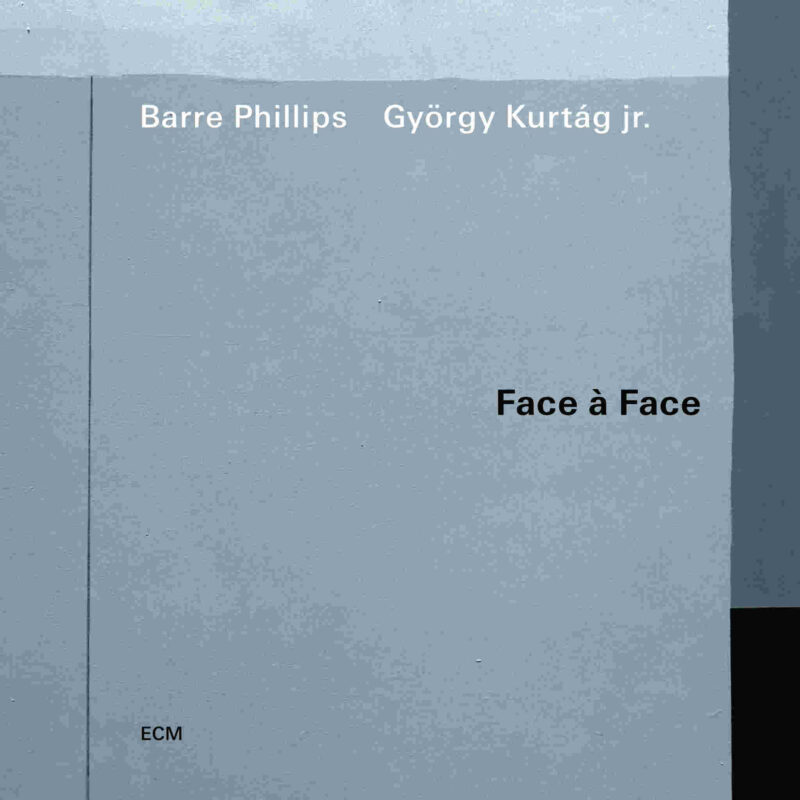#2211 『Barre Phillips, György Kurtág jr. / Face à Face』
『バール・フィリップス、ジェルジ・クルターグ・ジュニア /Face à Face(ファス・ア・ファス)』
text:Ring Okazaki 岡崎凛
ECM Records ECM2735
Barre Phillips: double bass (バール・フィリップス)
György Kurtág jr.: live electronics (ジェルジ・クルターグ・ジュニア)
1. Beyond 1:30
2. The Under Zone 1:53
3. Two By Two 4:12
4. Across The Aisle 4:22
5. Algobench 1:17
6. Chosen Spindle 4:15
7. Extended Circumstances 3:04
8. Bunch 3:10
9. Sharpen Your Eyes 2:10
10. Ruptured Air 3:10
11. Stand Alone 3:17
12. Forest Shouts 1:24
Recording/mixing:
September 2020 – September 2021
Studios La Buissonne, Pernes-les-Fontaines
by Gérard de Haro, Manfred Eicher,
György Kurtág jr., and Barre Phillips
Mastering: Nicolas Baillard
Cover: Fidel Sclavo
Produced by Manfred Eicher
Release date: August 19, 2022
<初めに>
バール・フィリップスについて書こうと思うと、「鬼気迫るアルコベース」とか「全身全霊の演奏」など、やや大げさな言葉ばかりが浮かんでくる。そうした表現を避けたいと思うと、今度は切り立つ崖や、見上げるような巨木を連想してしまう。おそらく彼の演奏は、ごく自然に、力強さや壮大さを感じさせるものなのだろう。そうしたスケールの大きさを感じた直後に、とても小さなものを見つめるような繊細さと出会う。アルコであれ、ピチカートであれ、何かを慈しむように弾き、何かを凌駕したいと願うように弾く。
2018年にECMからリリースされたフィリップスのソロ作品『End To End』を聴き、そんなことを考えた。ベースソロのアルバムはこれを最後にするということだが、3年後にリリースされた今回のデュオ作でも、自己のスタイルを貫き、全くぶれることのないバール・フィリップスに出会う。1934年10月27日生まれの彼は今秋88歳になるが、今後も意欲的なアルバム・リリースが続いてほしいと思う。
さて、バール・フィリップスのコントラバス演奏については、JazzTokyoの多くの記事で触れられているので、この記事ではもっぱら、共演者のジェルジ・クルターグ・ジュニア(以下、クルターグ・ジュニアと表記)の経歴や、彼の出身国ハンガリーの「前衛的」音楽事情に触れたいと思う。
<ジャンルを超えてインプロヴィゼーションを追求する2人>
クルターグ・ジュニアはハンガリーだけでなく、フランスを音楽活動の拠点としており、同国に暮らすバール・フィリップスとの共演は2014年に始まっていた。クルターグ・ジュニアは2009年に共同リーダー作『Kurtágonals』をECMからリリースしているが、こちらは電子音楽/アンビエントのアルバムでジャズ色はほとんどない。
2人の共演が実現したのは、おそらくどちらも即興 (Improvisation)を重視する演奏家だったからだろう。2014年にバール・フィリップスは the European Improvisation Centerをフランスで設立している。ちょうどこの頃、2人がともにジャズと電子音楽による即興演奏に取り組もうと考えていたなら、とても自然な流れだと思うが、裏付ける資料が見つからないので、あくまでも推測するだけである。
それはとにかく、クルターグ・ジュニアとバール・フィリップスは2014年にフランスのラジオ局のスタジオで共演し、2人の演奏を収録した番組が放送されたのちに、2018年に2人はハンガリーのフリー・インプロの名手たちとブダペストで共演し、2020年~21年にかけては、南仏のスタジオ・ラ・ビュイソンヌで、このデュオのアルバム(本作)が録音された。
<インプロ対決、またはインプロ・コラボレーションの成果>
本作はバール・フィリップスのソロ作『End To End』の余韻が漂うようなデュオ・アルバムである。3曲目の〈Two By Two〉ではデジタル・パーカッションが鋭い音を交えながら軽快にリズムを刻んだ後、コントラバスがじっくりと呼応し、アルコ音の表情が目まぐるしく変化する。これに続く〈Across The Aisle〉では、電子音とコントラバスの音が、バトルのように激しくぶつかり合う。その後は溢れ出す奇妙な電子音の中で、呟くようなコントラバスの低音が聴こえてくる。妖しく揺らめく電子音や、アフロリズムを思わせる打楽器風の音に包まれながら、バール・フィリップスの奏でる音の輪郭はくっきりと明瞭であり、2人の演奏は激しさと穏やかさの両極を行き交う。
本作の曲が短いのは、長い音源からハイライトシーンのようなパートを選び出しているからだろう。彼らはこのアルバムのために、2020年から2021年にかけて録音を続けた。編集とミキシングをなどを経て、このような臨場感に満ちたサウンドに出会えることを嬉しく思う。
<ジェルジ・クルターグ・ジュニアについて>
共演者のジェルジ・クルターグ・ジュニア(エレクトロニクス)の父は、クラシック界で著名なハンガリーのピアニスト、ジェルジ・クルターグ(シニア)*である。彼は現在96歳の父と同様に、作曲家の道を歩んできたが、ステージで演奏するのはピアノではなく、シンセサイザーなど電子楽器である。ロック、ジャズ、フォークロアなど、さまざまなジャンルの音楽家と共演する彼は、ハンガリーのジャズとクラシックを支えるレーベル、BMCのアルバムに演奏者として登場し、ECMからは2009年に共同リーダー作『Kurtágonals』をリリースしている。
(ジェルジ・クルターグ*について、カナ書きの表記例は他にもあり、ECM catalog のIndexには、「ジェルジ/ジェルジェ・クルターグ/クルターク」が挙げられている。)
1980年代にクルターグ・ジュニアはフランスに移り、フランス国立音楽音響研究所(IRCAM)で作曲家のリサーチ、コンピューター音楽の監修などを務める。作曲家マウリシオ・カーゲル、ペーテル・エトヴェシュ、シルヴァーノ・ブッソッティのもとで働き、ピエール・ブーレーズ〈ルポン〉米国ツアーに同行する一方で、音楽理論研究、電子楽器の改良に取り組んだという。1993年にはハンガリー映画の音楽を作曲して高い評価を受けている。その後彼の父、クルターグ(シニア)との共作で数年間エレクトロニック・ハイブリッド・ストリング・カルテットのための曲を書いた彼は、2009年にはプログレ・ロックバンドのSc.Artを結成しており、音楽ジャンルの垣根を超える身軽さに驚く。
<本作リリースまでのバール・フィリップスとクルターグ・ジュニアの共演歴>
フランスとハンガリーを拠点に、現代クラシック、ロック、映画音楽など、さまざまな活動に取り組んでいたクルターグ・ジュニアは、2014年頃からバール・フィリップスとのデュオ・ライヴを行っている。
2014年3月には、今回のアルバムの原型となるような演奏がフランスのラジオ局のスタジオで収録され、”A l’improviste”と題された番組で放送された。このときの動画はこちらに公開されている(約46分): https://dai.ly/x1vrmwd
こちらを見ると、フィリップスとクルターグ・ジュニアの演奏スタイル、共有するコンセプトが2014年にはすでに確立していたのが分かる。この動画は、2人がじっくりと築き上げる幽玄な世界を収録した貴重なものであり、今後も公開されてほしいと思う。
<ハンガリーでのフリーインプロ・セッション>
本作の紹介からはやや脱線するが、本作が生まれる少し前、ブダペストで開催された貴重なライヴについて書いておきたい。
2018年には、ハンガリーのBMC(ブダペスト・ミュージック・センター)館内にあるOpus Jazz Clubで、バール・フィリップスとクルターグ・ジュニアをゲストに迎えた特別グループが出演した。フリー・インプロを主体にした緊張感あふれるステージがYouTubeで視聴できる。
ハンガリーのフリージャズ界を牽引するサックス奏者、István Grencsó (イシュトバーン・グレンチョー) を中心としたグループは、GRENCSÓ SPONTANEOUS MUSIC ENSEMBLEと名付けられている。
ここに出演するハンガリーのミュージシャンたちが、どれほどバール・フィリップスとの共演を楽しみにしていたのか、ステージでの表情をを見ればありありと分かる。
1時間40分のステージには、時間をたっぷり使わないと表現できない演奏がある。コントラバス2台を擁した6人の演奏は、佳境に入るまでに少し時間がかかるが、中盤からどんどん面白くなる。フリージャズと室内楽、エレクトロニカが合体したような演奏だ。
<アルバム『Kurtágonals』(2009)について>
『Kurtágonals』(ECM 2097NS)のパーソネル:
László Hortobágyi synthesizers, computers ラースロー・ホルトバージ
György Kurtág Jr. synthesizers ジェルジ・クルターグ・ジュニア
Miklós Lengyelfi bass, effects ミクローシュ・レンジェルフィ
Produced by Hortogonals
ジェルジ・クルターグ・ジュニアの過去曲をトリオ・プロジェクト「ホルトゴナルズ(Hortogonals)」を通じて現代風に再編したものであり、ラースロー・ホルトバージが傾倒していたインドの音楽など、さまざまなサンプリング音源を綿密につないでまとめ上げる。ワールドミュージック色の強い2曲目〈Kurtagamelan(クルタガメラン)〉では、ガメラン(ガムラン)の音の響き、コーラス、鳥の鳴き声などを効果的に使いながら、迫りくるグルーヴを次第に強めていく。プログレッシヴ・ロック、インダストリアルの手法をうまく取り入れた珠玉作と言えるだろう。異様な緊迫感に満ち、北欧のフューチャージャズを連想させる〈Lux-abbysum〉にはダンサブルなノリがあり、案外聴きやすい。
このトリオに参加するベーシスト、ミクローシュ・レンジェルフィは、別のトリオ編成のバンドSc.Artでクルターグ・ジュニアと組んでいる。
ほとんどジャズ要素、インプロ要素がないので、バール・フィリップスのファンが楽しめるかどうかは分からないが、クルターグ・ジュニア作品の一端に触れる素晴らしいエレクトロニカ作品である。ただし本作はラースロー・ホルトバージにとっても重要なアルバムであるはずだ。ホルトバージのカラーが強く出た本作の続編は未だに出ていないようだが、もしも新作が出るとしたら、是非聴いてみたい。