JazzTokyo
Jazz and Far Beyond

-

Reflection of Music vol. 52 ミシャ・メンゲルベルク
ミシャ・メンゲルベルクはヨーロッパの音楽シーンにおける60年代のパラダイム転換を象徴するミュージシャンだった。
-
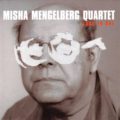
ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #17 『Hypochristmutreefuzz』
エリック・ドルフィーの<Last Date>でしかミシャ・メンゲルベルクの名を知らなかった筆者、訃報をきっかけにミシャのフリー・インプロバイザーとしての実力やICPなどでの活躍を知るが、フリー・インプロバイザーとジャズとを両立できる数少ないアーティストとして感銘を受け、ジャズ・プレーヤーとしてのミシャを解析して見た。
-

ミシャとサブ、そしてモンクを想うとき 望月由美
サブは数多くのミュージシャンを招聘し日本に真のフリー・ミュージックを紹介してきたが、振り返ってみるとミシャが一番良かったねとため息を漏らした。
-

Hommage to Misha Mengelberg Roberto Masotti, Millano
ミラノに住む著名な写真家ロベルト・マゾッテイが捉えたミシャ・メンゲルベルク。1978年を中心に最新は1998年のポートレイトまで。 *をクリックすると拡大表示されます。
-

ミシャ・メンゲルベルクの思い出 Onnyk
他のメンバーとは別に用意された6畳ほどの楽屋に、ミシャとペーターが座っている。そしてハンは広くも無い室内をうろうろしている。ヘビースモーカーで知られるミシャは紫煙を吐いて椅子に沈みこんでいる。
-

Misha Mengelberg 追悼 ~コーヒーとパフェと味噌汁と
するとミシャさんは、コーヒー、パフェ、そしてなんと味噌汁を同時に注文されたのだ。注文を取りに来ていたウェイトレスさんの一瞬「え!?」といった表情を未だに忘れていない。そして、それらを同時に頂いているミシャさんの姿を見て、サブさんと私は、「これこそフリーなんだよ!これぞDADAなんだよ!」とかワケの分からぬことを話していたのでした。
-

ミシャと囲碁
ミシャの腕前は二段くらいだったと思う。こちらは初段くらいだったのでちょうどよかった。やってみたらミシャの方が少し上で、力はあまり感じないけれど、形がよくて品がある。
-

追悼 ミシャ・メンゲルベルク
『逍遥遊』セッション@1994年10月6日 山口県防府市カフェ・アモレス
-

追悼 ミシャ・メンゲルベルク
その布で、ミシャはピアノを、ハンはドラムセットを被せ、紐で縛り始めた。聴衆は固唾を飲んで見守るばかり。楽器を縛りおえた二人は黙って会場を後にした。残された聴衆は一瞬の間ののち大きな拍手と指笛で彼らのパフォーマンスを讃えた。
-

ミシャ・メンゲルベルク追悼コンサート
ボケることも、言葉少なになるのも、忘れていくことも、人間にとって自然なこと...。
-

R.I.P. 生悦住英夫
喋るのも辛そうな状態だったので、話す負担すらかけさせたくない気持ちでした。私は作り笑顔で、部屋の雰囲気を暗くしないようにしようとする事がやっとでした。川島さんが「何か聴きたい音楽はありますか」と訊くと、やはり「船村徹」と答えられました。
-

追悼:生悦住さんと私 Onnyk (きんのよしあき)
また、特筆すべきは、私淑していたアメリカの音響彫刻家ハリー・ベルトイアのCDを出していただいた事です。ベルトイアのレコードは70年代、知られざる名作でしたが、全11枚のアメリカ盤の質の悪さは本当に情けない物でした。録音だけは生前の本人がしており、質は良かったので、なんとかこれをCD化したいものだと思い、生悦住さんに相談を持ちかけたのです。
-

連載第21回 ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報
ストレート男性の世界から音楽を拡張した「The New York Review of Cocksucking」(!)、カラフルで、ときに暴力的で啓示的でもあり、古くからのスピリットにモダンの美学を吹き込んだ「Sirene 1009」。
-

ニューヨーク:変容する「ジャズ」のいま 第13回 蓮見令麻〜手探りでたぐり寄せた、その糸で織ったもの
2作目のアルバム、ピアノ・トリオ作品『Billows of Blue』のリリースに至るまでに出会うべくして出会った数々の名盤と、ニューヨークの音楽家達。「ジャズ」とは何かという問いの追求について、自身が語る。
-

ある音楽プロデューサーの軌跡 #35 『山下和仁+ラリー・コリエル /ギター・オデッセイ: 四季』
背筋を伸ばし上半身を直立させて弾くラリーに対し、背中を丸めギターのボディに覆いかぶさるようにして弾く山下。この姿勢はおそらく大きなギターを抱え込んで弾いていた幼少の頃の癖が抜けきれないのだろう。
-

Live Evil #26 「横田明紀男レコ発インストア・ミニライヴ」
デコラティヴな奏法ながら全体としては設計のしっかりした構成美に富んだ横田の演奏からはどこかガウディの建築が想起されたといえば言い過ぎだろうか。
-

#1399 八木美知依、インゲブリクト・ホーケル・フラーテン、ポール・ニルセン・ラヴ/ディケイド〜ライヴ・アット・アケタの店
タイトルの『Decayed』は「腐った、衰えた」という意味だが、発音が同じ「Decade(10年間)」とのダブル・ミーニングであるのは間違いない。前作から10年後、2015年12月13日荻窪アケタの店での実況録音である。
-

#1398『V.A (大塚広子監修選曲) / PIECE THE NEXT JAPAN BREEZE』
DJ/プロデューサー/文筆家として多方面で活躍してきた大塚広子による、現代日本のジャズ・シーンを取りまとめたコンピレーション・アルバムの第三弾。『Jazz the New Chapter』シリーズがあえて取り上げることのなかった日本の現代ジャズ・シーンに触れてみるための、貴重なリアルタイム・ドキュメンタリー・アルバムである。
-

#1397『Rema Hasumi 蓮見令麻 / Billows of Blue』
すでにいくつかのレビューで触れられているとおり、後期の菊地雅章の到達を、この蓮見令麻のピアノは備えている、が、
-

#1396『GRERUM OMNIBUS / HANDFUL』
ピアノのティモシー・バンシェット(p)とドラムスのジェイミー・ピート(ds)はここ数年グレールムとのトリオのほかアムステルダムを中心に精力的に活動している若手で、二人とも楽器を鳴らし切っているところが好感を持てる。
-

#1395『ヒグチケイコ+神田晋一郎/passing and longing and there is only a trace left 過ぎしも愛しもただ跡だけが残り』(2017:Ftarri)
成熟が内包するスリルと、決して飼い慣らされぬ気高さ。移ろう一瞬が遺す残像の数々に絡めとられつつ、「うた」が志向する極北のエレガンスが味わえる。It is purely the thrill contained in maturity and an untamed noble dignity. Captured by the numerous residual images left by each fleeting moment, the listener can only enjoy the ultimate elegance that the “songs” and performers aspire to achieve.
-

#1394『Albert Cirera/ Hernâni Faustino/ Gabriel Ferrandini /Agustí Fernández: Before the Silence』
リスボンとバルセロナを股にかけるクァルテット。果てしなく続いていきそうな壮大なフリー・インプロヴィゼーションは、沈黙から爆音まで最大限の振れ幅でありながらも、緩みを一瞬たりともみせぬ頑健な構築力で無敵の存在感/Spanning the jazz scenes of Lisbon and Barcelona, this full-on quartet and their spectacular improvisations ranging from deep silence to roaring mayhem give the impression of a never ending river.
-

#1393『Craig Taborn / Daylight Ghost』
この『Daylight Ghost』の最大のポイントは、ズバリ、管のクリス・スピードの存在だ、このナナメになった棒読みトーンの官能だ、
-

#1392『ティグラン・ハマシアン / An Ancient Observer〜太古の観察者』
『Mockroot』の世界に、耽溺したうえで、このピアノ・ソロ作品は受け止められなければならない。
-

#1391『Shai Maestro Trio / The Stone Skipper』
借りパクも、剽窃も、孫引きも、ポップスの凶悪で生命線な力学である、これをジャズとして聴けるのかというと申し訳ないがまったくノーだ、
-

#1390『Matt Mitchell / Forage』
ティム・バーンの自己レーベル「スクリューガン」からリリースされるという事実、これが示すのはマット・ミッチェルの拒絶か、ECMアイヒャーの却下である、
-
#1389『Aron Talas Trio / Floating Island』
さりげなく21世紀型つんのめるドラムンベーススタイルのタイコの叩きを添えているのも、「コレが新しいんだ、カッコいいのだ」と鼻につくところもない(とっても重要)、つまりは、スマートなのだ、
-

#1388『Stephan Crump | Ingrid Laubrock | Cory Smythe / Planktonic Finales』
作曲の否定や即興の称揚というよりも、インプロヴィゼーションによって現れるだろうオルタナティヴな構造化――スポンティニアス・コンポージング――の探求。少なくとも本盤に残された有機的に発展していく「即興音楽」は、そうした行為のありようを物語っている。
-
#1387 『Aron Talas / Floating island』
その潔さとみずみずしさはジャズの本場からアウェイでいられることの大いなるプラスの面に違いない。
-

#944 橋本一子&中村善郎 duo
観客は、橋本がホステスを務めるTVジョッキーに中村がゲスト参加した番組を生で観ている風情。ボサノバらしいなんともインティメートな雰囲気に満たされた、しかしとびきりゴージャスなひとときだった。
-

#943 THE RESIDENTS ザ・レジデンツ – In Between Dreams –
『レジデンツ』とはステージ上の特定の誰かを指すのではなく、この時間を共有し錯乱した夢物語に参画するすべての人々が醸し出す集団的無意識の擬人化なのかもしれない。
-

#942 齋藤徹 plays JAZZ
ふたたび齋藤徹が抱きしめた「ジャズ」、「齋藤徹のジャズ」に向けた序章。
-

#941 植松孝夫+永武幹子デュオ
豪放で魅力溢れる音色を持つ植松孝夫のテナー、知的できらびやかな永武幹子のピアノ。大ヴェテランと新進気鋭とのデュオ。
-

#940 田崎悦子 Joy of Chamber Music Series vol.10
この「Joy of Chamber Music Series」は、田崎悦子がアメリカ留学時代に経験したタングルウッド音楽祭がベースとなっている。ルドルフ・ゼルキンやアイザック・スターンといった巨匠が若き音楽家と別け隔てなく生活を共にし、アンサンブルを楽しむ、音楽漬けの日々—。これが後の芸術家人生に及ぼす影響は測りしれない。
-

#939 OKABE FAMILY Young VIPs tour at BIMHUIS, AMSTERDAM
ヨーロッパで英語がノン・ネイティブのための共通語であるのと同様、ジャズが彼らと私たちの共通言語ということだろう。ジャズは健在なり。
-

#938 東京都交響楽団第825回定期演奏会Cシリーズ
「魔法使いの弟子」にしても、この「幻想交響曲」にしても、あたかも全力で格闘技を試みているかのような彼の一挙手一投足、あるいはステージ上の俳優が身体を張って演技するかのように彼のタクトに応える都響の迫真の熱演に、会場を埋めた聴衆の誰も彼もが思う存分酔わされたのではないだろうか。
-
#937 ダニエル・“ピピ”・ピアソラ・トリオ
ダニエル・“ピピ”・ピアソラは、タンゴに革命をもたらしたアストル・ピアソラの孫にあたる、アルゼンチン・ジャズ界を代表するドラマーで、エスカランドラム、エンセンブレ・レアル・ブック・アルヘンティーナ等にも参加している。
-

#936ダニー・マッキャスリン・グループ with マーク・ジュリアナ、ティム・ルフェーヴル、ジェイソン・リンドナー
急激にしかも世界的に注目されるようになったのは、デヴィッド・ボウイの遺作『★(Blackstar)』を支えるバンドに抜擢されたこと。グラミー賞授賞式では、ダニー以下バンドメンバーが登壇し、デヴィッドに代わりダニーが受賞しスピーチを行った。
-

# 337 『羽野昌二+庄子勝治 /Shoji & Shoji』〜Hear, there and everywhere #3
ドラムも負けていない。スピーカー空間一杯の拡散。絡むアルトの表現と音響上に素晴らしい効果を示した。
-

# 336 『羽野昌二+中村大 Duo/Soft Core』
シンバルの強調感が演奏以上の刺激を受けるのは、マイキングの仕業。
-

# 335 『Trouble Kaze / JUNE』
トランペットはいかなる奏法も音の出口は探れるが、ピアノは、通常のマイキングから、エフェクトがかかると変更せざるをえない。
-

# 334 『Aron Talas Trio / Floating Island』
シンバルの距離感を感じさせる扱いが、トリオの空間表現の要となる。
-

# 333 『八木美知依 本田珠也/道場 弐ノ巻』
さらにエレクトリックを上手く使って音像移動の仕掛けが面白い空間を造る。ディレイの効果等、ミックス段階でのきめの細かい作業が楽器の生をさらに異次元で聴く感触に。
-

# 332 『DJ大塚広子/ピース・ザ・ネクスト・ジャパン・ブリーズ』
すべての音楽が、聴いて楽しいので、録音試聴であることを忘れる。どの楽器も鮮明、音量感を持たせた録り方に、数多の経験を重ねた筆者ではあるが、思わず「一歩退く」。
-

# 331 『カオリ・ヴァイブス・カルテット/クロス・ポイント』〜Hear, there and everywhere #2
そしてエンジニアを含めて、緊張感で仕上げる「一発録り」。
-

#330 『川崎 燎 Ryo Kawasaki / Level 8』
録音段階から、イメージされた音色とエッジの立て方を計算しての録音だと推察。
-

#155 Aron Talas; アーロン・タラーシュ(アーロン・タラス)
その人の音楽上のアイデンティティは、多少の差はあってもあれこれのミュージシャンの無数の影響が集積されたものではないでしょうか。
-

# 154 川崎 燎 RYO KAWASAKI (Part 2)
基本的に、僕はジャズを学ぶのは学校ではなくて全部独学でできるはずだと思っている。音楽学校は音楽理論や演奏技術に長けていれば良い音楽家になれるという錯覚を作り出してしまう恐れがある。なぜかと言うと僕の観点では真の音楽家とは独自の音楽手法を編み出せる技量がないと存在し得ないと思われるから...。
-

#090「G-Modern~Psychedelic, Avant-garde, Underground Magazine」 Vol.25
G-Modern 25号を開いてみると、灰野敬二、JOJO広重、非常階段などの固有名詞があちこちに踊っている。表4の広告は灰野敬二のドラム・ソロのアルバムだ。そう、G-Modernは言ってみれば彼らの牙城だったのだ。
