JazzTokyo
Jazz and Far Beyond

-

悠々自適 #91「角田健一ビッグバンドと小曽根真 feat. No Name Horses」
新年早々の巻頭文では2つのビッグバンドが今回、いかなる興味尽きない演奏を行ったかに絞って報告することにしたい。
-

#16 フェスティヴァル in 2019
〜 フリージャズ、即興音楽 and beyond…2019年はフェスティヴァルによく足を運んだ年だった。6月7日〜10日に開催されたドイツ、メールス ・フェスティヴァルに行ったのを皮切りに、結果的に11月までの間に野外フェスから小規模なものまで7つのフェスティヴァルに出かけた。それを振り返る。
-
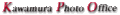
河村写真事務所 #002「高柳昌行|富樫雅彦」
共に東京生まれのふたりの異能のジャズ・ミュージシャン、高柳昌行(g)と富樫雅彦(ds) の共演の記録はいくつか残されている。
-

# 10 『Blue Note Voyage』
メンバーそれぞれの対抗心もプラスに作用し、その内容や気構えはかなりグッドそのもの。あれから半世紀以上かつてのBN名曲群が、J-ジャズの現場で見事に蘇生される姿。
-

#09 『狭間美帆 /Dancer in Nowhere』
『小曽根真 featuring No Name Horses /1515~Until We Vanish』text by Msahiko Yuh
-

#08 『歌女 kajo/遠ざかる、一つになる go far, be one』
チューバ奏者、高岡大佑と2人のドラマー/パーカショニスト、石原雄治と藤巻鉄郎によるインタープレイは「即響」という言葉が似つかわしい。公園での録音だが、環境音や蝉などの鳴き声と演奏の絶妙なバランスといい、その取り込み方はまさに借景だ。2019年に聴いたCDの中で一番の異色作。
-

#07 『Sluggish Waltz スロッギーのワルツ』
追悼・齋藤徹さん。亡くなる直前に、詩人やダンサーとのコラボレーションを模索していた。世界に生きる誰もが<この身体で/身体だけで>旅を続けなければならない。それが世界に向けられた齋藤徹さんの最後のメッセージではなかったかと思っている。
-

#06 『龝吉敏子+ルー・タバキン/エターナル・デュオ』
ホール残響を味方につける手法で、見事な音色のテナーの収録。ピアノも同様。
-

#05『加藤崇之 / 森の声』
加藤崇之のガットギターソロ3作目。故・津村和彦のギターを用い、八ヶ岳のふもとで録音されたバラード集。
-

#04 『land & quiet』
伊藤ゴロー、佐藤浩一、福盛進也が、2018年から活動してきたユニットが「land & quiet」と名付けられ、角銅真実とロビン・デュプイを加えてファーストアルバム『land & quiet』をリリースした。
-

#03 『Masahiko Satoh+Sabu Toyozumi / The AIKI』
『佐藤允彦+豊住芳三郎/合気』対決や優劣ではない。むしろ相手を抱え込む懐の深さだ。しかし、そこに張り詰めた緊張感は只者ではない。
-

#02 『沖縄電子少女彩 / 黒の天使』
沖縄電子少女彩をはじめ、現代産まれつつあるジャンル無用の表現者に対して如何に心を開けるかどうかで、これからの音楽の楽しみ方が大きく変わる気がするがどうだろう。
-

#01 『喜多直毅&黒田京子/残された空』
表現の可能性に果敢に挑みつづけながらも、単なるインパクトに終始せず、必ずやその先にある薫り高い音楽性にまで到達する二人の音楽の気概—その実像を堪能できる一枚
-

#13『龝吉敏子&ルー・タバキン/エターナル・デュオ』
玉石混淆の1年間を振り返る楽しさがある一方で、毎年思うことだが何か肝心なものを聴き(見そこなった)想いが消えない。
-

#12 『ジェイ・マクシャン・ライブ・イン・東京 1990 : Jay McShann Live in Tokyo 1990』
1990年年に来日したジェイ・マクシャン・トリオの日本公演が素晴らしいマスタリングで蘇ったアルバム。
-

#11 『Flin van Hemmen / Casting Spells And The Coves』
前作には参加していたタイション・ソーリー、ハスミレマ、も、含めて、この三人はニューヨークで21世紀のジャズ史の扉を開いた菊地雅章の音楽的後継者、チルドレンである
-

#10 『Peter Lemer Quintet – Son of Local Colour: Live at the Pizza Express, Soho』
サーマンとスキッドモアが、熱いバトルを繰り広げるトレーンの〈インプレッションズ〉一曲だけでも、買う価値大!
-

#09 『Matana Roberts / Coin Coin Chapter Four: Memphis』
マタナ・ロバーツによる「Coin Coin」シリーズの第4作。これまでよりもさらに語りの力を強めた印象深い作品である。記憶は語りなおされ、言葉と音楽とがその都度新たな意味を持って浮上する。
-

#08 『上原ひろみ/スペクトラム』
重厚なサウンドに驚愕。録音技術からの視点で、このサウンドを解釈すると、今までに聴いたことがない録音手法。
-

#07 『アンジェリク・キジョ/セリア』
いずれにしろこのアフリカン・クイーン、アンジェリク・キジョの力量が、十二分に発現された注目の作品だと思います。
-

#06 『Jaimie Branch / FLY or DIE Ⅱ: bird dogs of paradise』
2019年もジェイミー・ブランチの快進撃は止まらなかった。2017年に鮮烈な印象を残した初リーダー作『FLY or DIE』の続編。
-

#05 『カミラ・メサ&ザ・ネクター・オーケストラ/アンバー』
チリ出身のカミラ・メサが、弦楽四重奏を加えた8人編成の新ユニット「ザ・ネクター・ジャズ・オーケストラ」を結成、『アンバー』を発表し、2019年9月にはブルーノート東京公演を行った。
-

#04『Paul Bley Trio / When Will The Blues Leave』
ベテラン・トリオが聴衆と即興の醍醐味を共有する巧みさを発揮した秀作。
-

#03 『Lookout Farm / Live At Onkel Pö’s Carnegie Hall, Hamburg 1975』
このグループの凄さをあらためて魅せ付けさせられた1枚であった。
-

#02『Miles Davis/Rubberband』
ただの未発表アルバム発掘リリースではなく、お蔵入りプロジェクトをマイルスの遺志を継いで完成させたこのアルバム作品、筆者はもっともっとメディアで騒がれるべきだと強く感じた。最初にEPとして5つも違うバージョンを作って公開したことも音楽的にはかなり成功していると信じる。
-

#01 『Marshall Allen, Danny Ray Thompson, Jamie Saft, Trevor Dunn, Balazs Pandi, Roswell Rudd / Ceremonial Healing』
マーシャル・アレン師を中心に6人の猛者がデタラメを極めた本作は、混迷する世界の癒しの儀式のサウンドトラックなのである。
-

#11 Asian Meeting Festival 2019
観たのは東京ドイツセンターでの最終日のみだが、会場のあちこちに位置した複数の出演者によるパフォーマンスがノンストップで、しかも様々な組み合わせで変化しつつ、同時進行で繰り広げれられる様は刺激的だった。
-

#10 三浦一馬(バンドネオン) × 岡本和也(ギター) 第2公演
Kaleidoscope 〜万華鏡〜一馬君のピアソラへの対し方はあくまでこの偉大な音楽への礼節をわきまえたものだ。次世代の若者によって再発見されたピアソラ像がなんと瑞々しい香気に満ちていることか。
-

#09 齋藤徹×沢井一恵
追悼・齋藤徹さん。亡くなる直前の鮮烈な演奏。
-

#08 山崎比呂志 Try Angle@なってるハウス
大いなる緊張感を孕みながら「哀切」を存分に謳いあげた男たちに酔った宵。
-

#07 渋さ知らズオーケストラ「真夏の夜の夢」
「真夏の夜の夢」と題された、渋さ知らズの公演。渋谷毅、森山威男らレジェンドの参加に惹かれて足を運んだが、強烈に印象に残ったのはゲストの池間由布子だった。
-

#06 秋宵十話〜高雄飛、黒沢綾、エマ・アルカヤ
2019年に初めて聴いた内外ミュージシャンの中で最も度肝を抜かれた特別な存在が、1995年生まれで、金沢在住の若き才能、ピアニスト高 雄飛(たか・ゆうひ)。
-

#05 The Music of Anthony Braxton
アンソニー・ブラクストンの音楽の方法論と本質に触れた2日間3セットは、とりもなおさず、自分の音楽に対する受容に変更を迫る「体験」であった
-

#04 藤井郷子デュオ&トリオ
藤井郷子の多作家ぶりはつとに知られたところだが、その成果が見事に現れたデュオとトリオのコンサート。
-

#03 橋本孝之 Solo Improvisation
このような理想的な表現環境がより広く伝わり実践されれば、神様なんかいなくても、この世の中をもう少し住み良い世界に創り直すことが出来るに違いない。
-

#02 高橋悠治作品演奏会Ⅱ/般若波羅密多 Prajna Paramita (プラジュニャー・パーラミター)
スコアの収集から浄書、演奏することによって楽曲を更新してゆくという、時を繋ぐ、時間の芸術としての音楽の在りようを改めて現時に問うた
-

#01 音楽と風景の時間
沢田穣治・馬場孝喜・山田あずさ・沼直也そして浅野達彦の5人による音と映像の静かなる冒険。
-

#10. ブラッド・メルドー/ソロ
玉石混淆の1年間を振り返る楽しさがある一方で、毎年思うことだが何か肝心なものを聴き(見そこなった)想いが消えない。
-

#09 アングイッシュ Anguish(ウィル・ブルックス、マッツ・グスタフソン、ハンス・ヨアヒム・イルムラー、マイク・メア、アンドレアス・ヴェリーン)
世界的に近代の枠組み、リベラルな価値観が崩壊しているとしか感じ得ない日々、それに伴う漠然とした不安感、不穏感が漂う現在のリアリティ、それを体現したステージだった。
-

#08 ギンガ、モニカ・サウマーゾ
そう、このコンサートは「来日ツアー実行委員会」によるクラウドファンディングで成立、そしてヤマガタ(の「山ブラ」)は今やブラジル音楽の聖地のひとつなのだ。
-

#07 LA FAMILIA LÓPEZ-NUSSA: ラ・ファミリア・ロペス・ヌッサ
“これまでにない新しい形のジャズ、一見に値する”という触れ込みで来日した『ラ・ファミリア・ロペス・ヌッサ』。
-

#06 デイヴィッド・マレイ+ポール・ニルセン・ラヴ+インゲブリグト・ホーケル・フラーテン
デイヴィッド・マレイが、パワープレイとそれゆえの繊細な音色を身上とするノルウェーの実力者ふたりに突き上げられ、本来のあらあらしさを取り戻している。
-

#05 ノースシー・ジャズ・フェスティヴァル2019〜メトロポール・オーケストラ 挾間美帆、リズ・ライト、べッカ・スティーヴンズ、カミラ・メサ
グラミー賞にもノミネートされた”ジャズ作曲家”挾間美帆が、フル編成のメトロポール・オーケストラを任され、女性ヴォーカル3人の魅力を最大限に引き出すコンサートを成功させた。
-

#04 East Meets East「日本/韓国のこころの歌」
ECMからデビューした福盛進也は日韓を中心にアジアに新しい地図を描こうとしており、こういう新世代の台頭をたいへん心強く思い、できる限りサポートしていきたい。
-

#03 Hiromi @City Winery Boston
今年2019年に見たライブの中で、ロバート・グラスパー、シオ・クローカー、ジェイコブ・コリアー、スナーキー・パピーなど忘れられないライブはいくつもあるが、意外性という意味でHiromiを選んだ。そのライブは筆者の期待をはるかに超えたものだった。そして、過酷な練習を積み重ねてきた者だけに許される表現の自由を見せつけられた。
-

#02 Peter Kolovos 来日公演 2019 feat. 川島誠/内田静男/山㟁直人/橋本孝之
自分も観たり聴いたり論じたりするばかりではなく、実践者として現在進行形のシーンに関わらなければならない、と背筋を正される思いがした。
-

#01 ストップギャップ・ダンス・カンパニー「エノーマス・ルーム」
英国発・気鋭のダンスカンパニーが問う、「人と違うこと」そして身体の意味
-

連載第39回 ニューヨーク・シーン最新ライヴ・レポート&リリース情報フリン・ヴァン・ヘメンへのインタビュー
パーカッショニストのフリン・ヴァン・ヘメンへのインタビュー。彼はニューヨークに2007年に来て以来たくさんのことに関わってきた。リーダー作としては、2016年に『Drums of Days』、そしてこの9月に『Casting Spells & the Coves』をNeither/Nor Recordsからリリースしている。
-
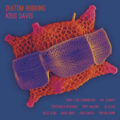
ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #50 Kris Davis <Diatom Ribbons>
NYで活躍するカナダ人、クリス・デイビスの『Diatom Ribbons』がこの9月に発表された。アバンギャルドとかフリーとかにカテゴリー分けされているが、彼女の作曲能力は恐ろしいほど高度だ。タイトル曲<Diatom Ribbons>、その絶妙な構成と、これだけ複雑に仕込まれた曲なのに全く奇をてらったように聴こえない部分と、使用されているセシル・テイラーの語りのサンプルを解説してみた。
-

タガララジオ 55 track 480-485
radio Tagara track 480-485昨夜編集 CDR 友だちのホソダさんと居酒屋で、おれは今年の1枚はハスミレマだよ!と勢いを放つと、あ、わたしもそうですよと静かに微笑む、
-

ジャズ・ア・ラ・モード#29. ルイ・ジョーダンで明けましておめでとう!
新しい年の幕開けには、明るく楽しく、お目出度い、ルイ・ジョーダンでスタート。
-

Hear, there and everywhere #16 追悼ヴァネッサ・ブレイ
偉大な父、ポール・ブレイの支配から逃れて、封印していたピアノを弾けるようになったヴェネッサだったが。
-

小野健彦のLive after Live #037~#045
脳梗塞の後遺症による半身麻痺の不自由な巨躯を1本のステッキに預け今日も巡ります東京近郊のライヴ・スポット
-

#100「ECM catalog増補改訂版 ~The 50th Anniversary」
ECMは想像力のこのうえない触媒である。ECMの音楽は空と海の間、消失点から響いてくる。
「フリー・アット・ラスト」。我々は、聴く自由によって解放される。 -

#099 纐纈雅代『音の深みへ』
ふたたび音楽に光明を見出し自立するまで、時に痛ましく、時に愛おしいひとりの女性の生きざまがむしろ淡々と語り継がれていく。
-

#1657 『Fucm Hawj / Steeple』
クリス・ピッツィオコスが作曲したスコアを基にした演奏である。ジャズ的な即興イディオムは殆どなく、クラシック音楽に於ける即興曲に似たコンセプチュアルなノンイディオマティック演奏が収められている。
-

#1956『札幌ジャズアンビシャス/One More Time!』
『Sapporo Jazz Ambitious / One More Time!』札幌ジャズアンビシャスに、北海道に住むことになったマシューズにもすでに「地の霊」は降臨していて新しい音楽が確実に芽生え始めたようだ。
-

#1655 『日野皓正/Beyond the Mirage』
ジャズのメインストリームを半世紀以上にわたって走り続けてきた男が世代の架け橋になるというミッションに燃えた。
-

#098 『Jazz Art of Takao Fujioka』
LPアルバムの復活があちこちで聞かれる昨今だが、藤岡にとっては作品発表の場としてまたとないチャンス到来といえるだろう。
-

#097『フリージャズ &フリーミュージック 1960~80:開かれた音楽のアンソロジー』(ディスクガイド編)
Free Jazz&Free Music 1960~80: Anthology for Open Music (Disc Guide)折角の労作である。再度、最後の詰めを期待したい。
-

#1119 山下洋輔トリオ結成50周年記念コンサート
爆裂半世紀11月に『ECM catalog 増補改訂版』の上梓で「ECM50周年」が一段落したと思ったら、続いて「山下洋輔トリオ 50周年」が巡ってきた。
-

#1118 EAST MEETS EAST「日本/韓国のこころの歌」
ECMアーチストによるアジア発のこの手作り公演がアジアにおけるECMの今後の展開を示唆していると言っても過言ではないだろう
-

#1117 八木隆幸トリオ
text by Masahiko Yuh
-

#1116 エリオット・シャープ/臼井康浩/さがゆき
天啓のキャッチ&リリース、その匙加減の僅差に露わになるものこそ表現者の真骨頂/ The catch and release of inspiration, the very things that are revealed in the narrow margins of that balancing act, show what the artist is truly made of.
-

#1115 クニ三上「0才からのジャズコンサ-ト」
子連れ参加者たちに必要な配慮が行き届いているのも、この企画が日本の各地で人気を博している理由の一つだろう
-

#1108 ラ・フォル・ジュルネ・ド・ナント 2019 Carnets de Voyage
作曲家の旅から生まれた音楽にフォーカス。挾間美帆は<処女航海 組曲>ビッグバンド版を演奏した。
-

#575『小曽根真 featuring No Name Horses』
鮮明なバランスに乗ったサウンドに身震いさえする。
-

#574 『日野皓正/ Beyond the Mirage』
空間感の造成から浮くようにトランペットの音像が現れるのが面白い。
-

#573 『清水くるみ4+1/City of Peace』
奏者のエネルギーが音圧で激しく耳に響く。
-

#572『明田川荘之/世界の恵まれない子供達に』
何も仕掛けのないライブ感が気持ちいい。
-

#571『清野拓巳/Piled Distance-Big Apple 2』
音像の音圧に充実を感じオーディオ的な快感を感じる。
-

#570 『佐藤允彦&豊住芳三郎/合気』
『Masahiko Sato & Sabu Toyozumi/Aiki』ドラムの近接感。ピアノのオンマイク感。これが密度の濃い音場を作り出してる。
-

#569『西村健司セクステット/Coco-Doco』
マルチマイクの音像とは異なって、ワンポイントの音像を閃かせる空間感に大きなショックを受ける。
